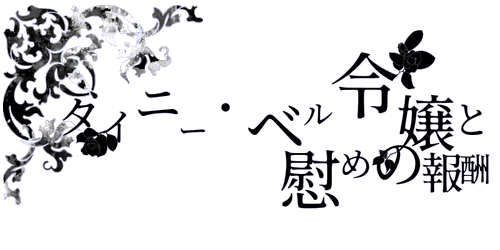そんな大切な女の子が一昨日呪われたのだ。よりにもよってヘンリーの目の前で。
そもそも一昨日の王宮での晩餐会より早い時間帯に二人きりで一度会おうとイザベルを誘ったのはヘンリーであった。
ここしばらく研究所詰めの日が続いていて、研究所と自室との往復で終わっていたのだ。更に王宮での晩餐会では他の家族もいる手前、イザベルとあまりゆっくり話せないだろうことが予想された。
それで、ついほんの少しでも良いからと二人きりで会える時間を望んでしまったのだ。
イザベルとは老舗菓子店で待ち合わせをしていた。食事会に持参する手土産を選びたいと彼女が言っていたので、昼休憩にヘンリーも同行を願い出た。頭脳労働に甘いものは欠かせないので研究室の差し入れとしてヘンリーも何か簡単につまめるものを購入しようと考えながら。
季節限定の甘酸っぱく香り高い苺とクルミのざくざく感をほどよいバランスでしっとり包んだチョコレート菓子を二人で選び、オーキッド侯爵家の者が先にそれを持ち帰った。早い段階で決まり、イザベルと隣のカフェのオープンテラスでお茶を飲もうと話していた矢先の出来事だった。
いつものようにごくごく自然にヘンリーがイザベルを先に通すために扉に手をかけたが、なかなか開かなかった。王都屈指の老舗店で建物も古く、建て付けが少々悪かったようだ。ヘンリーが魔術で滑りを良くし、今度こそ勢いよく扉を開けた瞬間、ごう、と風が吹いた。
通りから吹き上げてきた風が二人にぶつかり、抜けていく。少しでも風を遮ろうとイザベルの前に立とうとしたが、遅かった。そのときにはもうイザベルの姿はなかった。強い風にドレスの裾を大きく煽られ、小柄なイザベルがオープンテラスに勢いよく転がった。
慌てて追いかけたヘンリーは、ぞっとするものを覚えて立ち止まった。周囲の空間へと神経を研ぎ澄ませた瞬間――
彼が感じ取ったのは、衝撃であった。
巨大な魔術式がオープンテラスの中で一気に渦巻き膨れ上がる――
咄嗟のことで、そこに展開された魔術式の構成が実際にどういったものなのかは彼には理解できなかったが、ヘンリーにできたのはひとつだけだった。
できる限り広大で深い空間を意識して、全力で防御の魔術式を展開する。
完全な盾とはならないだろうが、イザベルがそこにいる。守らねばならない。
第四王子は目で合図する。最後まで王子のそばに控えていた護衛も黙したまま首肯し、疾く駆けていく。イザベル付きのオーキッド家の護衛はヘンリーよりも先に主人の下に駆けていた。
「イザベル!」
ヘンリーが辿り着いた瞬間、閃光が走った。次の瞬間、怒号と悲鳴の不協和音が弾けた。
「お前がカモに!」
「お前がネギに!」
「なるんだよ!!」
「わあ!?」
オーキッド家の護衛に守られるように囲まれ、座り込んでいたイザベルを抱き起こす。怪我も痛みもないと眉を下げてけなげに微笑むイザベルに安堵しかけ、ヘンリーは息を呑んだ。
イザベルの耳には――艶々とした長ネギとみられるものがぴょこりと生えていた。
「なんだなんだ?」
「痴話喧嘩か?」
「まあ! 物騒だこと」
閃光と騒音に驚いた人々がオープンテラスに集まり始めていた。イザベルを自分の胸に抱き寄せ、思案する。認識阻害か、記憶忘却か――
どちらの魔術にしろこの人だかりでは大掛かりな術式が必要である。
と――
「ブラボー! いやあ、私の演技指導の出番は全く必要ないですね! 皆さん、その調子でゲネプロも本番もお願いしますよ!」
やけに明るいテノールと大きな拍手が周囲に響き渡った。
線の細い両手を合わせた痩せぎすの赤髪の男が榛色の瞳を細めて破顔した。すると、周囲の波はあっさり引いた。
「なんだ演劇の練習か、人騒がせだな……」
「ねえ、今の赤髪の方、今話題の劇作家のハートリッチ先生じゃない?」
「ああ、ウィリアム・ハートリッチならば今度の新作もド派手な演出に違いない」
各々が好き勝手に納得し、嘘のようにオープンテラスから散っていく。
と――
「斬り捨てますか、殿下?」
護衛たちがその赤髪の男を縛り上げ、指示を仰いでくる。他の護衛は女性二人を捕縛し、目の前に座らせた。ヘンリーは指示を出しかけ、大きく目を見開いた。
彼女たちは知り合いだったのだ。それも王立魔術研究所の同僚で隣と斜向かいの研究室の魔術師である。
ゆるくウェーブした黒髪とまっすぐな鳶色の髪の女性二人は突然捕縛されたのにも関わらず、やけにすっきりとした表情をしている。まるで納期明けの、いや、納期明け以上に実に晴れやかな顔だ。
ヘンリーは怪訝に思いつつ、ひとまず魔術式を紡いだ。指をパチンと鳴らして始動させる。古くより伝わる認識阻害の一種だ。この術式の範囲内にいる者は、一定の短い時間、術式の外にいる人間から特にどうという存在でもないものとして認識される、いわば道端の石ころ同然のように目を留められず気にかけられなくなるという魔術である。
術式の完全な展開を待ってから、黒髪の同僚が丁寧に頭を下げた。
「恐れながらヘンリー第四王子殿下。わたくしたちに発言をお許しいただけますか?」
鳶色の髪の魔術師も動じることなく静かに微笑んでいる。
護衛が拘束を強めるか目で問うてくるが、右手で軽く制した。イザベルを強く引き寄せ、頷く。
「許す」
イザベルや自分を狙ったものなのか、ひいては王家への反逆であるのか知る必要も権利もあるのだ。
拘束されたまま二人は深々と頭を下げた。
「私たちの呪いが降りかかったそちらのお嬢さんには大変申し訳ないと思いますが」
「心よりお詫び申し上げますが」
「が……?」
腕の中でイザベルが首を傾げる気配がした。ネギがぴょこりと揺れた。
同僚二人は微笑んだまま叫んだ。赤髪の男をまっすぐと指差しながら。
「この赤毛の軽薄が服を着て呼吸している男こそが元凶ですので!」
「お嬢さんの元にも改めてお詫びに伺いますし、迷惑防止条例第八条と第ニ十四条違反の罰金は謹んでお支払いいたします。ですが、口から先に生まれたそこのハートリッチにもどうか熨斗をつけて罰金を命じてくださいませ!」
焔を滾らせた熱い二つの眼差しを受け、腕を後ろ手に縛られた赤髪の男は余裕たっぷりと頷いた。榛色の瞳が燦然と輝く。
「そう! 全てはこの私の美しさと溢れ出る才能こそが罪! こちらの花の如き愛らしいご婦人たちがこの私を巡った恋の鞘当てとして、王都エセルの迷惑防止条例第八条で禁じられた喧嘩などによる迷惑行為での店への著しい威力業務妨害を起こしてしまったのも、第ニ十四条で規制された他者への魔術による攻撃及び呪いを発動せずにはいられなかったのも、全てはこの私の! 人を惹きつけて止まない美しさと! 嫉妬を誘わずにはいられない才能! 神が何物をも私に与えたことこそが原因なのです!!」
やたらと良く通るテノールでやかましく訴えてくる男にヘンリーは頭痛を覚えた。とりあえず、眉を寄せて告げる。
「……あなたにはまだ発言を許可していませんが」
男は微塵も懲りた様子はなく、キラキラキラキラとやかましく目を輝かせるばかりだ。
「……殿下、やはり斬り捨てましょうか?」
困惑しきりの表情で提案してくる護衛に、それも良いかもしれないと一瞬頷きかけたが、ネギが肩に触れたことで我に返る。腕の中でイザベルがヘンリーの顔をじっと見上げ、やんわりと首を振った。一呼吸置いてから彼女はやわらかな頬を彼の胸に擦り寄せる。ヘンリーは彼女を抱く腕に力を入れ、護衛を制した。
長く息を吐く。イザベルはこの三人の茶番だろうか茶番だろうな茶番に違いない諍いの末に呪われたのだ。
頭痛がひどくなりそうな予感しかしないので手短に同僚に報告させることにした。条例違反に関しては騎士団や然るべき場所での判断に委ねるべきことなので、あくまでもイザベルや自分、王家に対する攻撃であったのかを先に確認しておきたい。
同僚の話は、やはり頭痛を覚えずにはいられない報告だった。
要するに、痴話喧嘩というものだった。
この赤髪の男性――ウィリアム・ハートリッチは最近王都エセルで名を轟かせている劇作家である。顔も良ければ声も良い。作る話も面白い。俳優も顔負けの端麗な容姿にして庇護欲をそそる守ってやりたい系男子として数々の女性と浮名とやらを流しているらしい。
三国一美しい王子と謳われる兄を持つ身からすると「なるほど綺麗な顔だなあ」という感想しか抱けないが、それはそれ、これはこれ、だ。
件の同僚二人はそれぞれ古くから続く伯爵家と王都随一の商家の令嬢である。この劇作家に入れ上げ、彼が伸び伸びと快適無敵な環境で執筆に専念できるようパトロンよろしく甲斐甲斐しく働いて得た収入でせっせと貢いでいたのだという。
この劇作家もまめに二人とそれぞれ逢瀬を重ねて愛を囁いていたとのことだが、今日ついにそれぞれとの逢瀬の予定が思い切り重なり、ハートリッチの二股が発覚した。そして、痴話喧嘩、否、彼女たち曰く「オトナのクールな話し合い」に発展したのだという。
極めつけにこの劇作家は反省や謝罪どころか、二人からの「私たちのことをどう思っていたのか」との真剣な問いに対し「鴨がネギを背負って庭で歩いていたようなもの」などと発言し、火に油を注いだ。
そして、激昂した彼女たちはほぼ脊椎反射のように利き手に杖を掲げ、
「そんなに鴨とネギがお好きなら!」
「お前が鴨に!」
「ネギに!」
「なるんだよ!!」
と――渾身の力でそれぞれが鴨またはネギになる呪いを男にかけた。
だが、不幸にも強風に煽られたイザベルが男の足元に転がり込み、その勢いで男が椅子ごと後ろにひっくり返り、術の一部がイザベルに命中したということであった。
大きくまばたきを三度繰り返し、イザベルがぽつりと零した。
「鴨はどこに……?」
同僚も護衛も首を傾げる。不幸中の幸いと言ってよいのか判断つかないが、イザベルには耳からネギしか生えていない。
「殿下! その疑問には私がお答えしても? どうか発言にご許可を! さあ! さあ!!」
劇作家が拘束されたまま、またしてもキラキラキラキラと激しく榛色の双眸を輝かせて主張してくる。
「……許す」
「私の胸元のポケットに答えがございますよ!」
護衛が思い切り嫌そうな顔をしながらハートリッチの胸元のポケットを探る。護衛が手にしたのはやけに分厚い干し肉であった。
「そう! 胸元に入れていた手帳がご覧の有様です! 時に愛は行き過ぎた愛を重すぎると理解を拒み、憎しみへと変化する。いやはや呪いとは実に恐ろしい! この先の予定は美味しくいただけてしまうということですな! わはははは!」
何やら一人で最初から飛ばしているが、それは無視する。
「……じゃあ、一同解散ということで。彼ら全員は騎士団の詰め所へ。僕とイザベルは研究所で解呪を――」
「お待ちください! 殿下!」
いつになく真剣な眼差しで劇作家が縋るように叫ぶ。
「よくよく拝見すればそちらの可憐なお嬢さんは、オーキッド侯爵家のご令嬢にして殿下の大切な婚約者殿ではございませんか?」
自ずと眉が寄る。まだ社交界デビューを果たしていないイザベルの顔を知る者は少ないはずだ。まして成人男性がイザベルを知る機会は更に限られている。
ヘンリーの冷たい眼差しに男はやんわりとかぶりをふった。
「仕事柄、作品の参考として貴族名鑑を拝読することも噂話を耳にする機会も多いのです。それはそれとして、殿下!」
「なんです?」
「不幸な事故とはいえ愛する婚約者殿に呪いが! なんと嘆かわしい! さあ、殿下! 今の苦しい胸のうちをぜひともお聞かせください! 言葉少なくともかまいません。むしろその方が私の筆がいっそう唸るというもの! さあさあ、このハートリッチにすべてお任せを!」
全く堪えていない逞しさというか図々しさにヘンリーは怒りを通り越して呆れ果てるしかなかった。同僚二人が嫌そうに首を振った。
「……殿下、この男は、口から先に生まれたと言っても過言ではないのです。顔と声だけは良いのに」
「ええ。顔と声の良さだけと引き換えにデリカシーや慎み、気遣いなど人間社会で生きるのに必要な要素を根こそぎ置き去りにして生まれたような最低男ですわ! こんな男に入れ上げたなんて人生最大の屈辱よ!」
「奇遇ね! 私もそう思っていたところ! 口さえ開かなければいい男なのよ。口さえ開かなければ。この男と過ごした日々は黒歴史というものだわ! これ以上の汚点はこの先の人生で誕生しそうにない感じ! いっそのこと、汚点そのものであるこの男を聖都ファティマのアリオン川にでも投げ捨てたいわね」
「あら素敵! わたくしもそう思っていたところ。でもこんな歩く軽薄男なんて川に捨てたら、聖都が汚染されてしまうわ! それにしてもなんだか気が合うわねわたくしたち!」
「私もそう思っていたの! 罰金払い終えて、こちらのオーキッド先生のお嬢様のところにお詫びに行った後で、お茶をご一緒しませんか?」
「まあ素敵! こちらこそお願いします!」
逞しくも美しい友情の握手を熱く交わす同僚たちに頭痛を覚えつつ、ヘンリーは護衛たちに合図した。
「解散ということで」
言いたいことは三者それぞれあるだろうが騎士団の詰め所で言うようにとヘンリーがぐったりと指示を出す。劇作家が微笑んで首を傾けた。
「最後に一つだけよろしいですか?」
彼を拘束している護衛の顔つきが険しくなったが、ヘンリーは一言だけならばと条件を付けて許可した。
静かな声音で男は告げる。
「望んで得た恋は素晴らしい、望まずして落ちた恋はさらに良い――私たちの恋もまさにそうでした」
同僚二人が深々とため息を吐いた。
「いえ、わたくしたちの恋は完全にもらい事故や打ち上げ花火みたいなものだったでしょう?」
「俄然その通りよ。出会い頭に衝突して慰謝料で食わせたり、眺めの良い特別ボックス席に注ぎ込んでいたりしたようなものだったわね……」
「殿下、わたくしたちが言うのもアレですけれど、ハートリッチの話は八割ほど差し引いてお聞きするのがちょうど良いかと存じます……」
散々な言われようだが、ハートリッチは微笑みを絶やさず耳を傾けている。いや、次の作品にこの会話さえ使おうとしているようにも見える。
「浮気も何もこのひとがわたくしたちに対して本気でなかったことなどはどうでも良いのです」
「え?」
「ええ。元々積み重なっていた火種に、この今日のデート日時の丸かぶりという炎が飛び込んでついに爆発しただけですもの」
「……え!?」
分からずにヘンリーは聞き返す。思わずイザベルを見下ろせば、彼女と目が合う。イザベルも眉を下げ、困ったように首を振った。
「殿下、『慰めの報酬』というものをご存知ですか?」
隣の研究室の同僚の言葉にヘンリーは首を振った。
「いや、初めて耳にする」
「親しい人間同士、例えば恋人や友人関係にあるひとたちにおける慰め――互いの心を思いやり楽しませるものの量のことです。この量は互いへの不満や不信などで減っていき、それがゼロになったときについに関係が壊れるのです」
「要するに日々の積み重ねというものですな!」
日々の積み重ねで負債を弾き出し、養ってもらっていた女性二人からこっぴどく袖にされたはずの劇作家が何やら明るくウキウキと言っている。ヘンリーはやはり頭痛がした。この男との慰めの報酬がゼロどころかマイナスにまで減少したという同僚二人を見るが、二人とも呆れ果てたような顔というよりは、仕方がないなあというような表情であった。それは、どこか慈しむ笑みだった。
「殿下、何ですか? 顔に何か付いていますか?」
「いや、ついに彼を川に投げ込むのかと……」
ヘンリーの返事に二人は口の両端を吊り上げた。
「あらいやだ。人聞きの悪い」
「殿下はなかなか過激なことをおっしゃいますねえ。わたくしたちを一体何だと思っていらっしゃるんですか?」
「……」
王立魔術研究所付きの手練れの魔術師と零しそうになり、咳払いをして誤魔化した。二人の魔術で思い切りヘンリーの婚約者が呪われたのだが、ぐっと我慢した。早く彼女たちから離れてイザベルを安全なところで休ませたい。
「この男に心底腹は立ちますが、私たちの大金でこのひとが元気よく飲み食いし、素晴らしい作品を生み出したことは事実ですから後悔はしていません!」
「はい。後世に残るであろう『あの恋を数えて』『眺めの良い窓』『エセルは燃えているか?』『あの鐘を鳴らすのはそなた』を始め、稀代の劇作家ハートリッチの作品の数々が私たちの大金のほとんどでできているのはむしろ誇りですらあります!」
ヘンリーには度し難い結論をあっさり言いのけ、二人は晴れやかに笑う。
「そ、そういうものかなあ……」
護衛を見やると、彼らも困ったように笑うばかりだ。
「閃きました!」
ハートリッチが良く通る声で叫んだ。
「次の作品はズバリ! カモになった王子! 令嬢の金と勇気と希望で忌まわしい呪いが解けるのです! そして深まる二人の愛と絆! 売れる予感しかしない! ああ、私の才能が怖い!」
「殿下、今すぐ斬り捨てますか?」
護衛が真顔で抜剣許可を請う。ヘンリーは深く息を吐いた。
「騎士団の詰め所で頼む。解散」