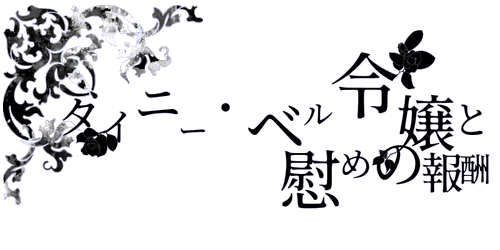「ええ、それはもう! とても燃える作品でした! 連れて行ってくれたお姉様には感謝してもしきれないわ!」
グレイスが熱いため息をつく。彼女の胡桃色の長い睫毛が揺れた。夢見るようなグレイスの言葉にマーガレットも深々と頷き、薄藍色の瞳にいつになく強い光を灯した。
「ええ。私も祖母と母と観に行ってとても燃えたわ」
「ヒーローがヒロインと共に爆破する廃墟を後にしながらフィナーレを迎えるシーンは特に燃えましたよね!」
なるほど、燃えている。
「あと、森でマシュマロを焼くシーンも良かったわね。とろりとしたホットチョコレートがとても美味しそうだったわ」
「ええ、ええ! ヒーローが親友と兄弟の杯を交わす、そこは鉄板でしょう! うちのお姉様ときたら、あのシーンの感動をまだ毎日私に語ってきますもの! でも、やっぱり私は『機密は人命より重い』と崖の上から海に飛び込んで自ら爆破する道を選んだ親友にとても燃えました!」
確かに燃えている。
感激しっぱなしのグレイスとマーガレットの観劇トークにイザベルはただ目を丸くするばかりだ。劇作家ウィリアム・ハートリッチの作品を観たことがあるか、という軽い質問がこんなにも弾けてヒートアップするとは思わなかった。
けれども、二人が朗らかに笑う声を直に聞くのはやっぱり楽しい。話に花を咲かせる二人のためにお茶のおかわりを届けるよう、イザベルは家の者に頼んだ。
二人はすっかり話に夢中で、空になったティーカップには全く気づかずにティースプーンをぐるぐる回したり、何度も口元にカップを傾けては熱弁を振っている。三人そろって――イザベルは今は聞き役に徹しているが――おしゃべりに花を咲かせるのはいつも通りのごくごくありふれた光景だ。それがなんだか懐かしくて、嬉しくて。イザベルもへにゃりと頬を緩めた。
今週始めにイザベルはひょんなことから呪われた。そして翌日、呪った人物とその原因である人物たちからオーキッド家は丁寧な謝罪を受けた。
イザベルの父は苦虫をかみつぶした顔をしたり、魔術師としての血が疼いたのか術式の甘さを指摘したり、悪びれもなく貢がせていた男と貢いでいた若い娘たちに父親として思うところあるのか、「呪うならばもっと全力で取り組みなさい」と説教したりと大忙しだった。
お詫びとしていただいたのは茶葉の詰め合わせだ。王都エセルでも指折りの香り高く高級な紅茶に父はなんとも複雑な顔をしていたが、茶葉に罪はない。母も「たくさんいただいたわけですし、きっと飲み終える頃には今回の件も思い出話になりますよ」と静かに父を諭した。
そんなわけで、大量にある高級紅茶を気持ちよく飲んでくれる客人はとてもありがたい。イザベルはせっせと友人におかわりを用意した。
グレイス・アルブリトンとマーガレット・ウォーターハウスはイザベルの友人である。女学院に入学して以来、淑女が何であるのかも知らない、それこそ制服に着られていたひよこ時代から同じ学び舎で過ごし、苦楽を共にした得がたい友である。
二人は、耳からネギが生える呪いを受けたことを理由に今週いっぱい登校自粛となってしまったイザベルの見舞いがてら、学院帰りに授業のノートを届けに来てくれたのである。
「稀代の劇作家、ウィリアム・ハートリッチの舞台をイザベルも観に行きましょう! それで一緒に燃えましょう。質問するほど興味を持てた今が鑑賞するチャンスよ!」
「ええ、ええ! とても燃えるわよ。大人も子どももお兄様もお姉様もおじいさまもおばあさまもとにかく幅広い観客層が、彼の作り上げた物語に劇場で目をきらきら輝かせている光景を見るのも楽しいわよ。我が家ではおばあさまが一番熱中しているわ。『あの鐘を鳴らすのはそなた』ロングラン上演記念特典として、人気シーンの台詞が刻まれた栞が配布されているのだけれど、おばあさまったら立派な額縁に入れて大事に飾っているのよ」
「イザベルの場合、ヘンリー殿下とご一緒に観に行くのも良いかもしれませんね。燃えること間違いなし!」
深い森の緑に似た瞳を輝かせ、グレイスが息巻いた。緩く波打つ髪を肩の下で編んでまとめていたリボンが大きく跳ねた。三人の中で一番落ち着いて大人びた佇まいの彼女がこんなにも高揚しているのは珍しい。
「うーん……」
劇作家ウィリアム・ハートリッチはイザベルとヘンリーに起きた不幸な玉突き事故の見本市こと、耳から呪いの長ネギ事件の大元凶である。呪われたイザベル以上に胸を痛めているヘンリー殿下に「ハートリッチの舞台をぜひ共に観劇して感激しましょう☆」などと提案したら、燃えるどころか爆発して灰と化しそうだ。殿下の良心が。
「前向きに検討いたします」
とりあえず、よく聞く大人の返事で微笑んだ。
「人気すぎて今月分はもう完売だから来月以降を検討した方が良いかもしれませんね」
「はい。決して近くはない遠い未来に……」
「遠すぎません?」
グレイスの目が三角になった。
「まあまあ。グレイスくん、落ち着きたまえよ」
マーガレットがやんわりとなだめてくれた。彼女は鷹揚に笑い、鼻の下をちょいちょいと指で撫でる不思議な動きをした。あたかも口元に蓄えた髭を整えているように見えた。それから左手を軽く上に向けて動かした。ワイングラスだかパイプだかを揺らしているつもりらしい。そして、膝上に丸を描くようにわしわしと撫でる動作をした。猫ちゃんを撫でているのだろう。先ほどまで二人が熱心に話していたハートリッチの演劇に出てきたとかいうボスの貫禄とやらを表現しているらしい。芸が細かい。
「グレイス、考えてもごらんなさいな。イザベルはウィリアム・ハートリッチの燃える舞台よりも第四王子殿下と過ごす甘い日々に胸を燃やしてドキドキすることの方が大事でしょう?」
「そうね。メグ、真理を突いているわね。さて、殿下との仲は近頃どうなのですか? お見舞いに毎日いらしているわけだし、何か甘い進展はありますかありますよねありましたよね現場のイザベルさん?」
いつになく真剣な眼差しをこちらに注ぐ二人にイザベルができたことは――
「ワーイ、週明アケノ歴史ノ小テスト、範囲ガ広スギテ胸ガドキドキシマスネ!」
先ほど受けたばかりである歴史の小テスト実施の悲報に向き合うことだった。
「逃げるな逃げるな。小テストは逃げない。よって、イザベルも殿下のお話から逃げる必要はない。はい、証明完了」
「そうですよ。夏には卒業するのだし、三人そろって一度くらい追試を経験するのも良い思い出になるわ。ほらほらイザベル! 私たちに聞かせるときめき☆愛しの殿下トーークと小テスト、どちらが大事なんです?」
「小テストですが!?」
むちゃくちゃな理論をぶつけてくる二人にイザベルは悲鳴を上げた。
婚約者であるヘンリー第四王子は臣籍降下を早くから、イザベルがまだ女学院に入る前から決めてくれていたので、イザベルは王子妃になる者が受けるという正式な教育を王宮で受けたことはない。だが、ヘンリーの長兄の奥方である第一王子妃とたまにお会いすると、気品も佇まいも機知に富んだ話も眩しいほどに素敵なのだ。妃教育の成果もあるのだろうが、何よりもベルジーネ妃のたゆまぬ努力の賜物なのだろう。そんな素敵な未来のお義姉さまに憧れてイザベルが勉学に励むのは当然の真理だ。
つい先日の晩餐会でも――ひょんなことからイザベルが呪われた記念すべき日でもある――ベルジーネ妃はイザベルに女学院の話を熱心に尋ねてくれ、イザベルの語る女学院の日々に懐かしそうに目を輝かせていた。イザベルが呪いのことを気にせずに食事会を楽しく過ごせるよう心を砕いてくれていたのだ。
「落ち着いたらまたアイスクリームを食べにいらっしゃい。タイニー・ベルの女学院の楽しい話をもっと聞きたいわ」
とイザベルだけに向けてくれたあの眩しくも美しい笑顔を、追試になったなどという残念な報告で曇らせたくない。まして、ヘンリーの話で盛り上がりすぎたことが原因で追試になってしまったとしたら、恥ずかしすぎる。ヘンリーにもベルジーネ妃にも顔向けできない。
「ベルジーネ様、とっても素敵ですものねえ。イザベルが憧れるのも分かるわ。私のお姉様も夜会でたまにお見かけするそうだけれど、『聡明で美しい内面を映し出すかの如きたおやかな笑顔を拝見するたび、寿命が伸びる』と言っていますもの」
「レオナード殿下は長生きするわね」
マーガレットの神妙な相槌にイザベルも軽く頷いた。ヘンリーの話では彼の祖父である国王陛下も、父親の王太子殿下も、長兄のレオナード第一王子殿下も毎年の健康診断結果がオール良好とのことなので、長生きされるとは思う。
それに、ラグランド第二王子殿下も「生命線が三人ともびっくりするほど長いからね」と笑っていた。
「あら! レオナード殿下には元気よく長生きしていただかないと!」
グレイスが眉に力を入れた。
「ベルジーネ様の守りたいあの笑顔を、我々が末永く拝見するためにもレオナード殿下にはずっとお元気でいただかなくては!」
グレイスの熱の籠もった言葉にイザベルも深々と頷いた。
イザベルにとって頼れるやさしいお義兄様とお義姉様の二人には、末永く幸せに笑顔を分かち合う夫妻であってほしい。
「と――つい我らが麗しのベルジーネ妃殿下に誤魔化されたけど、ヘンリー殿下に顔向けできなくなることの方がイザベルには大きいのでしょう?」
「冬季考査も殿下に歴史の勉強を見ていただいたって言っていたものねえ?」
「ああ、いつもより頑張れたって言っていた、イザベル史上最高得点を記録した例の冬季考査ね?」
毎年、女学院では冬の星祭り――新年を迎え、遠い春を待つまでの安寧を星に祈る祭りである――の直後に試験を行っている。
星祭りは王都エセルで開催される一年で最も大きな祭りであるが、この冬季考査も秋に進級した生徒たちが新学年で臨む初めての大きな試験なのだ。「星祭りできらきらふわふわ華やぐ王都の空気にあてられて羽目を外すことなく、各々抜かりなく基本に忠実に勉学に励むべし」との教師陣からのありがたい訓戒である。
グレイスとマーガレットはにやにやと頬を緩め、立ち上がった。二人は目配せして左右に分かれると、目を白黒させているイザベルを中央に挟むようにして座った。戸惑うイザベルをよそに、グレイスは白くたおやかな左手を制服の胸元のリボンに寄せた。
苦悩するように眉を下げ、深い緑の森を思わせる瞳を伏せる。それから右の手のひらを天に向けて厳かに告げた。
「憧れの君のためにたゆまぬ努力をする乙女!」
マーガレットも薄藍の瞳を閉じ、制服の勿忘草色のリボンの前で両手を組んだ。
「見守らずには居られない可憐さは、香木の鐘を打ちならさんと蕾をやわらかく膨らませる椿の花に似ていた!」
即興詩を作って大仰にからかう二人に、イザベルは口を尖らせた。
「だって、がっかりされたくないですもん」
冬季考査の頃はヘンリーも王立魔術研究所の仕事が学会を控え、とても忙しくなり始めた時期だ。
仕事と研究で疲れて頭も身体も休ませたいこともあっただろうに、休日には時折イザベルに会いに来てくれたのだ。彼は試験勉強の進みを聞くと、陽当たりの良いこのサロンの長椅子でイザベルの隣に座り、歴史の勉強を見てくれたのだ。
すぐ隣から響くヘンリーの低く落ち着いた声。白銀の髪とおそろいの睫毛が、青い瞳に光を散らし影を落とす横顔。イザベルは思いがけない独り占めになんだかどきどきしてばかりいた。青空に似た彼の瞳に自分がいっぱいに映されるのが気恥ずかしい。
そういうわけで、あの日のイザベルは、地図を指し、教科書のページを丁寧にめくるヘンリーの骨張った長い指を見つめるのに忙しかった。父と兄と同じくヘンリーの短く整えられた爪に、この方も正真正銘魔術師なのだなと感じ入ったのを覚えている。
「……おかわりの紅茶にはミルクも砂糖もいらなかったね」
「……ええ。十分甘いです。ごちそうさま」
二人は生温い笑みを浮かべ、「そうそう、そういうので良いんだよ」と声高にティーカップで乾杯した。
「だから話したくなかったんですよう……!」
椅子の上で手足を丸めて身を縮めたイザベルの頭を、二人がやさしい手つきで撫でてくれた。
「でも、努力するのは自分のためであるのはもちろんだけれど、その強力な後押しとして、愛しのヘンリー殿下がいらっしゃるのは素敵じゃない?」
マーガレットが薄藍色の瞳をやわらかく細めた。
「はい。ヘンリー殿下の隣に誇らしく並び立つために、その時一番ふさわしく素敵でありたいと自分を磨くイザベルはとっても眩しいですよ」
グレイスも頬をおっとりと緩めた。
「うん。それにとっても可愛い!」
二人は破顔して中央のイザベルをぎゅうぎゅうと抱きしめた。
「メグ、知っていましたか? 頬にネギが当たるととても冷たいのですね?」
「うん。見た目以上に艶々しているし、冷たさの中に芯の強さを感じる。でもグレイス、この長ネギを頬で触れるのって今だけでしょう。しっかり味わっておこう!」
二人の明るい声にイザベルも口元をほころばせる。胸から溢れる喜びが笑顔へと変わっていった。
陽だまりに満ちたオーキッド侯爵家のサロンに少女たちの笑い声が弾けて揺れた。