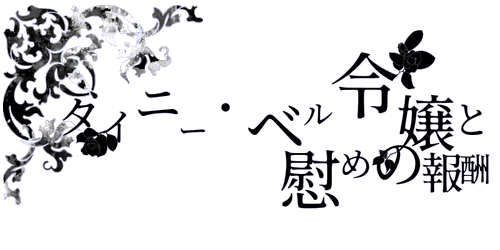うららかな陽気のせいもあって、王都の大通りはいつもより人も馬車も多い。窓の外では惜しげもなく太陽の光が降り、草木の新芽が煌めいている。
通い慣れた道なのにイザベルはしつこく馬車の窓を確認してしまう。
イザベルは左右を向いたり、首を傾げてはぐるりと回してみたり、はしたないことだと分かっていたが大きく仰け反ってみたりしては、窓を矯めつ眇めつ覗き込んだ。
ガラスに映るのは、色のぼやけた金髪を少しだけ後ろにまとめた、薄い紫色の瞳の少女である。つまりはイザベル・オーキッド、自分自身の姿だ。
左右の髪を耳にかけてはおろし、かけてはおろす動作を注意深く繰り返す。
間違いない――
「耳から生えたネギが! 全部まるッと消えています!!」
「お嬢様? いかがなさいました!?」
運転席から御者の慌てたような大声が飛んできた。そこでイザベルは我に返った。朝からずっと繰り返している動作だった。誰に見られたわけでもないのになんとなく気まずくて、「何でもありません!」と返す声が上擦った。
今朝、イザベルが目覚めたときには呪いのネギは消えていた。あの日からちょうど七日目の朝である。両親も兄も家の者たちも心から喜んでくれた。
彼らは今ひとつ信じられない思いで鏡を真剣に覗き込んだり、耳をぺたぺた触ったりを繰り返すイザベルを、何か微笑ましいものでも見るかのようにあたたかく見守ってくれた。
『明日はいつもの温室でご一緒しませんか』
昨日受け取った手紙にはシンプルにそう書かれてあった。「目には目を。お手紙にはお返事を」というイザベルのおねだりに、ヘンリーが長椅子の隣で笑いながら書いてくれたものだ。
二人にとってのいつもの場所といえば、オーキッド侯爵邸のサロンと王立魔術研究所の温室のことである。二人は小さな頃から特別愉快な娯楽を求めることはせず、いつもの場所で二人ゆったりと過ごす時間を好んだ。
二人でピアノを連弾したり、長椅子に並んでキング船長の海洋冒険シリーズを読みふけったり、温室を散歩しながら季節の変化に目を和ませたりする時間はいつも穏やかに流れていた。
ヘンリーの次兄ラグランド殿下とイザベルの兄ニールは学校の友人同士である。
オーキッド家の陽当たりの良いサロンとそこに置かれたピアノをことのほか気に入った第二王子殿下が足繁く通うようになり、その兄のお供でヘンリーもオーキッド家に遊びに来るようになった。
それがヘンリーとイザベルの二人の物語の始まりだ。
王立魔術研究所の温室は、元々は、昔、王都エセルで大規模に開催された王国博覧会のために作られた特別温室であった。博覧会観覧に訪れた隣国の貴賓の客間を飾る花栽培のために建築されたのだ。
美しい花々を楽しむ貴賓にどこから摘まれた花なのかを尋ねられても誇らしく答えられるように、当時の最高峰の建築家とガラス職人の合同作業で建築された豪華な歴史建造物であるという。
その役目を終えた今では王立魔術研究所の施設として使われている。きっかけは、博覧会での功績を大きく称えられた若い魔術師に下げ渡されたことにある。
その若い魔術師は植物が専攻ではないものの魔術分野における光と水の研究が得意であり、貴賓を楽しませる花の育成に大いに寄与していた。 その魔術師はこのほど結婚したばかりだったのだが、この温室の花の育成に駆り出され、自身の発明品のお披露目のために博覧会本番にも連れ回され、東奔西走していた。
彼は妻も魔術も愛していたが、残念なことに新妻に花を贈る暇もなければ、花を贈るセンスも持ち合わせていなかった。
けれども、同世代の王太子殿下が心を砕いてくれた。国のために貢献してくれたのにそれが夫人とその周囲にはほんの一部しか伝わらなかったら気の毒だろう、と。
「王国博覧会の成功は、ひとえに彼の魔術の数々の発明、そして、身も心も粉にしながら日々も家庭も犠牲にして献身してくれたことが大きい」
王太子殿下は議会と国王陛下に十分な報奨を与えるよう提案してくれたのだ。
しかし、その若い魔術師は金と時間さえあれば研究所に籠もることを良しとする根っからの魔術師であったので、報奨品の領地授与はあっさり辞した。ならば、より一層研究に励むことができるようにと、満場一致でこの温室が授与されたのだという。
その魔術師には花を贈るセンスはなかったが、妻を大切にしたいという気持ちは人並みに存在していた。それで、この温室をまるごと妻にプレゼントしようとし――笑顔で断られた。
「研究に励むあなたを、病めるときも健やかなるときも一番近くで見守る永遠のあかしを、わたくしはもう手に入れているのでそれ以上のものは何もいりません」
けなげな妻に感激した彼は、自分のように若い魔術師の今後の研究に役立ててほしいと王立魔術研究所にこの温室を貸し出すことにした。妻の好きな花と展覧会ゆかりの花、季節の花を今後も変わらず大切にしてくれることを条件に、と。
その結果、この温室では今でも常時色とりどりの美しい花々が訪れる人の目を和ませている。
「お母様のあの一言は、お父様がお母様に渾身の想いで捧げたプロポーズよりもずっと胸に響く一言だったよ」
その魔術師ことジーン・オーキッド侯爵――つまりイザベル・オーキッドの父親だが――は愛妻シルヴィアとの間に誕生した子、ニールとイザベル兄妹に何度も王立魔術研究所の温室について語った。
ジーンは、代々続く魔術師の大家の次男であったが、数々の研究と発明の功績を認められ、若くして侯爵の爵位を授かった。そして博覧会の報奨品としてこの温室を授かり、あっさりと研究所に貸し出し始めた。その後、彼は研究が煮詰まったときの気分転換にはもちろん、休日には妻と子どもと連れ立ってこの温室に通い、季節の花を愛でた。
イザベルにとって、この温室は、家のサロン同様、幼い頃からなじみ深い場所なのである。
家の陽だまりに満ちたサロンでイザベルが温室の花の様子をヘンリーに語り、興味を持ったヘンリーもイザベルの父の許可を得て一緒に出入りするようになった。そして、今では研究所の魔術師となったヘンリーも仕事の息抜きにここを訪れ、また、季節の花が咲くとイザベルを誘って散策するようになった。
ちなみに博覧会の大規模展示用に作られた温室は、今では王立公園となり、広く一般に公開されている。
温室の入口にはヘンリーがそわそわと気もそぞろに立っていた。
イザベルが淑女の礼を終えるよりも早くヘンリーが駆け寄ってくる。彼は黙したままこちらの両頬に手を添え、そっとイザベルの額に彼の額を合わせた。
思わず三度目を瞬く。いつもイザベルを待ってくれる、年上の婚約者であるこのひとの慌てる姿は珍しい。
ヘンリーは大きくゆっくりと息を吐き出し、そのままイザベルの顔をじっと見つめる。彼の青い瞳は溶け出しそうに滲んでいて、イザベルだけが映っている。
「……ああ、タイニー・ベル。無事に呪いが解けて本当に良かった」
「……ありがとうございます」
ヘンリーの掠れた声にイザベルは、胸のあたりがきゅうとなる。
「ロー様の仰った通り、七日で解けました。ロー様は素晴らしい魔術師さまですね」
イザベルが頬を緩めて惜しみなく称えると、彼は大きく眉を下げた。
「そうかなあ……結局、僕には経過を見守ることしかできなかったし、オーキッド先生と君の兄上からこの呪いへの手出しはくれぐれも古来より伝わるあれまで――口付けまでならばと特別にお許しをいただいていたけれど……先生とニール殿の毎日の声がけはイザベルにもしものことがあったら絶対に許さないというプレッシャーがとてつもなかったし、お二人は婚約者としても魔術師としても僕を試していた」
黙したままそっと彼の両手を取り、撫でる。彼はぐったりと息を吐いた。
「……だいたい、口付け一つで呪いを解呪できるようにするには、呪いそのものによく整理したとびきり選りすぐりの術式をじっくりと丁寧に織り込む作業が必要なんだ。絵本の王子と姫は術式の工程から解説を全部まるッと端折って一瞬で解呪しているのが納得いかない」
いつになく険のある声音でヘンリーは呟いた。子どもっぽく拗ねた顔つきにイザベルはつい頬が緩んでしまう。
「でも、わたしはロー様と毎日お会いできて……ロー様がわたしのために毎日お時間を作っていただいたことも口付けという手段でずっと解呪と加護の魔術をかけてくださっていたことも嬉しかったです。とても」
イザベルは魔術師ではないので細かい術式は読み解けないが、魔術師の娘である。小さな頃から常に魔術はそばにあった。
ヘンリーがこの毎日、イザベルの元を訪れては絡まった術式を解す術式と小さな加護――椅子に頭をぶつけたときなどの衝撃をほんのり和らげる程度の弱いものだ――を口付けに仕込んで贈ってくれていたのを知っている。呪いのネギがちょっとしたことで傷ついたり、何らかの衝撃で術式によろしくない影響が起きたりしないように、効力の弱い簡単な加護の術式を毎日紡いでくれていたのだ。
ややあってから、ヘンリーが熱い息を吐いた。
「……君が魔術師でなくて本当に良かった」
「どうして?」
「君の殺し文句はとにかく鋭く的確すぎて、君の紡ぐ言の葉の前では、僕はいくつ心臓があっても足りないってこと」
眉を下げた彼の耳は、朱く染まっていた。
ヘンリーの腕に手を添え、歩く。
海洋冒険譚の主人公、キング船長が第六巻で脱出大作戦に使ったという南国の長くて丈夫な蔓植物。船長の相棒である二頭のシャチの賢いジャックと熱血エースに、彼らを慕う島の子どもたちが贈った夕焼け色の丸い花冠。
イザベル妃――ヘンリーの祖母でこの国の王妃様だ――が博覧会で大絶賛したという白薔薇はまだ蕾すら付いていないが、茎も枝も毎年変わらず凜と背を伸ばしている。
小さな頃から両親や兄、ヘンリーと何度も通った温室であるが、季節が巡るたびに咲き誇る花々を観る喜びが色あせることはなかった。訪れるたびに懐かしい思い出も新しい発見もある。春のやわらかな新緑に、イザベルもヘンリーも頬を綻ばせた。
「椿、ですか?」
ヘンリーのエスコートで辿り着いた花壇に、それは咲いていた。
明け方の光を受けた空に雪がほんのり舞ったかのような淡い朱鷺色の小さな花だ。やわらかい花弁が常磐色の葉に守られながら揺れている。イザベルは、「かわいい」と目を細めた。
「そうとも。タイニー・ベルだからね」
「え?」
三度、大きく瞬いた。
ヘンリーは艶めく葉を撫で、告げる。
「この椿の名前は、タイニー・ベルというんだ」
イザベルは、息を止めた。うまく言葉が見つけられない。いや、伝えたい言葉は次から次へと浮かんであふれそうなのに、それを正しく選びとって声に乗せることができない。震えた指を握り、椿の小さな花とヘンリーをじっと見つめることしかできない。
「君は覚えているかな? 兄上たちが君をサロンに残したまま街まで遊びに出て行ってしまって遅くまで帰ってこなかった日のこと」
「……はい」
声が、震えた。
もちろん覚えている。それはイザベルが初めてヘンリーと出会った日のことだ。忘れるはずがない。ラグランド第二王子殿下のお供として、ヘンリー第四王子殿下が初めてオーキッド家に足を運んだ日のことなのだ。
イザベルの年の離れた兄のニールは寡黙だが面倒見は良く、休日はいつも小さな妹のそばに居てくれた。しかし、あの日の兄は遊びに来てくれたラグランド第二王子殿下と市街地へ出かけてしまったのだ。
サロンに置いて行かれてがっかりしていたら、同じく二人に取り残されていた小さなお兄様がピアノを弾いてくれた。
退屈していたイザベルのためにピアノを弾いてくれた彼の心遣いも、イザベルを誘って隣に座らせてくれた王子様力も、鍵盤に向けた澄み渡る青空に似た瞳も、白銀の髪が影を落とす静かな横顔も、陽だまりの満ちたサロンのピアノの音色もずっとずっと素敵だった。
ピアノを習い始めたばかりのイザベルには、ヘンリーの指使いを真似て、鍵盤の上で指をもたもた動かすだけでいっぱいだったのだが、彼は邪険にせず、根気よく耳を傾けてくれた。
それからサロンに置かれていた花の図鑑を長椅子の隣でイザベルと一緒に読んでくれた。ヘンリーは兄のようにムズカシイ解説はせず、「これは僕のおばあさまも好きな花で、春になると毎年庭で大きく咲く花だよ」「こんなに丸くて大きくふくふくとした形の花は僕も見たことがないなあ、君はある?」「君も観に行ってみたい花はあるかな?」など、イザベルが退屈しないように穏やかにおしゃべりをしてくれた。
ヘンリーは口を閉じては開くのを繰り返すのがやっとのイザベルに、ふっと笑みを浮かべた。
「あの日、オーキッド侯爵家の小さなレディが一際目を輝かせて笑ったことがあって――そう、図鑑でこのタイニー・ベルを見たときだよ。ぱあっと花咲くように笑ったんだ。アメジストの瞳をきらきらさせて、『ようせいみたいでとってもかわいいおはなですね』って――あのときの君はとびきり可愛かった」
君は今ももちろん可愛いけれど、などと王子様はさりげなく甘い言葉を付け加える。
空と同じ鮮やかな青の瞳に真っ赤な顔をした自分が閉じ込められている。イザベルはますますいたたまれなくなり、逃げるように顔をうつむけて、自分を落ち着かせるためにそっと息を吐き出した。
「いつか君にこの花が咲き誇るのを、いや、君と一緒に僕もこのタイニー・ベルが咲き誇るのを観たいと――花のように愛らしく笑う君の隣でこの花を観たいとずっと思っていたんだ」
臣籍降下を決めて以来、魔術学院進学を経てひたむきに研究を重ね、魔術師としてようやく独り立ちしたヘンリーは、この温室の始まりのように大切な人のために花を育ててみたいという願いを持ってしまったのだという。
「本当は格好良く君の誕生日に間に合わせて一緒に観たかったのだけれど、こればかりは自然のことだから仕方ないね」
眉を下げて少し困ったかのように浮かべる微笑み――イザベルの胸がきゅうっとなる、いっとう好きな笑顔だ。咲いた花を手折らずに一緒に観に行こうと誘ってくれる彼は、イザベルと図鑑を読んでくれた頃からずっと変わらずやさしい。
「でも、ゆっくりとこの花が蕾を膨らませていくのを待つのは、オーキッド侯爵邸の陽当たりの良いサロンで君が顔を見せに来てくれるのを待つ時間にも、君が年を重ねる毎に素敵なレディになっていくのをずっとそばで見ることができた時間にも似ていて、僕には待ち遠しくもとても愛おしかったよ――さて、レディ」
ヘンリーが言葉を区切った。イザベルは小さく首を傾ける。
「はい」
イザベルは顔を真っ赤にしながら口を開けたり閉じたりした。
「レディ・タイニー・ベル。改めて、お誕生日おめでとう」
彼は丁寧に腰を折り、膝をついた。
「レディ・イザベル・オーキッド」
王子様はイザベルをもう一度呼んだ。彼が愛称ではなく、イザベルの名を正しく呼ぶのは公の場にいる時ととても大事な話をする時だ。
ヘンリーはそっと彼女の左手を取り、口元まで掲げた。ヘンリーのやわらかな唇が薬指に触れ、かすかな吐息がかかる。
それは指先から、イザベルの胸の底までもを甘く痺れさせた。
「この先の日々を、君の隣で僕が歩むことを誓わせてほしい」
誓いの証人となる司祭はここにはいない。
大きく早鐘を打ち続ける心臓をなんとかなだめる。声が、震えた。
「何に、誓うのですか?」
「君と、僕自身に」
そのひとの遮るもののない澄んだ青空に似た瞳いっぱいにイザベルだけが映っている。
胸の奥の色々なものが溶け出してしまいそうで、イザベルは答えられなかった。言葉では。
代わりにヘンリーの右手に指を絡めて握り返した。そして、彼の袖を右手で掴んできゅうと引き、その胸に思い切り飛び込んだ。
温かな体温に包まれながら頬を擦り寄せる。そのひとはイザベルの長い髪を梳き、そっと耳にかけてくれた。とっておきの宝物を手の中に包み込むように、慎重でやさしい手つきだった。
イザベルの婚約者であるそのひとの聞き慣れた穏やかな笑い声が、耳元に甘くやわらかく届いた。