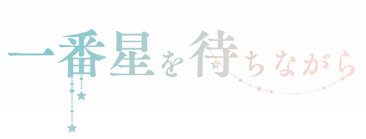
第4話 夕さりに知る星の宿り
「できれーす、とは何ですか?」
始める前から結果の分かっている勝負や競争。つまり、出来の良いレース。
不届きなことを言ったのは誰なのだろうか。そう思うよりも早く脳裏に浮かんだのは、模範的な解答だった。
光都リータスから王都エセルに最近戻ったばかりの少女は、王都ならではの特別なイベントか何かだろうと解釈をしたようだ。どんなお祭りなのですか、と無邪気に首を傾げてくる。
ベルマ・シュプリーム。シュプリーム侯爵家の令嬢で、シュプリーム宰相閣下の末の孫娘だ。バーナテッド・シュプリーム氏はラグランドの祖父であるアルカディア国王の懐刀であり、親友としても名高い男である。
そんなこの少女は、男の子の孫ばかりに恵まれたシュプリーム侯爵家と、侯爵家と古くから付き合いのあるサージェント王家にとっても希少な女の子、否、愛らしい小さなレディであった。宰相の屋敷にチェスをしに行く祖父に連れられて、ラグランドも何度か会ったことはある。
「何度か」とか、「希少な」等と形容してしまうのにはわけがある。祖父と両親、兄二人、王家の人々からも目に入れても痛くないほどに大切に大切に育てられたそのお姫様は、それはもう大変大人しく、控え目で人見知りたっぷりのレディに成長した。
それで、シュプリーム家のお姫様が直接顔を見せてくれるのは指で数えるほどだったのだ。ラグランドたち兄弟が屋敷へ遊びに行ったときも、祖父君のお供で王宮に来てくれたときも恥ずかしがり屋の少女はなかなか自分から姿を見せてくれなかった。宰相閣下や兄君二人の背から少女の栗色のやわらかそうな髪がふわりと揺れているのを見て、「髪が伸びたなあ」「大きくなったんだなあ」というのをサージェント王家の人々は感慨深く確認をしていたのであった。仕事で光都に赴く父親のブライアン・シュプリーム氏に妻子が付いていき、王都から離れていた期間があったことを差し引いてもお姫様の顔を拝むのは極めて希少な機会であったのだ。「幻の生物を研究するのって、きっとこれくらい難しいことなのでしょうね」と言っていたのは少女と同学年に当たる次弟デイビスである。
そんな引っ込み思案の娘を大人たちは心から案じていたらしい。ブライアン氏の光都での任地は元々八年の予定なのだが、母親のエレイン夫人は娘のベルマ嬢を連れて早く戻ってきた。娘を初等部のうちに王都の女学院に馴れさせるためだった。任期を終えてからでは、初等部の上級学年に食い込む年齢になってしまうからだ。おかげで、父親のブライアン氏は光都と王都を行き来する生活になったようだが、それはそれでちょっとした小旅行気分を味わうことができるとのことで楽しいらしい。
光都リータスは北部の広大で緑豊かな土地だ。王都エセルよりものんびりとした気風でゆったりとした時間が流れる光都は、大人しい少女にもやさしい環境ではあったのだが、その引っ込み思案にますます拍車を掛けたのだという。両親は女学院下級学年のうちに間に合うよう、娘を王都に戻すことを決意した。
「同じ年頃の色々な子と接して、学び舎で共に勉学だけでなく、世の中のことを学ぶ得がたい経験はあなたの今の年頃でないとできないことだから」
エセルの方がリータスよりも人口も子どもの数も圧倒的に多い。年齢が進むにつれて、元々できあがっている輪に外部から新しく合流することは難しくなるものだが、引っ込み思案の娘にとって、同じ年頃の友人を作るのは更なる困難を極めるはずだ、と。だが、子どもの数が多い王都ならば、友人関係の一つや二つや三つ、五つくらい足踏みしたり躓いたりすることがあったとしても、まだ学年が幼い時代の方がより多くの、より新しい次の選択をすることが可能だろう――という両親の教育方針だ。
何故、シュプリーム家の教育方針をラグランドが知っているのかというと、これには長兄レオナードが深く関係する。
ラグランドが大きく言えたことではないが(年上と同学年の女の子との交流はラグランド自身が苦手だし、できることならばやりたくない)、兄レオナードもまたそれほど社交は得意ではないのだ。
祖父や父の右腕として動けるよう勉学に日夜励む後継のレオナードは、実はそれほど器用な性質ではない。そのため社交は最低限の業務しかおこなっていない。
たまに参加する茶会や夜会での交友もビジネスライクな関係ばかりなので羽目を外すことは当然ない。大変立派である。兄は、近頃王都で新星の如く現れたハートリッチだかバードウォッチングだか(なんでも天才若手劇作家でまだうら若き学生らしい)が話題をさらったとかいう、盗んだ馬車で走り出す若さゆえの暴走劇とか何とかは決してしない。苦手を日々のたゆまぬ努力で克服しようとしている。さすが兄上。さす兄である。
しかし、周囲にとっては、幼い頃から王宮でも男子学校でも黙々と勉学に励むレオナード第一王子を立派だと評価する一方、年頃になっても浮いた話が一つもないのは心配の種でもあったようだ。大変余計なお世話である。
あんなに立派な兄が女性陣になんとなく敬遠されているのは、「三国一美しい王子様」がすぐ下の弟で、その麗しすぎる見目と自分とを比べられたらひとたまりもないとかなんとかいう話も一部ではあるようだ。嬉しくない渾名を付けられた本人からしたら実に巨大なお世話である。むしろ、兄の素晴らしさを理解できない者が未来の義姉になるなど言語道断、こちらから願い下げである。
さて、そんな実直な兄に試しに妃候補を立ててみてはどうか、という話が内々で持ち上がった。
第一王子殿下の異性との社交訓練のお相手にふさわしく自身も家も主張の激しくない子女であること、家格と年頃が釣り合うこと、他にも政治的思惑やら家系に親戚、健康調査、その他様々ないわゆる大人の事情やら配慮やらの結果、メッセル侯爵家のベルジーネ嬢、そして、シュプリーム侯爵家のベルマ嬢が候補として立てられた。
候補、といっても世間にはっきりと公表しているわけではない。両者とも善き関係が成就しなかった場合に、兄はともかくとして、候補となった令嬢たちの名誉を徹底的に守るためである。それで、ラグランドたちの祖母である王妃が一肌脱いだ。
若者との交流は六人の男の子の孫ばかりだと日頃から嘆いている王妃殿下が、優秀な若いお嬢さんを話し相手に招き、そのお礼に王室の書庫を案内したり淑女教育をしたり茶を振る舞ったりするサロンならぬ小さなレディたちとの「お勉強会」を始めた。つまり、兄の妃候補ではなく、あくまでも祖母の年の離れた小さな友人として招き始めたということである。多くの少女たちを妃候補に立てなかったのは、隣国の元お姫様でやや内向的な祖母もまた社交を趣味としていたわけではないからだろうと、ラグランドたち兄弟は考えている。
ベルジーネ嬢は兄の一学年上で女学院でも優秀な成績を修めている令嬢らしい。彼女の祖母君は、隣国から嫁いで来たばかりの頃のラグランドたちの祖母イザベル妃を陰に日向にと支えてくれた友人であり、こちらも祖父母とは古くから深い親交がある。祖母としては、友人の自慢の孫娘がこれまた自慢の孫であるレオナードと結ばれたら嬉しくてたまらないものなのだろう。親友同士の子どもたち、または孫たちが両親や祖父母の願いで生まれる前から将来の約束を交わしているというのは、物語の世界では昔から人気の設定なのだ。
兄とは五歳年下のベルマ嬢が立てられたのも、昔から可愛がっているお嬢さん枠なのではないかな、とラグランドは考えている。年単位でしばらく王都を離れていた引っ込み思案の少女が学院の他の友人たちに気後れしないよう、王都での暮らしに早く慣れ親しみ、淑女の知識を得る機会を少しでもあげたいと祖母が声を掛けたことがきっかけらしい。
「そうねえ。レオと二人のどちらかが未来明るい関係になったらとても嬉しいわ。でも、二人とも昔からよく知っているお嬢さん方でしょう? お義母様はお勉強会で孫娘を甘やかすおばあちゃま気分をたっぷり味わいたいそうよ。この頃はレオそっちのけで、あの内気なベルマさんに甘えてもらうにはどうしたらよいかベルジーネさんと二人で燃えていらっしゃるのですって」
と笑っていたのは母で、
「なるほど。希少動物でも王宮に直接呼べば絶対に顔を見られますものね。懐いてもらうには餌付けが一番早い」
と妙に納得していたのは「氷の王子様」こと上の弟デイビスだ。
祖父ほどシュプリーム家に遊びに行く機会がなかった祖母にとっては、孫娘のように慈しんでいるベルマ嬢の顔を見るチャンスはめったになかったのだ。今では祖母が希少ゲストの顔を我が家で一番多く見ているひとだ。
「男の子もいいものだけれど、女の子もいいわねえ。もう可愛くて、可愛くて……」
勉強会の後、祖母はいつも夢見るようにうっとりと息を吐く。
王族の私情が入り乱れすぎているようだが、引っ込み思案の愛娘に家と学院の他にも交流の場が新しくできたことにシュプリーム家の人々は両親をはじめ、皆が歓迎してくれていた。
さて、「出来レース」と囁かれているのは、ベルジーネ嬢に兄レオナードが心を寄せているのが分かりやすいからだ。
兄より一つ年上のベルジーネ嬢には弟が二人いるので包容力もあるのだろう。楚々としたお嬢様然のふるまいの割にはおおらかなひとである。
三人の弟たちにとって誰よりも善き兄であろうとする兄に、己の背を預ける同士も肩の荷を下ろした姿をためらいもなく見せて甘えることができる存在もできたことは大変喜ばしい。そして、初めての恋(たぶん。おそらく。きっと初恋だと思われる)にやや浮かれている兄を見るのはなんだか少々気恥ずかしい。
そして、気恥ずかしいのにはもう一つわけがある。
レオナードを見つめるベルマ嬢の瞳には熱があるのだ。
皆でお茶にしましょうね、と祖母の計らいで「お勉強会」のあとには毎回レオナードも呼び出されている。「だって、こうでもしないとあの子ったら全然お嬢さん方とお喋りしないのよ」とは祖母と母の言い分だ。学院で過ごす時間の他は、分刻みで勉学に励んでいる兄を少しでも息抜きさせる名目もあるようだ。この頃はラグランドもついでに呼ばれることが増えてきた。年長者との接触でお喋りレベルがアップしたラグランドを、口下手な兄の代わりのお喋り係に任命したいのだろう。
真剣コーディネートバトルに巻き込まれたら敵わんと固辞していたのに、その細腕のどこに力があるのか、「こわくない、こわくない」と母に強引に部屋に放り込まれた。どうやら母はラグランドにも同年代との交流の復帰訓練をさせたいらしい。
実際に会ってみたら、ベルジーネ嬢もベルマ嬢も出会い頭にラグランドを飾り立てるコーデバトルをするような厄介なお嬢さんではなかった。二人とも女学院で流行っているカードゲームやボードゲームを親切に丁寧に教えてくれた。二人とも頭の回転が速く、兄もラグランドもいつも苦戦を強いられた。王子相手に手心を加えず、真剣勝負に挑んでくれるのは新鮮で心地が良かった。
この小さな茶会では、一番年少のベルマ嬢を軽んじることなく、誰もが彼女を可愛がった。この場に会する年長者にとって、シュプリーム家のお姫様は特別強いカードであったのだ。
無理もない。ベルマ嬢は、兄にとってもベルジーネ嬢にとっても弟しかいない彼らを惜しみなく無邪気に慕ってくれる初めての年下の女の子なのだ。可愛くないはずがない。妹同然に、否、弟以上に可愛がっている。……これは嫉妬ではない。これっぽっちも。決して。別に。絶対に。
勉強会での一番小さな女の子、というのを差し引いてもベルマ嬢は愛らしかった。大人しくて人見知りが強すぎて引っ込み思案な少女は、警戒心の強い子猫のようだったのだ。
勉強会を始めたばかりの頃は、付き添ってくれたシュプリーム宰相閣下や母君のエレイン夫人の袖を最後まで離そうとしなかった。おかげで祖母もベルジーネ嬢も兄もベルマ嬢の顔と声、ひととなりを知るよりも早く、宰相閣下の好きな夕食のメニュー、夫人の好みの茶と菓子について詳しくなってしまったらしい。小さな茶会に呼ばれるようになったラグランドもまた、少女の好みよりも先に宰相閣下についてまた一つ知識を深めている日々だ。
ベルマ嬢は部屋まで毎回付き添ってくれる家族から離れるのに難儀していた。物陰に隠れずに祖母とベルジーネ嬢、兄や自分に向けて顔と声を出して挨拶をしてくれるようになるまで随分と時間がかかったものだ。
そんな怖がりの子猫のような少女が打ち解けて、初めて笑顔を見せてくれた日の夕食はいつもより豪華だった。子猫の木登り成功を公爵家における特別記念日に制定したグレアムの気持ちがよく分かる、と祖母は喜びいっぱいの叔父を例に出し、青い瞳を潤ませていた。
周囲に愛情をたっぷりと注がれて育った愛らしい子猫を思い出すベルマ嬢の瞳は、ある日を境に、兄レオナードを見つめるときにだけ熱を帯び始めた。
兄に淑女の礼をするとき、兄からその所作にお褒めの言葉をもらったとき、兄が椅子を引いて少女を席に案内し終えたとき、ベルマ嬢は太陽の眩しさに目を細めるようにして、くすぐったそうに笑うのだ。
いつだって真摯で紳士な王子様。いや、正真正銘のこの国の第一王子殿下なのだが。やさしくて、格好良くて、誰よりも努力家である兄の素晴らしさを正しく解する少女がついに世に現れたことは大変喜ばしいし、誇らしい。それこそすぐにでも記念日として制定したいくらいだ。
兄がベルマ嬢を見つめる瞳もとてもやさしい。けれど、そこにはベルマ嬢のそれと同じ熱はない。レオナードのそれは、可愛い妹をどこまでも深く慈しむあたたかさだ。
兄はやさしすぎる。そう、やさしすぎるのだ。それが兄の良いところでもあるが、時にやさしさは相手を何よりも鋭い刃で傷つける。やさしいからこそ、少女もまた期待を抱き、夢を見てしまうのだ。
内々での第一王子妃候補ではあるので、ベルマ嬢にも兄の心を射止めるチャンスがあるはずだ。あるはずなのだが、初めての恋真っ只中の王子様の心は鉄壁だ。よほどのことがない限り、ベルマ嬢が兄の牙城に迫ることは難儀であろう。
質が悪いことに、レオナードもその第一王子妃候補として一応はライバルに当たるベルジーネ嬢もこの年下の少女に甘いのだ。それもとびきり。どうしたらこの少女が自分たちのことを「お兄様」「お姉様」と呼び慕ってくれるのか、二人で真剣に作戦会議をしているくらいには。
ベルマ嬢も二人のことを心から慕っている。ラグランドは見ていて居たたまれないものがあるのだが、妃候補はあくまでも内々での話であるので口を挟むことはできない。シュプリーム侯爵家にとっても、末の娘が、第一王子とその候補の令嬢を兄と姉のように心から慕い、生き生きと王宮で過ごせる時間があるのはよかろうの姿勢なのかもしれない。
ラグランドはこの「お勉強会」にもベルマ嬢の初恋の行方についても口を挟むことはできない。けれども、叔父の家の子猫のように、ようやく懐いてくれた愛らしい少女が傷ついてしょんぼりする姿は見たくないな、と思っている。
どう説明したものかな、と考えあぐねていたら、聞こえていなかったと思われていたらしい。もう一度「できれーすとは何ですか?」と質問された。
「……そうだなあ、それはそれは見事に綺麗な仕上がりのレース」
であったらいいのにねえ、と胸中でこっそり付け加えた。
「とても美しいレース飾りのことなのですね。殿下はご覧になったことがありますか?」
「……いや、ないなあ。まだ」
肩をすくめかけたラグランドは、息を呑んだ。少女が笑ったのだ。黄昏の空に蜂蜜を溶かした色彩の瞳を蕩けさせて。
兄や祖母たちの前では緊張するのか、いつもはほのかに頬を緩めるだけで精一杯の侯爵家の末のレディが屈託なく笑う姿を、ラグランドは初めて見た。
「では、私がいつかご覧に入れられるかもしれません」
「うーん」
「そこは長音になさらなくて良いところだと存じます」
「うーん……」
急に飛び込んできた少女の笑顔と冗談に取り繕う余裕なく、ラグランドの目線が落ちた。
大きな刺繍枠が囲っているのは、ステッチの大きさが自由自在で、糸の長さも緩さもどこまでも伸び伸びとした――まだたどたどしい刺繍だった。
「わ!?」
ベルマ嬢は素早く刺繍枠を後ろ手に隠し、顔を俯けた。少しだけ見えた小さな指先は、絆創膏がいくつも巻かれていた。
栗色の髪がさらさらと落ちて小さな頬を覆う。ちょこんと見える耳と頬が朱く染め上がっていた。林檎のように。
「……その、なんだ、伸びしろがあるのは良いことだよレディ」
こくん、とベルマ嬢は頷いてくれた。けれども、昔からよく知る恥ずかしがり屋の少女が持つ二つの黄昏空は、その日、隠れたままだった。