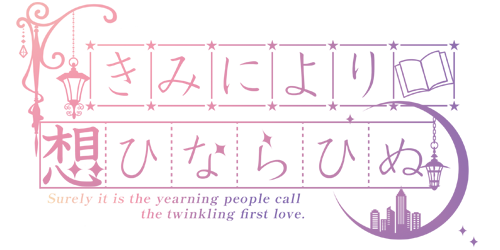空が、広い。
青く澄み渡り、白い雲が濃く白く大きく遠くに浮かんでいる。赤、橙、黄に染まり始めた稜線も街並みも三門市で見えるそれよりも、はるかに遠い。
朗らかな声が風に乗って届く。
「はいはい。おふたりさん、笑って笑って!」
ファインダーの越しに、北見茉椰が口角を大きく吊り上げている。チェシャ猫のように。にんまりと。
北海道である。古来より「北海道はでっかいどう」とはよく言ったもので、広い。とにかく広い。初めて上陸し、目で見て音を聞き肌で感じる風光明媚な土地にも、肥沃な大地と広い海に育まれた多彩な食文化にもその美味しさにもひたすら圧倒され続けた北海道修学旅行も今日が最終日である。
「こらこら真澄! 息止めない! 変顔になるでしょうが! ほら吸って! 吐いて!」
茉椰がこちらになにやら声をかけてくるが、真澄にはもはやそれどころではない。それどころではないのだ。目下、宇田川真澄が一年生の頃から紫のバラのひとになりたいと願ってやまないひと――歌川遼そのひとが真澄の隣に立ち、微笑んでいらっしゃるのだ。心臓の瞬間打鍵最高速度を更新しそうである。どきどき。どくどく。どんどん。どっどど どどうど どどうど どどう! と鳴り響く鼓動が、音漏れしているのではないか、気が気ではない。
「北見さん、タイム」
「歌川名人も甘やかさない! 撮れ高足りてないんだから!」
茉椰が文字通り目を三角に吊り上げながら叫び返してくる――
それを受け流すように歌川は眉を下げて笑いかけてきた。
「さすが炎の写真部兼アルバム委員。情熱がすごいな……」
真澄もコクコクうなずき返す。今日の茉椰の気迫はとにかくすごい。ひたすらにすごい。
写真部に所属する茉椰は、ファインダー越しに見る世界に青春を捧げてきた少女だ。一年次にクラス委員長以外の係と委員会をくじ引きで決め、二年次もほぼそのまま引き継ぐことをよしとした我らがC組であるが、アルバム委員を一年次に見事に引き当てた茉椰は「重すぎる……」と喜ぶどころか戸惑いを覚えていた。高校生活の思い出あんなものこんなものそんなもの全部がぎゅうぎゅうに詰まった卒業アルバム。その貴重で大事な一瞬を切り取る係を拝命するには若輩者の己には荷が重い、と。それくらい彼女は写真に情熱を注いでいるのだ。
そう。修学旅行である。
高校生活三大煌めき山場のひとつである。ちなみにあとの二つは体育祭と文化祭だ。(炎の写真部部員兼アルバム委員調べ)
歌川遼への憧れをあたため続けた真澄は勇気を振り絞って彼と同じ班に――なることはなかった。日々の挨拶をするだけでも一日分の勇気をありったけ全部かき集めないと声をかけられないのだ。そんな勇気があれば、毎朝教室に入る前に心の中で独りスクラムを組み深呼吸を繰り返すなどしない。
班分けが決まった後、友人――今年も無事に同じクラスになった北見茉椰も市川あゆみも、図書委員会の同僚にしてツッコミの名人菊地原士郎プロも「何故ベストを尽くさないのか!?」と顔にも口にも出したものの、「まあ、緊張しすぎで前日眠れなくて当日寝坊するよりずっとマシだよね」と腕組みしながら神妙な表情で一様にうなずいていた。
「これよりプランBに移行する。名付けて、卒アル大作戦」
そこで、一肌脱いだのは、炎の写真部エースにしてアルバム委員の北見茉椰だ。
曰く、「真澄から歌川くんに『写真一緒に撮ろ☆』言うのは無理でしょ。言えたら修学旅行で雨が降る。嵐になる。まあ、ここは私に任せなさいな。大船に乗ったつもりでどかーん!」だ。ちなみに「大丈夫? その船、座礁してない?」と醒めた口調で指摘を入れてくれたのは菊地原プロである。いつでもどこでも誰にでも丁寧に的確にツッコミを入れてくれる彼の仕事の流儀は、常に情熱大陸である。
少年よ、大志を抱け――
北海道開拓の父ウィリアム・スミス・クラーク博士はそう仰った。
その偉大なる父を彫った像の前で。北見茉椰は宣言した。
「ここを『どっちが歌川☆宇田川SHOW!』のキャンプ地とする!」
どちらが歌川で宇田川なのか。偶然にも苗字の響きが似た少年と少女は、同じクラスになって以来、隣の席になって以降、クラスメイトも教科担任をも混乱の海に引きずり落としてきた。……実害は、前任の日直が日誌と黒板に次の当番者名を書く際に書き間違えやすい程度ではあるが。両者とも交えて会話するときに「どちらに濁点がいるのか、いらないのか。ややこしや」という苦情はたまに寄せられるレベルではあるが。
卒業アルバムにはふたり並んだ写真コーナーを設け、どちらが歌川でどちらが宇田川なのか。アルバムを見たC組生以外の者を混沌に引きずり込む! という魂胆らしい。
「学年企画『五等分の佐藤め』があるならば、クラス企画もあって然るべき」
『五等分の佐藤め』とは、学年に五人いる佐藤氏を集めた卒業アルバム合同企画だ。
「そういうわけで協力を要請する」
茉椰は左腕に着けた臙脂色のアルバム委員腕章を掲げると、目をきらきらさせて身を乗り出してきた。カメラを構え、なにやら笑みを浮かべている。
「はいはい。おふたりさん、笑って笑って!」
自分から同じ班に誘う勇気も度胸もなかったのに、誘われる自信も驕傲も持っていなかったけれど、歌川と同じ空の下でふたり笑い合う写真が残る――
胸が、きゅう、となった。
「炎のアルバム委員様のお達しだ。宇田川さん、がんばろうな」
すぐ隣から届けられた笑顔がまぶしい。熱血! 炎のアルバム委員塾のひとから、ふたりは何度も何回もポーズにも笑顔にもダメ出しをされ続けている。今もクラーク博士と同じ「遙か彼方にある永遠の真理」を指すポーズを取るよう熱い指導が入っている。「真澄、あと二センチ右に寄って!」「歌川名人! 左上方向に顔をあと〇.四度上げて! そう、それ。よし!」などなど。それでもなお、歌川は疲れなど見せず苛立ちもせず、ただ爽やかな笑みをたたえていた。そのうえ、すぐ隣で、真澄を緊張させないように時々声までかけてくれている。
歌川くんスマイルの一日の摂取量、そろそろ超えたのでは――
体感温度が更に五度はアップした。そろそろ頭から立ち上る湯気が写真に残りそうである。真澄の心臓はますます激しく熱いビートを刻み続けた。
「うるさ……」
こちらを眺めながらメロンミックスソフトクリームに舌鼓を打っている菊地原が、なにやら顔をしかめるのが見えた。
秋の空は高い。うつくしい紺碧の天井は、他のどのような季節の空よりもはるか遠くまで澄んでいる。
見上げた空には大きな白い雲が競うように連なっている。空と雲の陰影コントラストは、夏の頃よりも強くはない。ふわふわと並ぶ雲は、刈り取られる羊毛のようでなんだか微笑ましい。先月の修学旅行で眺めた羊の群れを思い出し、頬が緩む。
空気が透き通っている。そう表すのが一番、秋の大気にはふさわしい。夏の靄は消え、何もかもが澄んで色濃く見える気がする。
朝方に止んだ雨が残した水たまりに映る自身を見下ろして、少女の唇が緩んだ。寝癖もないし、ネクタイも忘れていないし、形良く結べている。と――
とっ、とっ、と頭の上で音が跳ねる。
雨が落ちてきた。慌てずに鞄から折り畳み傘を取り出す。「ねえ、傘は持った? 木虎さんが『朝は傘があると安心です』と教えてくれたわよ! 今!」と出掛けに祖母から言われ、準備していたものだ。おっとりしている祖母にしてはなにやら慌てた口調だった。その血を色濃く受け継いでいるのんびり屋の父も「それは大変」と食パンを咀嚼しながら傘立てから鉄紺色の傘を取り出していた。こうかはばつぐんだ!
家でトラブルがあったというわけではない。家族そろって寝坊したわけでもない。祖母はボーダーの〝ご贔屓さん〟こと木虎藍さんの朝の情報番組ゲスト出演録画に朝から忙しかったのである。なんでも今日は、老舗和菓子店「鹿のや」の秋季限定品を木虎さん(と嵐山隊の皆さん)がリポートをしてくれるのだという。予約録画の準備は先週から入念にしていたようだが、真剣な顔つきで番組開始前から録画レコーダーの動作をチェックしていた。備えあれば憂いなし。
木虎さんの言う通り、雨が降った。清々しい晴天から一転、またもや傘を差すはめになったが、自分の傘を見上げて真澄は頬を緩める。菫色のその傘は、ほのかに青みが強く、赤と青の溶け合うトーンが綺麗なのでお気に入りのものなのだ。
朝から雨だというのに口笛まで吹いてしまいたくなるくらい気分が良い。くるくる傘の柄を回しながら足取りも軽く歩いていると、後ろから聞き覚えのある声が聞こえた。
「宇田川さん」
びっくりして少女は立ち止まり、全身で振り返る。くるりと。
「う、たがわくん……」
留紺色の傘を差した歌川遼が立っていた。
「おはよう」
「お、おはよう」
こんな時間にこんなところで彼に逢えるとは思ってもみなかった真澄は動揺する。去年の五月からひともすなる朝読書というものを始めて以来、登校時間を早めるようになったが、歌川はさすがと言うか然も有りなんと言うべきか、真澄よりも早く登校していることが多いのだ。教室の外で会うのは新鮮だ。新しい朝が来た! 希望の朝だ! freshだ! 非常にとてつもなくべらぼうな勢いで新鮮だ。今週分の幸運を使い果たしたかもしれない。
歌川は空を見上げて、「予報通りとはいえ、せめて教室に着いてから降り出して欲しかったよな」と眉を下げた。少し拗ねたような言葉が可愛い。しかし、切れ長の瞳はいつも通り爽やかな笑みをたたえている。
真澄もコクコクコクコクうなずいた。上機嫌で高らかに口笛――日曜朝の戦隊ヒーロー番組テーマ曲――を吹きながらスキップしていたところを目撃されたのが恥ずかしいし、それを指摘したり茶化したりからかったりしない歌川のベリージェントルソウルぶりにも感激するし、何よりも朝一番に逢えたのが歌川であるのが嬉しくてたまらない。〝歌川くん基金〟が今日も元気に捗ってしまう! とにかく胸がいっぱいで最適解の言葉を弾き出せなかったのだ。
小さな雨粒が傘に当たる音がする。一定のリズムを保って落ちる地面の雨をそっと弾きながら、ふたりは並んで歩き始めた。
昼には雨が上がりその後は穏やかな秋晴れが週末まで続くこと(木虎さん情報)、三時限目の体育は体育館でマラソン練習になるだろうこと、六時限目の英単語小テストのこと。それから可愛い小学三年生の弟と柴犬の最近の様子。
歌川の会話サーブにつっかえながらもラリーを続ける真澄に、彼は微笑んで耳を澄ませてくれている。
ふ、と天使が通った。どちらからともなく、会話ラリーが切れたのだ。
真澄は傘を少し上げる。
雨に煙る街の景色からは、夏の気配は完全に消え失せ、秋の輪郭も匂いも濃くなってきている。街路樹の木々の葉が紅く、あるいは黄色く色づき始めるにはまだ早く、けれども夏の頃の萌え立つ緑のくっきりとした鮮やかさはもうない。
地面に落ちる影が薄いのを見て、しんとした空気を吸い込むたび、真澄は秋を実感する。秋深き隣は何をする人ぞ、と芭蕉の一句を胸中で呟きながら。
雨音を聞き、深まる秋を感じながら、沈黙も共有している――
胸が熱い。頬がどんどん朱く染まるのを自覚し、真澄は大きく息をついた。大きく吸って、大きく出して。もう一度吸い、震える唇を開いた。
「歌川くん」
「うん」
「この前の文化祭、観に来てくれてありがとう」
噛みしめるように、真澄は声に乗せる。
六頴館高校の文化祭は先週終わった。特に大きなトラブルもなく、晴天にも恵まれ、惜しまれながら幕を下ろした。
書道部レギュラーの真澄もまた、他の部員同様に粛々と作品展示に取り組んだのだ。
お祭りムードいっぱいに飾り付けられた賑やかな廊下の奥。三年生の校舎最上階、最果ての地にある書道室は、大いに盛り上がる地上とは少しだけ離れているからか、静かだった。真澄の作品を観に来てくれた友人のあゆみも茉椰も「まるで神社の如き静謐感」「汚れつちまつた悲しみも心も洗われるようだ」「拝んどこ」「なむなむ!」などとうなずき、展示作品の前で二礼二拍手一礼していたほどだ。
六頴館高校の書道部は、かの書道パフォーマンス甲子園を目指して日夜練習に励む活動はしていない。栄光の架け橋は見えないかもしれない。華々しさはないかもしれない。けれども、部員全員それぞれが紙にまっすぐ向かい、毛筆と墨を用いて黒と白のコントラストに挑んでいる。従来の書道の形に囚われることなく、文字を自由に表現することを楽しんでいるのだ。
好きな漢詩に和歌。ぐっと来た漫画や小説、ドラマに映画の台詞。部員それぞれが一筆一筆に、とめ・はね・はらいに想いも魂も込めた作品の集大成。その展示を、歌川遼も観に来てくれたのだ。
あゆみと茉椰に倣い、二礼二拍手一礼しようとしたそのひとを刮目した真澄の心臓は停止した。「う、歌川くん!? おやめくださいおやめください!」とつっかえながらも声を出せたあの日の自分を今でも褒めたいくらいだ。自分の作品を彼に拝ませるだなんてとんでもない! どう振り返ってもお忍びで城下に降りた若君を諫める爺やの口調になってしまったが、歌川くん参拝事件は未遂に終わった。めでたしめでたし。
「どういたしまして。宇田川さんの展示、綺麗だったなあ」
真澄が展示した作品のひとつは、心の師匠にして平安朝のイタリア男・在原業平の和歌だ。彼が紀有常 の家を訪ねたときに詠んだという、『伊勢物語』は第三十八段のものだ。屈託のない友人同士のやりとりが楽しくて、選んだのだ。
「ありがとう。歌川くんは、やさしいね……」
ふ、と留紺色の幕が上がった。歌川が大きく傘を上げたのだ。身をかがめて、真澄の顔を覗き込んだ。雨音で聞こえなかったのかもしれない。その近さにどきどきする。そのひとの切れ長の瞳をまっすぐと見上げ、もう一度、告げる。歌川くんはやさしいね、と。
「……そういうことにしておこうか。今は」
雨は変わらずやさしく降り続いている。雨粒は、ずっと一定のリズムを刻んでいる。曲を奏でているようだった。それに合わさるように聞こえたそのひとの声に、少女は一瞬、周りの風景が、音が、すべて消えてしまったように感じた。
「――え?」
そのひとは微笑んで、骨ばった長い指で、「どんぐり発見」と指差した。小学三年生の弟を中心に最近の宇田川家の通貨がどんぐりとなっていることは、先ほど彼に話したばかりだ。
「遼太も太郎も大喜びしそうだな」
大きくて丸いどんぐりを彼は拾い、ポケットから取り出したハンカチで拭いた。それから手をこちらに向かって差し出す。
ぱちぱちとまばたきを繰り返す真澄に笑うと、彼は、こちらの左手を取った。手のひらにころんと転がったのは、つやつや輝く丸々とした立派などんぐりで。そっと触れて温もりを伝えてくれたのは、彼の長くて筋張った指だった。それは細かな雨でしっとり濡れているのに、あたたかかった。手のひらから伝わる熱を理解した途端、少女は、呼吸を忘れた。礼を言うのも忘れた。できたのは、彼をまっすぐ見上げることだけだった。
空の端から、陽光が降りてきた。まもなく通り雨は止むようだ。朝の光が、歌川の笑顔とどんぐりを明るく照らしている。
彼は、まぶしい。まぶしくて、手を伸ばせない。そんな気持ちを、彼は知る由もないのだろう。
その笑顔を目で追いながら、真澄は胸を押さえた。なんとか出せた「ありがとう」の声は、やはり震えていた。
教室の外で彼と長い時間、話をする権利も関係も約束も持っているわけではない少女にとって、今朝は忘れられない秋の思い出となるだろう。
雨脚が、少し弱くなっている。代わりに雨音よりも真澄の心臓が激しく跳ねていた。
強く、強く、胸にビートが刻まれていく。
傘を揺らせば、雫が束になって落ちた。どんぐりをブレザーのポケットに仕舞う。そして、震える指先で柄を握り直す。ぎゅう、と。
まっすぐに空から滴る十一月の雨。雨粒は、アスファルトを、秋に包まれた街を、そして、真澄の想いにもやさしく降りかかっている。
蓋をしないと、すべてあふれてしまいそうだった。
君により思ひならひぬ世の中の人はこれをや恋といふらむ
展示作品前で目を細めたそのひとの横顔。雨の朝、すぐ隣で歩くそのひとの穏やかな微笑み。まぶしくて、まぶしくて、たまらなかった。
朱く染まった顔を、傘が隠してくれている。
雨が、少し、好きになれそうな気がした。
青く澄み渡り、白い雲が濃く白く大きく遠くに浮かんでいる。赤、橙、黄に染まり始めた稜線も街並みも三門市で見えるそれよりも、はるかに遠い。
朗らかな声が風に乗って届く。
「はいはい。おふたりさん、笑って笑って!」
ファインダーの越しに、北見茉椰が口角を大きく吊り上げている。チェシャ猫のように。にんまりと。
北海道である。古来より「北海道はでっかいどう」とはよく言ったもので、広い。とにかく広い。初めて上陸し、目で見て音を聞き肌で感じる風光明媚な土地にも、肥沃な大地と広い海に育まれた多彩な食文化にもその美味しさにもひたすら圧倒され続けた北海道修学旅行も今日が最終日である。
「こらこら真澄! 息止めない! 変顔になるでしょうが! ほら吸って! 吐いて!」
茉椰がこちらになにやら声をかけてくるが、真澄にはもはやそれどころではない。それどころではないのだ。目下、宇田川真澄が一年生の頃から紫のバラのひとになりたいと願ってやまないひと――歌川遼そのひとが真澄の隣に立ち、微笑んでいらっしゃるのだ。心臓の瞬間打鍵最高速度を更新しそうである。どきどき。どくどく。どんどん。どっどど どどうど どどうど どどう! と鳴り響く鼓動が、音漏れしているのではないか、気が気ではない。
「北見さん、タイム」
「歌川名人も甘やかさない! 撮れ高足りてないんだから!」
茉椰が文字通り目を三角に吊り上げながら叫び返してくる――
それを受け流すように歌川は眉を下げて笑いかけてきた。
「さすが炎の写真部兼アルバム委員。情熱がすごいな……」
真澄もコクコクうなずき返す。今日の茉椰の気迫はとにかくすごい。ひたすらにすごい。
写真部に所属する茉椰は、ファインダー越しに見る世界に青春を捧げてきた少女だ。一年次にクラス委員長以外の係と委員会をくじ引きで決め、二年次もほぼそのまま引き継ぐことをよしとした我らがC組であるが、アルバム委員を一年次に見事に引き当てた茉椰は「重すぎる……」と喜ぶどころか戸惑いを覚えていた。高校生活の思い出あんなものこんなものそんなもの全部がぎゅうぎゅうに詰まった卒業アルバム。その貴重で大事な一瞬を切り取る係を拝命するには若輩者の己には荷が重い、と。それくらい彼女は写真に情熱を注いでいるのだ。
そう。修学旅行である。
高校生活三大煌めき山場のひとつである。ちなみにあとの二つは体育祭と文化祭だ。(炎の写真部部員兼アルバム委員調べ)
歌川遼への憧れをあたため続けた真澄は勇気を振り絞って彼と同じ班に――なることはなかった。日々の挨拶をするだけでも一日分の勇気をありったけ全部かき集めないと声をかけられないのだ。そんな勇気があれば、毎朝教室に入る前に心の中で独りスクラムを組み深呼吸を繰り返すなどしない。
班分けが決まった後、友人――今年も無事に同じクラスになった北見茉椰も市川あゆみも、図書委員会の同僚にしてツッコミの名人菊地原士郎プロも「何故ベストを尽くさないのか!?」と顔にも口にも出したものの、「まあ、緊張しすぎで前日眠れなくて当日寝坊するよりずっとマシだよね」と腕組みしながら神妙な表情で一様にうなずいていた。
「これよりプランBに移行する。名付けて、卒アル大作戦」
そこで、一肌脱いだのは、炎の写真部エースにしてアルバム委員の北見茉椰だ。
曰く、「真澄から歌川くんに『写真一緒に撮ろ☆』言うのは無理でしょ。言えたら修学旅行で雨が降る。嵐になる。まあ、ここは私に任せなさいな。大船に乗ったつもりでどかーん!」だ。ちなみに「大丈夫? その船、座礁してない?」と醒めた口調で指摘を入れてくれたのは菊地原プロである。いつでもどこでも誰にでも丁寧に的確にツッコミを入れてくれる彼の仕事の流儀は、常に情熱大陸である。
少年よ、大志を抱け――
北海道開拓の父ウィリアム・スミス・クラーク博士はそう仰った。
その偉大なる父を彫った像の前で。北見茉椰は宣言した。
「ここを『どっちが歌川☆宇田川SHOW!』のキャンプ地とする!」
どちらが歌川で宇田川なのか。偶然にも苗字の響きが似た少年と少女は、同じクラスになって以来、隣の席になって以降、クラスメイトも教科担任をも混乱の海に引きずり落としてきた。……実害は、前任の日直が日誌と黒板に次の当番者名を書く際に書き間違えやすい程度ではあるが。両者とも交えて会話するときに「どちらに濁点がいるのか、いらないのか。ややこしや」という苦情はたまに寄せられるレベルではあるが。
卒業アルバムにはふたり並んだ写真コーナーを設け、どちらが歌川でどちらが宇田川なのか。アルバムを見たC組生以外の者を混沌に引きずり込む! という魂胆らしい。
「学年企画『五等分の佐藤め』があるならば、クラス企画もあって然るべき」
『五等分の佐藤め』とは、学年に五人いる佐藤氏を集めた卒業アルバム合同企画だ。
「そういうわけで協力を要請する」
茉椰は左腕に着けた臙脂色のアルバム委員腕章を掲げると、目をきらきらさせて身を乗り出してきた。カメラを構え、なにやら笑みを浮かべている。
「はいはい。おふたりさん、笑って笑って!」
自分から同じ班に誘う勇気も度胸もなかったのに、誘われる自信も驕傲も持っていなかったけれど、歌川と同じ空の下でふたり笑い合う写真が残る――
胸が、きゅう、となった。
「炎のアルバム委員様のお達しだ。宇田川さん、がんばろうな」
すぐ隣から届けられた笑顔がまぶしい。熱血! 炎のアルバム委員塾のひとから、ふたりは何度も何回もポーズにも笑顔にもダメ出しをされ続けている。今もクラーク博士と同じ「遙か彼方にある永遠の真理」を指すポーズを取るよう熱い指導が入っている。「真澄、あと二センチ右に寄って!」「歌川名人! 左上方向に顔をあと〇.四度上げて! そう、それ。よし!」などなど。それでもなお、歌川は疲れなど見せず苛立ちもせず、ただ爽やかな笑みをたたえていた。そのうえ、すぐ隣で、真澄を緊張させないように時々声までかけてくれている。
歌川くんスマイルの一日の摂取量、そろそろ超えたのでは――
体感温度が更に五度はアップした。そろそろ頭から立ち上る湯気が写真に残りそうである。真澄の心臓はますます激しく熱いビートを刻み続けた。
「うるさ……」
こちらを眺めながらメロンミックスソフトクリームに舌鼓を打っている菊地原が、なにやら顔をしかめるのが見えた。
秋の空は高い。うつくしい紺碧の天井は、他のどのような季節の空よりもはるか遠くまで澄んでいる。
見上げた空には大きな白い雲が競うように連なっている。空と雲の陰影コントラストは、夏の頃よりも強くはない。ふわふわと並ぶ雲は、刈り取られる羊毛のようでなんだか微笑ましい。先月の修学旅行で眺めた羊の群れを思い出し、頬が緩む。
空気が透き通っている。そう表すのが一番、秋の大気にはふさわしい。夏の靄は消え、何もかもが澄んで色濃く見える気がする。
朝方に止んだ雨が残した水たまりに映る自身を見下ろして、少女の唇が緩んだ。寝癖もないし、ネクタイも忘れていないし、形良く結べている。と――
とっ、とっ、と頭の上で音が跳ねる。
雨が落ちてきた。慌てずに鞄から折り畳み傘を取り出す。「ねえ、傘は持った? 木虎さんが『朝は傘があると安心です』と教えてくれたわよ! 今!」と出掛けに祖母から言われ、準備していたものだ。おっとりしている祖母にしてはなにやら慌てた口調だった。その血を色濃く受け継いでいるのんびり屋の父も「それは大変」と食パンを咀嚼しながら傘立てから鉄紺色の傘を取り出していた。こうかはばつぐんだ!
家でトラブルがあったというわけではない。家族そろって寝坊したわけでもない。祖母はボーダーの〝ご贔屓さん〟こと木虎藍さんの朝の情報番組ゲスト出演録画に朝から忙しかったのである。なんでも今日は、老舗和菓子店「鹿のや」の秋季限定品を木虎さん(と嵐山隊の皆さん)がリポートをしてくれるのだという。予約録画の準備は先週から入念にしていたようだが、真剣な顔つきで番組開始前から録画レコーダーの動作をチェックしていた。備えあれば憂いなし。
木虎さんの言う通り、雨が降った。清々しい晴天から一転、またもや傘を差すはめになったが、自分の傘を見上げて真澄は頬を緩める。菫色のその傘は、ほのかに青みが強く、赤と青の溶け合うトーンが綺麗なのでお気に入りのものなのだ。
朝から雨だというのに口笛まで吹いてしまいたくなるくらい気分が良い。くるくる傘の柄を回しながら足取りも軽く歩いていると、後ろから聞き覚えのある声が聞こえた。
「宇田川さん」
びっくりして少女は立ち止まり、全身で振り返る。くるりと。
「う、たがわくん……」
留紺色の傘を差した歌川遼が立っていた。
「おはよう」
「お、おはよう」
こんな時間にこんなところで彼に逢えるとは思ってもみなかった真澄は動揺する。去年の五月からひともすなる朝読書というものを始めて以来、登校時間を早めるようになったが、歌川はさすがと言うか然も有りなんと言うべきか、真澄よりも早く登校していることが多いのだ。教室の外で会うのは新鮮だ。新しい朝が来た! 希望の朝だ! freshだ! 非常にとてつもなくべらぼうな勢いで新鮮だ。今週分の幸運を使い果たしたかもしれない。
歌川は空を見上げて、「予報通りとはいえ、せめて教室に着いてから降り出して欲しかったよな」と眉を下げた。少し拗ねたような言葉が可愛い。しかし、切れ長の瞳はいつも通り爽やかな笑みをたたえている。
真澄もコクコクコクコクうなずいた。上機嫌で高らかに口笛――日曜朝の戦隊ヒーロー番組テーマ曲――を吹きながらスキップしていたところを目撃されたのが恥ずかしいし、それを指摘したり茶化したりからかったりしない歌川のベリージェントルソウルぶりにも感激するし、何よりも朝一番に逢えたのが歌川であるのが嬉しくてたまらない。〝歌川くん基金〟が今日も元気に捗ってしまう! とにかく胸がいっぱいで最適解の言葉を弾き出せなかったのだ。
小さな雨粒が傘に当たる音がする。一定のリズムを保って落ちる地面の雨をそっと弾きながら、ふたりは並んで歩き始めた。
昼には雨が上がりその後は穏やかな秋晴れが週末まで続くこと(木虎さん情報)、三時限目の体育は体育館でマラソン練習になるだろうこと、六時限目の英単語小テストのこと。それから可愛い小学三年生の弟と柴犬の最近の様子。
歌川の会話サーブにつっかえながらもラリーを続ける真澄に、彼は微笑んで耳を澄ませてくれている。
ふ、と天使が通った。どちらからともなく、会話ラリーが切れたのだ。
真澄は傘を少し上げる。
雨に煙る街の景色からは、夏の気配は完全に消え失せ、秋の輪郭も匂いも濃くなってきている。街路樹の木々の葉が紅く、あるいは黄色く色づき始めるにはまだ早く、けれども夏の頃の萌え立つ緑のくっきりとした鮮やかさはもうない。
地面に落ちる影が薄いのを見て、しんとした空気を吸い込むたび、真澄は秋を実感する。秋深き隣は何をする人ぞ、と芭蕉の一句を胸中で呟きながら。
雨音を聞き、深まる秋を感じながら、沈黙も共有している――
胸が熱い。頬がどんどん朱く染まるのを自覚し、真澄は大きく息をついた。大きく吸って、大きく出して。もう一度吸い、震える唇を開いた。
「歌川くん」
「うん」
「この前の文化祭、観に来てくれてありがとう」
噛みしめるように、真澄は声に乗せる。
六頴館高校の文化祭は先週終わった。特に大きなトラブルもなく、晴天にも恵まれ、惜しまれながら幕を下ろした。
書道部レギュラーの真澄もまた、他の部員同様に粛々と作品展示に取り組んだのだ。
お祭りムードいっぱいに飾り付けられた賑やかな廊下の奥。三年生の校舎最上階、最果ての地にある書道室は、大いに盛り上がる地上とは少しだけ離れているからか、静かだった。真澄の作品を観に来てくれた友人のあゆみも茉椰も「まるで神社の如き静謐感」「汚れつちまつた悲しみも心も洗われるようだ」「拝んどこ」「なむなむ!」などとうなずき、展示作品の前で二礼二拍手一礼していたほどだ。
六頴館高校の書道部は、かの書道パフォーマンス甲子園を目指して日夜練習に励む活動はしていない。栄光の架け橋は見えないかもしれない。華々しさはないかもしれない。けれども、部員全員それぞれが紙にまっすぐ向かい、毛筆と墨を用いて黒と白のコントラストに挑んでいる。従来の書道の形に囚われることなく、文字を自由に表現することを楽しんでいるのだ。
好きな漢詩に和歌。ぐっと来た漫画や小説、ドラマに映画の台詞。部員それぞれが一筆一筆に、とめ・はね・はらいに想いも魂も込めた作品の集大成。その展示を、歌川遼も観に来てくれたのだ。
あゆみと茉椰に倣い、二礼二拍手一礼しようとしたそのひとを刮目した真澄の心臓は停止した。「う、歌川くん!? おやめくださいおやめください!」とつっかえながらも声を出せたあの日の自分を今でも褒めたいくらいだ。自分の作品を彼に拝ませるだなんてとんでもない! どう振り返ってもお忍びで城下に降りた若君を諫める爺やの口調になってしまったが、歌川くん参拝事件は未遂に終わった。めでたしめでたし。
「どういたしまして。宇田川さんの展示、綺麗だったなあ」
真澄が展示した作品のひとつは、心の師匠にして平安朝のイタリア男・在原業平の和歌だ。彼が
「ありがとう。歌川くんは、やさしいね……」
ふ、と留紺色の幕が上がった。歌川が大きく傘を上げたのだ。身をかがめて、真澄の顔を覗き込んだ。雨音で聞こえなかったのかもしれない。その近さにどきどきする。そのひとの切れ長の瞳をまっすぐと見上げ、もう一度、告げる。歌川くんはやさしいね、と。
「……そういうことにしておこうか。今は」
雨は変わらずやさしく降り続いている。雨粒は、ずっと一定のリズムを刻んでいる。曲を奏でているようだった。それに合わさるように聞こえたそのひとの声に、少女は一瞬、周りの風景が、音が、すべて消えてしまったように感じた。
「――え?」
そのひとは微笑んで、骨ばった長い指で、「どんぐり発見」と指差した。小学三年生の弟を中心に最近の宇田川家の通貨がどんぐりとなっていることは、先ほど彼に話したばかりだ。
「遼太も太郎も大喜びしそうだな」
大きくて丸いどんぐりを彼は拾い、ポケットから取り出したハンカチで拭いた。それから手をこちらに向かって差し出す。
ぱちぱちとまばたきを繰り返す真澄に笑うと、彼は、こちらの左手を取った。手のひらにころんと転がったのは、つやつや輝く丸々とした立派などんぐりで。そっと触れて温もりを伝えてくれたのは、彼の長くて筋張った指だった。それは細かな雨でしっとり濡れているのに、あたたかかった。手のひらから伝わる熱を理解した途端、少女は、呼吸を忘れた。礼を言うのも忘れた。できたのは、彼をまっすぐ見上げることだけだった。
空の端から、陽光が降りてきた。まもなく通り雨は止むようだ。朝の光が、歌川の笑顔とどんぐりを明るく照らしている。
彼は、まぶしい。まぶしくて、手を伸ばせない。そんな気持ちを、彼は知る由もないのだろう。
その笑顔を目で追いながら、真澄は胸を押さえた。なんとか出せた「ありがとう」の声は、やはり震えていた。
教室の外で彼と長い時間、話をする権利も関係も約束も持っているわけではない少女にとって、今朝は忘れられない秋の思い出となるだろう。
雨脚が、少し弱くなっている。代わりに雨音よりも真澄の心臓が激しく跳ねていた。
強く、強く、胸にビートが刻まれていく。
傘を揺らせば、雫が束になって落ちた。どんぐりをブレザーのポケットに仕舞う。そして、震える指先で柄を握り直す。ぎゅう、と。
まっすぐに空から滴る十一月の雨。雨粒は、アスファルトを、秋に包まれた街を、そして、真澄の想いにもやさしく降りかかっている。
蓋をしないと、すべてあふれてしまいそうだった。
君により思ひならひぬ世の中の人はこれをや恋といふらむ
展示作品前で目を細めたそのひとの横顔。雨の朝、すぐ隣で歩くそのひとの穏やかな微笑み。まぶしくて、まぶしくて、たまらなかった。
朱く染まった顔を、傘が隠してくれている。
雨が、少し、好きになれそうな気がした。