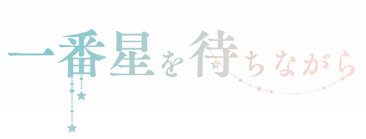
ボーナストラック掌編#10 喜びのときも悲しみのときも
どうやら、美人は三日で飽きる、というものらしい。統計が確かであるのか調べたことはないけれど、少なくとも自分には立証できそうにない。
だって、そのひとは、いくつもの季節を隣で過ごすようになった今でも三国一どころか世界一美しく、とびきり格好良くて、朗らかで清らかで。いつもやさしく、ときどきいじわるで。時折びっくりするほど可愛らしい顔を自分に見せてくれるのだ。自分だけの一番星となってくれたこのひとの煌めきは、色褪せるどころかどんどん輝きが増しているのだ。毎日が発見ばかりで目が離せないし、新しく加わるフレーズもおかわりのリフレインも微笑ましくて、愛らしくて飽きそうにない。どうしたって頬も口角も緩んでしまう。
煌めく金の糸。妖精の職人が月光を厳選して丹精込めて紡いだかの美しさ。ため息も心臓の音も時の流れさえも止めてしまいそうなほど綺麗なそれは、レースカーテンを透かすやわらかな陽光を淡く弾いて周囲に光を散らしている。世のレディたちが幼い頃から何度も読み聞かされ、何度も夢見たであろう物語のお姫様も王子様も王様方も満場総立ちで拍手喝采を送るに違いないほどの、見事な金髪である。何色の絵の具で色を重ね合わせたらこの輝きが生まれるのだろうか。
「ベル」
この美しいひとが身に纏うのは、華やかな飾りを付けた黒を主体とした騎士服だ。
胸を飾るのは、花菱草を象ったブローチで、小さく散らした黄玉が夜空を彩る星のように煌めいている。肩から提げたマントは果てのないスカイブルー。腰に帯びているのは儀式用の絢爛たる剣。
アルカディア王国近衛騎士隊の正装である。
「レディ・ベルマ」
ぴゃっ、とベルマは肩を揺らした。名を、呼ばれていたらしい。
司祭の立ち会いの下、二人で夫婦となる誓いの言葉を交わしたばかりのそのひとが晴れ渡った春の空色の瞳の中にベルマだけを捉えていた。その美しい瞳にまっすぐと見つめられるのは、もう随分と慣れたはずなのに、いつだって心臓の刻むリズムが速くなってしまう。
「そんなに君に熱心に見つめられると穴が空きそうです。いや、おそらく空く。確実に空いてくれ。よし、空くぞ。それはもう蜂の巣もびっくりの大盤振る舞い。そういうわけで、晩餐会は欠席しよう」
上機嫌にのたまうと、そのひとはレモン水を飲み干した。
ぼう、と見蕩れていたのはお見通しだったらしい。さっと目を逸らす。そのひとの小さく笑う声が、ベルマの鼓膜をやわく撫でた。もっとご覧になってぜひとも穴空けにご協力ください、と。
三国一美しいと謳われているこのひとは、茶会も夜会も苦手としているのだ。故に、何かと理由を付けて徹底的に出席を避けていた。
その身分と美しさ故に、古来より巷の小説や舞台で定番の「ドキドキ☆恋の駆け引きバトル」が勃発して毎回主役に抜擢されていたから、というわけではない。このひとを巡り、おはようからお休みまで、髪型も服装も装飾も何もかも、美術館の展示品の如く、お残し禁止の勢いでもりもりきらきら飾り立てられる戦いが頻発してしまうからだという。
この三国一美しい王子様が結婚式で身に纏う礼服を誰がデザインするのか、誰が作るのか、布地はどこが卸すのか問題で、王都エセル、いや、アルカディア王国中が大きく揺れ――はしなかった。
ラグランド第二王子殿下そのひとが強く宣言したからだ。近衛騎士の正装にします、と。
「兄も身に纏ったそれに自分も続きたい」と願い出た兄想いの王子様に国中が微笑んだ。そして、デザイナーと針子と兄王子は泣いた。悲しみと感激で双方の思いは北風と太陽、黄昏と東雲、全くの対極に位置していた。
「特定の職人も店も選ばず、服飾市場の経済を混乱させなかった兄上は実に良いお仕事をなさいましたね」
先ほど挨拶にいらしたデイビス第三王子殿下が青い目を細め、しみじみとそう仰っていた。
ちなみに近衛騎士の人々が、三国一美しい王子殿下が晴れの舞台で纏う前に慌てて正装した姿を恋人や愛娘、孫、両親など大事なひとの前に披露しに行ったと聞いた。曰く、「三国一美しい王子様の御前でこれを着るのは無謀にもほどがある」「己の足の短さが露見してしまう」「度胸試しにもほどがある」「難易度が高すぎてどんな勇者でも詰む」とのことだ。
そんな一コマを思い出し、ベルマは眉の力を抜いた。
「そんなこと仰らないでください」
「君が可愛すぎるのがいけない」
唇を尖らせる王子様――正確には、臣籍降下をなさっているので元王子様だが――にベルマは口角が緩んでしまった。
「花嫁になってくれた君の可憐さを三国中に見せびらかして自慢したいけど、減るから出たくない」
「……減りませんよ」
上気する頬と、干上がりそうな喉をなんとかしたくて、ベルマもレモン水に口を付けた。
花婿の衣装は早馬もびっくりの速度で決まったが、花嫁のものは随分と時間が練られた。
花嫁の注文が多かった、からではない。花婿からの熱心な注文は――いささかあったが、微笑ましい範囲であった。採寸と試着を進めるたびにイザベル王妃殿下とラグランドが画家殿を何度も呼ぼうとしたので少々大変なことになったのは内緒の話だ。
一番時間を注いだのは、サムシングフォーだ。それは、結婚式の日に花嫁が身に着けるといつまでも幸せになれると伝わる四つのものだ。
ラグランドと作戦会議を開き、二人で議論を重ねた。
何か古いものは、かつて祖母と母が纏ったウエディングヴェール。何か新しいものは、祖父と両親から贈られたイヤリング。何か借りたものは、王妃殿下のティアラ。そして、何か青いものは、リボンだ。
ドレスの内側のレースに、青いリボンを縫い付ける。アイテムを決めるのは早かったが、完成までに最も時間を要した。
けれど、それはかけがえのない、特別にいとおしい時間でもあった。
晴れ渡った春の空。ベルマが知る限り、それは、世界でいっとう美しくて果てのないスカイブルーの瞳を持つとても可愛らいひとの色だ。そっくり同じ色のリボンをそのひとと一緒に選ぶのも、それをラグランドと二人で肩を寄せ合って練習を重ねてから縫い付けるのも、何物にも代えがたく、いとおしい時間であったのだ。
澄んだスカイブルーの瞳が眩しげに細められた。
昇る太陽にも道を照らす月光にも喩えられる輝きを持つ金色の眉。瞳に降りた影が大きく見えるのは、淑女の皆さんが羨むほどにその睫毛が長いせいだ。
「ベル」
夫となったばかりのそのひとの声が、やわく耳に届く。
「はい」
呼ばれ、ベルマも微笑んだ。
そのひとは、人差し指を立て、提案した。
「一、左手。二、右手。どちらを握られるのがお好みですか?」
「……どちらかでないといけませんか?」
夫は笑って頷いた。
「難しい質問ですね、レディ」
悪戯に微笑む夫は、ベルマの名をもう一度呼び、丁寧に腰を折った。それから彼はまず左手を取った。
骨張った長くて大きな指が、世界でいっとうやさしくていじわるな指先が、二人だけの永遠のあかしである煌めく左薬指をゆっくりとなぞる。やがて、長い指は彼女の右手も宝物のようにそっと持ち上げると、甘やかに緩やかに絡めた。
絡められた指をベルマも握り返し、力を込めた。ふにゃりと頬が緩むのは止められなかった。
「ベル」
「はい。ラグ様」
喜びのときも悲しみのときも、病めるときも健やかなるときも、富めるときも貧しいときも、愛し、敬い、慈しむ誓いを交わしたそのひとが、ベルマの隣に居てくれている。
どちらかが何かを語らずとも妙な気詰まりはない。いつでも甘やかで楽しく笑い合う会話を交わすわけでもない。身体に触れ合って、ずっと甘え、戯れているわけでもない。沈黙をそっと分かち合う。
けれども、ただ、このひとの隣に居るだけで、胸のうちにはじんわりと温もりが広がっていく。
ベルマにとって、ラグランドとの物語の始まりもそうだったのだ。きっと、物語そのものも、結末も――
二人で手を取り合ったまま窓の外を見る。
天を飾る陽は傾き始め、藍色の帳には一番星が灯ろうとしていた。