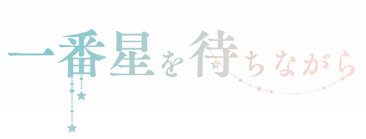
第2話 夕星、まなうらに咲く
ラグランド・S・サージェントの祖父は、このアルカディア国で王杖を掲げることができる、大変やんごとなきひとである。
祖父は国王陛下なのでそれはもう忙しいことこの上ない日々を過ごしている――らしい。推定や伝聞になってしまうのは、ラグランドたち兄弟も王宮に居る時間よりも学校で過ごす時間や就学準備のために講師について勉学に励む時間が長くなってきており、日中の祖父の様子を実際に刮目できているわけではないからだ。
けれども、食事で顔を合わせる際の祖父はいつだって鷹揚で余裕たっぷりで、せわしなさを孫には見せようとしない。家族と食事を共にすることをいつだって心がけてくれるひとだ。
朝食か夕食のどちらかには時間の合う者同士が必ず一緒に食事をすること――
サージェント王家の決まりは、祖父母と両親の方針である。
「家族が食卓を囲む時間はとても大事でかけがえのないものだ」
王太子である父も、臣籍降下をして久しい叔父も、口を揃えてラグランドたち四兄弟と従兄弟たち――叔父の息子二人である――にことあるごとに言い聞かせた。そういうわけで、祖父も父も叔父も皆、ラグランドたち孫世代が大きくなった今でも仲が良い。父は暇と小遣いをやりくりしては、叔父ご自慢の愛猫たちに贈るおもちゃの最新カタログを取り寄せ、仕事よりも熱心に祖父と議論を重ねているくらいだ。
娘を甘やかして娘に甘えられる父親の気持ちを味わってみたいのよねえ――とは祖母と母の見解である。とはいえ、王位簒奪や国家転覆とは縁遠い仲良しぶりは平和でおおらかで清らかで大変良きことである。
そんな祖父には、古くから懐刀と名高い幼馴染みがいる。
宰相のバーナテッド・シュプリーム氏である。優秀な文官を輩出し続けてきたシュプリーム侯爵家の現在の長だ。冷静沈着で頭が切れ、宰相職にふさわしい実力と頭脳、功績を持つひとだ。
実は祖父とは隣国のお姫様であった祖母を巡ってドキドキ☆恋の鞘当てバトルをしたということは全くなく、ごくごく普通に良縁に恵まれて互いに結婚をして、家庭を築いた。仲良しの幼馴染みは、現在も家族ぐるみでほどよく交流を続けている。
さて、そのシュプリーム宰相には三人の孫がいる。子息二人、令嬢一人の三兄妹だ。
子息はラグランドよりも二学年と一学年上である。上の方の子息はラグランドの兄レオナードと同学年に当たる。ラグランドにとって二人は兄のようでもあり、ほどよく打ち解けた先輩のように頼れる存在だ。一方、令嬢の方はというと、三学年下でラグランドの次弟と同学年に当たる。シュプリーム家の二人兄弟の下に誕生した年の離れたその妹君は、それはもう目に入れても痛くないほどに大切に大切に育てられた。ラグランドたちの祖父母も両親もまるで自分たちの孫娘や娘のように少女を慈しんだ。
「ほら、ベルマ。陛下とラグランド殿下にご挨拶しよう。お二人はお前の見送りに来てくださったんだ」
切れ者と名高い宰相閣下の珍しく弱り果てたような声。その後ろから様子を窺うように顔を出した少女。ようやっと視線がかち合った。その途端、零れ落ちるのではないかというくらいその蜂蜜色の瞳が大きく開いて潤んだ。こちらが声を掛けるよりも早く、少女は再び宰相閣下の大きな背に身を隠してしまった。
「しばらく会えなくなるこの爺にもレディのお顔を見せてくれると嬉しいなあ」
国王陛下こと祖父のショックを受けたような声もまた珍しい。叔父の家の子猫にそっぽを向かれたときと良い勝負だ。
周囲から大切に護られ、すくすくと育ったその少女は、大変慎ましく、控え目で大人しすぎるレディへと成長したようだ。
「うーん。ラグも人見知りをする子だが、レディも良い勝負だなあ……」
祖父が大きく眉を下げた。
「三国一美しい王子様」だとかなんとか全然嬉しくもありがたくもない渾名がついて回るせいで、ラグランドは昔から他者との交流、とりわけ女の子との社交を好まなかった。巷の物語や舞台でおなじみの「ドキドキ☆恋のチキチキ駆け引きバトル」が彼を巡って勃発していたわけでも権謀術数渦巻く王位簒奪劇に巻き込まれていた――というわけでもない。端的に言えば、誰が一番ラグランドを美しく華麗に着飾らせることができるかという真剣コーディネートバトルに巻き込まれるのが非常に面倒くさいことこの上ないからだ。
兄レオナードの後ろばかり付いて回るラグランドを心配した両親が同じ年頃の子息と子女たちを招き、茶会を開いてくれたことがあった。しかし、招かれた子どもたちは子息も令嬢もいかに自分がラグランド王子と仲良くなるか、いかに自分が彼のそばでふさわしい友人やレディになれるかではなく、誰がラグランドを一番美しく着飾らせることができるかで大喧嘩になってしまった。日頃からお人形遊びをよくしていたり、その年頃の男の子たちよりも元々お喋りが得意だったりする傾向にある女の子たちの方がそのコーデバトルに白熱していた。
茶会はその後、開かれることはなかった。
ラグランドの人見知りはますます加速した。
けれども、同年代の子どもを避けて兄の後ろばかり付いて回る孫がやはり心配の種だったのだろう。
祖父と祖母は自分たちが外出する際、時折二番目の孫に供をさせた。友人や知人に会わせては、「うちの孫もこんなに大きくなったんですよ」「兄に付いてばかりいますが、二人の弟の前ではなかなか立派にお兄ちゃんをしておりまして」「最近は三番目の孫がその真似をするのが可愛いやら面白いやらで」等々、天気の話題の如くごくごく気軽な挨拶に参加させた。たいていは祖父母と同年代のひとたちなので彼らは孫のように扱ってくれたし、国王陛下と王妃の前でコーデバトルを始めようとする勇者はよほどのことがなければいなかった。よほどのことがあったときには、叔父の家の猫がいかに愛らしいかを饒舌に語り、祖父母は決してラグランドの端麗な容姿に口を挟ませようとしなかった。
年長者たちとの交流の場数が他の兄弟よりも多かったからか、ラグランドは人見知りをするくせにすっかり口の達者な少年になってしまった。次弟デイビスが寡黙な割に聞き上手なのは「ラグお兄様の楽しいお喋りばかり聴いていたからね」とは母の談である。
ところで、今日ラグランドがこの場に連れて来られたのは、宰相閣下の息子夫妻がしばらく仕事で王都エセルを離れることになったからだ。上の孫たちは学院での勉学をそのまま続けるため、宰相閣下と共に王都に残る選択をした。末の娘はまだ就学前ということもあり、両親に連れられてエセルを離れることになる。その見送りに祖父はラグランドに供をさせたのだ。ちなみに長兄レオナードは学院の学年末試験中のため見送りは遠慮するように言い渡されてしまった。ラグランドもこの秋から学院に入学することになっているが、兄でさえも苦戦する試験というものはそんなにも恐ろしいものなのだろうか。先ほど宰相閣下の孫君――兄がローレンで、下がロビンだ――に何気なく尋ねたら、二人ともただ静かに微笑んだ。目は調理された魚のように輝きを失っていた。
「ほらベルマ、お顔を見せて」
「ベルマが可愛いお顔を見せてくれたら、兄様たちも試験をうんと頑張れるのになあ」
「見せてくれなかったら大変なことになるなあ、兄様たちの試験結果が」
「そして、急上昇するおじい様の血圧……なんという悲劇!」
「おじい様、負けないで! おじい様、頑張って!」
「さあ、ベルマも兄様たちと一緒におじい様を応援しよう! 応援にはベルマの可愛い笑顔が必要だ」
やんややんや。ローレンとロビンが掛け合いを始めた。
宰相閣下の眉間に刻まれた影が深くなったようだが、二人はあっさり無視して妹君に元気よく声をかけた。
「そろそろ出発の時間なので……」
息子夫妻が宰相閣下に声を掛けた。それを合図に祖父が青い瞳で宰相閣下を鋭く射貫いた。
国王の眼光に促されたバーナテッド・シュプリーム宰相閣下は嫌そうに眉を大きく顰めたが、すぐに大仰な動作で胸を押さえ、よろめいてみせた。
「頭痛が! 頭痛が痛い!」
一瞬、その場に居合わせた者たちの心が一つになった。目を丸くして、一同が視線を交わし、かぶりを振った。祖父は「腹芸での交渉は得意中の得意なのにこれはひどいぞバーニー」とこめかみを押さえて重いため息を零していた。
「おじい様、大根役者すぎでは……」
「天下の切れ者宰相、とは……」
「ああ、孫二人が今日も阿呆すぎる悲しみで胸も頭も痛い。あまりの痛みで心臓が張り裂けてしまいそうだ。ベルマだけが唯一の希望にして、我が光……」
演技に対する周囲からの痛ましげな視線にも負けず、宰相閣下は粘った。
と――
「おじいさま、死なないで」
とうとうシュプリーム家のお姫様が顔を出した。澄んだ大きな蜂蜜色の瞳が、初夏の陽射しを浴びて眩しく光っている。
お姫様は顔を出した途端、大粒の涙をぽろぽろ零し、祖父である宰相閣下に抱きつき再び顔を隠してしまった。
宰相閣下は泣き止まない孫娘を抱き上げると、上の孫二人を睨みつけた。二人は懲りた様子も見せず、ただ肩を軽くすくめた。
「いやだなあ、おじい様。泣かすつもりはなかったんです」
「そうですよ。おじい様に可愛いベルマの顔を見せるため、僕たちも肉を切らせて骨を断つ算段? だっけ? をしたわけです」
「おじい様が大根すぎる事故も起きちゃいましたけど、さじ? 匙? あ、些事です些事」
「……おじい様はお前たちの試験結果が楽しみでならないよ。心の底から」
しがみつく孫娘の栗色の髪を大きな手のひらでやさしく撫でながら宰相閣下は微笑んだ。
「うへえ」
「目が怖いですおじい様」
「二人とも夏季休暇にしっかり励むように」
とびきりの笑顔に縮み上がるローレンとロビンの背を、父親のブライアン・シュプリーム氏が叩いた。
「おじい様も父上も俺たちの今回の学年末試験にまったく期待していないってこと?」
掠れた声で問いかける息子たちに父親は頷いた。あっさりと。
「うん。父さんにもよく分かったからね。お前たちの文学と語学の残念な成績は試験終了を待つ必要がないと」
「冷たい……おじい様よりも父上の冷たさで身も心も凍える……」
全身をカタカタ震わせ始める兄弟に、ブライアン氏とエレイン夫人がからりと笑った。
「ローレン、ロビン。しばらくは父さんも母さんもそばに居てやれなくてすまない。困ったことがあったらすぐにおじい様を頼りなさい。言いにくいことならば陛下に相談するのもありだぞ」
「それ、もっと言いにくいです!」
「うむ。いつでも良いぞ。成績表も君たちのおじい様より先に見てあげよう」
「陛下、さすがに洒落にならないです!」
大きく頷く国王に兄弟は頬を思い切り引きつらせた。
「しっかりね、お兄ちゃんたち」
エレイン夫人は息子二人の額に口付けを落とし、やわらかく微笑んだ。それから夫人は末の娘を宰相閣下から受け取った。
シュプリーム家のお姫様は泣き疲れたようだ。小さな手で眠たげな目元を擦っている。
「ごめんな、ベルマ。あっちでも元気で」
「手紙、たくさん書くからな」
兄二人がやさしく声を掛け、少女の頬と頭を代わる代わる撫でた。
こくん。
くすぐったそうに頬を緩め、少女は頷いた。大きな蜂蜜色の瞳が光っていた。まるで叔父の家で陽だまりに寛ぐ猫のようにやわらかく蕩けたその瞳は、初夏の緑の輝きにも引けを取らず、きらきらしていた。
ラグランドは祖父に肩と背を叩かれ、大きく瞬きした。
「どうした?」
祖父は少しかがむと、気遣わしげにラグランドに視線を合わせてきた。
「陽射しが強かったか」
祖父の深く青い瞳には、ぽかんと大きく口を開いたひどく間抜けな顔をした自分が映っていた。近くの日陰に案内をしようとする宰相閣下と孫君、前に立って大きな背でひとまず影を作ってくれた護衛の気遣わしげな声が耳を通っていった。
だいじょうぶです、とだけ返す。
ラグランドは光都リータスへと旅立った、小さくなっていく馬車をぼんやりと見送った。