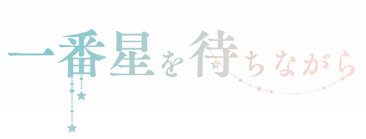
ボーナストラック掌編#2 内緒の乾杯
大きくかがみ、ゆっくりと目線を合わせる。青空に似た色合いの瞳がのろのろと見返してくる。
一時期は同年代の子どもを避けて一番上の兄の後ろばかり付いて回っていたこの孫は、妻と自分とで代わる代わる連れ回した甲斐があったのか、人見知りはまだ鳴りを潜めていないものの、すっかり口の達者な少年に育った。けれども、強い陽射しに参ったのか、今日はなんだかぼんやりとしている。
形の良い額に手を伸ばす。熱はないようだ。
ほっと息を出す。
どうやら自分の兄よりも少し上の学年の少年たちに会うというのは思いのほか、緊張するイベントだったのかもしれない。何度かこの少年たちの祖父であり、自分の友人の家にも供をさせていたのだが、そういえば、この子は自分か一番上の孫の隣に居て、ずっと静かにしていたのだった。
このあとも馬車での移動が控えているのだ。少し気分を変えてやる必要はあるだろう。見えた看板に彼は眉と肩の力をやわく抜いた。
片目を閉じて笑ってみせる。
「レオとイザベルには内緒だぞ」
孫がぱちぱちと長い金色の睫毛を閉じては開き、開いては閉じるのを繰り返した。彼はもう一度、青い瞳を和ませた。
よく冷えたグラスを満たす透明な水。大きな泡がしゅわしゅわ浮かんでは消えている。まだきょとんとしたままの孫にも一つ持たせ、合わせる。
きん。
「乾杯」
そのまま一気に煽った。大粒の泡が喉の奥を通り、酸っぱさと甘さ、そしてまろやかさが口いっぱいに広がり、刺激した。護衛も友人も孫君たちもにこやかに喉を鳴らして飲んでいる。孫も恐る恐るといった様子でグラスに口を付けた。
「わ」
青い瞳に、星が弾けた。
「レモン炭酸水だよ」
肩をびくりとさせ、目も口もぱちぱちとさせる孫に、彼は思いきり破顔した。何やら、友人が悪戯をとがめるような眼差しを送ってきているが、それは無視。
正体を知ってもまだ不思議だったらしい。孫は恐る恐るグラスに鼻を近づけ、レモンの香りを確かめている。
孫が神妙な顔つきでもう一度グラスに口を付ける様子を見て、彼はまた笑った。二番目の息子の可愛がっている子猫が初めて階段を上り下りした姿によく似ていたのだ。
「イザベルもレオも初めて飲んだときに今のお前とそっくりのびっくり顔をしていたぞ」
身をもって正体を確かめた勇気ある孫の髪を、わしわしと撫で、彼はまた屈んで目線を合わせた。
「レオの試験が終わったら今度は二人も誘って飲みに来よう」
今度は額に手を伸ばし、彼はゆっくりと撫でた。「三国一美しい王子様」と謳われているらしい二番目の孫ラグランドは、長い睫毛をふるりと震わせ、思い切り頬を緩めた。それは、陽だまりに満ちた部屋でお気に入りのクッションに寝転ぶ子猫を思い出すような安心しきった笑みだった。