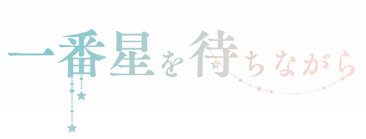
第5話 一番眩しいあの星の名前は
ひとが恋に落ちる瞬間を見てしまった――
そんなフレーズが脳裏に横切る体験をしたことが、ラグランドにはある。
それは、兄レオナードの妃候補として、祖母が小さなお友達と「お勉強会」を始めたばかりの頃だ。
見頃になった春薔薇を楽しもうと祖母が中庭に少女たちを連れ出した日の出来事である。孫たちのちょうど良いエスコートの練習にもなるだろうと、ラグランドも長兄レオナードと次弟デイビスと一緒に呼び出された。末弟ヘンリー・ローはまだ小さかったので部屋に残って母に絵本を読んでもらっていた。
昔、祖母イザベル妃が博覧会で大絶賛した白薔薇。誇り高く清らかで甘い香りのする薔薇園で王妃殿下が王子と令嬢にエスコートの手ほどきを始めた。
兄レオナードがベルマ嬢を、次弟デイビスが祖母を。そして、ラグランドはベルジーネ嬢を相手にエスコートの稽古をすることになった。
組み合わせを決めたのは祖母だ。ベルジーネ嬢とベルマ嬢に対するデイビスの嫉妬心がはっきりと滲み出ていたのだ。いつも決まった時間に「お勉強会」に呼び出されている兄二人が(正確に言えばラグランドはいつもではなく呼ばれるのは時々で、しかも何かのついでであったのだが)、この令嬢二人に取られてしまったように感じていたらしい。ヘンリー・ローが生まれるまでは彼が一番末の弟だったのだ。思い出すだけで大変微笑ましいエピソードなのだが、祖母と長兄と自分がこの思い出話をすると、デイビスはいつも心の扉を猛スピードで冷たく閉ざしてしまうので、三人でこっそりとしかできない。母も誘ってこっそりと大いに盛り上がっているサージェント王家である。可愛い弟たちの話で飲む茶は美味い。今でこそ、四兄弟の誰よりも冷静で判断が速い「氷の王子様」の幼少期の可愛い思い出だ。
今思い返すと、この組み合わせになったのは、不機嫌な子猫のように敵意を隠そうとしないデイビスを宥める他にも祖母の思惑はあったのだろう。あの頃は、茶会で勃発したコーデバトルの恐怖をまだ引きずっていたこともあり、ラグランドは同年代の女の子との交流を敬遠していたのだ。それで、弟が二人いるという三歳年上のベルジーネ嬢を彼のパートナーに指名したのだろう。それから内気で引っ込み思案なベルマ嬢を、同学年とはいえ嫉妬心あふれるデイビスや女の子を嫌がる年上のラグランドの傍に置くのは心配だったらしい。毛を逆立て尾を大きく膨らませた不機嫌極まる子猫と、耳を後ろに倒してびくびく震える怖がりの子猫を隣に置くのは確かによろしくない。ベルマ嬢にはレオナードがエスコート役として任命された。
エスコート、といってもごっこ遊びの延長のようなものである。
淑女たちのカーテシーから始まり、相手の腕に手を添えて速度を合わせて歩いたり、椅子を引いて席に案内したりされたりすることを、春薔薇の甘く清らかな香りに包まれながら何度か繰り返した。
デイビスが隠そうともせずに不満たっぷりと金色の眉を顰めていたので(現在の氷の王子様と比べるだけでも大変面白い)、祖母はデイビスに徹底指導を始めた。淡雪に似た白い髪が交じっているが、今もなお輝きを失うことを知らない月光を紡いだような銀髪を上品に結い上げた王妃殿下。祖母であるそのひとをエスコートする金髪碧眼の小さな王子様。まるで一幅の絵画のように美しい情景だが、祖母は唇に薄い笑みを敷いているものの青い目は全く笑っていないし、弟は思い切り渋面だ。
王妃殿下にエスコートさせられている第三王子の練習を残りの参加者が木陰に用意された椅子に座って見守っていたときのことだ。
「ベルマ嬢、ちょっといいかな」
長兄が少女にそっと声を掛けた。
こてん、と少女が首を傾げているうちに、レオナードは背をかがめ、そっと跪いた。
ぱちん。
王子様の指が、少女の足先で外れていた靴のストラップボタンを留めたのだ。ころんと丸く、艶々とした紫紺色の靴のストラップで煌めくのは、星型をした蜂蜜色のボタンだった。
「うん。これでよし」
星を夜空に戻した王子様はやわらかな春の陽射しを受けた青い瞳をきゅう、と細めた。晴れやかな笑顔だった。跪いて少女をまっすぐと見上げるレオナード。それはどこまでも果てしなく誰がどう見ても世界で一番王子様であった。
「……ありがとうございます」
そんな兄を見下ろしてお礼を告げる少女は、頬をほんのり朱く染めていた。
「いえいえ」
やわらかな声で答えるレオナードをまっすぐと見つめ返すのは恥ずかしいのか、少女はぱっと瞳を伏せてしまった。
「レオナード、来てくれる?」
祖母に呼ばれ、兄がゆっくりと立ち上がった。渋るデイビスを褒める係として兄を呼んだのだ。頬を膨らませるデイビスを視界に収めた兄は、眉を下げ、小さく笑みを落とした。ラグランドを含め、弟たちだけに見せてくれる「お兄ちゃん」の横顔だった。
失礼、と声を出すと、兄は落ち着いた色合いの金髪を揺らし、祖母と次弟の元へ足早に行ってしまった。
れおなーどさま、と舌足らずな声で兄を見送る小さなレディ。
一番星が上がる頃の空が夕焼けに滲んで溶ける蜂蜜色。それをそっくりそのまま写し取ったような色の瞳には、ラグランドが見たこともない綺羅星が輝いていた。やわらかく蕩けたその瞳は、太陽に似た王子様の背中をまっすぐと見つめ、きらきらしていた。
ひどくあどけない口調で紡がれた長兄の名前が、そのとき、ラグランドには特別やさしい音符で聞こえた。
ひとつの恋に、幕が静かに下りる瞬間も見たことがある――
不可抗力ではあるが、そんな場面にも居合わせてしまったことが、ラグランドにはあった。
それはとてもよく晴れた秋の日に遭遇した事件、いや、事故であった。
枝葉の間から落ちる陽光がやわらかく道を照らす。髪と頬を通り抜けていく風も澄んでいて心地が良い。
爽やかな秋の青空。定期試験終了の開放感。口笛もいつもより伸び伸びとした音が出るというものだ。
ヴァイオリンケースを片手に中庭に出る。四阿に先客が見えた。やわらかそうな栗色の三つ編みが揺れている。女学院の制服に身を包んだベルマ・シュプリーム嬢であった。
胸元を飾る勿忘草色のリボンが秋風にふわふわとそよいでいる。どうやら女学院の授業後にそのままに呼ばれたらしい。「お勉強会」と称して祖母の話し相手に呼ばれたのだろう。
そういえば、女学院は個人面談のシーズンらしい。半日で授業が終わるので放課後に来てもらうのだと祖母がにこやかに話していた。小さなお友達から女学院生活のお喋りを聞くことも、少女たちを孫娘のようにとびきり甘やかすのも祖母の大きな楽しみなのだ。
制服姿の少女を見るのは初めてなのでなんだか新鮮だ。少女はラグランドが近づいていることには気づかず、黙々と刺繍を進めている。ふ、と顔を上げた少女が、ぴたりと静止した。蜂蜜色の瞳はびっくりしたように大きく見開かれている。ラグランドもつられてその先に目線を向けた。
そこにはよく見知った二人がいた。兄レオナードとベルジーネ嬢だ。二人とも学校の制服姿のまま背を並べて語り合っている。この距離からでは話の内容までは聞こえないが、二人の表情は明るかった。
ベルジーネ嬢が何事かを兄にお願いしたようだ。きょとん、と青い瞳を大きく瞬かせ、兄がかがんだ。陽射しを受けて兄の金髪から光が零れた。そっと背伸びをした令嬢の白い指先が、王子様の落ち着いた穏やかな色合いの金髪を撫で、離れた。令嬢の右の人差し指と親指が木の葉を捕まえていた。秋風に吹かれた葉が兄の髪に落ちていたようだ。
令嬢がその葉を摘まんだまま、何かを告げた。途端、兄の弾むような笑い声がこちらにまで届いた。
少女が一瞬、肩を大きく震わせた。栗色の三つ編みが肩から滑り落ちる。
兄の果てのない晴れやかな青空に似た瞳が何かとびきり眩しいものでも見つけたかのように、細められている。
思い切り破顔した王子様は、令嬢の右手をそっと捕まえた。令嬢もまた頬をほどけるように緩めて笑っていた。二人の指が、ゆっくりと絡んだ。
兄のあんな表情を、年頃の少年らしくあんなにもまばゆく笑ってみせる顔を、ラグランドは初めて見た。兄はいつも弟たちの前で穏和な善きお兄様だったのだ。いつも見せてくれるのは、「お兄ちゃん」の顔だったのだ。
少女はその光景から目を逸らすことなく、ただ、静かに見つめていた。少女の頬を大きな涙が伝った。届かない星を想い、涙する少女。
空が青から橙、琥珀、紫紺色にゆっくりと色を成してきた。まもなく一番星が上がろうとしている。
この黄昏空から澄んだ琥珀色を写し取って丁寧に煮込んだかのような瞳。
澄んだ琥珀色の大きな瞳から落ちた大粒の涙。夕明かりを受けて少女の頬をゆっくりと静かに伝う涙は美しかった。
懐き始めた子猫のように無邪気に微笑む少女の蜂蜜色の瞳。そのやわらかな光はいつもラグランドの胸の中を温めた。
けれども、追いつけない誰かの背中を想って静かに流す涙の温もりも、届かないと知りながらそれでも一番星に焦がれ、絶えることなく瞳の奥で静かに燃える焔の揺らめきもラグランドは今日まで知らなかった。
「殿下。殿下の番ですよ」
呼ばれた気がして、ラグランドはゆっくりと目を開いた。
「殿下。聞こえていますか?」
次いで、隠す気などさらさらない巨大なため息が聞こえてきた。
「次の手がないのでしたらば、この勝負もこちらの勝ちということで」
短く爪を切りそろえた几帳面そうな指が、盤面からキングもクイーンもひょいひょい追い出しにかかった。
「うわっ!」
ラグランドは大きく肩を揺らした。
「待て待て待て! ニール! 勝負はここからだぞ!」
オーキッド侯爵子息、ニール・オーキッドはラグランドの必死の叫びに金色の眉を動かすことはなく、淡い紫色の瞳を揺らしもせず、にべもなく答えた。
「待ったはなしだと仰ったのはラグランド殿下でしょうに」
「そうだったかな」
「どのみち、殿下は今回も詰みだったんだから良いでしょう」
淡々と言いのけ、彼はさっさと駒を箱の中に片付けていく。
「歴史に残る名勝負が永遠に失われた。世界の損失は大きい……」
「はい、はい」
「心が籠もってない……」
こちらの悲痛な声に相手は特にどうということもなく返事をしては、駒を全て片付け終えてしまった。
このニール・オーキッドはラグランドの初等学校時代からの友人だ。クラスの席替えで席順が隣になったのが交流のきっかけであったが、初等部を終えて、それぞれの進路が音楽院、王立魔術学院に分かたれた今でもほどよく付き合いが続いている。
彼はラグランドを王子殿下として妙に担ぎ上げたりすることもなく、「三国一美しい王子様」として敬遠したり持ち上げすぎたりすることもない。先ほどのようにラグランドに対する扱いは時折ぞんざいではあるが、自邸に招いてチェスゲームに付き合ってくれるくらいには気が置けない友人である。
今だって自分で好きな分だけ茶を入れて自分好みの温度と甘さで飲め、とティーポットをこちらに寄越してくれるほどにはほどよい関係を築けている。はずだ。
「それで殿下。何を悩んでいらっしゃるんです?」
むせた。思い切り。
「……!」
とっさにハンカチで口元を押さえ、咳をしながら友人を睨みつけるが、彼はどうということもなく自分のカップに砂糖を投入しているところであった。眉が僅かに寄っているのは咳き込むこちらを痛ましく思っているわけではなく、やかましく感じている程度だろう。
「急にうちのデイビスみたいなことを言う……」
この友人の冷静さと判断の速さと容赦のなさは、ラグランドのすぐ下の弟デイビスと良い勝負である。二人とも何のためらいもなく予備動作もなしに、助走すら付けずに的確に色々突いてくるのだ。そう、色々と。
「殿下はうちにおいでになると、最初はいつもサロンのピアノをご機嫌に演奏なさるのに今日はそれがありませんでしたし、チェスも気がそぞろなようでしたし――」
急に言葉を切るニールを怪訝に見やり、ラグランドはカップを口に付け――
「蜂蜜をいつもより四匙も多く入れていらっしゃったので。まあ、何か悩んでいらっしゃるのだろうな、と」
「そこ、わざと言葉切る必要あった!?」
口内のどろりどろりとした甘さに顔をしかめてラグランドは叫んだ。
行儀は悪いが大きなカップを所望し、手元のカップの中身を全てそちらに注ぎ直す。それからティーポットからもおかわりを足した。飲み残すことは本意ではないので、甘さを薄めて飲むことにしたのだ。
ほどよい甘さを確認した王子は、眉を寄せ、首を斜めに傾けた。
「……悩み、なの?」
「僕に聞かれましても」
珍しくニールが目を丸くしている。が、それはほんの一瞬だった。おもむろに立ち上がると、彼はそのままサロンの扉にゆっくりと手を掛ける。
「殿下。一曲お願いします」
扉の向こうには彼の年の離れた小さな妹君が、ちょこんと佇んでいた。淡い紫色の瞳を大きく三度瞬き、こちらをおずおずと見上げてくる。なるほど、まっすぐこちらに向けてくるこの妹君の瞳は、年の離れた兄君と形も色合いもよく似ていた。
「答えは僕も知りませんし、知るつもりもありません。でも、うちのピアノならばいつでもご自由に演奏なさってください。ピアノも妹も喜びます」
ニールの袖を引き、こくこく、と小さな妹君も頷いた。大きな窓から差すやわらかな陽射し。妹君が大きな瞳を期待いっぱいに輝かせている。
初夏と秋に一番近くで見た、星を仕上げにまぶしたかの如き蜂蜜色の瞳の煌めき。それが今、彼のまなうらの奥で揺らめいた気がする。