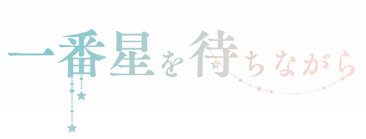
第6話 あの日見た星を探す
「どうした?」
顔を上げると、叔父が気遣わしげにラグランドを覗き込んでいた。
白いものが少し混ざっているものの、このひとの美しい金髪は、王子という身分を退いて久しい今でも輝きを全く失っていない。金色の長い睫毛がスカイブルーの瞳にやわらかな影を落としている。
叔父グレアム・Y・サージェントの屋敷の客間である。ここの長椅子は寝心地が良く、いつでもラグランドを、いつだってラグランドを、幼い時分の頃からやさしく受け止めてくれる。今日もここで寛いでいたのだが、胸の上で丸くなっていたレディ――叔父ご自慢の愛猫――の温もりに負けて居眠りをしてしまったようだ。
レディに声を掛け、やさしい手付きで彼女を抱き上げた叔父は首を傾げた。
「ラグ、どこか調子が悪いのか? 我が家の猫ちゃんたちに会えば、元気が百万倍は湧くものなのにそうならないなんてどこか悪いのだろう。隠す必要はないぞ」
すぐに侍医を呼ぼう、と叔父が眉を下げた。
にゃあ。
ラグランドが瞬きを繰り返しているうちにレディが代わりに相づちを打ってくれた。
そんないきさつを、叔父は茶を運んできた妻レイチェル――ラグランドたちにとっては叔母だ――に早速話した。叔母は目をぱちくりさせたが、ラグランドと夫の顔を交互に見て微笑んだ。
「まあまあ」
「やっぱり悪いのか?」
眉を下げる叔父を叔母は窘めた。
「いえいえ、グレアム様。昔からこの子はそうではありませんか」
「うん?」
息子二人が大きくなった今でもなお、比類なく美しい輝きを放つ青い瞳を、元第二王子殿下こと叔父グレアムはきょとんと瞬いた。
「ラグランドは何かふわふわした問題を抱えると、あなたや私のご機嫌伺だと我が家を訪ねてきては、うちの猫ちゃんたちを抱っこしたり、ソファで一緒にごろごろしたりして。いつもそれで解決の糸口を探すのですよ」
「そうか。うちの猫ちゃんは優秀な名医にして名探偵だったのだな」
とんちんかんな返事をする元第二王子殿下に細君は花浅葱色の瞳を丸くしたが、仕方ないなあとでも言うように頬を大きく緩めた。
こっそりとラグランドに声を掛けてくる。
「そうではないけれど、そういうことにしておきましょうか」
「はい。叔父上の猫ちゃんたちへの親馬鹿ぶりは相変わらずですね」
ラグランドも小さく頷いた。
「ええ。新婚時代からちっとも変わらないのよ」
かつて、「淑女が選ぶ三国一『子猫ちゃん』と呼ばれたい美しい男」と謳われていたグレアム・Y・サージェント第二王子殿下の妻となったそのひとは細い右手を頬に当て、にやりと笑う。
「可愛いでしょう。ラグが我が家でふわふわした問題の解決法を探す癖と良い勝負ね」
それには何も答えずにおかわりの茶を入れて叔母に渡す。ありがとう、と笑い、叔母は花浅葱色の瞳をじっと注いできた。
「まあ、悩みは無理矢理解決すればよいというものでもないのよね。その問題を分析して知ることが解決策に直結することもあれば、それとは反対に、問題から一旦距離を置くことが突破口だったりもするし。あなたがいつもする我が家の猫ちゃんを抱っこするとかね。それでもうまく行かない場合は、新しいことを始めてそちらに心を傾けて問題を忘れてしまうのも一つの手かもしれない」
茶を一口飲むと叔母は、ぴん、と人差し指を立てた。
「特にあなたの場合はヴァイオリンが趣味だし、将来の目標でもあるでしょう? 熱中するのもそれを大事にするのも良いことよ。あなたの演奏は聞いている私たちもいつもわくわくさせてくれるもの。でも、時には他にも目を向けることができたら、肩の力も抜けて、あなたももう少しだけ楽になるのではないかしら」
かつてラグランドたち四兄弟の音楽の先生であった夫人はやさしく彼を諭した。
「……はい」
ラグランドの返事に叔母はよろしい、と頷いた。
「先生もそうでしたか?」
ラグランドの問いに、レイチェル先生は花浅葱色の瞳を夢見る少女のように思い切り輝かせた。
演劇が大好きで、その世界に音楽で携わることを夢見ていた侯爵令嬢。道は大きく変わってしまったものの、演劇と音楽の楽しさを多くの子どもたちに音楽教師として伝えてきた日々はかけがえのないものだと笑うかつて少女だったひと。茶目っ気たっぷりな花浅葱色の瞳の煌めきはラグランドが幼い頃からちっとも変わらない。
「そうよ。それであのときは刺繍に裁縫に編み物にも手を出したし、剣術や馬術にも挑戦したのよねえ」
「レイチェルは私よりも優秀だぞ。剣術は一本も取れなかった」
どこかの王子様と令嬢が猫ちゃんの将来を巡って剣術勝負をしたことがあるとかなんとか、幼い頃に聞いたことがあったような気もするが、その対戦相手はこのひとだったらしい。
「でも、一番しっくりきたのはこの子たちかなあ」
叔父の膝の上でおすましをしているレディに笑いかけた。
にゃあ。
レディは甘い声で返事をするなり、軽い足取りで叔母の膝に移動した。ごろごろと喉を鳴らし、ふわふわの身体を擦り寄せて甘えるレディに叔母は惜しみなく頬を和らげた。膝の温もりが消えた叔父は、未練たっぷりのしょんぼりした眼差しでレディと叔母を見つめている。
叔父が巨大なため息を零した。幸せが逃げますよ、との叔母の指摘に叔父はかぶりを振り、更に大きな息をついた。
「……知っているか?」
一対の青空と視線がかち合った。
「我々がため息と共につい、『可愛い』と発してしまったり、笑顔になってしまう理由を。思い出すだけで胸のうちが温められるわけを」
叔父は小さく笑みを滲ませた。
「それは、無条件に五感が抱く、深い場所からの感情なんだ」
叔父のテノールが朗々と部屋に響く。
「地上に生まれ落ちた生命に対する慈しみ、『可愛い』と抱いてしまう気持ち。喜びだけでなく、無条件に守りたいと強く思わせる力。これは万有引力ならぬ、万有惹力とでも言うのではないかと私は常々考えているのだが――」
叔父の青い瞳がラグランドを射貫いた。一瞬、肩が跳ね上がりかけた。深く澄んだ一対の蒼穹に何もかも見透かされそうで、ラグランドはそっと視線を逸らした。
「その小さな身体、対して大きな頭、つぶらな瞳……。我々が赤ちゃんに抱く愛情にして種の保存の法則も、近づきたい対象そのものをもっと深く知りたいという探究心も、簡単に引き出してしまうんだよなあ、猫ちゃんは」
なんと偉大にして罪深くて恐ろしく可愛い生き物なんだ、と叔父は熱い吐息と共に言った。
叔父の大演説に対し、レディは、こてん、と叔母の膝で寛いだまま首を傾げてみせた。叔父の頬がでれでれと溶けてしまった。ファンサービスが過ぎる。
「ラグランド」
よく通るその響き。
ラグランドは座り直した。叔父は何か大事な話をするとき、いつも自分のことを愛称ではなく正しい名で呼ぶのだ。
カーテンが揺れ、透明な風が部屋を通り抜けた。白と金の混じった髪が揺れ、その輪郭は差し込んできた陽光にやわらかく縁取られている。
これは私の経験則だが、と叔父は表情を引き締めた。
「使えるものは何でも使いなさい」
叔父の美しいスカイブルーの双眸いっぱいに、目も口もぽかんと開いた何とも間抜けな表情の王子が映っている。
「お前の持つ全ての手札を存分に使え」
重ねられたその声。それはラグランドの胸を軋ませた。
「格好悪いとか、格好悪くないとか、自分の柄じゃないとか。それこそ大事ではないぞ。見目もパブリックイメージも使える手札だし、大事な駒だ」
かつて「淑女が選ぶ三国一『子猫ちゃん』と呼ばれたい美しい男」と名を馳せた元第二王子殿下は小さく笑みを漏らす。果てのない青空に似た双眸に、自分の姿が見える。
「大切なのは、持てる限りを尽くしてお前がそのとき考えて選択した最善、最良の道の先で誇れるかどうかだ」
ラグランドは何も言葉を紡ぐことができなかった。返す返事も見つからなければ、掛けねばならない言葉も見当たらない。そんなラグランドを見透かしたかのようにスカイブルーが和らいだ。
「ああ、もちろん公序良俗に反するのは駄目だぞ。兄上を泣かせたら甥だろうが王子だろうが容赦しない」
そのときはお前を何が何でも絶対に泣かせてやるぞう、と大層大人げないことを宣言するグレアムの姿に、父の姿が重なった。兄弟らしく、二人の顔立ちはよく似ている。口調こそ茶目っ気たっぷりだが、瞳には静かで強い光が揺らめいている。父が仕事で見せる表情そっくりだ。
「持てる限りを尽くすというのは、一気に、一度にという決まりはないぞ。徐々に、少しずつでも良いんだ」
プレストでもアンダンテでも良いということだ、と叔父は頷いた。
「色々回り道をして、今のお前がある。これから先のお前も全てそこにある。格好悪いのも格好良いのも失敗も成功も、迷いもその先の答えも、全てお前だけのものだ。だから、大いに悩みなさい。たくさん迷いなさい」
叔父の言葉は、ラグランドの胸を突いた。そして、奥底にしまい込んでいたはずのものを静かに揺さぶった。
「……叔父上もそうだったのですか?」
返事はなかった。遠い昔日に臣下に降りた元第二王子殿下は静かに微笑む。
みゃう。
代わりに返事をするようにレディが甘い声を出した。顔を叔母の胸元に擦り寄せて甘えるレディ。
元祖三国一美しい第二王子殿下の大きな左手が伸び、細君の膝の上で丸くなるレディを撫でた。ゆっくりと。次いで、叔母のたおやかな手が、その広い手の甲に重なった。
スカイブルーの瞳が、花浅葱色の瞳と交差して、ゆるゆると細まっていく。
猫のふわふわの背をゆっくりと動く大きな手。その広い甲に重なる華奢な手のひら。二人の薬指の指輪は静かな銀色の光をたたえている。
叔母の膝で丸くなっていたレディが、今度はラグランドの膝に鞍替えをした。
ふわふわの身体に重さ、温度がラグランドの腹を、膝を、手の甲を温めた。
澄んだ青い瞳に金髪碧眼の男が映っている。迷子になった子どものようにひどく情けない顔をしている。
レディは目を僅かに細め、そのままごろりと身を横たえた。それから、尻尾を振った。ゆったりと。
たし。たし。
子猫をあやすゆったりとしたリズムだ。撫でても良い、と励ましてくれているようだ。ラグランドが手のひらを伸ばすと満足そうに喉を鳴らして全身を擦り寄せてくれた。
その可愛さにノックアウトされた叔父が画家を早馬で呼ぼう、と部屋を飛び出した。いつものことだから、と叔母は呆れたように微笑んでいる。けれども、その花浅葱色の瞳はいとおしむ眼差しをしていた。
かつて「三国一美しい第二王子様」と謳われていたかのひとは、現在、「絶対猫一直線公爵閣下」「兄馬鹿で愛妻家の子煩悩にして超絶猫馬鹿公爵閣下」として国中に幸せな名を馳せている。
レディは大きく開いたままの扉には目もくれず、のんびりと欠伸をしていた。
「そういうわけでおにーさま。ちょっと顔貸せよ」
次の週末である。オーキッド邸に着くなりラグランドは宣言し、ニールを馬車に押し込んだ。
「何がどういうわけなのか皆目分かりかねます。藪から棒にもほどがあるでしょう、ほどが」
キング船長の冒険譚の登場三行で返り討ちに遭ったあのチンピラめいた物言いだったな、と内心ちょっぴり反省していると、向かいの席に座ったニールは教科書の手本になりそうなほどの見事な渋面をしていた。好物を前に胃が深刻な痛みを訴え始めているような、楽器選択を間違えたまま単位認定試験を受けに来たひとのような顔つきをしている。
「ニール、腹が痛いのか?」
「殿下」
友人は苛々と眉を更に中央に寄せた。
「ヘンリー殿下を今日は我が家にお連れしていましたよね?」
「うん……?」
急に登場した自身の末弟の名に首を傾げ――ぽん、と左手で作った拳で右の手のひらを打った。
「うん」
今日の王宮は祖父母も両親も仕事で、長兄も次弟も学院の課題で慌ただしく過ごしていた。それで、一人寂しそうにしていた末弟にラグランドは声を掛けてオーキッド邸に連れて来ていたのであった。
「ヘンリー殿下はどちらへ?」
「うーん……」
馬車の中をぐるりと見渡す。ニールと護衛の呆れきった冷たい眼差しがラグランドに刺さる。そういえば、末の弟の、ヘンリー・ローを、オーキッド邸に置き去りにした。気がする。
「ま、まあ、案ずるな。どうか案じてくれるな。ヘンリー・ローはうちの兄弟の中でもとびきり良い子で、社交性も可もなく不可もなくあるし、人当たりも良いから大丈夫でしょう。たぶん。おそらく。きっと」
「今日は両親が不在で家には年頃の妹が一人きりなんです。間違いがあったらどうするんですか。すぐに戻ってください」
「ええー…………」
間違い、とは。
そもそも年頃も何も弟はまだ十歳にも届いていないし、彼の妹君はそれよりももっと幼いはずだ。屋敷にはヘンリー付きの近衛騎士も残っているし、当然オーキッド家の護衛もいる。王宮の護衛は差し引いたとしても、オーキッド侯爵は遅くに生まれた愛娘を大層可愛がっていると聞く。屋敷の護衛も侍従も侍女も優秀な人材しかいないようなので、間違いが起きるどころか、何事も始まらないと思うのだが。そもそも末弟もとても大人しいというか、おっとりした子なので人様のお屋敷で木登りしたり、外を探検したりして妹君や屋敷の人々を困らせることはしないだろう。間違っても妹君に怪我はさせない……と思う。
ニールが黙したまま素早く懐に手を入れ、杖――王立魔術学院入学と同時に所持するようになったという魔術師必須アイテムらしい――を取り出した。護衛が彼の腕を掴むよりも早く、侯爵子息は天井を杖で叩き始めた。真顔で。ガンガン。ガンガンガンガン。
「すみません! 馬車を止めてください!」
「えー……」
「魔術じゃなくアナログなんだ……」
「――遅い」
ニールの腕を掴んだまま静止した護衛の額を、もう一人の護衛が指で小突いた。ニールはその護衛の片手で取り押さえられ、顔を座席のクッションに押しつけている。
万が一。億に一つ。見習いとはいえ、仮にも魔術師のニール・オーキッドがこの場で魔術を駆使してラグランド第二王子を害そうとしていたら――判断も対応も遅すぎることへの忠告だ。ニールは嫌そうに身じろぎをしている。
年の離れた妹君を殊の外可愛がっている友人にも、主の守護に真摯な護衛たちにもラグランドは頬が緩むのを抑えきれなかった。
「殿下、いかがしました!?」
御者が速度を緩め、びっくりしたような声で尋ねてきたが、ラグランドはいつも通りの声音で返す。
「何でもない何でもない。さあさあ、走って」
「はい」
再び馬車の速度が上がり始めた。
ものすごく嫌そうな友人のうめき声が聞こえてきたので、すぐに解放するようラグランドは指示を出した。
苛々と眉間に深い皺を刻むニールを、第二王子は温い笑顔で宥める。
「ほらほらニールくん。君の家のアーネスト殿はとても優秀だろう。こわくない、こわくない」
アーネストとは、オーキッド家の爺やこと家令だ。オーキッド侯爵夫妻が留守時には屋敷の一切合切を任され、万事心得てニールたち兄妹を護る優秀な人物だ。小さい頃から彼に育てられたといっても過言ではないニールにとって、両親の他に頭が上がらない人物の一人なのだ。
はー……。
馬車内に響いたのは、盛大なため息だった。目の前にいる王族への配慮など一切なかった。拘束から解放された侯爵子息は襟元を正し、座り直した。もう一度大きく嘆息すると、ニールは淡い紫色の瞳を再びこちらにまっすぐ向けてきた。剣呑な光は鳴りを潜めている。妹君のことは爺やに委ねる気持ちになったのだろう。
「……ラグランド殿下はひとに頼み事をするのが恐ろしく下手ですね。昔から」
「うん?」
「街に行きたいけれど、一人で行くのにはいささか差し障りが、いや、何かふわふわした問題がある。だから僕に供をさせて背中を押させようとなさったのでしょう。うん。下手というか、下手すぎですね」
「……うん」
「そういうときは、ただ一言『街に行くから供をしろ』と掛けてくだされば良いんですよ。近衛騎士の手でひとを馬車に無理矢理強引に押し込む前に」
「ごめん、でも」
自分の頼み事は、王子の命令にもなりかねないのだ。祖父母にも両親にもその間違いだけは絶対にしてはいけない、とラグランドたち四兄弟は幼い頃から厳しく教育されてきた。けれども、いや、だから、なのかもしれない。頼み事や願い事における匙加減だけは一向に上手くならなかったし、上手くなれなかった。何かを願う前に周りがそれを汲み取ってそれをすぐにしてくれたのもあるかもしれないが、どうにも昔から口に出すのは上手くいかないのだ。
ニールは淡い紫色の瞳を、ふ、と和らげた。
「では、誘い上手になられてみては」
「誘い上手?」
「そうですね。たとえば、今日の場合は、ただ一言『街に出よう』とお誘いになれば良かったんですよ。両脇を騎士殿で固めて出会い頭に問答無用で僕を馬車に押し込む前に」
「ごめんて……」
「頼むのではなく、お誘いならば殿下のお気持ちにも、相手の気持ちや立場にも負担にならないでしょう。善処なさってください」
「そういうものか?」
「ええ。その方が頼み事よりも重くはないので嫌だったら断りやすいし、誠実です。少なくとも僕なら断ります。はっきりと」
「ニール!」
必要とあらば諫言を呈することも辞さず、ノーを明確に示すことができる得がたい友人。感激のまま彼に熱い眼差しを向けると、ニールもまた深く頷いた。
人類最大の尊称は「友人」だと聞くが、全くもって究極の至言である。持つべき者は、善き友人だ。
「では、お後がよろしいようで。家に帰らせてください」
「ニール……」
騎士たちが大きく噴き出した。遠慮のない物言いに堪えきれなかったらしい。
「善きご友人ですな」
「大事になさいませ」
くつくつとユニゾンを奏で始めた笑い声にラグランドは頬を思い切り引きつらせる。
速度を緩めていた馬車が停まり、街に到着したことを告げる御者の声が車内に小さく届いた。
ラグランドたちが馬車から降りて足を向けた先は、目抜き通りの東側だった。春の昼下がり。やわらかな陽射しを受けて艶々と光るチョコレート色の三角屋根を横目で見ながら、早足で道を行く。時々、すれ違う民が「おお、ラグランド殿下だ」「今日もお美しいわねえ」「本物はやっぱ黄金比すっげーな!」等とざわざわ小波を立ててきたが、曖昧に笑ってやり過ごした。
民と交差するたびに微笑むこちらに思うところあったのか、ニールが認識阻害の魔術を提案してくれた。けれども、やんわりと断りを入れた。
「挨拶みたいなものだから。気にしてくれるな」
民の反応は、特別なものではない。ごくごく儀礼的な社交の「こんにちは」「さようなら」「今日は天気が良いですね」と何も変わりはないのだ。彼らは彼らなりにラグランドの小さい頃から健やかな成長と安寧を願い、見守ってくれているのだ。元気な姿を見せるのはラグランドなりの挨拶だ。
「ですが……」
気遣わしげなニールの眼差し。ラグランドは笑って首を振った。そういえば、ニールと街に来たのは今日が初めてだったな、と思い至る。この友人と会うときは、初等部時代は主に学院の教室だったし、進路が分かれた今は専ら彼の家に遊びに行くか、彼を王宮に招くのが常だった。
「いいんだよ。いつものことだ」
ニールの背を押し、目当ての角を曲がれば、人波が一気に減った。大通りの賑やかな街並みと比べると、建物も空気感も落ち着いたものへと変わる。
まず目に付くのは鉱石灯だ。暮らしを明るく照らす生活必需品の一つだが、建物のあちこちに飾られた鉱石灯は精緻な模様の色硝子が嵌め込まれて鮮やかな影を落とす芸術品の顔も持つ。今は昼下がりなので灯は消えているが、太陽の光を受けて、色とりどりの模様を道に落としている。並ぶ店の扉もチョコレート色の高級な木材が使われ、凝った細工が施されている。
王都エセルの中でも芸術家やそうした何かを創る趣味を持つひとたちが必要としている道具や材料、それに完成した創作品などを扱う店が連なる通りだ。
その中の一店に辿り着いた。ラグランドは三拍置いてから、ノッカーを叩いた。すぐに返事があり、扉が開かれる。折り目の正しい服を着た初老の店員が、ラグランドの姿を認めて一瞬目が丸くなったが、すぐににこりと笑う。
「ラグランド殿下。いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました」
店先の看板に首を傾げ始めた友人の背中をぐいぐい押し込み、ラグランドも笑顔を作った。
通りに面した窓の手前には、透かし細工の大きな衝立が置かれ、外からの陽射しをやわらかく受け止めている。店内には応接のための二対のソファが置かれ、衝立の薔薇模様が影を落としている。カウンター横の壁に奥へと続く扉が三つ並んでいる他は、天井から床に届くほどの大きな棚がひっきりなしに背比べをしている。彩り豊かな刺繍糸に毛糸。やわらかさや厚さも質感も様々取りそろえられた生地素材。大小様々な刺繍針、編み針といった手芸用品が棚の中で上品に佇んでいる。
店内を素早く見回した友人が、片眉を上げた。
「ああ、プレゼントですか」
「そうじゃない。まだ」
「まだ」
つられたように復唱したニールが、ぴたりと唇を閉じた。そして、もう一度ゆっくりと開き、確認するように動かした。
「……まだ」
「あー! そうだよそうそう。そうです俄然その通り。ご明察。大正解。コングラチュレーション。まだ! おばあ様の誕生日では! ない! まだ!」
「まだ何も言っておりませんが」
「そうとも。母上と叔母上の誕生日も終わったばかりだ」
「ですから、まだ何も言っておりませんって……」
淡い菫色の瞳が胡乱げになる。
「まだ贈るわけじゃない。まだ!」
「まだ」
「ああ、まだだとも! 仲良くなりたいなら、まずは相手についてよく知ることから始めろって昔から言うだろう? だから……、俺もあの子がいつも心を砕いている刺繍を、刺繍というものをまずは知ろうと思って。挑戦しに来たんだよ……」
「急に早口になる……」
ただ、あの瞳に映る世界を知ってみたくなったのだ。
一番星が上がる頃の黄昏空。あの空をそのまま掬い取って丁寧に煮込んだかのような澄んだ瞳。あの澄んだ色の大きな瞳から落ちた大粒の涙。あの日、夕明かりを受けて少女の頬を伝った涙は美しかった。安心した子猫のようにあどけなく微笑む蜂蜜色の明るい光は思い返すたびにラグランドの胸の中を温めた。けれども、あの、大切な誰かを想って静かに流した涙の温もりも、あの瞳の奥で揺らめくあたたかでやわらかな焔もラグランドは知らなかった。初めてだった。
ラグランドが知る少女は、とても内気で引っ込み思案で、人見知りが大きくて。そのくせ、ひとたび心を許したら母猫に甘える子猫のように安心しきった可愛らしいとびきりの笑顔を見せてくれて。それから、苦手な刺繍にいつもひたむきに取り組んでいた。
だから、ただ知りたくなったのだ。あの少女の澄んだ眼差しがまっすぐ向ける世界を。
ずっと燻っていたあれそれを言葉に昇華できたからか、気持ちは楽になった。だが、戸惑いと、こそばゆい温さが大いに含まれた友人の眼差しをまっすぐ打ち返すにはまだ時間も覚悟も足りそうにない。
たまらなくなったラグランドは両手で顔を覆い、天井を仰いだ。