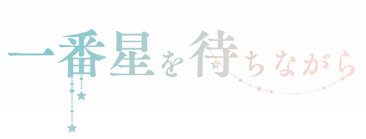
第7話 星よりひそかな序曲未満
くるり。くるり。もう一つ、くるり。銀色の針をしっかりと押さえ、糸を三回巻き付ける。親指の爪を立て、巻いた部分を押さえる。す、と糸を引く。
三拍置いて、息を整える。仕上げに糸の端を僅かに残して鋏を入れる。
丸い盃状に大きく開いた鮮やかな琥珀色の花。花菱草の刺繍の完成である。少々ガタガタしているが、それはそれで、味わい深い。と思う。
あの春の日に末弟を友人ニールの家に置き去りにし、ニールを誘って街まで出かけた店で購入した初めての刺繍キットだ。それがついに完成した。
初老の店主は人当たりが良く、右も左も分からぬ刺繍道入門者にもとびきりやさしかった。店主はラグランドの質問にも静かに耳を傾け、丁寧に応じてくれたのだ。
「初めて挑戦されるのでしたらば、目立つ色の糸で大きな模様を描くものが分かりやすく、作り上げたときのやりがいも大きいものですよ。こちらのシリーズはいかがでしょう」
店主はにこやかに微笑みながら、初心者用刺繍キットの紹介をしてくれた。薄く印刷された下絵に針と糸を入れ、基本の刺繍を繰り返し学んで練習すると図案が完成するという代物だ。青空を模した生地に白い雲模様を刺繍するものや、宵空に金色と銀色の星座を繋いで描くもの、花瓶や花壇、草原に好きな色の花を咲かせるものが定番だそうだ。
淡さと深さを併せ持つ蜂蜜色の刺繍糸に目を惹かれていたら、この花菱草の刺繍キットを勧められた。
早速購入したラグランドは、店主に断りを入れ、他にも必要な道具や教本がないかキットの説明書を広げて確認を始めた。十分ほど熟読し、ラグランドは首を斜めに傾けた。
「ニール。君は一行目を翻訳できるか?」
「我が家の書庫にも辞書がある国の言葉でしたら、少々お時間をいただければお力になれるとは思いますが……」
こそこそと顔を寄せて話し合う二人にはどんよりと暗雲が立ちこめていた。けれども、光明はすぐに差した。店主が手招きをしてソファに誘ってくれたのだ。
「初めての方こそ教本の説明が外国語や呪文のように見えるものですよ。さあ、こちらへ」
目元を細めて店主はふわりと微笑んだ。
それから彼は端切れをいくつかテーブルの上に載せ、玉結びと玉留めといった刺繍の入り口と出口、それから刺繍キット説明書に書かれた基本の縫い方まで実演披露し、二人にゆっくりと伝授してくれた。おっかなびっくり針と糸を持つラグランドと首を大きく傾げるニールにも一つ一つ丁寧に答えてくれた。
その日、置き去りにしてしまった末弟の回収にオーキッド邸までラグランドが戻ったのは、太陽が大きく傾き始めた夕刻であった。
店主の教えてくれたことをノートに清書したラグランドはその日から少しずつ、学院の勉強やヴァイオリンの練習の合間に自室にて黙々と刺繍に取り組んだ。順調に思うように上達していったわけではない。けれども、生まれてからずっと王宮育ちの王宮暮らしだったのだ。いつも誰かに何かをしてもらうことが当たり前だったから、自分の手で新しく何かを学べることも、それが少しずつ目に見えてできるようになっていくのも面白かった。
分からない部分や苦手な部分はニールを強引に誘い、こっそりとニールの母君やあの店の店主の元に通って教えを乞うた。
母や祖母、叔母に初めから指導を頼まなかったのは、照れが半分……いや、三割で、防衛反応が七割だったからだ。自分にも他人にも厳しい彼女たちのことだ。身内だからこそより厳しく熱心な指導になることが予想された。淑女の嗜みである刺繍道のてっぺんを獲るまで絶対に解放してもらえない恐れがあったのだ。特に隣国のお姫様であった祖母は、祖父の元へ輿入れする前、苦手な刺繍の練習に大変な苦労をしたらしい。孫にやさしい祖母のことだ。習いたいと頼み込めば、きっと若い頃の自分がした苦労を可愛い孫にはさせたくないと徹底的に厳しいご指導ご鞭撻を始めることだろう。
大きく伸びをして、肩と首の凝りをほぐす。針と糸を机から片付けて、息を吸い込むと、胸いっぱいに緑の匂いがした。開けていた窓を見やる。庭の万緑が紫紺色から蜂蜜色、朱鷺色に染まり始める。夏の朝が起き出していた。
星が飛び、鈍い痛みが頭に走った。誰かに呼ばれた気もする。
うっすらと目を開けると晴れ渡った青空と淡い菫色の二対の澄んだ瞳が飛び込んできた。次いで、目に入ったのは、赤に白、橙色の大小様々、色とりどりの花々である。
「え」
その花が、長椅子で横たわっていたラグランドの胸にも腹にも顔にも遠慮なく盛大に飾られて、いや、こんもりと盛られていたのだ。
「ええっ? なに? 何のコーデバトル!?」
飛び起きる。ひらひら。はらはら。花が舞う。比喩ではない。物理的に落ちている。サロンの大きな窓から差し込む光が花を照らし、光も散る。
「よかった、兄上!」
「おにいさま! ラグランドおにいさまがいきかえりました! キング船長みたい!」
心底ほっとしたように末弟が息を吐き出す。末弟の瞳は心なしか潤んでいるように見える。その袖口をきゅう、と握っていた侯爵家の小さなレディが飛び上がった。少女は淡い紫色の瞳をきらきらさせると、今度は自分の兄に飛びついた。このほどラグランドの末弟ヘンリー・ローと婚約を結んだばかりの小さな婚約者殿だ。このオーキッド侯爵家に住む友人ニールの年の離れた妹君でもある。
「ああ、殿下。ようやくお目覚めですか。ご機嫌麗しゅう」
心にも思っていない挨拶を、取り繕うとする気遣いなど一切なく、清々しいまでに正直どうでも良さそうに言い放つニールの冷たい声。妹君をやさしげな手付きで撫でながらこちらが風邪を引きそうなくらい凍てつく刺さる声を出すあたり、なかなか器用な男である。
「ええー……、心籠もってない」
「小さい弟妹を困らせる悪い王子様にはそれくらいがよろしいかと」
王子はゆっくりと膝上の薔薇の花を指で摘まむ。笑みを浮かべて問う。
「ごめんごめん。で、これは何のごっこ遊びですか?」
痛む頭を芝居がかった大きな動きでよろよろと押さえることも忘れずに。
ニールは淡々と事の次第を語る。
「ラグランド第二王子殿下があまりにも安らかな表情でその長椅子に横たわっているのをヘンリー殿下と妹が発見しました。ところが、その王子様は二人が何度懸命に呼び掛けても、揺すっても目を覚まさなかったそうです。『別れの棺は華麗に盛大に飾ろう。そして、笑顔で見送るのが彼方へ旅立つ者に我々ができる精いっぱいの勤めであり、心からの誠意なのだ』とキング船長の海洋冒険譚でしっかり学んでいた良い子たちが家中の花をかき集めましたとさ。おしまい」
「なんか雑なんだよなあその説明。肝心な部分、端折ってない?」
鋭く光った紫色の瞳。それをじっと向けられ、こちらにも思わず緊張が走る。やがて、友人は重々しく唇を動かした。
「殿下が不敬罪に問わないとお約束いただけるのであればお話しします」
「分かった。許す」
相手もまた頭が痛むのか、こめかみを押さえて重苦しい吐息と共に語り始めた。
「ヘンリー殿下と妹の痛ましい表情に心打たれた家の者たちが、王宮に早馬で報告するのと葬儀店に知らせるのはどちらが先なのか、真剣に協議を始めまして――」
「わあ……」
ラグランドは頬を引きつらせた。両親に祖父母、それからご先祖様の見目の麗しい部分をいい所取りの全部盛りで生まれたと言われている自分には、昔から「三国一美しい王子様」とかいうそれほどありがたくない称号が付いている。その少々厄介な称号には「守りたい、その儚げな王子様」もオプションで付いて回るのだった。くしゃみ一つで寝台から出してもらえなくなるし、宮廷医を全員呼ばれたりすることが幼い頃はよくあったのだ。
「雲行きが一気に怪しくなったので僭越ながら僕が殿下を叩き起こしました」
「叩いたのか、父上にも叩かれたこと――」
しおしおと眉を下げると、目の前の友人の双眸がますます緊張を孕んだ。ゆるゆる手を振ってやり、笑う。
「あるある。あるから! してはいけないことをついやらかして、父上にもおじい様にもおばあ様にも叩かれたことはある。気にするな」
世界を狙える鋭く正確なジャブだったぜ、と膝上の花を摘まんでニールに授ける。
「光栄です、殿下」
彼は恭しくそれを両手で受け取り、長々と息を吐いた。
弟妹たちと皆でサロンの花を拾い集め、再び昼下がりの寛ぎタイムとなった。
本から顔を上げたニールが呟いた。それにしても殿下は我が家に最近よくお越しになりますね、と。
手土産に持ってきたクッキーを咀嚼し、飲み込む。つい、目線が泳ぐ。
「いや、なんというか、その、王宮には兄上が居るじゃん?」
相手は何を当たり前のことを言っているのだという目つきで先を促してくる。
「今日はあのベルジーネ・メッセル嬢とシュプリーム家の掌中の珠、ベルマ嬢のお勉強日でして。兄上も一日王宮に居るわけで……その、身内の淡い恋のナントカを最前列で見るのはとてつもなく落ち着かないことこの上なく、非常に居たたまれない」
「どの口が……失礼、貴方がそれを言いますかそれを」
腹でも痛むのか、ニールは何故か眉を思い切り顰めている。それには答えずに次のクッキーに指を伸ばす。バターとレモンの皮のすりおろし、それからレモンジャムがたっぷりと練り込まれたクッキーは、口に入れた瞬間、爽やかなレモンの香りと酸味が広がる。さくさくとした軽い食感は、ついもう一枚と手が伸びてしまう美味しさである。
これは、「お勉強会」に来るシュプリーム家掌中の珠ことベルマ嬢も太鼓判をおしている味だ。同じ参加者のベルジーネ嬢がそれほど甘いものを好むお嬢さんではないということもあり、勉強会後に茶と共に振る舞う甘い菓子のメニューに祖母はいつも頭を悩ませていた。それで、ラグランドがこのレモンクッキーを料理人にリクエストしたのだ。祖母と兄、それからラグランド。王族三人を前に、耳を後ろに倒した警戒心全開の子猫のように身をすくませていた少女が、このクッキーを頬張った途端、蜂蜜色の瞳に大きく星を浮かべ、口角をほっと緩めた姿が印象的だったのだ。
ある夕方、帰り際のベルマ嬢が嬉しそうにこの味の素晴らしさを語ってくれた。うん、うんとラグランドも大きく頷いて耳を傾けた。
ラグランドのリクエストを祖母が叶えてくれたのも少女たちがそれを気に入ってくれたのも嬉しかった。しかし、この物静かで内気な少女が珍しく言葉を惜しむことなく、自分にお喋りをしてくれる姿はもっと嬉しかった。夕明かりを受けた蜂蜜色の瞳は、空に架かる一番星にも負けない煌めきをしていた。
それを祖母に報告したところ、レモンクッキーは「お勉強会」の定番メニューとなったのだ。祖母は小さい頃から気に掛けているあの少女にとびきり甘いのだ。つまり、今日、ラグランドとヘンリー兄弟は「お勉強会」の相伴に預かったおやつをオーキッド邸に土産として持ってきたのだ。
この土産について、今日の「お勉強会」に出ているおやつであることと、祖母始め、「お勉強会」メンバーの令嬢お気に入りの品だとにこやかに紹介した末弟に、ラグランドは目眩がした。
自分の供としてついでに遊びに来ていた頃とは目的がすっかり変わり、この屋敷の婚約者の元に熱心に通うようになった末弟は、相伴に頼らない土産というものについて一度学ぶ必要があるのではないか。
婚約者がいない自分が説教するのも妙だが、どう教えたものかと考えあぐねていると、「わあ、こちらがおねえさまたちに人気のお菓子なんですか!」「とってもおいしい!」と末弟の婚約者殿本人が頬を大きくほころばせ、ぴょんぴょん跳ねて喜んだ。ニールも目を細めて妹君の頭を撫でていたので何も問題なさそうだ。これからは末弟もこのレモンクッキーを熱心にリクエストすることだろう。
ニールはまた一つ大きな息を吐き、話を続けてきた。
「殿下にとって我が家の居心地が良いのは大変光栄なことですが、死んだふり……失礼、うちでの居眠りが最近多いのは目に余ります。きちんと休まれていますか? また何か抱えていらっしゃるのでは」
「……このサロン、日当たりよくて冬でもあったかいし、夏は風がよく通って涼しいし、ほんっとよい昼寝プレイスだよねえ。叔父上の猫ちゃんたちに紹介したら絶賛して通い詰めるだろうし、ヘンリー・ローだっていつもイザベル嬢とここで遊ぶのを楽しみにしてるぞ」
「……光栄です、殿下」
台詞の割にちっとも嬉しそうではない響き。その面白くなさそうな目線を追えば、なるほど、ニールの年の離れた妹君イザベル嬢と、ラグランドの末弟ヘンリー・ローがピアノの前に並んで座っている。このほど婚約を結んだばかりの小さな弟妹たちは真剣な顔つきで新しい楽譜と睨み合っていた。ラグランドが二人に渡したものだ。末弟の説明に妹君が首を大きく傾げた。末弟もつられて首を傾げ、二人そろって仲良く大きく右に傾き始める。
「失礼」
一言断りを入れるや否や、友人の指先が、ラグランドの髪に触れた。
「御髪に糸くずが」
友人の短く爪を切りそろえた指先が摘まんだのは、蜂蜜色と栗色の糸。息を、呑んだ。
「殿下はあれから熱心に刺繍を続けていらっしゃるのですね。僕はやっとあのキットの半分に辿り着いたところです。細かい魔術陣を描くよりも骨が折れます。殿下は……ラグランド様?」
「び」
「び?」
「び!」
「び?」
「びっくりしたあ!」
背もたれに大きく寄りかかったこちらを視界に収めた友人が目を丸くする。びっくりしたのはこちらですよ、と妙に緊張した様子で息を吐くニールにラグランドはかぶりを振った。
「うっかり恋が始まるところだった……悪いが、俺は君の気持ちには応えられない。すまない」
目の前の男は思い切り嫌そうに眉間に濃く深い影を刻んでいる。
女学院で流行している物語のワンシーンのようだったのだ、と説明をしてやる。
「よくご存じですね」
「うん。ベルマ嬢が教えてくれた。クラスで流行っているんだって」
ニールの問いに、ラグランドも素直に答えた。他にも教えてもらった物語をいくつか挙げ、再びこの物語の人気について説明をした。
夏の明るい陽射しの下、王子様が令嬢の髪に付いていた葉を払ってやるのがこの恋物語のラストシーンだそうだ。少女たちが夢中になっているシリーズでも人気のときめきポイントだと聞いた。そのシーンに二人の台詞はない。だが、そこが良いのだという。余韻や行間、今までとこれからの二人の日々に思いを巡らせるだけで心がぴょんぴょん? いや、きゅんきゅん、とかするものらしい。それを図らずも「三国一美しい王子様」が再現したのだ。たった今。
惜しむらくは、ごみを取ってもらったのが王子様で、取ってくれたのは侯爵子息ということだ。何も始まらない。たぶん。ニールとラグランドの間に淡い恋の何とかが始まったところで正直応えることはできないので願い下げだ。そうかといって、暗雲立ちこめる波瀾万丈の暑苦しい友情劇も少々、いや、かなり遠慮願いたい。彼とはほどよくフラットで明るくふわっとサクッと軽やかな友人関係をこれからも末永く続けていきたいものである。
ラグランドは座り直して姿勢を正す。「氷の王子様」も裸足で逃げ出すブリザード吹き荒れる一言が打ち返される予感がしたのだ。けれども、何もなかった。怪訝に思って友人をまじまじと見やる。
「なんだ。しっかり始まっていらっしゃるではないですか」
「うん?」
「まだ序曲未満のようですが」
「うん?」
友人のよく分からない言葉にラグランドは首を傾げる。
「いえ。殿下からお誘いになればきちんと始まるのではないかな、と」
やはりよく分からないことを言う。
ニールは瞳を伏せ、茶を静かに飲み干した。怪訝な顔でそれを見ていたら、「甘いものはもう十分いただきましたので」と、自分のレモンクッキーを皿ごとラグランドに進呈してきた。
ピアノの前に座る小さな婚約者たちが再びピアノを奏で始めた。ワルツの音色はまだ少々おぼつかないが、今日も軽やかで穏やかで、どこかやさしい響きをしている。
聞こえよがしに大きなため息がワルツに乗って耳に届いた。
淡いナントカを僕がもう一つ最前列で見ることになるだなんて、とニールがぼやく。至極面倒くさそうな内容を言ってのける割には、その声音も瞳もいつになく明るい。