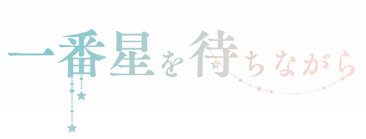
第8話 かそけく歌う小さな灯火
仲良く婚約者殿と陽だまりに満ちたサロンのピアノを連弾する末弟に影響されたわけでも、友人が発破を掛けていたと数日経って気づいたからではない。別に。決して。断じて。
夏は太陽が山の端に沈みきるまで時間が長いのだ。それで、ベルマ嬢とシュプリーム宰相閣下のための迎えの馬車が来るまで、互いの顔がくっきりと見えている時間も自ずと延びているのだ。
ベルマ嬢とははっきりとした約束のもとで待ち合わせをしているわけではない。
夕方にこの中庭でラグランドがヴァイオリンの譜面を確認したり、練習曲を弾いたりするのはいつものことだったし、「お勉強会」を終えた後、王宮に出仕している宰相閣下である祖父殿と一緒の馬車で帰宅するまでの間にベルマ嬢がこの白亜のベンチの四阿で刺繍の練習をしているのもまたいつものことだった。
王宮は安心安全が保証されている場所であり、護衛もそれぞれ見えない位置に控えているので完全に一人きりではないことは確かだ。けれども、この少女が広い中庭にぽつんと一人でいるのはなんだか放っておけないものがあった。
最初の頃は少女が宰相閣下と合流するまで少し離れた位置でヴァイオリンの練習の傍らに見守っていたのだが、いつしか隣で演奏をするようになってしまった。少女があまりにも楽しげに目を輝かせて演奏に耳を澄ませるものだから、もっと近くで聴いて欲しいと欲が出てしまったのだ。
だって、嬉しかったのだ。とても嬉しかったのだ。
音楽学院ではありがたいことに善き恩師に善きクラスメイト、善き友人に恵まれ充実した日々を過ごしている。苦労して進学した甲斐があったというものだ。
彼らは頼りになる演奏仲間であり、気の置けない友でもあり、得がたいライバルなのだ。卓越した腕前に真似できそうにない技巧、楽曲に対する深い造詣、演奏に向ける熱意とひたむきな姿勢。自分より一歩どころか何百歩、何千歩も先を進む好敵手たちに対する嫉妬、焦り、羨望。自分も追いつきたい、追い抜かされないようにしたい。学院で切磋琢磨し合う日々は、そういったことばかりに心が傾いてしまうことが多く、音楽が楽しいという気持ちを時折忘れてしまうのだ。だから、純粋に演奏を楽しんでくれる誰かに新たに出会えて嬉しかったのだ。
兄レオナードの他にもラグランドの演奏を楽しみにしてくれるひとがここにもいる。それは、ラグランドの心をいつだってほのかに温めてくれた。
練習の合間にはぽつぽつとお喋りをした。
学院であったこと、友人の家の陽だまりに満ちたサロンにあるお気に入りのピアノの話。学院の昼食に昨日の夕食のメニュー。兄や弟たちについて。幼い頃に訪問した光都リータスの景色と音楽。今取り組んでいる曲について。
ラグランドはベルマ嬢に色々なことを語り聞かせた。
内気な少女はお喋りに苦手意識があり、三学年上の王子殿下にも少々気後れしていたようだ。口を開いていたのはだいたいがラグランドであったが、少女はいつだって懸命にラグランドの話し声に耳を澄ませてくれた。
二人の共通の話題で(主にラグランドが)一番盛り上がったのは、やはり、長兄レオナードのことだろう。兄がどんなに素晴らしいかを語り合い、やれ今日はこんな言葉を掛けてくれた、やれ昨日のあれそれは実に王子様で立派だったと大いに報告し合う時間は楽しかった。
王妃とベルジーネお姉様に「お勉強会」で褒められたこと。焼きたてのレモンクッキーが美味しかったこと。刺繍が進んだこと。最近子犬が家族に加わったこと。子犬の毛並みは金色でふわふわでとてもやわらかいこと。それから、レオナード第一王子殿下が「こんにちは」と声を掛けてくれたこと。
少女がふわりと頬を緩めて語るお喋りに、うん、うん、と相づちをゆっくり打ちながら耳を傾ける時間は穏やかでもっと楽しかった。
孫娘を溺愛しているシュプリーム宰相閣下からのお咎めがなかったのは想定外であった。祖父殿は急な残業で孫娘との待ち合わせの約束を守れなくなるのが気がかりだったらしい。護衛が控えているとはいえ、末の孫娘に心細い思いはさせたくないそうだ。それで、ラグランドはベルマ嬢の演奏係兼お喋り係として任命された。
そんな日々を繰り返しているうちに、夏が終わり、秋が来て、冬になり、やがて春が訪れて、また夏が巡ってきた。
少女の傍らでヴァイオリンの練習はいつも通りしていたし、少女が心地よさそうに耳を傾けてくれるのもまたいつも通りなのだが、この頃は何故だかそわそわするものがあった。ご年輩の紳士淑女の皆さんに鍛え上げられたトーク術だけでは間が持たず、あわやお喋り係失格の危機でもあった。
ふと降りてくる沈黙が苦痛だったわけではない。むしろ、その沈黙はかけがえのない時間であった。
ベルマ嬢の刺繍を、刺繍を見つめる真剣なその横顔を近くで黙したまま眺める時間をラグランドは気に入っていた。それで、少しでも長くその時間が欲しいと思ってしまった。
ラグランドはベルマ嬢に刺繍の弟子入りすることを決めた。元気よく調子良く無理矢理お喋りを続ける必要なしに間近に少女の横顔を眺める口実ではあったが、自分の手で形になっていく刺繍が楽しくなってきたのも事実であった。
少女に「弟子にして欲しい」とストレートに言えば困らせることは分かっていた。王子が相手に何かを願うとは、そういうことなのだ。
頼み事や願い事に気が引けるのであれば誘い上手になれば良い、と友人は言ってくれた。
頼み事でもなく、願い事でも命令でもなく、ただ、相手を誘う。シンプルなようでこれがなかなか難しい。
唇を開いては閉じ、閉じては開く。祖父母に連れられ、ご年輩の紳士淑女の皆さんに存分に可愛がられ、鍛え上げられたおかげで調子の良いお喋りは苦ではなくなったはずだが、一言が出てこない。たった、一言なのだ。
そわそわと挙動不審な王子を、ベルマ嬢は根気よく待ってくれた。
「あなたの隣で俺も刺繍をしても良いですか?」
ようやっと絞り出せたのは、なんだか教科書に登場する初級会話構文のようなフレーズだった。
けれども、返事はなかった。
「あれ? 聞こえてる? もしもし。レディ?」
ひらひら。手のひらを、目の前で大きく振ってみる。
反応は、ない。
もう一度言わねばならないのか、とラグランドは内心葛藤する。王族の命令と取られていたら「ノー」とは言いづらいだろう。内気で引っ込み思案な年下の女の子なのだ。
ラグランドはその場にしゃがみ込んだ。肩も眉もしおしおと下がる。漏れ出たのは、弱り果てた声だった。だからお願い事もお誘いも苦手なんだよなあ、と。しゃがんだ拍子に頭が木陰からはみ出した。傾いだ太陽の光がつむじに当たり、じわじわ熱くなる。と――
「お返事は『イエス』と『はい』のどちらがお好みですか」
ラグランドは瞳を見開いた。ほのかに口角を上げ、恥ずかしそうに少女が微笑んでいる。ラグランドは目をまん丸にして、それをまじまじと見つめた。
その日最後の太陽の光を受け止めた蜂蜜色の瞳の眩しさに目を細め、ラグランドはゆっくりと立ち上がった。喉の奥からくつくつと明るい笑みが弾け出し、いらえを言葉に乗せた。
極めて難しい質問ですねレディ、と。