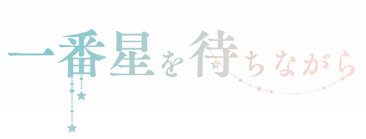
第9話 それぞれの星と空を巡ったら
「どこか違和感はございませんか」
鏡の前でタイを直すラグランドに、侍従が声を掛けてきた。
昔から面倒くさいコーデバトルに巻き込まれてばかりいたせいで、ラグランドはすっかり自分で身支度を調えるのが得意になってしまった。他人に委ねるとろくなことがないし、何よりも疲れるのだ。とても。
「ないない。いや、うそ。あるある。とてつもなくある」
横から鏡を覗き込む侍従にラグランドは真顔で尋ねた。
「やっぱり、俺が出るのは変でしょう。欠席していいよね?」
「許しません」
「ええー……」
「ラグランド殿下には雨が降ろうが槍が降ろうが必ずおいでいただくよう、王妃様からも王太子妃様と王子妃様からも指示が出ておりますので何が何でも出ていただきます」
「殿下が出てくださらないとこうなります、私たちが」
侍従の一人が顔をしかめ、首の前でピンと右手を伸ばして指先をそろえた。彼はそれを静かに横へスライドさせた。
物騒なジェスチャーにラグランドは思い切り顔をしかめた。
「槍が降ったらそれどころじゃないでしょうが……」
王族に血の雨が降るので大問題である。
「子どもが来月生まれるんです! 今から路頭に迷うわけには!」
「今だから言いますけど、家のローン組んだばっかりなんですよね。それを知った矢先に解雇なさるだなんて殿下はひどいおひとだ」
「殿下は人の心がない……」
「今日も手足が長いし、やけにきらきらしているし」
「あー、今日も殿下が美しすぎて色彩感覚が狂う」
散々な言いようである。
やんややんやと侍従も護衛も好き勝手に言ってくれているが、ラグランドは知っている。彼らは軽い冗談を飛ばし合い、気が塞いだラグランドの気分を盛り上げてくれているのだ。
今日はメッセル侯爵家で夫人の誕生日を祝う茶会が開かれるのだ。いつもは免除されている茶会嫌いのラグランドまで招かれたのは、主役のメッセル夫人が祖母の古くからの大親友で、その家の孫娘がラグランドたち兄弟とも長年親交を結んでいるからだ。
ベルジーネ・メッセル嬢は、王妃である祖母イザベルの小さなお友達であり、また、長兄ラグランドの妃候補として祖母主催の「お勉強会」に長年王宮に通っていたお嬢様なのだ。「お勉強会」後のティータイムの相伴という名目で、ラグランドも何度も社交訓練に呼び出されていたこともあり、彼女とは長年の親交があった。弟二人がいるお嬢様は、ラグランドにとっては姉のようなひとだった。いや、義姉になったのであった。
そのひとは長兄レオナードと大変やんごとなき関係になり――二人は結婚をした。
ついに。ようやく。とうとう。
第一王子の結婚について語るには、その副詞がオプションとして常に付いて来る。
婚約にも結婚にも踏み切るまで、孫が相手を随分と待たせたことに祖母は少々お冠だった。けれど、当人である第一王子妃が「そこが彼の良いところなので」と幸せそうに微笑むので角を引っ込めていた。
長兄の結婚を機に、ラグランドは臣籍降下をした。けれども、きちんと公表はしておらず、祖父母と両親、兄との内々での話である。
音楽院でまだ勉学中の身なのでまだ王宮にいるように、と家族は言ってくれた。その温情に甘え、ラグランドはまだ王宮で寝起きをしている。けれども、来年の卒業試験と音楽団の入団試験を終えたら王宮を出ることになっている。合格できないと冗談抜きで立つ瀬がないので、この頃は自分でもあまり考えないようにしている。
下の弟二人が心配そうに声を掛けてくるのをラグランドはいつも笑って交わした。弟の手前、兄のプライドもあり、不安を抱く姿を見せるわけにはいかないのだ。
けれども、彼自身、不安に駆られることもあった。そういうときは、例によって例の如く、叔父の屋敷を訪れて猫ちゃんを抱っこしたり一緒に長椅子でごろごろしたり、友人の家の陽だまりに満ちたサロンに駆け込み、ピアノをかき鳴らした。あとは、夕方に庭園の四阿で師匠と並んで刺繍に励んだ。
刺繍の師匠こと、ベルマ・シュプリーム嬢はあの頃から変わらずにいつも静かに穏やかにラグランドの隣で刺繍に取り組んでいた。
兄と義姉が結婚をしたことで王宮に通う「お勉強会」の一つの目的は終わってしまったのだが、少女は今もなお、変わらずに王宮に来てくれている。孫娘のように可愛がっていた少女の一人を一番上の孫に取られてしまったと嘆く王妃の小さなお友達として、話し相手を務めてくれているのだ。
そして、ラグランドのヴァイオリンにもいつも楽しげに耳を傾けてくれていた。
あの秋の日も、少女はけなげに微笑んでいた。
秋が来て、冬が過ぎ、春が訪れて、夏が終わり、また秋になった。
ある秋の昼下がり、少女は珍しく顔に笑みをいっぱいに浮かべていた。笑顔のまま、上擦った声でラグランドに話しかけてきた。
ラグランドは普段との違いに気づくことなく、少女のお喋りに気安く応じた。女学院は秋の個人面談シーズンで今週は帰りが早いのだ。ラグランドも試験が終わったばかりで高揚していたので、自然とよく口が回った。そのため、なんだか少女がいつもより頑張って自分からお喋りしてくれているな、と気づくのに遅れてしまった。
いつもならば、ラグランドの方から声を掛け、だいたいは少女が聞き役だったのだ。
兄のレオナード第一王子とベルジーネ嬢の婚約が決まったことを少女が初めて聴かされた日であった。
少女の琥珀色の瞳には、うっすらと涙の膜が張っていた。
婚約の報告は、兄が直接少女におこなった。
レオナードはベルマ嬢だけをこの四阿に誘い、二人きりの場で静かにベルジーネ嬢と婚約したことを語ってくれたのだという。兄なりの誠意だ。けれど、兄を心から慕う少女には残酷だ。鋭い刃で斬りかかったも同然だろう。
泣くかな、とラグランドは身構えたが、彼女は泣かなかった。
内気で引っ込み思案で、ひとたび気を許すと安心しきった子猫が陽だまりで寛ぐように頬を緩めて笑い、届かない一番星を想って涙を流した少女は、もう子どもではなかった。過ぎた歳月の分、背も髪も伸びたり、輪郭もやわらかくなったり、所作も大人びてきたり、ラグランドからしたらまだまだ小さいけれど、正真正銘のレディだった。
「大好きなお二人が、結ばれてとても嬉しいです」
そう一言だけ祝福した。けれど、ソプラノはかすかに震えていた。
一日の最後に太陽が色を成す、一番星が上がる黄昏空を写し取った色の瞳を揺らし、少女はそっと微笑んでいた。
思わず腕に閉じ込めたくなるのをなんとか堪えると、男はヴァイオリンケースを担ぎ直し、背を折って礼をした。少女が目をまあるくさせているうちに素早くその手を取って走り出した。
馬車を出すようにいきなり命じた第二王子に、御者も護衛も仰天した。けれども、第二王子が手を繋いだまま、その背で隠すようにしていた侯爵令嬢の泣きそうな顔を見て、もう一度だけ目を丸くすると、すぐに馬車を出してくれた。護衛の一人は、王宮に戻って行った。この少女は「お勉強会」後、いつも王宮勤めの祖父君と屋敷まで同じ馬車で帰るのだ。遅くなる旨を伝えに走ったのだ。
二人のしおしおとした気分とは裏腹に、雲一つなく、澄み切った青空である。王立公園は秋の明るい陽射しに包まれていた。
ラグランドは少女の細い手を捕まえたまま歩いた。心地よい秋風に金木犀の甘やかな香りが漂っていた。少女は何かを言いたげに唇を開いては閉じ、閉じては開くことを繰り返していたが、何も聞いてこなかった。
目当ての屋台に着くと、少女の希望を聞くことなくラグランドは勝手に注文を済ませた。
やがて、専用の丸く分厚い鉄板でほこほこと焼かれたクレープが完成した。
ふんわりと黄色い生地。その温もりにやわらかく包まれているのは、香り芳醇なレモンカードだ。仕上げに店主が薄くスライスしたレモンの果肉をたっぷりとトッピングしてくれた。
少女の両手に大きい包みを持たせると、ラグランドは少しだけ小さい自分の包みにかぶりついた。
「おお……」
ラグランドが大げさに眉を寄せ、唇をすぼめた。少女は蜂蜜色の瞳をまあるくしていた。
「酸っぱいなあ。これは、うっかり目から汗が出ること必至!」
ラグランドは戸惑う少女に笑いかけ、かぶりついては「とてつもなく酸っぱい」、一口終えては「今季最高の酸味」「香り高く芳醇でいて、その鋭さを隠す遠慮を知らない誇り高い酸っぱさ」等とレモンクレープに惜しみない賛辞を贈った。
「ほらほら。君も遠慮せず食べなさい。王子様さえ泣かす罪作りな味なんだぜ」
天を仰いだ王子は指先で目元を押さえ、この秋最高の速度と角度と美しさで、ふらり、とよろめいた。
三拍待った。それから努めてやさしい声で少女の名を呼び、誘った。
「君も一緒に食べてくれませんか」
こくん。
少女はやっとのことで頷きを返してくれた。
それから小さな唇を、クレープに付けた。
「酸っぱすぎるよね? だが、美味しい! 酸っぱさと甘さの見事なマリアージュに我々は泣く術しか残されていないのであった……」
「はい。本当に……」
少女は顔を俯けた。少女の頬からひとしずく、もうひとしずく、透明な粒が落ちた。少女の瞳から堰を切ってあふれた雨が、その頬を濡らした。
ラグランドは何も言わず、少女の正面に立った。
少女が小柄で、自分がひょろひょろと背が伸びていて、良かった。世界から少女を隠し、クレープを食べることにだけ意識を集中させる。
調子の良いお喋りだけは上達したが、勇気あるやさしいレディに掛けるべき言葉も、送るべき励ましも見つけることはできなかった。だから、今度は二人分のレモン水を注文した。カップを一つ少女の手に無理に持たせると、自分のそれを僅かに傾けて、乾杯をした。
そのあとで、男はそのひとのお気に入りのワルツを一曲だけヴァイオリンの調べに乗せた。
侯爵令嬢を唐突に連れ出し、王立公園で買い食いし、歩き回ったことについては、内心反省、否、猛烈に粛々と反省している。
あの日、二人並んで帰路についたのは、一番星……どころか二番星、三番星、と夜の演者が宵闇の天幕にすっかり登壇し終えた頃だった。星明かりに照らされた王宮の中庭に戻ると、シュプリーム宰相閣下が二人を待っていた。
閣下は含むような視線を送ってきたが、何も問わなかった。彼は、ラグランドに深々と臣下の礼を取った。それから大きな手のひらで孫娘の頭と頬を一度だけ撫で、さっさと馬車に乗せてしまった。けれども、その所作も、孫娘を見つめる琥珀色の瞳もひどくやさしげであった。
四阿に二つの影が差している。
何も言わず、何も問わず、繋がれた手を振りほどくこともなくついてきてくれた少女にラグランドは謝罪をした。
いつもの「お勉強会」後、昼が終わり、夕方にゆったりと曲目が変わる時刻である。
やわらかな風に髪を揺らし、少女はそっと首を横に振った。文句も苦言もなかった。
ラグランドは、幼い頃から知っている内気で引っ込み思案なこの少女が急に心配になった。悪い奴に付け込まれそうである。道端で怪しい壺を買わされそうだ。心配になって、つい、零してしまった。
「俺が悪い男だったかもしれないでしょう。駄目だよ、誰にでも気を許して簡単について行ったら」
少女はきょとん、と首を傾げた。それから三拍待って、小さな唇が、開く。ゆっくりと。栗色の眉尻は、ほんのり下がっている。
「……悪いひとは、もっとやさしそうな顔をします。あの日のラグランド殿下は、とても痛そうなお顔をなさっていましたから」
だから、心配することなんてひとつもありませんでした――と。
そう締めくくると、ほどけるようにふわりと頬を緩めた。
上目遣いにまっすぐと向けられた瞳。夕明かりを受けて煌めく蜂蜜色の瞳。その澄んだ瞳の中心に、男が一人、閉じ込められた。それは、ひどく間抜けな顔をした金髪碧眼の男だった。
少女が刺繍枠を持ち直し、顔を俯けた。栗色の長い髪がさらさらと落ち、白くたおやかな頬を覆い隠す。華奢な指が、針と糸でゆったりとワルツステップを刻んでいる。
髪からちょこんと出ている小さな耳は、ほのかに朱い。空が赤みを帯び始め、あたたかな色を成したせいだけではないようだ。
レモン水が、恋しくなった。
王立公園を散策しながらベルマ嬢とラグランドが飲み交わしたレモン水を、ラグランドは無性に飲みたくてたまらなかった。急激に喉が渇いたのだ。
日陰にいるはずなのに、眩しさに当てられたらしい。
「眩しすぎてこちらの色彩感覚が狂いそうです。さすが三国一美しい王子様」
出会い頭に失礼なことを言う友人ニール・オーキッドに、ラグランドは犬歯を見せて応戦した。
この友人に会うまでに散々似たような挨拶を人々から寄越され、コーデバトルにも巻き込まれたのだ。それでいて、寄ってきてもいい……というか、正直に言えば、寄ってきて欲しい、と思う相手はなかなか近付いて来ないのだから、世の中うまくいかないものである。内輪の茶会、と聞いていた割に招待客が多いのだ。同じ会場に居るはずなのに、見たい顔はまだまだ発見できそうにない。主役様の人望の厚さに心から賛辞を贈りたい。
ささくれだった心のまま、言ってやる。
「おうおうおうおう! ニールくんご挨拶だなこんにちはごきげんよう! 減るものじゃないからどんどん見ろ。狂っていいぞ。狂え。狂ってしまえ。それで魔術陣の次の実技試験に苦労しろ」
「すみませんでした」
「うむ。許す」
苦しゅうない、と顎をしゃくる。ニールはほっとしたように息を吐いた。魔術陣は色一つで性能も効能も変わり、採点方法がなかなかシビアで学生泣かせの代物らしい。
「……やりますか」
「……やりましょう」
いつものようにのらりくらりと言い合って、二人そろって正式なお辞儀を交わした。
よく手入れされた芝生と、二人の青年を陽光がやわらかく照らしている。メッセル侯爵家の庭園である。
「正装なさった殿下を拝見するのが久々でしたのでびっくりしました」
よくぞおいでになりましたね、と妙にお兄様めいた顔で感慨深げに褒めてくるものだから、ラグランドは肩の力が抜けた。
「周りのこれがかかってるからね、逃げられなかった」
人差し指で、首を示す。
「なるほど重い……」
友人もまた同情するように深い息を吐いた。
「お前こそ。来ないかと思った」
落ち着いた色合いで、ぱりっとした礼服は、淡い金髪のこの友人によく似合っている。
「妹のお目付役です」
何でもないことのように返答したニールの表情は、僅かにやわらかい。目線の先には、デザートコーナーがあった。そこには彼の年の離れた妹君がちょこんと椅子に座っていた。兄君そっくりの淡い菫色の大きな瞳をきらきらさせ、硝子の器と銀に輝くスプーンを宝物のように手に携えている。アイスクリームに舌鼓を打っているのだろう。淡い金色の髪が、一口進めるたびに歓喜でふるふるふわふわ震えている。
少女の隣では年上の婚約者が守るように控えていた。年上の婚約者こと末弟ヘンリー・ロー第四王子が王子や騎士と言うよりも忠犬のように目を光らせているので、ラグランドは噴き出しそうになった。
「そばに居なくて良いのか?」
「ええ。ヘンリー殿下がものすごく妹に気を配ってくださっているので、お飲み物をお届けしようかな、と」
この茶会には、レオナードたち兄弟にとっても、ベルジーネ嬢にとっても未来の義妹となるニール・オーキッドの妹イザベル嬢もまた招かれているのであった。両親のオーキッド侯爵夫妻は「まだ娘には早いので」と欠席させるつもりであったようだが、「内々の小さなものですし茶会の練習だと思って」と王妃イザベル妃の一声で参加することになったのだ。
それは大きな口実で、祖母は、孫娘に甘えられるおばあちゃま気分を味わいたかったのだ。今日の茶会の主役、お誕生日様であられるメッセル侯爵夫人は第一王子に嫁いだ自慢の孫娘をそばに置き、久しぶりに存分に可愛がっているのだ。
おばあちゃまを満喫する親友を羨んで、祖母は同じ名前のイザベル嬢をどうしても招きたかったらしい。子供二人、孫六人、と全員男子に恵まれた祖母は、女の子を殊更可愛がりたいひとなのだ。祖母は数年前に末の孫の婚約者になったイザベル嬢を、小さなお友達として、「お勉強会」に誘い続けているようだが、父親のオーキッド侯爵がのらりくらりと交わし続けるのでまだ実現には至っていないらしい。
末弟はニールにとって将来義弟になるのだが、彼にとっては既に弟分みたいなものだ。ラグランドがニールの家にしょっちゅう連れて行っていたので、ニールはいつも末弟を気に掛けて可愛がってくれている。寡黙なこの友人を、末弟もまた兄のように慕っていた。
飲み物がそろえられたテーブルには、祖母が見えた。そういえば今日はまだ挨拶をしていなかったな、と思い出す。
「俺も行くよ。おばあ様のご機嫌伺をしておかないと。イザベル嬢をお連れしたいとこだけど、レディだけの王子様がうるさそうだからねえ」
幸せそうにスプーンを使うイザベル嬢を眺めて微笑む弟の恋路を邪魔などしたら、馬どころか祖母にも蹴飛ばされるであろう。
「おばあ様、ご機嫌いかがです?」
「あらラグランド。ごきげんよう。おばあ様のご機嫌は、あなたが出席したのをきちんとこの目で確認できて、とってもよくなったわよ。たった今」
上品な笑みを口元にたたえているが、青い瞳は少しも笑っていない。すぐに顔を出さなかったので減点です、と厳しく言い渡された。
ラグランドは頬を大きく引きつらせた。レモン水をちびちび飲みながら、王妃殿下のお説教を右から左へと聞き流す。祖母が「もう!」とこちらの肩を指でつつくので、「持病の癪が」と胸を押さえてよろめいてみせた瞬間、鈴を転がすような笑い声がした。
祖母の後ろからベルマ嬢がひょっこりと顔を出したのだ。
「こんにちは、ラグランド様」
今日初めてラグランドと顔を合わせてくれた少女はほわほわ微笑み、淑女の礼をした。所作に従って、淡い勿忘草色のドレスの裾がふんわり揺れた。その所作に従い、栗色のやわらかな髪が後ろから滑り落ちた。細い髪は白磁のようになめらかな細い首元、華奢な鎖骨を撫でた。栗色の髪を飾るのは、蜂蜜色の星を象った髪飾りで。陽射しを受けてきらきらと光っていた。
呼吸を、忘れた。
この少女がいわゆる正式な茶会で正装している姿を見るのは初めてだったのだ。いつも「お勉強会」に来るときは、首元がきちんと覆われている楚々としたスタイルだったので、初めて目にしたその華奢なラインに脳の処理が追いつかなかった。
目を開くのと立つことだけに意識が傾いていたらしい。
「あっ!」
「殿下……」
少女の小さな悲鳴と、友人の困ったような声がラグランドを打った。
のろのろと視線を動かすと、右手に持ったレモン水がグラスから零れていた。少女のスクエア型のドレスがあらわにした細いネックラインにびっくりしたのだ。レモン水だってびっくりしたはずだ。そうだそうだと言っている。
「…………」
ラグランドの右手に洪水被害が出たが、誰の服にも零れ落ちなかったのは幸いであった。
祖母の合図で侍従が布巾を差し出すより早く、目の前で栗色の髪が接近した。
「よろしければこちらを」
差し出されたのは、ハンカチだった。
「失礼しますね」
目を丸くしていたら、少女の小さくて華奢な手のひらが、ハンカチごとラグランドの手のひらに伸びた。その細さ、白さ、そのやさしい手付きに瞠目し、ラグランドは急いでハンカチを受け取った。
広げようとした瞬間、少女が手を伸ばし、「殿下! 待って!」と悲鳴を上げた。
けれども、ラグランドは脳の処理が完了する前にそのまま広げてしまった。途端、少女の頭から狼煙が上がった。頬を朱色に染めた少女は、蜂蜜色の瞳を上目遣いに潤ませていた。
「……練習中なんです。まだ」
耳に届いたのは、かそけき声で。手の甲に伝わっていたのは、伸びてきた少女のたおやかな手のひらの温もりで。白いハンカチの半分にまで届いていたのは、蔓模様の控え目なレース飾りで。それはそれは見事に綺麗な仕上がりのレース刺繍だった。
ぱちん。
祖母が細い両手を合わせて微笑んだ。
「時にニールさん、おばあちゃまはイザベルちゃんとそろそろ久しぶりにお喋りがしたいわ」
「妹はアイスクリームに夢中なのできちんとお相手が務まるでしょうか……」
「いいのよ。アイスクリームの感想をたっぷり聞きたいわ。お気に入りのものをお土産にも包んでもらえるよう、おばあちゃまが手配しましょうね」
王妃殿下の美しい青の瞳。侯爵子息の淡い菫色の瞳。はっきりと。くっきりと。しっかりと。ばっちりと。眼差しだけで固い握手を交わした二人は同時に大きく頷いた。
あとはお若いお二人で、と。
ほほほほ、はははは、と何か含んだような声を立てて笑い、二人は足早にデザートコーナーに連れ立ってしまった。
実の孫より仲良しなのでは、と首を捻っていたところにベルマ嬢のソプラノが耳を撫でた。
「殿下の手のひらは、大きいのですね」
かたくてごつごつしていらっしゃる……と続いた言葉に、ラグランドは慌てて手を離そうとする。けれども、その手をもう一度、そおっ、と撫で、少女は笑った。
「ヴァイオリンを、それと、刺繍をとても頑張っていらっしゃる手のひらですね」
ものすごく気恥ずかしくて、それでもとても嬉しくて、誇らしい気持ちになった。
座れる席を探して二人、庭園をゆったりと歩く。すれ違う招待客一人一人に、ベルマ嬢は笑顔で挨拶をしていた。よく喋る彫刻像こと第二王子殿下が隣にいても、臆さずに、優雅に華麗に淑女として振る舞っていた。
今、少女は久しぶりに会った女学院の先輩たちとそれぞれの夫君とお喋りをしている。積もる話もあるだろうとラグランドは少しだけ離れて見守った。……新たなコーデバトルの気配を察知したからではない。
ラグランドは緑のアーチ下で少しだけ襟を緩めた。
さあっと、風が通り抜ける。透明な風は、ラグランドの髪と頬と耳を撫で、葉と緑を揺らした。葉が擦れ、枝葉の合間を縫って秋の陽射しがきらきら光を振りまいた。ふわりと甘く、強い芳香が胸を満たした。
小さな星の形をした金木犀の花越しに、お喋りに花を咲かせる少女たちを眺める。
ベルマが女学院に入った際に親身に面倒をみてくれた先輩たちなのだそうだ。ちなみに義姉ベルジーネの友人でもあるらしい。淑女らしく振る舞うベルマ嬢を、「あんなに小さなお嬢さんだったのにねえ」と眩しいものを前にしたかのように目を思い切り和ませている。
件のベルジーネ嬢こと義姉には先ほど挨拶をした。
三つ目のコーデバトルを終え(『茶会の殿下』とかいうタイトルの肖像画と等身大彫像が誕生することになってしまった)(王室の許可が必要であることは口頭でよくよく説明しておいた)、よれよれになっていた弟に兄夫婦はどこまでもやさしかった。長兄レオナード自ら甲斐甲斐しくレモン水を持ってきてくれたのだ。やさしさが胸にも喉にも目にも沁みた。
「ラグ、レモンパイとレモンクッキーは食べたかい? 疲れたときにはやっぱり甘いものが一番だよ」
気遣わしげに眉を下げる兄に、義姉も続いた。
「我が家のパイとクッキーは、レモンカードもメレンゲもこれでもか、これでもか、とふんだんに使うレシピなのです。目の覚める酸味と爽やかなお味をラグランド殿下にも楽しんでいただけたら嬉しいです」
こくん、と頷くラグランドのために、兄はまたしても自らレモンパイを届けようとした。今日もお兄ちゃんは弟を甘やかすのが上手である。けれど、義姉がそれをやんわりと止めた。
きょとんと瞬く晴れ渡った二対の青空。不思議そうな顔をする兄弟を見つめ、千草色の瞳を眩しげに細めた第一王子妃が笑う。
「ラグランド殿下。待ち人来る喜びあり、と昔から言いますでしょう? 本日はまだお会いできていらっしゃらないご様子ですが、きちんと取り置きしておきます。どうぞお二人でいらしてくださいませ」
目を瞬かせる義弟に義姉は、ふふ、と悪戯っぽく眦を細めた。
兄もおっとり首を傾げていたが、義姉が細い指で腕を突き、「取り置きはこの兄に任せておきなさい」と大きく頷いてくれた。
元監督生の先輩が時折ラグランドにちらり、と向けてくる眼差しは、先ほどの義姉のそれとよく似ていた。
積もる話に花を咲かせる先輩後輩たちをそっと見守る。夫君とは初めて会った様子だが、ベルマ嬢は時折笑顔も見せ、楽しげに応じていた。
あの人一倍内気で引っ込み思案で人見知りも強く、祖父や兄の後ろに隠れてばかりいた少女の成長に目を瞠る。
自分は随分大きくなったけれど、もしかするとこの少女は出会った頃からそのままなのではないか――
ラグランドはふと、そんな馬鹿げたことを考えていた自分に気づく。
頬を和らげて微笑み、相手ときちんと言葉を交わすベルマ嬢は、もう子どもではなくて、少し髪が伸びたり、輪郭がやわらかくなったりした分、正真正銘の立派なレディだった。
なにやら感慨深いもので、胸がいっぱいになる。子猫の木登りを見守っていた母猫もきっとこんな思いをしていたのだろう。
ぺこり、と少女がお辞儀をした。話が終わったようだ。
勿忘草色のスカートの裾をふわりと翻し、少女がこちらに向き直った。
ふ、と蜂蜜色の瞳と目線が合う。
ラグランドの姿を認めた途端、その瞳がゆるゆると細まった。ふにゃ、と頬を緩め、少女が笑う。陽だまりで寛ぐ安心しきった子猫のようだった。
それは三拍にも満たない束の間の光景だった。けれど、その短い瞬間に色々が一気にこみ上げてあふれそうになった。
彼女のあどけない笑み。ラグランドだけに向けられた、とびきり愛らしい笑み。
紳士淑女の皆さんたちの前では決して見せていなかった安心しきって寛いだ笑顔。
胸の奥から湧き上がるのは、きっと、優越感だ。
ラグランドは、まなうらと胸を焦がしたその蜂蜜色の瞳に、いつも紅茶に一匙入れる蜂蜜を思い出した。じんわりと胸のうちから満たしていく温もりとやさしさ。その笑顔を見ただけで、広がっていく甘やかな感情と湧き上がる優越感で胸がいっぱいになる。
緩んでしまう口元を、手のひらで覆った。
どうしようか、少女が戻って来る前に、この上機嫌をどうにかしなくては――
常磐色のアーチを金木犀の甘やかな香りが包んでいる。その清らかでやわらかな香りを胸いっぱいに吸い込み、口を開いては閉じ、閉じては開くを繰り返す。
いつものように調子の良い小粋な話はできなかった。やっとのことで捻り出せたのは、やはり教科書の初級会話構文であった。
「レディ、レモンクッキーを一緒に食べに行きませんか?」
三拍置いてから、少女は瞳と頬を和らげて、こくん、と頷いてくれた。
「殿下。お返事は『イエス』と『はい』のどちらがお好みですか?」
蜂蜜色の瞳の眩しさに目を細め、ラグランドも頬を緩めた。少女に、ゆっくりと手を差し出した。いつか少女に刺繍の弟子入りをしたときと同じやりとりだ。
木登りができたと誇らしげに瞳をきらきらと輝かせる子猫のようにあどけない笑顔。その笑みに乗せられた甘やかで悪戯っぽいソプラノ。
喉の奥からくつくつと明るい笑みが弾け出し、ラグランドは少女が重ねてくれた華奢な手をそっと握った。
とてつもなく難しい質問ですねレディ、と。
その後、そのひとと何を喋ったのか、ラグランドは所々しか覚えていない。なんだか、ふわふわ、きらきらしていたことだけははっきりと記憶している。思い出すと、胸の奥がぽかぽか温められるような、くすぐったい気持ちでいっぱいなる。
レモンクッキーとレモンクレープ、それからレモンパイを二人で食べ比べ、レモン水で乾杯し、甘味と酸味のバランスについて議論を交わした。王宮のレモンクッキーが彼女の中で不動の殿堂入りであることを確認してラグランドはこっそりと微笑んだ。
そして、零れ落ちていた星を拾い、空に戻した。
お喋りに夢中になっていたら、星が落ちそうになっていたのを見つけたのだ。
少女の細い足首を飾る、青いパンプスのストラップリボン。その青空から迷子になりかけていた蜂蜜色に煌めく星。
ラグランドはそっとかがむ。ストラップを留めて、そのひとの空に星を静かに灯した。
「ニール? おーい、ニール。ニールさん。ニールくんや。もしもしニール氏、聞こえてる?」
この友人が心あらずといった様子であるのは珍しい。暇さえあれば新聞『魔術日報』やら雑誌『月刊・魔術の徒』やらの新刊にバックナンバーも読み耽っている男なのだ。茶会の空気に当てられたのだろうか。昼間のガーデンパーティーということでノンアルコールしか振る舞われなかったはずなのだが。それとも祖母が色々と迷惑を掛けたのだろうか。……掛けたのだろうな。
いずれにせよ、この友人ニールの絵に描いたようなぼんやり姿は極めて珍しい。明日は雨だな、と空を確認したが、よく晴れていた。
ひらひら。とりあえず、ラグランドは目の前で手のひらを振ってやる。ようやく淡い紫色の瞳と目線が合った。
「ああ……殿下」
「うん」
何かを逡巡するようにニール・オーキッドは薄い唇を閉じ、まぶたも下ろした。
「殿下もちゃんと王子様なんですねえ」
「うん?」
ラグランドの臣籍降下はまだ内々でのものなので、世間的に一応はまだ第二王子ということになる。何を当たり前のことを言っているのか、片眉を上げれば、ニールが珍しく喉を鳴らして笑った。
「ラグランド様。今日の殿下は文句なく王子様でしたよ。それも、とびきり」
ふわりと緩められた淡い紫色の瞳。それはなんだかひどくやさしい光を宿していた。この友人が年の離れた妹君に絵本を読み聞かせたり、なぞなぞを出したり、長兄レオナードがラグランドの演奏に耳を澄ませてくれていたりするときだけに会うことができる、あの穏やかな「お兄ちゃん」の眼差しとよく似ていた。
「今日はとてもよいものを見ました。青空に星を灯す王子様」
友人の淡い菫色の瞳に悪戯めいた光が宿る。
ラグランドは目を瞬くと、友人が急に寄越したなぞなぞに首を傾げた。
けれども、ハンカチの蔓模様の飾りを見つめているうちに忘れてしまった。
兄と義姉の来年の結婚記念日までに出来の良いレースの縁飾りを編んだハンカチを贈る計画なのだ。どんな図案を刺繍するか、共犯のベルマ嬢と王宮の四阿で作戦を練る約束をしたのだ。
冬が来るまでは、時間が許す限り毎日落ち合う予定だ。
一番星を待ちながら。