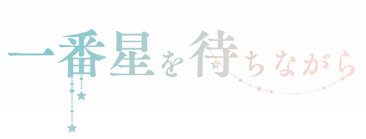
第10話 星の終まで誓う鍾愛
徐々に傾いていく陽の光が、隣に寄り添う花嫁の白いドレスもたおやかな頬もやわらかな栗色の髪も淡く照らしている。
「結婚しよう」
「したばかりではありませんか」
淡々とした返しだが、声音には笑みが籠もっていた。
秋が過ぎ、冬が来て、春が訪れて、夏が終わり、また秋になった。
庭園の四阿で一番星を待ちながら、お喋りと沈黙を二人でいくつ交わしただろうか。重ねた頁をいくつもいくつも捲るように巡る季節を過ごすうちに、いつしか愛称で呼び合うようになり、ついに今日を迎えた。
怖がり屋の子猫が木登りできるように大きくなるのと同じくらい、自分と打ち解けてくれるまで長い時間を要した侯爵家のご令嬢は、今日、ラグランドだけの花嫁となってくれた。
良い返事は何度聞いても嬉しいし何度でも繰り返し聞きたいものなのだ、と言えば、そのひとは口角を上げてほのかに笑った。可愛いおねだりですね、と。
「ではレディ。どちらが良いか、選んでいただけますか?」
人差し指を立て、提案をする。
「一、俺と結婚する。二、あなたはここにいるラグランド・S・サージェントを病めるときも、健やかなるときも、富めるときも、貧しきときも、夫として愛し、敬い、慈しむことを誓う」
瞳の中に花嫁を閉じ込める。
そのひとは恥ずかしそうに栗色の睫毛を伏せて、そっと唇を開いた。
「……どちらも同じではありませんか」
「そうだね。でも、どちらを選んでいただいても俺が幸せになる最高の未来になることだけは確実にお約束します。いかが?」
実際には三拍ほどだったように思うが、希う男にとっては永遠にも等しい時間であった。
「どちらとも選ぶのはいけませんか?」
ラグランドは目を一瞬見開いた。それから恭しくそのひとのたおやかな手を取ると、左薬指に唇を落とす。
黄昏の空を一晩かけて丁寧に煮込み、仕上げに綺羅星を散らした輝きを持つ花嫁の瞳。知る限りこの世でいっとう美しい色の瞳が男を、彼女だけの花婿を中心に捕らえたまま蕩けた。
「とても難しい質問ですね、レディ」
握り返された細い指先を絡め取る。世界で一番難しくて、幸福な質問に、くつくつと笑う。
そのひとも堪えきれなかったのか、その日最後の太陽の輝きにやわらかく照らされた頬をふわりと緩めていた。二人の左薬指にはおそろいの永遠のあかしが銀色に輝いている。
窓の外では藍色の天幕に覆われ始めた宵空にまもなく一番星が煌めこうとしていた。