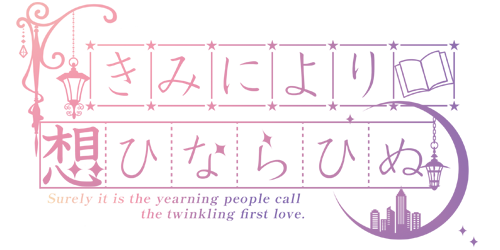「はあ? バレンタインデー延期のお知らせ? なにそれ?」
手本通りの鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしてくれたのは、気の良い友人菊地原士郎だ。
彼は思い切り眉と肩の力を抜いている。けれど、北向きで底冷えのする廊下をモップ掛けする手の力は一切緩めていない。いいひとである。
二月を迎え、世はまさに大学受験シーズン本番である。六頴館高校もまた三年生の自由登校が始まった。
雨の日も風の日も通い、友垣と学び、苦楽を共にした愛すべきこの学び舎への最後の奉仕活動とも言うべきか、受験一辺倒で頭も身体もカチコチになってしまった受験生への気分転換を兼ねているのか、数少ない週に一度の学年登校日にも清掃時間は設けられている。ただし、他の学年は昼休み中なので彼らの妨げにならぬよう充分な配慮が必要だ。
担当の教室内黒板清掃が終わり、掲示板の画鋲を留め直していた少女――宇田川真澄はにこにこと頬を和ませた。「図書室の本返却は早いめに」ポスターの傾きを直せたのだ。
「なにって、延期とは、ある事を行う場合に予定の期日や期限をあとに延ばすことだよ」
「ちょっと受験戦士。得意げに誇らしげに胸を張らないでくれる? 一年の春より語彙力も国語力も遙かに成長したのは評価に値するけどさあ。本命もその調子で頑張りなよね」
菊地原は隠そうともせず眉を寄せたものの、醒めた口調で律儀に指摘してくれた。
ここで無視することも黙殺することも決してせず、褒めて伸ばすことと本命大学受験への激励も忘れないあたり、彼はとてつもなくひとがよい。いつでもどこでも誰にでも丁寧に的確にツッコミを入れてくれる菊地原士郎を、三年間共に過ごしたクラスメイトが口々に「菊地原プロ」と呼び慕っている所以だ。その称号は、彼だけが知らない公然の秘密となっている。
この気の良い友人菊地原士郎は、真澄と三年間同じクラスに所属し、これまた三年間共に持ち上がりの図書委員を務めあげた頼もしい同僚だ。真澄が隣の席の歌川遼に向けられたやさしさに恥ずかしくない自分で在りたい、いつもすてきな彼の紫のばらのひとになりたいと希い、彼の素晴らしさを形容するにふさわしい語彙と教養を身につけるべく苦手な読書に目覚めたり、不得意だった国語の勉強に励んだり、〝歌川くん基金〟を始めたり、なんやかんやを経て、歌川と交際を始めることになったメモリーをよくご存じのひとりだ。
「うん。ありがとう。ちなみにクリスマスもだよ。十月に延期条約を円満締結しました」
「はあ? 歌川からなにも聞いてないけど……?」
菊地原の語尾も眉も大きく跳ね上がる。猫に似た色素の薄い瞳がますます丸くなった。
男の子同士の友人関係だとそういうものなのかな、と真澄はまばたきを返す。
ちなみに真澄は友人各位から根掘り葉掘り口頭試問があった。迫る大学入学共通テストへの鼓舞も兼ね、冬休みに新作期間限定もちもちドーナツを食べに行ったときのことだ。
訳あって、恋人の歌川遼とはクリスマスもバレンタインデーも開催延期条約を円満締結した。真澄が報告するなり、友人の市川あゆみと北見
「遅かれ早かれそうなるだろうと分かってはいたけど、これで確信したわ――この冬、ついに歌川名人、いや、歌川様が聖人の列に加わったと」
「うん。冬のドキドキときめき☆イベントラッシュにも〝待ちプロ〟レベルを常に磨き続ける見上げた歌川名人の高尚たる鋼の心、もっと世界に評価されるべきだよね。死後、歌川遼という名の星座が誕生するのも確定したでしょ。新世界の神じゃなくてもそうする」
月の土地を購入する金額にはとても届かないが、星の命名権を買うサービスは〝歌川くん基金〟からも気軽に購入できるリーズナブルな価格だ。真澄も調べたことがあるので知っている。今後の誕生日プレゼント候補として心のメモにしっかり記しておく。
「でもさあ、真澄」
ストローでぐるぐるとレモンティーをかき回しながら、あゆみが言う。
「本命大学受験目前にときめき☆浮かれ放題問題防止策とはいえ、歌川くんとお付き合いしてから初めてのクリスマスとバレンタインデーでしょう? お互い真面目な二人が決めたこととはいえ、お預けだなんて寂しくないの?」
真澄の本命大学受験日は、バレンタインデーの十日後に控えているのだ。
どう答えるべきか真澄が言葉を探している間に、茉椰が首を縦方向に上下した。
「うんうん。付き合う前、付き合った後。季節ごとのイベントを二人がどう過ごすかについてはマーガレット塾でも花ゆめ塾でも少年ジャンプ塾でも永遠の共通テーマだね」
「然り! 然り! 然り!!」
口ぶりこそおどけているが、二人ともまっすぐと真澄を見つめてくれている。二人が心から真澄を案じてくれているのが嬉しくてくすぐったい。真澄はつい口元をほころばせる。
「そうかな。でも、そうでもないよ。あのね、あの……」
真澄は言葉を探し始める。二人は顔を見合わせ、姿勢を正した。真澄も懸命に唇を開く。
「あのね、その……、遼くんとは、クリスマスから毎日、お互いがその日見たもののなかですてきだなと思ったものを一枚だけ携帯端末で写真撮影して、メッセージ入力も返信もなしで、画像だけを隔日交代で送り合うという大変心温まる交流をしておりまして……」
「クリスマスから」
「毎日」
二人がこちらをじっと見つめたまま大きくうなずいた。示し合わせた様子は一切ないのに、一言一句二人のユニゾンはぴたりとそろった。
「それすなわち現代の交換日記なり」
全身から湯気が立ち上る気配を感じ、真澄はアイスティーを飲み干した。頬が、熱い。店内の暖房が効きすぎているからではない。
あゆみがいつになく真剣な目つきで両手を合わせ、す、と立ち上がった。肩甲骨を隠すほど長く、緩やかな波を描く彼女の髪がふわりと靡く。茉椰もロングボブの黒髪を右の耳にかけ、続く。そして、二人は親指を立てた。天に向かって、びし、と。
「我希望紅茶二杯目牛乳以及砂糖零!」
「同意! 我賛成! 我的口内激甘! 速攻、全員分旨塩揚芋棒確保予定。拒否不可!」
早口でインチキ言語を交わし合い、二人は真澄の頭と頬を代わる代わるわしゃわしゃと撫で回した。言語と熱処理能力の限界を迎え、唇をあわあわ閉じては開くことしかできなくなった真澄を眺め、二人は晴れやかに爽やかに朗らかな笑い声を弾けさせた。
「ふたりはしあわせ! はい、決定!」
「歌川名人がうちの真澄を大事に大事にしてくれている」
「こんなにめでたいことはないね。新年早々景気が良い! 今日も元気だ白米がうまい。ごちそうさま!」
あゆみと茉椰は生温い笑みを浮かべ、声高に「そうそう、そういうので良いんだよ」と空になったグラス同士を合わせた。カキン、と。
「言われてみれば歌川、休み希望を全然出さないんだよな。クリスマスもそうだった」
「うん。遼くんはいつもすごく立派だよね。予定も前もって教えてくれるし」
またしても歌川のいいひと伝説を耳にでき、真澄は嬉しくなる。早く家に帰って〝歌川くん基金〟箱に今日の分を納めたい。
菊地原も歌川も街を防衛する巨大プロジェクトを担う界境防衛機関「ボーダー」の一員である。防衛任務シフトはどうしても外せない用事があるひとの休日希望を優先してほしい、と歌川はいつも公言しているのだそうだ。
「……ああ、なるほど。やっと合点が行った。道理で歌川も宇田川も初めてのクリスマスシーズンとバレンタインデーにしてはやけに静かだったわけだ」
菊地原警視長の鋭い指摘に真澄は息を呑む。ひゅ、と。
「ごめんね。いつもそんなにうるさかったかな……」
思えば、菊地原に真澄はいつも話を聴いてもらっていた。歌川のやさしさと素晴らしさを直撃し、爆発しそうで持て余してしまうどうしようもないこの気持ちを、彼はいつも図書当番登板時に呆れながらも傾聴してくれた。ちょうど二年前のバレンタインデー当日なんて正面玄関まで現実の再確認ツアーにも連れて行ってくれた。やはり、友だちは人間最高の尊称だ。そんな友だちに迷惑を掛けていたのならば申し訳ないことこのうえなしだ。
「うるさいというか、やかましいんだよね……まあ、宇田川の場合、勝ってるのは顔」
「か、顔……」
真澄はがっくりと項垂れた。心当たりがありすぎる。小学生の弟とトランプで遊ぶときさえもジョーカーの行方が顔に全部出て連敗し、姉の威厳はゼロなのだ。心頭滅却すれば涼しマインドが欲しい。心から。
「こら、あまりいじめるなよ」
冬の凜とした空気よりも澄んだ声が耳にも胸にも届けられた。
「りょうくん……」
「出たよ、噂をすれば心臓早鐘瞬間最速兼最多打鍵記録更新保持中常時紳士的微笑可能男」
「うん?」
菊地原がうんざりした口調でなにやら言っているようだが、歌川遼はいつもながら落ち着き払い、慈愛に満ちた爽やかな微笑みを浮かべている。彼のベリーベリーベリーベリージェントルソウルはこの冬も曇り知らずで、北向きの廊下をもまばゆく包む。
「ちょっと歌川。出会い頭に人聞きが悪いこと言わないでよね。いじめてるんじゃなくて、事件の真相に辿り着いて一件落着したとこなんだから」
「事件?」
きょとん、と歌川が首を傾げた瞬間――光が瞬いた。
「はい、整いました。歌川、ぼくが送ったツーショットを次の当番で送りなよ。宇田川に」
菊地原は猫目を細めて、口の両端を吊った。にんまりと。そして、歌川に恭しく両手でモップを授け、教室に戻っていった。取り残された真澄と歌川は、顔を見合わせる。
「あ」
ロッカーにモップを丁寧に片付けていた歌川が、ポケットから携帯端末を取り出した。彼の眦の角が取れ、たまらずといったように破顔した。それからそのひとの丁寧に爪を切り揃えた指が。大きくて、広くて、長くて、硬い指が。筋張っている手の甲が。やさしくて。ひどくあたたかいおとこのひとの手のひらが。真澄を誘った。おいで、と。
大きな手のひらに載せられた携帯端末。その画面に大きく収められていたのは、本命大学受験目前戦士と、彼女の夢が叶うようクリスマスとバレンタインデー開催延期条約をやさしく提案してくれたベリージェントルソウルに満ちた恋人だ。ふたりはそろって目も口もぽかんと大きく開いた表情で写っている。
どちらからともなく、ふたりは頬をほころばせた。
――二月二十五日、歌川の防衛任務シフトは休み申請しておくから。全力で受験に挑むよう宇田川に伝えておいてよね。
写真には菊地原サンタクロース先生からクリスマスプレゼントが添えられていたのだ。
「が、がんばります……!」
周囲のやさしい友人たちから、こんなにもあたたかな祝福と声援をいただいているのだ。合格を目指して心を燃やし、より一層勉学に励まなければならない。握る拳に力が入る。恋人となったひとが、「応援してるよ」と微笑みながら少しだけかがんだ。
ふたりの距離が、少しだけ近くなる。短く切り揃えられた清潔感のある栗色の髪も。形の良い額も。凜々しい鼻筋も。笑うと切れ長の眦の角が取れて、きゅう、と丸くなる、男の子のような笑みも。睫毛がその瞳に降りかかってやわらかく落ちている影も。落ち着いた声も。乾いているのに甘い唇も。ぐっと近づき、真澄は胸が甘くやわく締め付けられる。
「試験が終わったら迎えに行く。連絡して」
「エ」
ぎょっ、と目を開いた。
「はは。やっぱり緊張するかあ。でも、こっちの緊張も少しだけあれば、真澄さんは受験本番の緊張を忘れられるかもしれないよな」
そうっと頬にかかった少女の髪をすくいとって、丁寧に耳へかけ直してくれた恋人は、甘くやわらかに微笑んだ。
真澄に今日あったすてきなもの。それはまさにこの瞬間では――
体感温度が五度上がった真澄は、おろおろと視線を彷徨わせ、恋人を上目遣いに見た。
早々に教室に帰ってしまった菊地原カメラマンをもう一度撮影に呼び戻したい。けれども、恋人となってくれたこのひとが、こんなにも特別やわらかく甘やかな表情を自分にまっすぐ向けてくれている。それは、真澄だけのとっておきの秘密にしておきたくて。
しゅんしゅん。ぐつぐつ。ごうごう。ぐらぐら。真澄の全身が沸騰した。
*…*…*
「クリスマスとバレンタインデー延期のお知らせ?」
恋人となってくれた大事なおんなのこの大きな瞳が、零れ落ちそうなほど一際大きくまあるくなった。
「うん」
彼はゆっくりとうなずく。定期考査明けの昼休み。大学推薦入試の選出にも考慮される最後の大勝負が終わった三年C組教室内は、開放感に包まれていた。元気も熱気も絶賛大爆発している空間を離れ、恋人となってくれたおんなのこを中庭に誘う。校舎のあちこちから小波のように寄せては返す話し声を背景に、隣り合ってベンチに座った。
金色に満ちた秋光。散り始めた金木犀の淡く甘い残り香。五限目の授業がなければこのまま微睡んでしまいたくなるほど、あたたかくて穏やかだ。
卵焼きを箸で摘まもうとしていたおんなのこは、ぱちぱち、と音がしそうなほどせわしなくまばたきを繰り返している。
「ごめん。今話すことじゃなかったよな……」
「ううん。そんなことないよ。ちょっとびっくりしただけだから」
「でも、ごめん」
おんなのこの眦と頬が、ふわ、とやわらかく緩んだ。
「ううん。こちらこそ。気を遣っていただいてしまってごめんね……。ありがとう。遼くんはやさしいね」
深々と頭を下げる宇田川真澄に歌川遼は眉を下げた。それほどでもないよ、と。
いい奴。歩く誠実。長期戦の名人にして待ち構え人プロ中のプロこと〝待ちプロ〟に六頴館高校ベストジェントルマン賞三年連続受賞。そして、どこに出しても恥ずかしくない〝人生七周目〟の名人――友人やクラスメイトに付けられたニックネームには最早笑うしかないが、自分は決して皆に誇れるようなパブリックイメージ通りの善人などではない。
華奢な指で箸を静かに動かし、真澄が卵焼きを小さく分割した。少年ならば咀嚼せずに丸呑みできそうなほど小さく切られた卵焼き。それは、ゆっくりと、少女の唇の奥へ運ばれる。小さくて。みずみずしくて。しっとりとしていて。それなのにあたたかくて。少年はその唇がとてもやわらかく甘いものであることを知っている。
「返品不要、です」
彼女のソプラノが耳に届いた。はっ、と目を見張る。
くるりと綺麗に巻かれて黄金色に輝く卵焼きが、少年の唐揚げ横に着陸していたのだ。ちょこん、と。
「今日のだし巻き卵は、おばあちゃんが焼いてくれたものを産地直送しました。絶品ですので返品は受け付けません」
ほのりと頬を染め、おんなのこがやわらかに笑う。卵焼きを見つめていたのを物欲しそうに捉えたらしい。――正確には卵焼きをじっくりと味わう真澄の小さくてやわらかな唇をつい目線が追いかけてしまったのだが――
恋人となってくれた彼の大事なおんなのこが、たった今、隣で咲き染めの花のように頬も耳も首もほんのり朱く染めて笑っている。ひどくあどけなくて愛らしい。
このこがほしい。けれど、こまらせたくはない。
ふたつの背反する気持ちに胸も脳も全身も甘く苦く熱く灼け切れそうになる。
でも、大事なおんなのこだから。こまらせたくはないのだ。
「ありがとう。大事にします」
だから、噛みしめるようにただそれだけを呟く。
「え? はい。よろしくお願いします……?」
おんなのこは、きょとん、と瞬きを繰り返し、もう一度丁寧に頭を下げてくれた。その所作に黒髪がさらりと揺れ、秋の陽光を振りまいた。
女の子という生き物は記念日やトクベツが好きな生き物である――その命題は、幼い時分より姉と母から教わったので知っている。
恋人の宇田川真澄はとても真面目でやさしい少女だ。自惚れている自覚はあるが、真澄はきらきらとした眼差しをいつもいつでも何度でも歌川遼にまっすぐ向けてくれるのだ。それに時々びっくりするほどの行動力を発揮する勇ましいおんなのこでもある。そんなおんなのこが彼の恋人となってくれ、初めてクリスマスとバレンタインデーを迎えるのだ。
彼の大事なおんなのこは、彼を想って何かとびきり素敵なものを入念に計画してくれるだろう――自惚れている自覚は充分ある。
歌川遼自身も恋人と初めて迎える冬季イベントに浮き足立つ気持ちはある。当然ある。大いにある。六頴館高校ベストジェントルマン賞三年連続受賞と呼ばれても、そうした気持ちは存在するのだ。健全な男子高校生なので。だが、ふわふわ浮き足立つ雑念は、一切合切滅却しなければならない。
今はとても大事な時期なのだ。恋人となってくれた彼の大事なおんなのこは、この冬に国立大学の入試を控えているのだから。
「あのね」
恋人が小さくやわらかな唇を、ゆっくりと震わせた。
「遼くん」
「うん」
「あの、ええと、その……」
「うん」
真澄のソプラノが耳と胸にそっと届く。このやわらかな声をじっと聴いていたい。だから、先の展開を急かしたり、先回りして言葉を挟んだり、無理に引き出したりはしない。
「あの、ね、クリスマスとバレンタインデー開催延期条約の提案にはびっくりしたし、初めてなのにちょっと残念だなって思うのだけれど、嬉しい気持ちも大きいの」
恋人は言葉を切った。ふるり。目の前で長い睫毛が大きく震える。
「自惚れているってことは自分でもわかっているよ。わかっているの……でも、わたしが浮かれず受験に専念できるよう配慮してくれているのも。遼くんがわたしを、わたしの夢も、わたしとのお付き合いも大事にしてくれていることもわかるから。それがわたしは嬉しいの。とても」
上目遣いにまっすぐ注がれた瞳。陽だまりを受けて綺羅星を灯す瞳。今、彼の大事なおんなのこの澄んだ瞳の中心に居るのは、一人だけだ。たった一人。目の前の男が、一人。
それはとうに知っているはずなのに。ずっと前から知っていたはずなのに。
防衛任務の帰り道、夜空に輝く星を見つけたときのように彼の胸にやわらかく灯る。
「延期ってことは、中止ではなくて。未来を約束してくれているということでしょう? 最初だけじゃなくて……最後まで予約できたら、嬉しい」
眦をまぶしげにやわらげて、真澄は花がほころぶようにわらう。
恋人となってくれた彼の大事なおんなのこは、効果ばつぐんの言葉を時折まっすぐと惜しみなく紡ぐのだ。
このこがほしい。けれど、こまらせたくはない。どうしてくれようか――
歌川遼にできたのは、手のひらで口元を覆い、天を仰いで慎重に息を吐くことだけだった。次に八拍数える。それから胸中で元素周期表をたっぷり五周唱え、表情筋に力を入れる。
「え、と……、その、ごめんね。今のなし」
おんなのこは、遅れて我に返ったらしい。それだけを口走り、恥ずかしそうに長い睫毛を伏せた。髪を小さな耳にかけ直しては、おろすことを繰り返している。
「返品不要だったよな」
ふるり。頬も耳も首も薔薇色に染めたおんなのこがふるえた。恥ずかしさと嬉しさが入り混じったおんなのこの顔を、うすい涙の膜が張った瞳を、彼は上から見つめ、わらう。
「え」
「覚えてるかな? オレが真澄さんに長期保証は無期限でお願いしていたこと」
「え、と……?」
戸惑いを隠さず小さく揺れる上目遣いの瞳に、彼はわらう。
「真澄さんも知ってると思うけど、オレ、長期戦も待つことも得意なんだ。だから――」
陽だまりであたためられた風にやわらかく揺れるおんなのこの黒髪へ、指先を伸ばす。それを小さな耳にそうっとかけ直す。そっとささめきごとをするように。少年は、少しだけかがんでおんなのこの耳元で囁く。
「こちらこそ、真澄さんの最初から最後までをこの先もずっと予約させてもらえたら。嬉しいです。とても」
真澄からの返事はなかった。言葉では。
彼の大事なおんなのこの澄んだ瞳が、まぶしげに細まった。ふにゃり。眉も頬も小さくてやわらかいその唇も大きくほころばせ、薔薇色に頬を染めたおんなのこは、花咲けるように微笑んだ。そうして、恋人となってくれた彼の大事なおんなのこは、深く大きくうなずいてくれた。こくん、と。
思い返せば、互いに大胆な約束を交わしたわけだが許されたい。先攻は真澄からだったのも許されたい。クリスマスもバレンタインデーもお預けとしているので差し引きゼロだ。
自惚れている自覚は存分にある。やさしくて素直な真澄のことだ。自分と初めて迎えるクリスマスとバレンタインデーにも当然注力するだろう。このおんなのこは、一年生の頃から〝歌川くん基金〟なるものを始め、今も続けているのだという。けれど、これから受験本番に向けて大詰めの大事な時期になる。今まで真澄がひたむきに続けてきた努力が大きく伸びて実を結んでほしい。目先の娯楽を優先することで、その引き換えに悲しい思いも後悔もしてほしくないのだ。決して。
それに余計な疑問を差し挟まない素直さは彼女の可愛くて美しいところだ。クリスマスとバレンタインデーの開催延期条約を締結するだけでなく、この先の最初と最後をそのままもらい受ける無期限長期保証まで言質をとった男は、気を抜けば緩んでしまいそうになる眉と頬と口元を引き締めた。
「大本命の決勝戦は……まず共通試験を突破しないと入場券すら手に入らないのだけれど」
へにゃん。真澄の眉が下がった。母が持たせてくれたみかどみかんを半分に割り、真澄に差し出せば、
「ありがとう。いただきます。わたしからは卵焼き一切れだったのに。わらしべ長者かな」
くすぐったそうにわらいながら受け取ってくれた。おとなしく、物静かな少女が自分にだけまっすぐ向けてくれる寛いだ笑み。胸に込み上げて光るのは、優越感だ。
三年生に進級する直前、真澄と正式に歌を交わして男女交際する関係になってから(一年生の頃に朝読書を始めたという彼女の言葉の引き出しは、時々びっくりするほど愉快だ)、毎日昼休みのたびに一分ずつふたりで過ごす時間を増やし続けてきた甲斐があるものだ。その長期戦には菊地原はじめ友人たちに散々呆れられたし、笑われたりもした。だが、去年の今頃は朝夕に教室で交わす挨拶だけでも緊張を露わに震えていたおんなのこが、今では少年の隣で淡く頬を染めて、くすぐったそうにわらってくれているのだ。みかどみかんの今シーズンの糖度について感想まで分かち合いながら。プライスレスだ。
「ずっと応援してるし、力の限り応援するよ」
「うん。ありがとう」
真澄が目指している国立大学もまた他の国公立大学と同様に前期日程試験が二月二十五日に行われる。バレンタインデーのほぼ十日後だ。多くの大学と同じく、その前哨戦、一月の大学入学共通テスト成績が合否判定に深く関わってくるのだ。
三門市立大学にボーダー枠で一足早く推薦合格が決まった歌川遼や他のボーダー隊員たちを、真澄は妬んだり羨んだりすることはなく、心から祝福してくれた。
――この街も、この街に暮らす誰かも、その誰かが何かを大切に想う気持ちも、それをいつも大切に護ってくれるひとたちが正当に評価されて嬉しい。
まぶしそうに、きゅう、と眉を下げ、祝福してくれたのだ。
彼の大事なおんなのこの素直でやさしい気持ちをがっかりさせたくないし、大切にしたいなと思う。真澄が大切にしている夢を大事にしたい。それを応援したい。心から思う。
自惚れている自覚はある。非常にとてつもなく尋常ならざるレベルでその自覚はある。
このやさしいおんなのこは誰かの喜びも自分のことのように喜んでくれる素直な心を持っている。ささやかな喜びも大きな楽しみも共に分かち合うことを惜しまず大切にしてくれ、ほのりとわらってくれるのだ。だから。
「ひとつだけ、真澄さんにお願いをしてもいいかな?」
*…*…*
防衛任務から帰り、母の用意してくれた夕食をゆっくり堪能し終えた頃。胸元が震えた。微睡みから醒めた少年は、深く寄りかかっていたソファから立ち上がる。それから姿勢を正して座り直した。
胸ポケットから携帯端末を手に取り、人差し指でスワイプする。
メッセージの新着通知アイコンがぴこぴこ点滅していた。そわそわ。わくわく。うきうき。どの副詞も該当しそうだな、と彼は緩みきった頬のままメッセージアプリを開く。
届いていたのは、写真が一枚。黄金色に輝く、ふわふわふくふくしたものが一本だけ写っている。大地に降りた落ち葉を踏みしめたアングルで威風堂々、凜々しく直立しているのは、真澄の家で暮らす愛犬、太郎の可愛い前脚だ。
恋人からのメッセージは一言もない。タイトルも付けられていない。彼が真澄にそう願ったからだ。
その日見たもののなかで素敵だと思ったものを一枚だけ携帯端末のカメラで撮影する。その画像にはメッセージを一切入力せず、ふたりで交代しながら一日おきに送り合う。ふたりはそれを――友人の菊地原と先輩の宇佐美には「出たよ、現代の交換日記」「ひゅー! ハッピーじゃん」と思い切りニヤニヤされたが――クリスマスからずっと続けている。
それぞれが撮影と送信を担当するのは隔日一枚。メッセージもタイトルも決して入力してはいけない。届いた写真には返事もスタンプも送ってはならない。撮影時、決して〝映え〟を追及してはならない。次の登校日に何を撮影していたのか簡潔に答え合わせをし、それがどんなに素敵なものであるか感想を伝えて分かち合う。
クリスマス及びバレンタインデー開催延期条約締結時、恋人に少年が希ったことだ。
直接逢うことも話すこともなかなか叶わないから。受験本番に向けてひたむきに勉学に励む真澄を応援したいから。けれど、真澄の時間も思考も独占してこまらせたくないから。大事なおんなのこなのだ。
二月の本格的な受験本番シーズンに突入してから、六頴館高校も自由登校となった。幸運にも三年間ずっと同じクラスになれたとはいえ、二月二十五日に決戦を控えた真澄と、秋には三門市立大学のボーダー枠推薦合格を手にしていた彼とでは放課後の予定は見事なほど合致しなかった。受験を終えた少年には防衛任務が次々に割り振られたし、真澄が選択受講している課外授業――三年生に進級してから開始した国公立大学と難関私立大学を目指す生徒向け補習授業だ――の入っていない日が合致する放課後は、秋から冬にかけてもやはり少なかった。
「歌川が自分からシフト希望出さないからでしょうが」
半眼になった菊地原から冷たく指摘され、返す言葉もない。けれども、防衛任務シフトは用事がある者の休日希望を優先してほしいのだ。それに――まるでひとひらの光の如く、真澄からまっすぐに届けられた言葉が、今も少年の心を静かに照らしてくれているのだ。
――ボーダーのひとたちがこの街を護ってくれているから遼太も太郎もわたしも、ううん、街の皆も。皆が安心しながらこうして散歩できるんだなって。ここで街の灯を見るたびに思ってる。
その気持ちを大切にしてくれるやさしいひとが、可愛がっている弟と愛犬と明日も安心して散歩できる街であってほしいから。特別外せない用事がない限り、体調不良でない限り、決して部隊にも自身にも負担にならない範囲で彼は防衛任務に向かっている。
逢って声を聴きたい。ほのりとわらう顔を隣で見たい。けれど、こまらせたくはない。真澄は大事なおんなのこなのだ。ふたつの背反する気持ちに揺れる少年に答えを授けてくれたのも、彼の恋人となってくれた大事なおんなのこだった。
――貴方と次にお逢いできるときに、なにからお話ししようか、なにを伝えようか、考えるのも楽しいのです。まぶしそうにわらって、貴方がじっと耳を傾けてくれるのが嬉しくてたまらないのです。だから、次にお逢いできるときまでにひとつでも多く、素敵なものをたくさん見聞きしておきたいな、と、わたしはどんどん欲張りになっています。
春に真澄から贈られた手紙には、そう綴られていた。
理系コースに進み、苦手としている漢字小テストと古典単語小テストのたびに窮したようにいつも眉を下げている真澄が、少年への想いを込め、まっすぐでいつまでも見つめていたくなるうつくしい筆跡で綴ってくれた手紙だ。それは、彼のとっておきの宝物だ。
晴れて交際を始めた直後、彼はボーダーの遠征に赴くことになった。せっかくの春休みだが、デートをすることも通話をすることも叶わなかった。そこで春休み中に手紙を書き、新学期にそれを交換しようと約束し合ったのだ。互いに照れ笑いを浮かべながら。
逢えない時間が愛を育てる――古今東西、和歌にもポエムにも歌にもしるされているテーマだ。なるほど、それは確かなことだ。真澄と逢えない日々でも「現代版交換日記」を交わすうちに、少年もまたその定説を実感した。
おばあちゃんが焼いてくれたふっくらだし巻き卵。防衛任務に向かう道で見つけた淡いピンク色の乙女椿。解き終えたばかりの移動する点P問題。夕空と焼き鳥屋の赤い幟。陽だまりに向かい凜々しく座る柴犬のふわふわの耳。最寄り公園で膨らみ始めた梅のつぼみ。立春を越え、日脚の伸びた庭でひなたぼっこをする弟と愛犬の後ろ姿。母と作った鶏そぼろと卵ときゅうりの三色丼。夕陽に包まれた赤本の表紙。明日の登校日――前期日程直前だ――に彼女へ渡す縁起の良い駄洒落た名称で受験生にお馴染みのチョコレート菓子。
ふたりで交換した画像は、どれもごくありふれたものばかりだ。けれど、そのどれもひとつひとつがいとおしい。言葉は交わさずとも、真澄の横顔も真澄が過ごした時間も真澄のやさしい眼差しを通した世界も垣間見えるからだ。
未明に降ったみぞれは、量も少なく、降る時間もほんの僅かだったようだ。日が昇る頃に道はすっかり乾いていた。午後の駅前通り。風は時折吹くものの、顔をしかめたくなるような冷たさはない。初春の陽だまりがあたためてくれているらしい。
朝まで降り続いたり、路面が凍結したりするトラブルがなくて良かった。今日だけで何度目にもなる安堵の息をつき、彼はマフラーを少しだけ緩めた。
下校児童の見守りを呼び掛ける本日二回目の三門市役所無線放送が始まると同時に、ホームに滑り込んで来る電車が見えた。
改札口を出入りする人波が割れた。紺青色のダッフルコートに身を包む真澄が見えた。首元でころんとした結び目を作った白い毛織りマフラーを、渡る風にふわふわと揺らしている。こちらに気づいた恋人は、安心しきったように頬と眦を緩めた。
「真澄さん、お疲れ様。おかえり」
「ありがとう。ただいま。遼くん」
いつも通りの穏やかでやわらかな笑みだ。けれど、疲れも滲んで見える。無理もない。ずっと目標に掲げていた大学で入学試験本番に臨んだのだ。併願校の受験も終えて得意な数学と理科の試験に挑んだとはいえ、本命との決戦だったのだ。長期にわたった戦いをようやく終えて会場を後にした今は、張り詰めていた緊張も解けて緩む頃だろう。
試験の手応えについては聞かない。何も聞けない。今から彼にできることは何もないのだ。けれど。
――今日の試験本番までひたむきに歩き続けた真澄の元にもさいわいがやってきますように。
天空目がけて枝をいっぱいに伸ばす街路樹にそっと祈る。桜だ。まだつぼみは一つも見えない。待ち侘びた春を告げる花のつぼみが膨らむ頃、彼女の元にもあたたかな春が訪れてほしい。
春の陽射しを受けて淡く光る鴬宿梅に目を細めていたおんなのこに、彼は笑いかけた。
「真澄さん。――オレと一緒に悪いことしないか」
おんなのこは、きょとり、とまばたきをした。首を傾げたおんなのこにほんの少しだけ待ってもらうようおうかがいを立て、彼は足早にコンビニエンスストアへ入る。
「真澄さん、本当にお疲れ様」
ほかほか白い湯気を立てる中華まん――三月には終売する金の豚まん――を真っ二つに割り、大きい方を彼女に差し出す。
彼女の小さくやわらかな唇と大きな瞳がまあるく開かれた。冬ざれに煌めくイルミネーション。晩夏に染まる街の灯。枝葉の合間を縫って大きく降りた秋の夕明かり。やはり、このおんなのこが灯す瞳には、まろくやわい春の陽がよく似合う。たとえば今日のような。穏やかに降り、教室のカーテンを明るく透かして世界をやわく包み込むような春の光が。
「このあとお夕飯だよ……?」
「うん。楽しみだな。おばあちゃんの特製クリームシチュー。でも、大丈夫だよ。まだ少し時間もあるし、日も随分長くなったし。鞄を置いたら遼太と太郎も誘って散歩に出よう」
試験を終えた真澄を迎えに行くことは、彼女の家族に報告していた。真澄の祖母も母も弟の遼太も「夕飯を一緒に食べよう」とにこにこ上機嫌に誘ってくれたのだ。ご厚意に甘え、現在に至る。
「でも、少しだけ。お疲れ様会も兼ねて一緒に悪いことしよう。ふたりだけで」
真澄は、ぼう、とこちらの指先を見ていた。けれど、徐々に淡く頬を染めて、くすぐったそうにきゅうと眉を下げ、睫毛も伏せた。長い睫毛が、ふわ、と春風に揺れる。咲き染めの花が震えるような笑みに少年もまたつられて口元を緩めた。
恋人は丁寧に紙包みを開くと、まるで宝物を手にしたように瞳をきらきらさせた。
そうして、彼の大事なおんなのこは、その小さくやわらかな甘い唇で中華まんにゆっくりとくちづけをした。
「りょうくん」
「うん」
おんなのこの右手と右足が、同時に前へ出る。頬を緩めて真澄のソプラノに耳を澄ます。
「あの、あのね」
「うん」
「あのね、久しぶりだからかな。遼くんと一緒に帰るの、すごくどきどきする……」
おんなのこの左手と左足がそろって前へ出る。おんなのこはマフラーと、制服スカートと、髪を、細い指先でそわそわおろおろ整えている。かがんで真澄の顔をそっと覗き込む。
「……爆発しそう?」
「う、うん。するかも。どうしよう…………今日は家に帰りたくない」
頬も耳も薔薇色に染め、炸裂弾よりも遙かに威力絶大なことを紡いだ彼の大事なおんなのこの小さくやわらかでとびきり甘い唇。意識と理性を総動員して彼は視線を引き剥がした。大きく天を仰ぐ。元素周期表と古語動詞活用種類を脳裏で七周ずつマラソンさせる。
慎重に吐息すると、少年は彼女の頬にかかる髪に指を伸ばした。緊張と羞恥で潤んだ瞳のまま、上目遣いに首を傾げるおんなのこをまっすぐ見つめ、わらう。指に絡めていた髪を、その小さくやわらかい耳にかけ直しながら。
「うーん。どうしよう。どうしてくれようか」
一度下ろした手のひらを差し出す。ふわ、と眦も頬もやわらげておんなのこがわらう。おんなのこは、そうっと少年の手の上にやわくたおやかな手のひらをのせた。
ふたりで鴬宿梅を眺める。春雪に似た白い花は、陽射しを受け止め輪郭もやわらかい。
捕まえた指先に移るあたたかな熱が、ふたりの境界線をとかしていくように思えた。真澄はとっておきの宝物を見つけたときのように瞳を煌めかせている。彼のすぐ隣で。
近くまで降りてきた春の足跡を、ふたり同じ歩調でゆっくりと探す時間は思いのほか楽しく、そしていとおしかった。