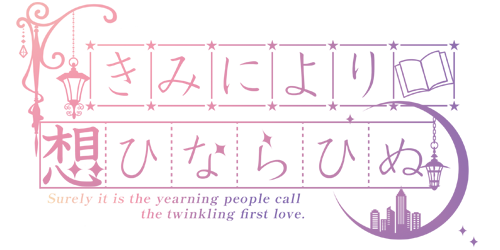決意して、頤から手を離す。小さく甘くやわらかな唇を、そっと、彼のものから解放する。
ふるり。意識も時間も呼吸も――ひょっとすると心臓までも停止していた彼の大事なおんなのこが、ちいさくふるえた。おりていた瞼が静かに押し開かれる。澄んだ大きな瞳は、明け方に葉と花びらの上で結ばれた露のようにまあるい膜を張り、潤んでいる。宵闇に灯り始める星の光を宿した瞳の中心には、眉を情けなく下げた男の姿だけが閉じ込められている。
「りょうくん」
おんなのこが、囁いた――聞き逃したのには訳がある。甘くやわい唇と煌めく瞳に意識も視線も何もかもが縫い止められていたのだ。彼のパーカーの裾が、引かれた。きゅう、と。
ぼう、とこちらを見上げた恋人は、朝陽に縁取られてやわらかに光る甘やかな唇を、そうっと開いた。
「……あの、おしまい?」
瞬間、さあっと風が吹き、足元の秋草を揺らした。風の音以外、虫の音も、常磐色の樹下のベンチまで届いていたはずの公園内で弾む笑い声も、少年の呼吸もすべて止まった。
身体が、芯からふるえる。その言葉は通常弾よりも速く鋭く、心のいちばん奥までまっすぐに飛び込んできたのだ。
歌川遼は理性を総動員し、脳裏に不定積分の公式、定数倍、和・差の定積分の公式、それからジュールの法則を光の速さで七回綴った。その後、十六拍数えてなんとか表情筋に力を入れる。恋人となってくれた彼の大事なおんなのこの長い髪をそうっと耳にかけ直し、細い背に手を回す。それから努めて静かに息を吐く。燃え続ける額を小さな肩口に押しあてて、やっとのことで呟いた。
おかわりは何杯までいいのかな、と。