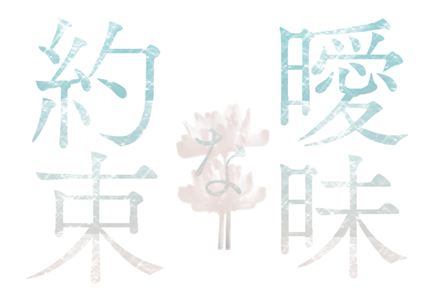
とりあえず、状況を把握しようと、彼女は顔を上げた。
「あ、一番星」
ため息混じりにぽつりと呟く。途端、あくびが一緒に漏れた。
どこまでも澄んだ夕焼け空に浮かび始めた星を見上げ、少女はのろのろと手足を丸めた。
あたりは静けさに包まれていた。耳を澄ませば、時折、遠く校庭から生徒たちの声(おそらく体育委員会の活動だろう)が聞こえてくる。
少女はというと、あたたかい日の光が差し込んでくる絶好の席でのんびり優雅に星空観察の準備中――
「やっぱり、痛いかも」
――というわけではなかった。
忍術学園には校庭を始め、広い場所がいくつもある。いうまでもなく、実習訓練のための場である。授業や試験のため、また、単純に自分自身の能力を高めるためにと放課後や休み時間を費やし、鍛錬に励む生徒も多い。
内容は今日授業で習ったばかりの実践をはじめ、ランニング、同級生たちとの組み手、武器やら火器やらの練習。更に上級生ともなれば本格的な罠作りにまで及ぶ。
ところで仕掛けた罠はというと、たいていはそのまま放置される。いわく、「忍者としての勘を磨くため」の訓練にも使えるからだ。仕掛け、回避、脱出といったように一粒で何度でも美味しいという鍛錬なのである。そのため、下級生は度胸試し以外では演習場を独りで歩き回らないことが学園内で暗黙の了解となっていた。
頭上には、今まさに落とされた落とし穴が、大きく口を開けている。
落下の衝撃に関しては、受身を取ったため、それが緩和材となってそれほどではなかった。ただ、受身を取ろうとした拍子に肘を擦りむいたようで、傷口からはじわりと血が滲んでいる。
痛いけどお腹すいたなあとか、食堂よりも先に保健室に行かなくては駄目かなあとか、そんなことを考えながら少女はしみじみと嘆息した。
服についた土を軽く払いながら立ち上がろうとする。
――途端、足首に痛みが走り、彼女は地面へと再びへたり込んだ。
どうしたもんかなあ、とまた一つため息が零れた。
と――
何か脳裏に閃くものが走った。少女は双眸を眇めた。
来る――
とっさに身構え、座ったまま数歩後ろへ下がる。それは、判断によるものではない。本能がささやいたのだ。
次の瞬間――
「おわあぁぁぁぁっ!?」
叫び声とも雄たけびともつかぬ音が鼓膜をたたく。
同時に、凄まじいスピードで落下してきた何かが、地面に激しくぶち当たった。
どすんっ!
短い音とともに、地面が衝撃に揺れる。
土埃がすっかり舞い上がってから、数秒――しばらく待ってから少女は顔を上げた。
視線の先では人のようなものが地面に倒れていた。気のせいでなければ多少めりこんでいるようにも見える。
「……ええと、生きてます……よね」
うっすらと冷たい汗が額に浮かぶのを感じつつ、少女は、その人影へと近寄ってみた。草色の忍者服に、同じ色の頭巾。すぐそばに落ちている算盤。これは相当な重さのようで、地面に鋭く突き刺さっていた。
見覚えがある。というより、他に思いつかない。同じ忍術学園の三年生である。うつ伏せに倒れたまま、ぴくりとも動かない少年をのぞき込んで、少女は息を呑んだ。呼吸をしていなかったら全力で逃げるべきか、それともそっと埋めてやるべきかを思案しつつ、少年の背中へと手を伸ばす。
と――
「あー、吃驚した!」
がば、と急激な速度で少年が起き上がった。彼は頭上にできあがった巨大なたんこぶなど全く気にせずに左右へと視線を振ると、こちらへと向き直った。自然、互いの視線が交わる。
その瞬間、二人の時間が止まった。
時間にしてほんの数秒。二人は口を開いたまま、果てしなく間の抜けた表情で互いを見つめ合った。
「ええと、こんにちは」
先に沈黙を破ったのは少女だった。
「何をとぼけたことを言ってるんですか。今は『こんばんは』の時間です」
少年のどこかずれた――けれども迷いなく放たれた――指摘に、少女はやや遅れた拍子で手をポンと打った。
「あ、そうでした。こんばんは」
「どうも。こんばんは」
互いにぺこりと頭を下げる。
「ところで」
「何ですか」
「その算盤、何だか地面にめり込んでいるみたいですけど、大丈夫なんですか?」
少女の投げた疑問に少年はぱちくり、と瞬いた。算盤へゆっくりと視線を送る。そして、――再びこちらにまっすぐと向き直った。眉一つ動かさず、どうということもないように口を開く。
「問題ありません。特注の一〇キロ製ですから。無駄に頑丈なんです」
「いやいやいや、問題ありすぎですよ。そんな危険なもの落下させないで下さい!」
少女は声がひっくり返るのを自覚しつつ、相手の爆弾発言に力の限り抗議した。
相手はちょっと迷惑そうに眉間にしわを寄せた。
「委員会活動中だったんです。仕方ないでしょう」
「へ……委員会ってもしかして」
少女がぼんやりとした声で聞き返した。
「神崎ー、いるか? いたら返事しろ」
聞こえてくる声――
それに対して少年が顔を上げるのが見えた。
「潮江せんぱーい! ここです、ここにいます! 塹壕の中ですっ!」
少年が穴の外へと叫び返す。
「何ィ!? 塹壕だと? たまごとはいえ、仮にも忍者が塹壕に落ちるなど言語道断! 全くもってたるんでる――」
怒鳴りながら穴を覗き込んできた『先輩』のしかめ面をとらえ、少女はへらりと頬を緩めた。
「げ」
先輩――会計委員会委員長・潮江文次郎そのひともこちらの姿を認めたらしい。よく見慣れたその顔がひくり、と引きつるのが見えた。
「こんばんは」
ひらひら、と手を振ってやる。けれども、彼はそれをあっさりと無視し、眉間に深くしわを刻んだ。
「そこで何をしている?」
「ええと、世間話?」
同意を求めるように会計委員の少年へ視線を向ければ、彼もまた首を傾げながら頷いた。
やや引きつった声音で再び文次郎が問う。
「……なぜここにいる?」
「やだなあ。わかりきったことを聞かないで下さいよ」
「…………何?」
こちらを睨みつけてくる表情が一気に険しくなったようだが、彼女はそれを無視した。ぴん、と人差し指を立てて告げてやる。
「そこに穴があったから」
「面白くない上に上手くないことを言うな!」
「ぎゃあ!」
降り注いだ怒号に、塹壕内の二人は座り込んだまま飛び上がった。
早鐘のように鳴り響く心臓をなだめ、少女は口を尖らせる。
「ちょ、ちょっとしたお茶目に本気で怒鳴ることないじゃないですか」
と――
気のせいでなければ、小さな音が聞こえた。小気味よく、何かが切れる音。つまり、ぷつんという音だった。
「はははは……」
「潮江先輩?」
「? なんですか?」
「はっはっはっはっはっはっは……」
潮江文次郎は、上体を反らして笑い続けた。その大音声に塹壕内の空気がびりびりと震えた。やがて、彼はこちらを見下ろす。ゆっくりと。
双眸に激しい炎を燃えたぎらせ、彼は言い放った。
「よし、お前ら俺が今から十を数える間に這い上がって来い。一秒遅れるごとに褒美としてグーで殴ってやる」
「げげげっ。潮江先輩、無茶を言わないで下さいよう!」
神崎少年が絶叫し、慌てて立ち上がった。その顔色は蒼白を通り越し、ほとんど土気色のようだった。彼は壁面にくないを立て、のたのたと上り始める。
「いーち、にーい……」
一方、地上で笑みを浮かべながら数え始める潮江文次郎はひどく楽しげだ。しかし、その笑顔はちょうど影が覆いかぶさっていて、どう見積もっても不気味なものにしか映らなかった。
「……しーち、はーち」
「うへえ、助かっ、たっ……!」
ぜえはあと息も絶え絶えに、神崎少年が叫んだ。どうやら無事に地上へとたどり着いたらしい。
彼女は座ったまま、ぱちぱちぱち、と拍手を送ってやった。神崎少年がぐったりしつつも上から軽く会釈を返してきた。
「伽夜」
名を呼ばれ、少女は目をしばたたいた。
「いつまでそこで呆けているつもりだ。お前もさっさと上がって来い。本気で殴るぞ」
「や、あのですね、さっさと上がりたいのも山々なんですが」
「…………何だ?」
たっぷりと沈黙をつけて、相手が聞き返してきた。そのしかめ面をまっすぐと見上げ、答えを紡ぐ。
「足をひねっちゃったみたいです」
「この馬鹿タレ!!」
ばさばさばさっ!
鳥の羽ばたきが、激しく耳朶を打った。
唐突に鳴り響いた彼の怒号に反応し、一斉に飛び立ったのだ。ギャアギャアという鳴き声が徐々に遠ざかっていく。
「そういうことは早く言えっ!」
ひんやりとした風が頬を撫で、髪を揺らす。
久しぶりに地上の空気を吸って、彼女はしみじみと嘆息した。
潮江文次郎の背中に負われ、塹壕からようやく地上へと帰還を果たしたのであった。
「文次郎ちゃんって何だか……」
「何だ?」
「忍者みたいですね」
「馬鹿タレ! 『みたい』じゃなくて忍者だ!」
文次郎が怒鳴り返し、背中が揺れる。振動が伝わってきて、小夜はびくりと首をすくめた。
ぼそりと呟く。
「そんなに大きな声で言わなくても聞こえますってば」
「…………!」
彼の目つきがますます鋭くなった。
「あのー、潮江先輩……」
背中に負ぶさったまま、視線をめぐらす。困惑したような表情で紫色の忍者服に身を包んだ少年がこちらを見つめていた。彼の他にも井桁模様の忍者服を着た一年生の姿もあった。
それなりに視線を集めていることに気づき、伽夜はへらり、と笑う。彼らもまたぎこちなく微笑み返してくる。
と――
文次郎が、とりなすように軽く咳払いをした。
「あー……、お前ら、その……またな」
そして。彼はこちらを見上げたたまま凍りついた後輩たちの前をそそくさと通り過ぎる。
振り返り、伽夜は手をひらひらと振った。
「神崎君、さよなら」
「さよならー」
草色の制服の彼もまた律儀に手を振ってきた。
「ぎゃあ」
「何だ」
黙々と歩いていた文次郎が動きを止め、怪訝な表情でこちらを見やった。
微苦笑を浮かべ、伽夜が呟く。
「や、その、ひねったのとは反対の足をつったみたいで」
「…………」
文次郎が冷たい視線をこちらに送ってきた。思い切り嘆息したようではあるが、結局、彼は何も言わなかった。かぶりを振ると、彼は姿勢を正した。そして、弾けるように駆け出す――
「わあ!」
たまらず伽夜が思い切り仰け反った。
背中から落ちないよう反射的に――いっそ首を絞める勢いで文次郎の襟を引っ張った。
「うおっ!? 馬鹿っ! 首が、絞まる……!」
「だ、だって、文次郎ちゃんが一気に走るから……! 足がますますつるんですってば」
「もたもたしていたら日が沈んじまうからだっ……こらっ! 首を絞めるな! 絞めるなっ!!」
半眼で、うめく。
「嫌なら降ろして下さいよう」
「却下だ」
「担ぐの止めて下さいよ」
「不許可だ」
「じゃあ、自分で歩かせて下さい」
「だから駄目だと言ってるだろうが。だいたいそんな足でどうやって校舎まで戻る気だ。よもや保健室まで匍匐前進するつもりではないだろうな?」
「ど、どんとこい匍匐前進……」
ひくり、と喉をひきつらせて伽夜は答える。
「まったく、お前という奴は……」
文次郎が困ったように吐息した。けれども、その表情は穏やかなものだった。
「昔ッから変なところで強情だな」
浮かんでいたのは、小さく落とすような笑みだった。
目を伏せて、伽夜も答える。
「文次郎ちゃんほどじゃないですよー」
「何?」
ぴくり、と文次郎の肩が上がった。
「風邪を引いてますよね。声がいつもよりしゃがれてます」
「ななな、何を言うか! 断じて違うぞ。これはだな、その、ほら! お前と神崎に怒鳴ったせいで声が枯れたというわけで」
ぎぎぎぎ、と首をぎこちなく反らし、彼は捲くし立てた。目がせわしなく泳いでいる。
ふうん、と呟いて、伽夜はその首に腕を巻きつけた。絞める勢いでもう一度かじりつく。
「ばっ、なにをす、る!?」
げほごほと咳き込む文次郎の目は心なしか潤んでいた。
「ほら、やっぱり風邪引いてるじゃないですか。息を吸うたびに喉がひゅうひゅう鳴ってますよ」
その指摘には反応せず、彼はただ大きくため息を吐いた。
「なあ伽夜」
日が沈みかけた空を見上げ、文次郎が口を開いた。
伽夜もその視線を追う。夕焼けの橙色が紫色、藍色の宵闇へと飲み込まれ、溶けていく光景は不思議と美しかった。
「何度も言うようだがな」
そこで言葉を一度閉じ、彼は声を落とす。
「一人で演習場をふらつくのは止めろ。お前が怪我でもしたら、叔父上と叔母上に俺が泣きつかれるだろうが」
しがみつく腕の力を強め、伽夜も言い返す。
「文次郎ちゃんこそ、ギンギンに徹夜までして鍛錬するのは止めて下さい。ひどい風邪でもこじらせたら伯父上も伯母上も心配しますよ」
文次郎が深々と嘆息した。
「……無理な相談だな」
「ですよね。休暇は明後日からですし、なんというか、その、もうやっちゃいましたし……」
つらくて重い沈黙があたりを覆う。
なんにしろ――
文次郎が、ため息をついた。
「……一緒に怒られるか」
「……はい」
こちらの返事に頷くと、文次郎が再び虚空を見上げた。その表情は途方に暮れた色を帯びていた。それはまるで――すっかりくたびれた『おとうさん』のそれのようで。
伽夜は、何となく吹き出したくなるのをごまかそうと、従兄の背中に体重を思い切り預けた。