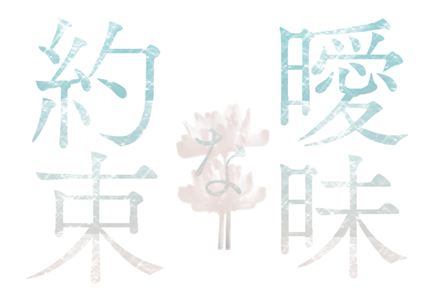「そういえば、お前――何だかよく笑うようになったな」
「なんですか。いきなり」
湯のみから口を離し、一つ違いの従妹はまばたきを繰り返した。
正面からこちらを見上げてくる彼女は、合点がいかなかったようで怪訝な表情を浮かべている。
「昔はもっと……ほら、愛想がなかったじゃねえか」
「そうでしたっけ」
彼女は首を傾けて、ぼんやりと返事をする。
「少なくとも初めて俺んちに遊びにやってきた頃はそうだった。あんまり口も開かないし、何より能面みたいに無表情でな」
――そのくせ、何か本当に言いたいことがあるときは、袂を掴んでじっと大きな瞳で見上げてくる子どもで……
「もしかしたら」
耳を突いたのは、囁くような音だった。
意識を現実に呼び戻され、文次郎はまばたきをする。そこには、今ではもうすっかり見慣れてしまったやわらかな笑みがこちらへと向けられていた。
「もしかしたら?」
とりなすように彼が反芻すると、彼女はますます笑みを深めた。
何か面白いものでも見つけたかのように、きらりと強い光を点した瞳。それがこちらへとまっすぐに注がれている。
「いつも一緒に遊んでくれる、笑わない誰かさんの分も笑ってやろうって思ったからかもしれません」
「…………ばかたれ」
文次郎は少し眉根を寄せると――口元に手を当て、わずかに目を細めた。