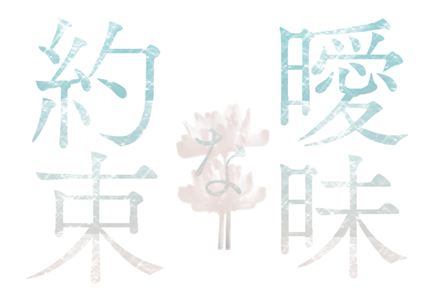「そういえば、お前――何だかよく笑うようになったな」
「なんですか。いきなり」
思わずまばたきを繰り返す。
飲みかけたお茶――ちょっと熱い――から口を離し、正面に座っている従兄をまじまじと見上げる。
「昔はもっと……ほら、愛想がなかったじゃねえか」
「そうでしたっけ」
彼女は狐につままれたみたいに首を傾げた。
「少なくとも初めて俺んちに遊びにやってきた頃はそうだった。あんまり口も開かないし、何より能面みたいに無表情でな」
――あの頃は、自分と同じ年頃の子どもを見るのは初めてで。どう接していいのか分からなくて。けれども、初めてできた友達のような、それでいておにいちゃんのような存在がうれしくて。
――もしかしたら、いつもそばにいてくれた文次郎ちゃんのおかげなのかもしれない。
文次郎がはっとしたように、目を瞠る。
思わず声が零れてしまったようだ。間を空けずに、彼が二、三回ほどまばたきをするのが見えた。
彼女はふっと頬を緩める。
「もしかしたら?」
つられたように彼が繰り返す。
どうやら肝心な部分までは漏れていなかったらしい。
そっと安堵の息を漏らし、改めて従兄殿を見つめ返す。
文次郎はどっかりと腕を組んだまま、まるで興味などないかのような素振りをしていた。けれども、ちらちらと何度も煩いくらいに視線をこちらへ投げつけている。
思わず吹き出したくなるのをこらえて、彼女はそっと言葉を紡いだ。
「いつも一緒に遊んでくれる、笑わない誰かさんの分も笑ってやろうって思ったからかもしれません」
「…………ばかたれ」
乱暴な言葉が、その場の空気を震わせた。
文次郎はちょっと眉根を寄せ、顔をしかめている。
けれども、隠すように手を当てた口元はきっと緩んでいる。だって、硬さが取れて幾分柔らかな声音に言の葉が乗せられていたのだから。