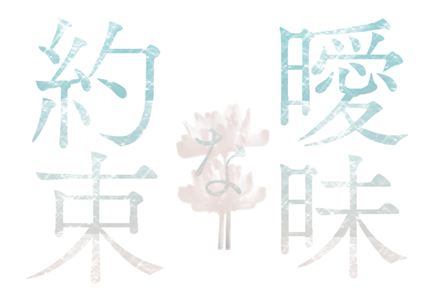
目を開くと、見慣れた天井がうっすらと見えた。まだ夜が完全に明けきってはいないのか、外からはうっすらと弱い光が差し込んでいるようだ。
彼女は再び重いまぶたを下ろす。呼ばれた方向に、のろのろと声を投げた。
「…………ははうえー、今日から夏休みなんですよ? もう少し寝かせて下さい……」
けれども、聞き慣れたはずの母の声は返ってこない。
何か冷たいものが、背中を通った。
思わず伽夜は布団から跳ね起き、転がるように寝床から抜け出した。少し遅れて、そばにあった人影が、拳を枕に突き立てた。そのまま半歩ほど下がり、僅かにあがった息を整える。
まだ開くことに抵抗しているまぶたを無理やりこじ開け、そちらを見据える。
「……喧嘩はうっかり売ったり買ったりすることはあっても、暗殺されるような覚えはありませんっ」
「バカタレ! 暗殺する相手を叩き起こす間抜けがどこにいる!」
「……」
そっと人差し指を向ける。正面へ。
刹那。
目の前で星が瞬いた。否、何か硬いものが頭頂部に激突した。
「……目ェ覚めたか」
頭を押さえ、うめく。
「ううう。それはもうばっちりと……」
「そうか。それは何よりだ」
「といいますか、文次郎ちゃん。仮にも乙女の寝こみを襲うだなんて失礼ですよっ」
伽夜が口を尖らせると、従兄殿――文次郎は不思議そうに目を見開いた。が、すぐにどうということもないように、ふん、と鼻で息をする。彼はどっかりと腕を組み、こちらを見下ろしてきた。
「失礼も何も、起こしても起きないお前が悪いんだろうが」
「そんな馬鹿な。いくら何でも横暴すぎます。……知ってますか? そういうの、異国の言葉で『じゃいあん』っていうんですよ」
「ほう」
満足したように文次郎は目を細めた
「すみません、褒めてないんですけど……」
伽夜はぐったりと、ただそれだけをうめいた。
夜が白々と明けていく。
紙に記された文章に一通り目を通した。そして、頭の中に浮かべて反芻する。それを七度は繰り返した。つまり、すべての意味を理解するまでにそれだけの時間を要した。
元のように紙を折りたたむ。持ち主の文次郎へ返しながら、伽夜は嘆息した。
「夏休みの宿題、ですか」
「…………」
黙したまま、相手は首を縦に動かした。気のせいでなければ、額にうっすらと汗が浮かんでいるようだ。
「ええと、虫取りが?」
「おう……」
今度のいらえは、きちんと声に乗せられていた。勘違いでなければ、その声音は引きつっていた。
伽夜はまばたきを繰り返し、最後の質問を声に乗せた。
「……つかぬことをお伺いしますが、文次郎ちゃんって今年、何年生でしたっけ」
「俺とお前の認識に相違がなければ六年だが?」
「…………」
とりあえず、伽夜は微笑んでみた。へらりと。
「こら。何だその沈黙は。何だその微妙な笑顔は」
「イエイエナンデモナイデスヨ?」
つらくて重い沈黙が、あたりを包みこんだ。
とりなすように伽夜が咳払いをすれば、従兄殿はぎこちなく口角を吊り上げた。――笑っているつもりらしい。
「お前のことだから、どうせこの休みも宿題以外に予定がなくて暇しているんだろう。そんなお前に朗報だ。俺の供にしてやる。喜べ」
「…………?」
とりあえず、文次郎のぎこちない笑顔を見つめ返すが、意味が分からない。伽夜は視線で問い返した。文次郎は眉根を寄せることなく、それどころかますます口元の笑みを深めた。
「だから、俺の昆虫採集に付き合え、と言ったんだよ」
冷たい汗が頬を伝った。
伽夜は相手から目線を外し、ざっと後ろへと下がる。口元を緩めようとしたが、上手く微笑むことができなかった。
身体中の血の気が引いていくのを感じながら、告げる。
「いやいやいや。お忙しい文次郎ちゃんのご心配にはとてもとても及びませんよう。目下、暇を持て余す練習に励む所存ですので。今だってほら、惰眠を貪っているところだったんですよ? というわけで、お休みなさい。良い夢をー」
ちっ、と苛立たしげな舌打ちが、耳朶をついた。文次郎はこちらとの距離を一気に詰め、後ろ衿を尋常ではない速度で掴んできた。ぎりぎりと絞まる衿を必死で押さえながら、叫ぶ。
「きょ、強硬手段に出るつもりですか!? それならこっちにも考えというものがっ!」
「何?」
相手の顔がますます険悪に歪められた。
ひんやりとした空気を肺いっぱいに吸い込み、叫ぶ。
「母上、母上ー!」
たまらず、文次郎が叫び返した。
「こら! 卑怯だぞ」
半眼のまま伽夜は相手を見上げた。吐き捨てるように、言ってやる。
「フッ。何とでも! 使えるものは何でも使う。それが忍者です」
「こんなときだけ忍者しやがって……」
苛立たしげに文次郎の眉が、その眉間へと深く皺を刻みこんだ。
「光栄です」
「褒めてねえ……」
二人は睨み合う。ただし、片方は笑顔だが。けれども、百年続くかのように幕を上げたその睨み合いは、すぐに終わりを告げた。
「あらあら。伽夜。どうしたのですか、こんなに朝早くから大きな声なんて出して……」
間延びしたような声が室内に飛び込んできた。
ぱっと顔を輝かせ、彼女は素早く母に縋りついた。母は首を少しだけ傾けたが、すぐに伽夜の頭を優しく撫でた。
縋りついたまま、悲鳴をあげる。
「母上! 助けて下さい! 文次郎ちゃんが嫌がる私を無理やり山へ連れて行こうと!」
「叔母上、聞いて下さい! 俺はただ、こいつの不抜けた根性を叩き直してやろうと!」
こちらと相手とを交互に見やり、母はやわらかく微笑んだ。
「文次郎くん、伽夜のことくれぐれもよろしくお願いしますね」
虚を突かれて伽夜は言葉を失う。
ふふっと笑みを零して、母は続けてくる。
「道ならあとでうちの人に聞いて下さいな。いくら慣れ親しんだ山とはいえ、伽夜の案内では全くあてになりませんから」
「もちろんです」
文次郎が真顔で会釈した。
「な、なんでそーなるんですか、ははうえ……」
にこにこと容赦なく放たれた母の宣言に、伽夜は力なくその場にしゃがみ込む。
「良いではありませんか。せっかく文次郎くんが誘ってくれているのですよ? 気分転換でもしていらっしゃい」
「だ、そうだ」
「なんでそーなるんですかっ!?」
けれども、伽夜の悲鳴は誰の耳にも届かなかったようだ。
ふわりと口元をほころばせて、母は両手を胸の前で合わせた。
「しっかり者の文次郎くんのことです、朝ごはんにおにぎりでも持参したのでしょう? でも、せっかくですから、おにぎりと一緒にうちの朝餉を食べてお行きなさいな。夏とはいえ、あたたかいものが一番の活力の素になりますからね」
「はい。ぜひ頂きます。叔母上の作る食事は何でも美味しいので、俺としてはとても楽しみです」
「まあ、嬉しい! そう云ってもらえると、作り甲斐があるものですよ。伽夜なんていつも味が薄いと不満ばかりで……。たんと召し上がれ」
「ありがとうございます。では、遠慮なく頂いていきますよ」
「…………」
二人の他愛のないおしゃべりを聞きながら、ただ伽夜にできたことは、単にそこにいることだけだった。しゃべりながらも、二人はてきぱきと歩を進めていく。やがて、その声も遠ざかって行った。
「…………」
やわらかな朝日が部屋に差し込む中、何の言葉を発することもできずに、伽夜はただ立ち尽くしていた。