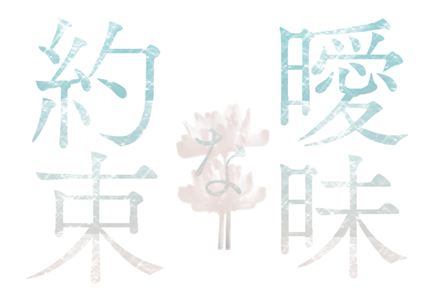
やわらかな橙色の明かりがあたりを包みこんでいる。
不意に、ぽつりと背中へ声が届いた。
「日が暮れるのがすっかり早くなったな」
「そうですね」
「昼間は暑いが、なんだかんだでもう秋なんだよなあ」
「そうですねえ」
頬を撫でていくひんやりとした空気にほっと息をつく。
その風に乗って、虫の鳴き声が耳を通った。
しばらく黙していた相手が次の言葉を紡いだ。
「……来年からは」
「ひとり、ですね」
「…………」
僅かに眉を寄せると相手は嘆息した。
「あ! なんですか、文次郎ちゃん。その盛大なため息は? 少しは隠そうとして下さいよ」
口を尖らせると、相手は半眼で見下ろしてきた。じっとりと。
「誰のせいだ、誰の」
「…………」
しばし、沈黙。
伽夜は、ぽん、と手を打った。そっと呟く。あさっての方向へ。
「その時の彼はまだ気がついていなかった。そう。己の見えざる敵が、己自身だったということに――」
「おい。何の語りだ。それは」
「まあまあ。それは置いておいて。文次郎ちゃん」
「何だよ」
文次郎を見上げ、口を開く。深い色の双眸を射抜くようにまっすぐと見つめる。
怪訝そうに相手の眉が寄せられた。
「大丈夫ですよ? 私はもう子どもではありませんから。……一人で、歩けます」
そっと。馳せるように息をつく。それでも、瞳は僅かに揺れた。相手にだけは悟らせまいと、強く、手のひらを握り締めた。
「……そうか」
口を噤んだ彼女の頭を、のびてきた指がくしゃりと撫でた。
文次郎がほんの少し目を細めたのが分かった。自身の眉が少しだけ下がっていくのも。
――ああ、気付かれた。
頭の片隅で、ぼんやりとそんなことを思った。
「……もう子どもではないんですってば。文次郎ちゃん、分かってます?」
「はいはい」
「……返事は一回」
「わかったわかった」
睨みつけるこちらの頭をぽんぽん、とたしなめるように彼は叩いてくる。
その大きな手のひらを、自身のそれで包んだ。
「……証拠を見せて差し上げます。学園まで私の後について来て下さい」
文次郎の手のひらを握り、引っ張った。
「待て待て待て!」
弾かれたように、文次郎が叫んできた。
「言ってるそばから逆方向じゃねえか! 学園はあっちだ、あっち!」
が、彼女はへらりと微笑んで応じてやる。
「厭だなあ。知らないんですか、『急がば回れ』ということを。こっちでいいんですって」
「知ってるがこの場合当てはまらねえよ! 明らかに反対方向だろうが!」
「えー?」
ぐい、と強い力で引っ張られ、前へ大きくつんのめる。
「……まったく。来年からが果てしなく思いやられるな。もう一度だけ言うからよく聞けよ」
口調とは裏腹に彼の目元には柔らかなものが浮かんでいた。
「もう一度だけ聞くのでよく言って下さい」
おどけるように軽口を叩けば、軽く頭を小突かれた。
空いている方の手で押さえる。
繋がれた手のひらのぬくもりは、あたたかかった。
よく知っているそのぬくもりに、安堵を感じるよりも先に、心臓をぎゅっと掴まれるような苦しさが走る。
こんなに近くにいるのに、さびしいと感じてしまうのはどうしてだろう。
けれども――
――今は、まだ。どうか、少しでも長くこの道のりを一緒に……
「……だなんて絶対に秘密ですけど」
「……何か言ったか?」
「ええと、ほら! あの赤とんぼさんに、虫取り会計委員長の恐怖の虫取り網に捕まらないうちに逃げるよう言ったんです」
「そうかよ。無駄口叩いてないでさっさと行くぞ」
文次郎は半眼で虫籠を背負いなおす。そして、こちらの手を強く握り返すと、乱暴に引っ張って歩を進めた。
耳を撫でて、草を揺らす風の音が心地よく響く。
そっと視線を伸ばせば、学び舎が見えてきた。