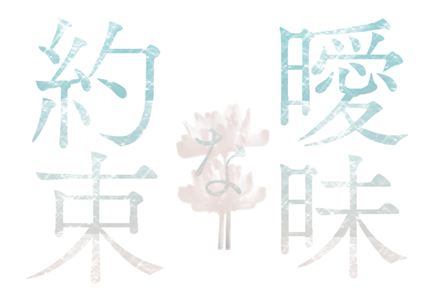
忍術学園はその日も晴天に包まれていた。
穏やかに広がる青い空。透明な風に流れていく白い雲。
学園内はなにごともなく、平和なようだった。通りかかる生徒の足音も、敷地内からあふれる活気もざわめきも、すべてが平穏を告げる証だった。
「平和ですねえ」
ぽつり、と黒木庄左ヱ門が呟いた。
竹箒を動かす手を止めて、鉢屋三郎もうなずいた。
「平和だよなあ」
ひんやりとした空気を胸に吸い込みながら、大きな伸びをした。ついでにあくびが漏れ出た。すると、後輩がつられたように大きなあくびをした。目じりにはうっすらと涙が浮かんでいる。
「こらこら、庄左ヱ門くん。夜更かしはいけないなあ」
口の端をにやりと歪める。
不服そうに庄左ヱ門が口を尖らせた。
「好きでしたんじゃありませんよう」
膨れた頬のせいで、いつもの彼より子供っぽく見える。
「昨日、は組の生物委員の預かっていた毒虫が、脱走しちゃったんです」
「脱走!?」
引きつった声で、三郎は聞き返した。冷たい汗が背中を伝っていく。
「大丈夫ですよ。は組全員で何とか探して捕まえましたから。明け方までかかりましたけど……」
「あー、悪かった悪かった。頑張ったなあ、は組のよい子達は!」
疲れきったように嘆息する後輩の頭を彼はがしがしと撫でてやった。
それから三郎は庄左ヱ門の竹箒を取り上げる。きょとんとする相手を見下ろし、彼は咳払いをした。
「……後はいいから。補習も課題もないなら、今日はこのまま晩御飯まで寝とけ」
「え……でも」
どこか困ったように見上げてくる庄左ヱ門に彼はとっておきの一言を放った。
「先輩命令」
みるみるうちに庄左ヱ門の顔がほころんでいく。三郎は満足してうなずいた。刹那。
だんっ!
何かが地面に激突したような音だった。続いて、ばたばたばたというけたたましい足音が猛烈な勢いで近づいてくる。
一瞬、二人は顔を見合わせ、きょとんとそちらを見やった。
「え?」
「鉢屋くー―――んっ!」
判断を迷う暇はないようだった。庄左ヱ門の肩を掴み、三郎は大きく飛びのいた。
「わあっ!?」
突進してくる同学年のくの一教室の生徒が、先ほど彼らのいた辺りで動かなくなった。
「…………」
何かを言いたげにこちらを見上げてくる庄左ヱ門に、彼は小さなため息を返した。
転んでいた少女が、むくりと起き上がって三郎に縋る。
「かくまって下さい!」
「断る」
「今夜のから揚げ定食を分」
「よし、俺に任せろ!」
がしり、と少女の肩を掴む。
「…………」
何かを言いたそうにこちらを見つめてくる二つの視線を、三郎はあっさり無視した。
正門そばの茂みにしゃがみ込み、三郎は口を開いた。
「で?」
「何です?」
ぱちくり、とまばたきをして少女が返す。
「今回は何をやらかして潮江先輩を怒らせたんだ?」
「何ですかその言い方は? 失礼です! 謝って下さいっ!」
相手が眉を鋭く吊り上げた。けれども、三郎は真顔で、ちゃ、と後輩に手を向けた。
「はい、庄左ヱ門くん」
彼――庄左ヱ門は一瞬、目を白黒させたが、すぐに答えてきた。
「だって、くの一教室五年の上月伽夜先輩は、あの学園一ギンギンに忍者しているあの潮江文次郎先輩の従妹で、その潮江先輩の説教の四割といえば、上月先輩ですから」
「ううう。一年生のよい子にまでそんな不名誉な認識をされているなんて……」
引きつりまくった表情で伽夜がうめいた。
透明な風が通り、茂みを揺らした。
ふう、と大きなため息をつき、伽夜が重々しく口を開く。
「この間、裏々山であった校外実習で……」
「ははあ」
三郎は、腕組みをしてうめいた。半眼で、彼女を見下ろす。
「不合格だったのか」
「失礼なっ! 合格しましたよ、実習は!」
湯気が出そうなくらい顔を赤くして、彼女が抗議の声をあげた。三郎はそれをやんわりと流し、視線で先へと促す。不満そうにじっとりとこちらを見つめるものの、彼女は素直に言葉を紡いだ。
「それが、その……不幸なことに文次郎ちゃんの耳にその実習の時の話が入りまして。それがものすごーく気に入らなかったようなんですね」
「あー、なるほどね。わかったわかった。皆まで言うな」
手で軽く制す。彼女は眉を下げ、ぴたりと口を噤んだ。
何が分かったんだ、と言いたげに後輩が首を傾げた。三郎は庄左ヱ門に目線を合わせ、説明してやる。
「つまり、だ。この上月は実習の集合場所へ辿り着くまでにかなりの時間を要しましたとさ」
「……裏々山ですよね裏々山ですよね」
何やら哀れみの混じった視線を投げてくる一年生に――
「冷静に二回も指摘しないで下さいよう。……否定はしませんけど」
彼女がぐったりとうめいた。
――と。
「こらああああああああっ! 伽夜ー―――! 出て来いっ!!」
大声で叫びながら校庭の方角へ潮江文次郎が疾走していく。遠くからでも目の下の隈が見えた。不気味なくらい。はっきりと。その必死の形相は、泣く子も黙るどころか気絶しそうなものである。
しみじみと聞く。
「あのさ。前にお前が言ってたけど、本気で泣かしたことあるのか? あの潮江先輩を」
「ありますよ」
遠ざかっていく文次郎の背中を隣で見送りながら、彼女はそっと呟いた。
「あれは忘れもしない私が一年生の時……」
「潮江先輩が二年生の時ですね」
庄左ヱ門の落ち着いたあいづちに、彼女は小さく微笑みを返した。
「一つ違いとはいえ、一年早く生まれて、一年早く学園で勉強している文次郎ちゃんには、手でも口でも何一つ敵わなくて……」
そっと彼女は目を伏せた。
「あの日も口喧嘩に負けまして。ものすごく悔しくて、思わず近くにあった石を文次郎ちゃんの頭めがけて投げたのでした」
「ははっ」
たまらず三郎が吹き出した。
「そりゃ泣くだろ。さすがの潮江先輩でも。何せ当時、二年坊主じゃなあ……!」
一同は顔を見合わせると、笑い声をあげた。朗らかな空気があたりを包む。
やがて、ふう――とため息をついて、伽夜が虚空を見上げた。
「でも、さすがに食堂の漬物石は悪かったかな☆と反省してます。ちょっとだけ」
「漬物石!? 食堂のアレを? アレが? ちょっとだけっ!?」
三郎の絶叫がその場の空気を震わせた。けれども、むなしく震わせただけだった。