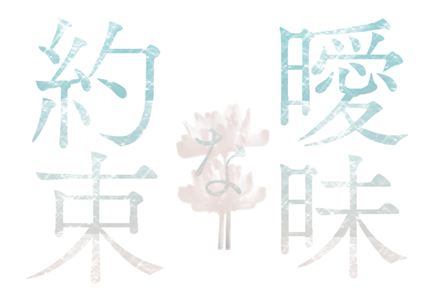
渡り廊下を、風が勢いよく吹き抜けていく。澄んだ空気の塊が、一気に全身にぶつかってくる。身体の芯に突き刺さるような冷たさである。
借りてきたばかりの図書を抱きしめるように身を縮め、うめく。
――早く春になればいいのに。
零れ落ちた息は、空気を白く染めた。吐息と同時に図書室で得たぬくもりが少しずつ外へ出てしまうようで、何だか惜しく思えた。
空気が妙にしんとした。同時に体が軽くなる。――風が、止んだのであった。
「こんなにも寒いと、何か温かいものでも食べたくなりますねえ」
果てしなくのんきな声が冷たい空気を揺らした。
そちらへ首を向ける。両の指先を擦り合わせながら息を吹きかけている上月伽夜の姿が、目に映った。白い吐息がゆっくりと溶けるように消えていく。
相手を見据え、半眼で言ってやった。
「お断りします。明日の予習で忙しいんです」
「えー、まだ何も言ってないじゃないですか」
不服そうにうめく彼女へ釘を刺すように宣言する。
「言わなくたって分かります。それに、何手も先を読むのが忍びというものでしょう」
「久作くんは今日も元気に忍者してますね。よきかな、よきかな」
こちらの突き放した物言いに、さして戸惑う様子もなく、彼女はただ力を抜いて緩やかに笑った。
少しだけ眉が寄る。
彼女のその笑みが、何だか苦手なのだ。初めて見た時から、ずっと、ずっと、そうだ。久作は上月伽夜のその笑顔が苦手だった。
この先輩のこうした態度は今に始まったものではない。決して長い付き合いというわけではないのだが、同じ図書委員会で活動していく中で、久作が見かけるときの彼女は笑っているのが常であった。
また、久作のこうした物言いも今に始まったわけではない。付き合いが二年近くも続けば、自然と遠慮の垣根というものは取り払われるものである。しかしながら、彼女が遠慮がちに微笑んでいるのか、屈託なく笑っているのか――何を考えているのか、それとも何も考えていないのか。久作には未だに読めない。
けれども、こちらの力まで抜けてしまうようなその微笑みは、少なくとも嫌いではなかった。
ぐるぐると回っては戻る思考に、少しずつ苛立たしさが募っていく。
と――
「あーっ!」
素っ頓狂な声があたりに響いた。その声に久作は我に返り、目を閉じた。
「何だよ、きり丸……」
一つ呼吸を置いて、怪訝な表情で後輩を振り返る。
きり丸が口と目を大きく開いたまま、一点を指さしていた。自然と久作もその指先を視線で追う。
草色の装束に身を包んだ六年生の二人組――会計委員長と体育委員長である――が、木の下で身体をほぐしているのが見えた。これから自主トレーニングでも始めるのだろう。さして気にとめるような光景ではない。
怪訝な表情を強めると、後輩が「違います。上です、上ッ!」と叫ぶように言ってきた。
言われるままに視界を、六年生よりも上方へずらす。
枝の先に小さな小さな蕾が膨らんでいるのが見えた。そういえば、あの木は桜であった。雲の切れ間から差し込む陽の光を浴びて、それは淡く光っているように映る。
「……まだまだ寒いけど、春になるんだなあ」
無意識に声が零れ落ちた。けれども、言葉にして初めてそれを強く実感する。枯れ木の中にも春は着実に芽吹いているのだ。
「春かあ……」
馳せるようにそっと息をつくと、きり丸は思い切り顔を綻ばせた。
「何だよ。その気持ちの悪い笑顔は……」
「いやー、春になったら洗濯のバイトにもっと励めると思うと、もう今から待ち遠しくって。そういう久作先輩だって、春が楽しみでしょう?」
でへへ、とだらしなく頬を緩めて、きり丸が問いかけてきた。
「まあ、否定はしないよ。春になれば、ずっと暖かくなるから今より予習復習がしやすくなるし」
「おおー、さっすが久作先輩。なんて素敵な面白みのない答え」
「うるさい。バイトもいいけど、そういうお前だって春になったら進級するんだからもっと勉学に励めよ」
「へーへー」
面倒くさそうに返事をするきり丸の声に、久作は視線を鋭くする。
二年に上がったら授業の内容はもっと厳しくなるぞ、と言ってやろうとしたが、止めた。二年に上がっても“アホのは組”のままだな、とお見舞いしようと口を開きかける。
不意に、ぽつりと声が届いた。
「春になったら――」
呟きはそこで途切れた。それは、哀しいくらい静かな響きだった。
たまらなくなって視線を転じる。伽夜が同じように桜の木をじっと見つめていた。その瞳に灯っていた光が、徐々に翳りを帯びていく。
――違う。彼女が見ているのは、桜じゃない。先輩の方だ。
「上月先輩!」
「……久作、くん?」
気がついたら、彼女の名を呼んでいた。
すぐに笑みを返され、一瞬、ほっとする。けれども、久作はすぐに表情を引き締めた。彼女の顔に微笑みはあっても、いつものような柔らかな面影はそこにはなかった。
――犬みたいだ。それも飼い主とはぐれた、迷子の犬。
彼女の手をひったくるように乱暴に掴む。その勢いのまま、一気に告げる。
「お汁粉、食べに行きましょう。寒さとか余計な考えとか全部吹っ飛んじゃうくらいとびきり熱い奴を。きり丸におごらせてあげましょう」
「お任せ下さい! 喜んでお引き受けしまーッす!」
きらきらと目を輝かせ、きり丸が飛び上がる。
「ってあれ……? おごらせてもらう。おごらせてくれる……いいんだよな?」
彼の疑問符はそのまま無視して、掴んだ手に力を入れる。
自分より僅かにあたたかな体温が、手のひらを通して伝わってくる。握ったその手のひらは、自分が思っていたよりもずっと小さかった。
出会ってから――久作が学園に入学してから――季節はもうすぐ三度目の春を迎えようとしている。自分はその分大きくなったが、ひょっとしたら彼女は出会った頃からそのままなのではないか。
そんな奇妙な錯覚を覚えた。
彼女が、痛いほどまっすぐと久作を見据えていた。じっと注がれる視線から口を開く気配がないことを悟る。久作は眉を寄せ、自分から声をあげた。
「何ですか。もう決定事項です。まあ、おごるのはきり丸ですけど……。とにかく、行きますよ」
戸惑いを含んでいた伽夜の瞳の色が、ふっといつもの彩りを取り戻していく。その瞳は大きく弧を描いた。眉も少しずつ下がっていく。そして、伽夜は黙したまま、ゆっくりと、噛み締めるように小さくうなずいた。
何だか目を合わせていられなくて、久作はとっさに顔を背けた。手を掴んだまま、地面に縫いつけられたように止まっていた足を再び動かす。
「ありがとうございます……」
耳を通った声は、僅かに掠れていた。それには聞かなかったふりをして、彼は歩く速度を上げる。
渡り廊下を、二人の間を、風が大きく通り抜けていった。冷たさがまだ色濃く残るそれは、とても忌々しい。けれども、同時に安堵する。
――寒くてもいい。風も空気も冷たくていい。このままずっと冬のままでいい。春なんて、来なくていい。
矛盾した想いをかき消すように、久作は繋いだ手のひらを強く握り直した。