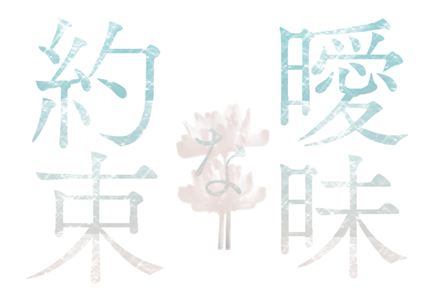
酉の刻に入ると、すっかり日も暮れて夜の帳が下りた。
昼間の暑さもようやくやわらぎ、澄みきった空気があたりを包む。空は深みのある群青の幕で覆われ、縫いとめられた星々が静かに瞬いている。
「……そろそろ食堂の最終注文の時間だ」
驚くほど近くで響いた声に、心臓が大きな音を立てた。
少しだけ後ろを振り返る。そんなことをしなくともよく響く低い声で、相手が誰なのか分かっていた。ただ、ほんの少し間がほしかったのだ。誰かと話をするために、心の準備をする時間が。
膝を抱えたまま、そっと名前を声に乗せた。
「中在家先輩」
「…………」
図書委員長の中在家長次は黙したまま、こちらに近寄ってきた。
「七夕大会の受付当番、放り出してしまってごめんなさい」
謝罪の言葉は、あっさりと紡ぐことができた。相手は首を左右に振ってみせた。
「気にするな。代わってくれた者には後で礼を言っておけ」
「……はい」
上背のある彼は身体を折るようにして目線を合わせてきた。その動作は少し大げさに見え、まるで自分が小さな子供のように扱われている気がした。
長次は静かにしゃがみ込んだ。
「……願い事は書けたのか?」
「……中在家先輩もおんなじことを聞くんですね」
文次郎ちゃんと、と彼女は胸中で付け加えた。
「……難しく考えずに、素直に書けば良い」
言って、長次は一年生から預かってきたとかいう短冊を掲げて見せた。
一枚はとてもよく見慣れた筆跡でただ簡潔に『銭』とだけ書かれていた。もう一枚は『もっと食べたい』というものだった――こちらは不思議なことに糊づけされたのかわずかに光っていた。
思わず、眉間に皺が寄る。
「……願望じゃなくて思いっきり欲望ですよ、それ」
「…………」
伽夜の小さな指摘に何も返さず、長次は別の短冊も差し出してきた。先ほどのものよりはわずかに整った文字で書かれた『打倒、一年は組』に、もっと整った文字で書かれた『引っ込め四年』『出張るな三年』というものであった。
「…………どちらかというと野望のような気がします」
「…………どちらにしろ、願い事であることにはかわりない」
「まあ、そうかもしれませんけど……」
真顔で図書委員長に返され、伽夜はわずかに言いよどむ。
「うまく言葉にできないのならば、いくつか挙げてみるから好きなのを選ぶと良い」
言って、長次はゆっくりと指を折り始めた。
「……学内平和に家内安全、学力向上、恋愛成就、健康第一。それから、幸せになれますようにとかいうものもあった」
「最後のだけは遠慮します」
何故だと瞳で問うてくる長次をまっすぐと見つめ返し、伽夜は答えた。
「今が幸せではないというわけではないから、いいんです」
相手は少しだけ眩しそうに眼を細めた。
「無欲だな」
「そんなこと……ありません」
真面目な顔で、こちらを見つめてくる長次に、伽夜は口の端を引き上げた。ただ薄く嗤う。
「立派な忍になんてなれませんように――そう、願ってしまいましたから」
言って、伽夜は俯いた。相手のまっすぐな視線には耐えられなかったのだ。
「そんなこと書かなくたって、文次郎ちゃんが必ず立派な忍になれること、分かってます。だって、毎日毎日、あんなに一所懸命に鍛錬しているんです。でも」
「でも?」
長次は眉ひとつ動かさず、ただただ静かに水を向けてくる。
「でも、立派な忍になるってことは、信頼も信用もされるけれど、それだけ命の危険と隣り合わせになる忍務も任されるということで……。もちろん、それがとても名誉だってことも文次郎ちゃんの昔からの一番の夢だってことも分かっています。だけど」
ゆっくりと長次が口を開いた。星明かりを受けたその表情は、とても穏やかに映った。
「……おまえは、やさしい。文次郎のことをそんなにも思って心配している」
「そうでしょうか」
こぼれたのは、苦くて痛い笑みだった。
声が、震える。
「いつか命を落としてしまうかもしれない。仮に助かったとしても、大きな怪我をしてしまうかもしれない。やっと夢を叶えてなったはずの忍には二度と戻れないくらいのものを負ってしまうかもしれない」
伽夜はそこまで言うと、口を噤んだ。
黙したままの相手の言葉を待たずに、伽夜は震える喉をこじ開ける。
「――――そうなってしまった文次郎ちゃんを見て、自分がひどく傷ついてしまうのが怖い。そんな自分勝手なわがままなのに?」
長次はゆっくりとうなずいた。その瞳は優しげに細まっていく。
「あいつを大事に思うからこそだ。何とも思っていなければ、何も感じるはずがない。わざわざ傷つく理由がない」
淡々と彼は告げる。けれども、その低い声音はとても穏やかでやわらかいものだった。
「だから、おまえがそう願うことは必ずしもわがままではないだろうし、文次郎を不幸にすることではないだろう」
伽夜は何もできずに、ただ黙って耳を傾けていた。何も言えない。何も言葉にできない。
できたのは、顔を上げることだった――相手の瞳が見えるように、ほんの少しだけ。
その瞳には静かな笑みが宿っていた。
伽夜は力なく笑う。意識しなくても自身の眉が下がっているのが分かった。
「…………敵わないなあ、中在家先輩には。今夜の先輩はなんだか饒舌すぎて歯が立ちそうにありません」
「七夕だからな」
年に一度くらいは、と彼はぼそりと付け加えた。
「では、そんな先輩を拝見できた今夜の私は、とんだ果報者ですね」
天の川のお二人だって悔しがりますよ、と伽夜は冗談混じりに返す。彼の瞳が、ぎこちなく、けれどもとても緩やかな弧を描いて細められた。
「……そろそろ戻るか」
「はい」
長次が立ち上がるのに続いて、伽夜も立ち上がる。彼は足を踏み出そうとして、それを止めた。
怪訝に思って彼を見上げる。と――
「……どうやら痺れを切らした代理の係が迎えにきたようだ」
礼をきちんと言っておけ、と付け加える。それから彼はぽん、と軽く伽夜の頭を叩き、足音を立てずに駆けて行ってしまった。
「ありがとうございました……?」
訳が分からずに、伽夜は遠ざかっていく長次の背中に呟いた。
後ろの見知った気配を認めて振り返る。闇にうっすらと浮かぶ若草色の制服。剣呑に眉をひそめたその顔は泣く子も黙る――
「まったく、お前という奴は。なんて世話が焼けるんだ」
――従兄殿だった。
ぱちくりとまばたきを繰り返し、伽夜は震える人差し指を相手に突き付ける。
「ええと……、受付係……?」
「おう。何だかよくはわからんが、お前がいなくなった後で長次に押しつけられた」
大きく首を縦に動かすと、文次郎は自身の肩をほぐす。ばきり、と硬い音が鳴った。
「あ、あの……」
言うべき言葉を見つけられないまま、伽夜は口を噤む。文次郎はただ面倒くさそうに頬を掻く。そのまま何も言わず、こちらに背を向けた。
「あ……」
無意識に手が伸びて、彼の袂を掴む。
縋るように、願った。行かないで――と。
驚いたように文次郎が振り返った。彼はまばたきもせずに伽夜を見下ろした。
「伽夜」
名前を、呼ばれる。
伽夜はやはり何も言えず、縋ったまま相手を見つめ返すことしかできなかった。すると、相手に袂を掴んでいた手を外された。その手のひらはとても大きくて、とてもあたたかかった。
自身の指先はというと、すっかり白くなっていた。袂を掴むのに必要以上に力が入っていたようだった。
「どうした」
夜の闇に浮かぶ漆黒の瞳が、先ほどよりも近く見える。どうやら少しだけかがんでくれたらしい。
「あ……、いえ。ごめんなさい」
伽夜はたまらずに瞳を伏せた。
静寂が、耳朶に痛く響いた。
ごほん。
わざとらしく、とりなすように文次郎が咳払いをした。その視線は、うろうろと落ち着きなく彷徨っていた。
「……あー、その、何だ。腹が減ったんだろう」
「へ、平気です。おにぎりなら鉄粉入りのを持っています」
わたわたと手を振り、懐からそれを取り出そうとすると、これまた相手に制された。解せずに眉根を寄せる。
ほら、と目の前におにぎりが差し出された。――鉄粉はどこにも見当たらない。
伽夜が呆然と見つめていると、文次郎が嘆息混じりに告げてきた。
「おばちゃんが握ってくれた。ありがたく頂戴しろ」
「……はい」
おずおずと手を伸ばし、受け取る。まだおにぎりには、ほかほかと温もりが残っていた。
ありがとうございます――と伽夜は小さく微笑んだ。食堂のおばちゃんと、おにぎりをおばちゃんに握ってくれるよう頼んでくれたおせっかいな従兄殿に向けて。
「……戻るぞ。受付を片づけるんだろう?」
気まり悪げにぼそりとうめき、今度こそ文次郎は背を向けた。
「はい!」
伽夜はゆるゆると瞳を細め、その背を追いかけた。
零れた星明かりに照らされて、笹の葉がほんのりと淡く光っている。耳元を吹き抜ける風は透明で、ひんやりとしていた。
机の上に残っていた短冊に筆、硯を風呂敷に包む。短冊の余った分は、明日の当番の委員に回すことになっている。
すっかりきれいに片づけられた机を前にして、伽夜は文次郎をまっすぐと見つめた。ゆっくりと、頭を下げる。
「このたびは受付当番を代わって下さり、ご迷惑をおかけしました」
「まったくだ」
微笑みは、予想通り真顔で返された。たまらずに彼女は吹き出した。
「持ち帰って、後で書き上げたものを受付当番もしくは他の図書委員に預けるのも大歓迎です」
「?」
すらすらと紡いだ七夕大会受付当番の口上に、相手の顔は怪訝そうに歪められた。
伽夜は少し目を瞬かせて、微笑んだ。
「できました。そういうわけで、受付当番さま、この短冊を高く高くあの笹にかけて下さいませんか」
そっと短冊を差し出した伽夜に、文次郎は目を大きく見開いた。けれども、目線は願い事をゆっくりとなぞっていく――『私の大切な従兄殿の夢が実を結び、やさしいかたちで終わりますように』と。
彼は、伽夜の頭の上に手のひらを置いた。
「ばかたれ」
言葉とは裏腹に、文次郎の口元は小さく弧を描いていた。
「……知ってますか? ばかって言う方がばかなんですよ」
伽夜は従兄殿に口を尖らせた。頭上に置かれた手のひらを邪魔だ、と片手で追い払いながら。
けれども、伽夜はこの手のひらの温もりを本当は誰よりもよく知っている。
込み上げてくるものはとめどもない笑みなのに、うっすらと目に浮かび上がってくるものは涙だった。