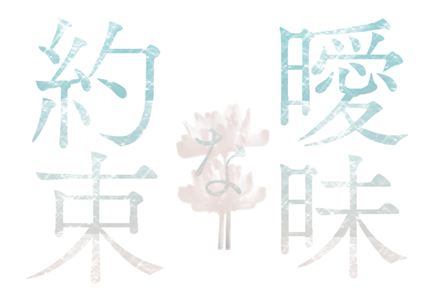
正門付近の広い道。周りを彩るのは赤く紅く色づき始めた木々だった。華やかに染まる木に囲まれて、正門はまるで夕焼けの中にそびえたつような風情である。落ち葉は地面に色濃く広がり、午後のどこまでも穏やかな日差しに美しく映える。風が渡ると木の葉の山が崩れ、虚空へと舞い上がった。――無情にも振り出しに戻ることを告げる合図であった。
「あのう、鉢屋先輩……」
「……何だね、黒木少年」
「一向に終わる気がしないのですが」
「同感だ」
本日七度目の後輩の嘆きに、七度目もこれまた同様にしごく真面目な面持ちで鉢屋三郎はうなずき返した。
「まあ――」
あくびを噛み殺したまま、肩越しに振り返る。視線の先――陽光の降り注ぐ鐘楼に学園長の愛犬、否、忍犬の姿が見えた。
「鐘が鳴るまでの辛抱だから。そろそろだろ」
言い終えるのとほぼ同時に鐘が鳴った。
掃除道具を両手に携え、倉庫への道を辿る。通り抜ける風で小さくなったとはいえ、道なりにいくつもの落ち葉の山が並んでいる。本日の委員会活動の証である。
庄左ヱ門が小さく息をついた。
「それにしてもこの落ち葉、『集めるだけ集めれば良い』って何に使うのでしょうか」
「木の葉隠れの実習に使うとか。あー……、でも、言いだしっぺがあの学園長先生だからなあ」
「なるほど……実りの秋・食欲の秋、焼き芋でほくほくにゴー、ですね」
「おいおい。冷静にすごいことを言うなあ……」
「?」
不思議そうにまばたきを繰り返す庄左ヱ門に、三郎は半眼でため息を返した。
――さすが学園のトラブルメーカー一年は組……
けれども、まったくの真顔で庄左ヱ門は口を開いた。
「学園長先生、最近は料理の書物にご執心だそうですよ。『返却期限をぶっち切りすぎだ』とうちのクラスの図書委員が文句を垂れていました」
「……そりゃ、黒古毛センセイが関わっていないことを全力で祈るばかりだな」
とりあえず、うめいた。
風が吹き抜けていく。梢からも、落ち葉の山からも葉っぱが舞う。
「おーい! おつかれさま~!」
果てしなく朗らかな声が耳を通った。一瞬、後輩と見つめ合い、そちらへと顔を上げる。事務員がひらひらと片手を振りながら、箒を動かしていた。
「おおー、出たな。二大学園トラブルメーカーこまったさん、否、小松田さん」
「なるほど。あとの一人とはご自分のことなのですね、鉢屋くん」
がさり。落ち葉の山が割れた。
「うわあっ!?」
悲鳴をあげるが早いか、庄左ヱ門が右足にしがみつくような姿勢で貼りついてきた。
彼の肩を宥めるように軽く叩いてやりながら、うめく。
「上月……お前、なんでここにいるんだよ」
「なかなかのご挨拶ですねえ。どうも鉢屋くん。なんでって、木の葉隠れの練習ですよ……?」
同学年のくのたまは、何故だかゆっくりと首をかしげた。その所作に従い、彼女の頭上に乗っていた葉っぱがひらひらと舞い落ちた。
「…………」
こちらの無言の返事を平然と流し、彼女は木の葉の山から抜け出した。肩に乗った葉っぱをぱたぱたと落としながら言ってくる。
「冗談は置いておいて。……知りたいですか?」
にっこり。上月伽夜は、見ている側の力が大きく抜けてしまうような笑みを浮かべた。
三郎も負けじと微笑み返して断言する。
「いや、全然」
「えー」
思い切り不服そうな声をあげる相手に畳みかけるように続ける。
「あいにく今日は知的好奇心とか探究心とか、そういう高級なものを持ってませんから。まったく。これっぽっちも。ビタ一文たりとも」
ふう――と隠そうともせずに少女は特大の嘆息をした。じっと半眼でこちらを見上げてくる。
「自分で話を振っておいてそういうこと言いますか、普通。薄情です」
「だって、忍者だもん」
「もんって、仮にも忍者が可愛らしく言わんで下さいよう」
ぐったりと肩を落とし、力のないうめきを彼女が漏らした。
「もういいです……」
彼女は周囲へとざっと視線を巡らし、急き込んで告げた。
「ええと、私、長屋への道を急いでいるので失礼します。庄左ヱ門くんでしたっけ、どうもお騒がせしました」
「いえ、どうも……」
「それでは、また」
ちゃっ、と手をあげて、上月伽夜は足早に立ち去った――正門の方へ。
「え?」
と、これは庄左ヱ門の声。
「上月先輩! そっちはくのたま長屋の方角じゃありませんよ!」
けれども、彼の指摘がその背へ届くことはなく――伽夜の姿はみるみるうちに小さくなる。やがて、見えなくなった。
「…………」
声を失くす庄左ヱ門を見下ろして、三郎はぽつりと呟いた。
「あれは三年にいる方向音痴忍たまズにも匹敵する音痴だな。学園内方向音痴コンテストがあったら、歴史に残る名勝負が繰り広げられる……かもしれない」
「ええと、あの、思いっきり校外ですけど、いいんですか」
うんうんと、三郎はうなずいた。腕組みして同意する。
「確かに“公害”だよなあ」
「のんきに駄洒落てるバヤイですか!?」
はっきりとこちらを見上げ、叫んできた。
「大丈夫だ。問題ない」
三郎は組んでいた腕をゆっくりとほどく。
「むしろ外に出てくれた方が、後処理が楽だ。うん」
「え?」
庄左ヱ門は怪訝そうに顔をしかめる。
にやりと口の端を上げ、人差し指を立てた。
「庄左ヱ門、とぼけてくれちゃ困るなあ。ここがどこだと思ってるんだ」
「そりゃあ、忍術学園ですけど……あ!」
庄左ヱ門が慌てて振り返る。
先ほどまで熱心に掃き掃除をしていた事務員の姿はすでに消えていた。
遠くから、男の間延びしたような声。
一人ではないようだった。足音と、何か大きなものを引きずるような音……
正門へ目を向けると事務員が姿を現した。同時に、上月伽夜――ずるずると引きずるような音を立てていたのはこれだ――の衿首を掴んだまま引っ張っている。
「もー、困るなあ。外出届と出門表にサインをしてからでないと外出できないって何度言ったらわかるんだい?」
「学園から出てません。私は無実です。だから放して下さい……」
「まったく。往生際が悪いなあ。許可なく裏々山まで行っておいて、とぼけるなんて。性質が悪すぎるよ」
「ぐ、偶然です。または何かの陰謀に巻き込まれただけですってば! それにほら、あそこは学園の庭みたいなものではないですかっ!」
伽夜が絞まる衿を押さえて叫んでいるうちに、事務員の小松田秀作は空いている方の手で出門表を取り出す。しごく当然に言ってきた。
「ま、いいや。何でもいいんでサインして下さい」
「…………!」
視線を下ろすと、突っ伏した姿勢で、伽夜が倒れていた。
「あれ、何もないところでどうして転んでいるの?」
うめき声をあげながら、のたのたと伽夜が体を起こした。
「違います。ずっこけただけです……」
「ふうん? どうしてまた――」
「小松田さん……」
のらりくらりと続けようとする事務員を遮って、伽夜が震え声をあげた。遠目でもその瞳にはうっすらと涙のようなものが光っているのが見えた。
「サインします入門表の方にもサインしますもう何でもいいから放して下さい後生ですから」
名前の記された出門表に入門表、外出届を受け取り、小松田が満足げに吐息する一方、伽夜は崩れ落ちるようにその場にしゃがみ込んでいた。
不意に、視線の端に見慣れた草色の制服が映り込む。
色の落ちた草色の制服は、赤く紅く色づいた落ち葉を一層鮮やかものへと彩る。彼は無言で周囲を見渡すと、嘆息した。そのまま事務員と少女の方へ足を向ける。
――ご愁傷様だな、上月。
思わず心の中で両の手を合わせる。
そのひとは、辛辣な声をあげた。
「……小松田さん、そいつをこちらに引き渡してもらえますか」
「げ」
完全に消耗しきって蹲っていたのにも関らず、彼女は素晴らしい反応速度で顔を上げた。
「仮にも女子が『げ』とか言うな!」
「だ、男女は等しくあるべきだ――そう思いませんか思いますよねといいますか思うに決まってますよね、小松田さん!」
「ええっ? 僕に振られても……」
縋りつく伽夜を、迷惑そうな表情で小松田が見下ろす。
「僕の仕事は終わったし、どうぞ、潮江くん」
「どうも。小松田さん」
事務員から彼女の首根っこを受け取ると、潮江文次郎はますます眉間の皺を深く刻んだ。
「伽夜……お前、また実習前に迷子になったそうだな。ん? 聞いているのかこら」
「わーん」
彼女の叫び声は、泣き声に変わっていた。
学園長からご褒美として賜った焼き栗を頬張りながら、三郎は告げた。胡乱な視線で前方を指さす。
「だから言っただろう? 外に出てくれたほうが処理が楽だって」
しっとりとしていて、しつこくはない甘さが口の中で広がり、ゆっくりと溶けていく。
ふうふう、と栗に息を吹きかけながら、庄左ヱ門は首を斜めに傾けた。わけが分からないというように目を白黒させている。
「ええと、つまり、そのこころは……?」
「学園一忍者してる潮江先輩にギンギンに詰め寄られた揚句、あの歩く迷惑方向音痴を探すという理不尽な不幸に遭わずに済む」
「はあ、なるほど」
「ようやく分かったみたいだな」
「はい。同学年って大変なんだなあってよくわかりました。先輩、手を貸して下さい」
「どうした?」
三郎が右手を差し出す。後輩はためらいもなくその手のひらに赤く色づいた葉っぱを載せた。
「ささやかな気持ちです。鉢屋先輩っていつも周りに迷惑をかけているのかと思っていましたけど、実はかけられてもいたんですね」
後輩は、にこにこと邪気のない笑みを顔いっぱいに浮かべている。
「……それはどうも」
半ば引きつった笑みを、よい子に返す。
紅葉を、じっと見下ろす。
――これは潮江先輩と今日一番の功労者である小松田さんに献上するべきなんだろうなあ。
手のひらのかろやかな重みを転がし、三郎は複雑な思いで嘆息した。