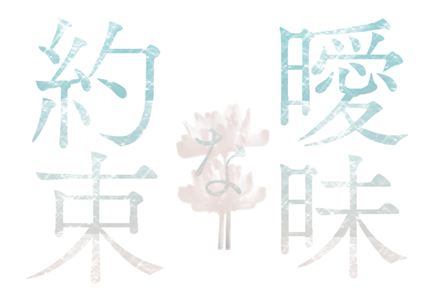
ござの上にずらりと並び、そのひとつひとつが自身を主張するかのように大きく広げられた本は、なかなか壮観であった。
からりとした空気を乗せた風が通り抜け、陽の光から書物を守るように包み込んでいた梢や葉の影が、大きく揺れる。
夏の頃と陽射しの強さはそんなには変わらないものの、肌に当たるそれはさほど暑くはない。むしろ、あたたかくて心地よいくらいであった。絶好の陰干し日和である。
陽射しのあたる特等席で手足を丸めたまま、彼女はぼんやりと前方を眺めた。図書委員会顧問から割り当てられた分の書物を一年生が並べているところであった。顧問の松千代がはにかみながら小声で指示を出し、それを確認するために投げ返された声がこちらの耳にまで届く。
本日の委員会活動が始まってから、かれこれ半刻が経過しようとしていた。
彼ら一年生は懸命に顧問の指示に応えようと奮闘している。
けれども、かなしいかな――五年生ともなると慣れやら要領の良さやらのおかげで特にどうということもなく終わってしまう仕事であった。
単に屋外での活動だからなのか、それとも大がかりな仕事で気分が高揚しているからなのか。判断の迷うところではあるが、一年生たちはいつもの図書室内での活動よりも心なしか声が弾んでいるようであった。
遠目でもそれぞれの瞳に楽しげな色が浮かぶのが見て取れた。
眩しいなあ――とこっそりとため息を零す。
「いやあ、元気だねえ一年生は」
降りそそぐ快活な声に、振り返る。
青々とした空を背景にして、その空に透けてしまいそうな茶色の髪が映った。忍たま教室五年生、同じ図書委員会に籍を置く不破雷蔵であった。
こちらを見下ろしてくる彼の色素の薄い瞳は、ほんの僅かに細まっていた。
はしゃぐ一年生たちの姿をぼんやりと目線でなぞり、伽夜もうなずいた。
「そうですねえ」
途端、大きな欠伸が漏れた。目尻に浮かんだ涙をそっと指先で拭い、うめく。
「私なんて、眠くてたまりません……」
小首を傾げて雷蔵が尋ねてきた。
「夜更かしのしすぎ、とか」
「いやいや、どこかの誰かさんみたいに夜中にギンギンに訓練なんてしやしませんよう。夜はさっさと寝ています。ただ……」
またひとつ、欠伸が零れた。
相手は何も言わない。しかし、その目は先を促している。口を開けば飛び出しかねない欠伸と格闘しながら、伽夜はのろのろと告げる。
「ただ、このところ目が覚めるのが妙に早くて……」
「へえ……?」
首を傾げたまま、彼の動きが止まった。
――ああ、不破くん、いつもの迷い癖ですか……。
ぼんやりとした思考回路でも理解はできたが、指摘してやるほどの気力まではわかなかった。
互いに口を閉じたまま、視線を交わす格好になった。
風がそよぎ、本の頁がぱらぱらと一斉に音を立てた。子守唄のように弾む下級生の高い声が、風に乗って右から左へと通って行く。
彼は苦笑して、それからようやく再び口を開いた。
「ちゃんと布団をかけているのかい? この時期の朝晩は冷えるから少しでも暖かくしないと」
「なるほど……試してみます」
かくり、と首が落ちかける。
「うわわわ、寝るなあ! 寝ちゃだめだ! いくら穏やかな気候でも外なんだから風邪ひくよ」
「……たぶん、大丈夫ですよ。たぶん。昔から昼寝をしない子だと祖母や母から定評があるのです」
相手に投げた声はふらふらとしていた。視界に映る相手の顔もふらふらと揺れている。相手がこちらの両肩を揺さぶっているからなんだな、と思考の糸を手繰り寄せながら思う。
「『たぶん』が重複しているじゃないか」
「……ああ、不破くんがツッコミさんに。これはまさしく――」
「――夢じゃないって。思いっきり現実だ! 起きろ、起きろー!」
がくがくと更に大きくこちらの肩を揺さぶりながら、雷蔵が声を投げた。
「ほ、ほら! 伽夜ちゃん。見てごらんよ、あのきり丸の顔」
力を抜けば降りてしまう瞼を半ば強引にこじ開け、伽夜の瞳が雷蔵の指を追う。並べ終えた様子なのにもかかわらず、一年は組のきり丸の表情はまったく冴えないものであった。例えるならば、死んだ魚のような眼をしていた。
「……ああ、あれは例の『顔から出るもの全部出す寸前』ですね」
「うん。いつもの傾向からして、松千代先生にお駄賃の話をしたものの、さらりとただ働きを宣告されたんだろうなあ」
「気の毒ですけれど、なかなか面白い眺めですねえ……」
「だろう?」
透けるように色素の薄い髪を少し揺らしながら、彼は苦笑した。
同情するなら銭をくれとか、出すもの出さないと出るとこ出ますよ、とかなんとかいう悲痛な叫びが響き渡った。
「……それから、怪士丸のあの生き生きとした動きもなかなか捨てたもんじゃないと思わないかい」
顔を上げると、顧問に飛びつかんばかりに迫るきり丸の背後へと、怪士丸が走り出していた。まろぶような勢いである。けれども、その顔に浮かんでいたのは呆れたような笑みであった。
伽夜もふっと目を細める。
「そうですねえ。陽の光の下で見ると、何かの幻想風景のようで心が洗われます……」
「……おまけに直射日光を浴びすぎて倒れてしまわないか、何だか心配になるな」
頭の上で聞こえた音――低く、抑揚のない音。
唐突に第三者の声が舞い込んだ。その声の主は中在家長次。図書委員長そのひとであった。
「あれでは余計火に油を注ぐようなものだろう」
まったくの真顔のまま、長次が告げる。
足元にしがみついた怪士丸を振りほどこうともせず、きり丸は抗議を続けている。
「……止めるんですか?」
返事を受け付けるつもりも寄こすつもりもないらしい。音も立てずに彼は、視線を集める輪の中へと歩を進めて行く。
長次の伸ばした右手が、きり丸の右肩に乗った。予想通り、きり丸は面倒くさそうにその手を振り払う。けれども、長次はどうということもなく、真顔のまま手を伸ばす。きり丸はやはりそれをはたき落とす。――三回はその行為が繰り返された。
四度目、目に炎を滾らせ、きり丸が振り返る。
「…………」
静寂が、訪れた。
「真打ち登場、ですね。きり丸くんが恐怖で固まっています」
のんびりとした口調で伽夜が呟けば、隣から朗らかに相槌が返ってきた。
「うん。見事に凍りついたね。なんだかんだ言って、あいつもやっぱり一年生なんだな。中在家先輩の笑顔って、慣れると何だか微笑ましいものがあるのに」
「それ、いつぞやに福富屋のお嬢さんもそんなこと仰ってましたよ。なかなかよい審美眼をお持ちのようですねえ」
「へえ、やっぱり天下の福富屋なだけあるねえ」
「あの、先輩方。ご隠居同士の会話にしか聞こえないんですが……」
遠慮がちな、けれども、呆れたような声が投げられた。
視線を転じると、青い装束に身を包んだ久作がこちらを半眼で見つめていた。
「久作くんも混ざりませんか? こちらは日当たり良好で、“后のくらひも何にかはせむ”心地が味わえますよ」
おいでおいで、と手招きすれば、彼は呆れたようにため息を吐き出す。伽夜と隣で愉しげな笑みを浮かべる雷蔵を交互に見やると、ぷい、と背を向けてしまった。
「けっこうです。委員会中ですので」
投げ返されたのは、なんとも生真面目な答えだった。どうしたものかと思考を巡らし、伽夜は眉を下げたまま雷蔵と顔を見合せる。彼もまた、困ったように微笑んだ。
「仕方ないですねえ。怒られちゃいましたし、そろそろきり丸くんにも教育的指導といきましょうか」
「そうだねえ。あったかい特等席でのんびりと本を読めるのが一番のご褒美だってこと、きり丸にも教えてあげよう」
髪が風に揺れてなびく。彼の透けるような淡い色の瞳が柔らかな弧を描いて細められた。屈託ない、穏やかに晴れ渡る青空のような眩しい笑顔だった。
彼の言葉に何だか嬉しくなって、伽夜の頬は自然とほころんだ。
お互い笑い合い、図書委員の視線の集中する輪の中心へと歩き始めた。