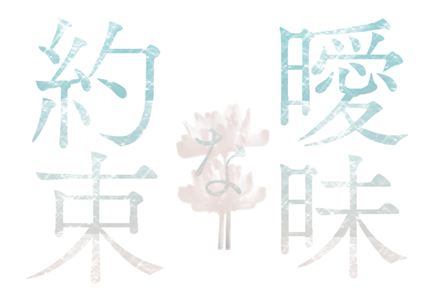
閉じた写本を放り投げようと片手で持ち上げたものの、止めた。さすがに本当に投げたりはしない。そんな真似は絶対にできない。ドケチの悲しい性である。
せめてもの腹いせにそれを机の向こうに押しやり、おれは開け放たれた窓を見やった。窓の向こうに広がる空はどこまでも青かった。風が、乾いた空気と共に校庭の弾んだ声を運んでくる。朗らかな笑い声がとても忌々しい。
だからこそ、心の底から思うのだ。
「……あーあ、こんなにいい天気なのに書庫整理なんてついてないなあ」
「きり丸、そう言うなよ。五月雨の前に整頓・点検をしないと後が大変なんだから」
雷蔵先輩が微苦笑のようなものを浮かべながら声をあげれば、おれの斜め向こうで巻物を広げていた伽夜先輩もその手を止めた。巻物をさっと丸め、彼女はこちらをまっすぐと見つめてくる。
「そうですよ。雨が続くと紙も湿気を吸って傷みやすくなりますから、この子たちが元気な時に補修の必要があるのか点検して、期間中も活躍してくれるようにきちんと手当てをしないとだめです」
やんわりとした諫言に雷蔵先輩も大きく首を縦に動かした。
「うんうん。五月雨の間はお客さんが大勢来て繁盛するからねえ」
「大繁盛!」
「――まあ、ただで大量に貸し出すわけですけどね」
ぽつりと伽夜先輩が付け加えた。
一気に上昇した情熱は、一瞬にして冷え切った。
「……疲弊したドケチにその一言はひどすぎるるるる」
おれは机にとうとう突っ伏した。
「あははは」
先輩方の緩やかな笑い声が耳に痛い。
じっとりと恨めしく伽夜先輩を見つめると、目線がかち合った。
この際だ。早抜けしたい正当な理由を申し添えても罰は当たらないだろう。極度の方向音痴の伽夜先輩が他の図書委員に捕獲されずに図書室に現れたということは、だ。明日は雨が降るかもしれない。だからこそ、おれは今日のこの貴重なお天気を有効に活用しなくてはならないのだ。
言おうとしたおれの口は半開きで止まった。
机の上にあったはずの山が遥かに縮んでいた。反対に雷蔵先輩と伽夜先輩の分の山が、それぞれその背丈をぐんと伸ばしている。
伽夜先輩は、きょとんとまばたきを返してきた。
「どうかしました?」
観念して、おれは吸ったままだった息を静かに吐き出した。残りわずかとなった山の一冊目にぐっと手を伸ばす。
「……いえ。伽夜先輩が珍しく自力で
先輩は大きな目を更に丸くする。けれども、それ以上は追及しようとはしなかった。ただ静かに微笑むだけだった。
手狭になった机を広くしようと、三人で先に点検の終わった本をそれぞれの棚へと返しに行く。
元の席に滑り込むと、安堵の息が漏れた。ずっと座っていたからか、気分転換になったようだ。先に戻っていた雷蔵先輩がこちらに笑いかけてきた。
「お疲れ様。あと一息だから頑張ろう。でも、ちょっとした息抜きついでに何か面白い話でもしようか」
「面白い話、スか?」
おれは首をひねった。面白い話。改めて言われると、ピンとこないものである。
雷蔵先輩も笑いかけた表情のまま、動きをぴたりと止めていた。提供するための話題に迷っているようである。
「安藤先生の最新のご冗談ならば、会計委員や優秀な一年い組の子から仕入れるのがよろしいかと思います」
素早く茶々が入った。声の方に視線を伸ばす。いつのまにか伽夜先輩が元いた席の後ろの棚に寄りかかっていた。どうやら図書室内では迷子にならないらしい。
「いや、ぞっとしないです。それ」
かの優秀な一年い組の教科担任の脂の乗った顔が自然と浮かび、つい口の端が下がった。
「きり丸の今の顔の方が面白いと思うけど……」
あくまでも冷静な、雷蔵先輩の呟きが耳を通って行った。
「面白い話といえば、今の季節にぴったりなお話がありますよ」
「ぴったりな話?」
おれの疑問にはすぐに答えずに、伽夜先輩は面白そうに微笑んだ。机のそばまでやってくると、とっておきの内緒話をするかのように手のひらで口元に筒を作ってみせる。その姿勢のまま彼女は声をひそめた。
「開かずの巻物――というものがこの図書室にあるのをご存じですか?」
「お、怪談ですね。それはいいや! 禁書扱いになっていたり、読むと呪われたりするって奴ですよね」
思わず身を乗り出す。
「そうですねえ。呪いというのでしょうか、不思議なことにどんな力でも決して開くことができないのです」
物語を朗読するような口調で伽夜先輩は語り始めた。
「何らかの特殊な方法で強力に固められたその巻物は、何人たりとも開くことはできませんでした。しかし、処分することもままならず、とうとう禁書としてこの図書室の奥に安置されることとなりました。誰の目にも、誰の手にも二度と触れることのないように……」
深刻な陰を表情に落として、伽夜先輩は最後に囁いた。
「――その巻物に最後に触れた子は図書室から消えたそうです」
気が付けば、おれは両腕をさすっていた。図書室内の空気が一気に冷えこんだような錯覚を覚えたのだ。
伽夜先輩はあくまでも微笑んだまま尋ねてくる。
「おや、どうしたのですか? きり丸くん。そんなに怯えて……」
と――
肩に衝撃が走った。何者かに軽く叩かれたのである。
振り向いたおれは、文字通り凍りついた。
「な――」
そこには、何故か伽夜先輩がいた。彼女はこちらには目もくれず、
「……人の顔で下級生を驚かすなんて悪趣味すぎますよ、鉢屋くん。脚色にもほどがあるでしょう?」
半眼でもう一人の伽夜先輩を見上げた。――なるほど。二人の伽夜先輩の背丈には大きな差があった。縦に長い方の伽夜先輩、否、変装の名人である鉢屋三郎先輩がぺろりと舌を出した。
「なあに、たまたま寄ってみたら面白い話をご所望のようだったからさ。ちょっと味付けして提供したまでだ」
「そーいうのを悪趣味って言うんです」
完全に半眼のまま伽夜先輩が口を尖らせる。
「へ? じゃあ、呪いの巻物って嘘なんですか?」
「いや。残念だけどそれは本当にあった話なんだ」
やんわりと否定の声が入った。声のした方に顔を向ければ、三郎先輩――に顔を借りられている雷蔵先輩が困ったようにほんの少しだけ眉を下げていた。
「その巻物はね、ある日、強力なノリらしきもので全く開かなくなったんだ」
雷蔵先輩の声が冷静ではなく冷淡に聞こえるのは、おれの今の気分が作用しているからだと信じたい。
「補修が終わるまでは図書室奥で保管しようということになったんだけど、どうしても開かないから手の施しようがなくてそのままというわけなんだ」
嫌な感覚が走った。どこかで聞いた、いや、違う。よく聞いたことがあるどころか、どう見積もっても聞き覚えと見覚えがありすぎる。その強力なノリと関連人物。点と線が一気につながり、冷たい汗が流れ落ちていく。
「じゃ、じゃあ、消えた生徒っていうのは……」
喉の奥から絞り出せた声は、どう大目に見積もっても震えていた。
おれが恐る恐る伽夜先輩の顔を見やると、彼女は笑みを漏らした。にっこりと。
「――――図書委員の名簿上から消えて頂いた、それだけのお話です」
けれども、その目は笑ってなどいなかった。