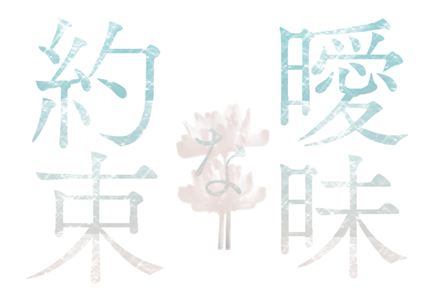
目的地まで辿り着くように移動するのではなく、風景で目を和ますために歩く。風景を楽しむためではなく、目的地を探すために歩く。
木に刻んだ目印は、ついに十一本目に達した。
どちらが本来の目的だったのかいよいよ怪しくなってきたなあ――と少女は首を捻って考える。
深呼吸と嘆息とをないまぜにしたような息が漏れた。
うす曇りの空。湿った足元。色で表すならば、灰色の日だった。この天気のせいか、前にも後ろにも人影はない。
目印代わりの大樹を見上げれば、枝の合い間から濁った空が顔を出していた。
立ち尽くしているうちに、袖から出た腕が冷たくなってきた。少しでもあたためようと、伽夜は両腕をさする。
「あ」
灰色だった世界に唐突に緑色が割り込んできた。まばたきを繰り返す。草色の装束に身を包んだ見慣れた長身が立っていた。
「おう。文次郎んとこの」
こちらの姿を認め、食満留三郎は何の気もなしに近寄ってくる。伽夜はぴたりと動きを止めた。けれども、すぐにへらへらと笑みを浮かべながら、そのまま後ろへ下がる。
「こんにちは。食満先輩。さようなら」
驚きを含んだ視線は、すぐに怪訝な色へと変わる。彼は柳眉をひそめた。
「お、おう。なかなかのご挨拶だな。……迷子なら案内するぞ?」
「けっこうです」
ぎこちない笑みを貼り付けたまま即答した。顔を正面に向けたまま、あたりへと意識を集中させる。
――大丈夫。まだあれはいません。まだ。
「だって、お前そんなボロボロで……」
呆れたような声音が耳を通った。
とりあえず、言われるままに自分自身を見下ろしてみる。肌によくなじんでいる制服には泥が跳ね、くっきりと水玉模様を作っていた。何とはなしに髪に手をやると、ほつれていた。
伽夜はごまかすように――ごまかしきれるとは思いもしなかったし、他の方法を思いつかなかったのであるが――笑って、ぎくしゃくとうなずいてみせた。
「だって、食満先輩の近くにいるとあれとの遭遇率がぐんと上がるじゃないですか」
「奇遇だな。俺はお前と遭遇する度にあれに出くわすもんだとばかり思っていたんだが――――」
犬歯を見せてから、彼もまたぎこちない笑みで応じた。伽夜もまた口の端を無理矢理引き上げた。
固い沈黙にあたりは覆われた。腕を撫でていく風が、冷たい。
と、いきなり拳を突き付けられた。
「な、何ですか!?」
突然の出来事に声がひっくり返った。構えを取り、目をぱちくりさせているうちに手を引っ張られる。伽夜は落ち着かず困惑したまま、食満留三郎の握り拳と、自分の手のひらとを見た。
ぽろり。手のひらに小さな何かが転げ落ちてきた。
干菓子、だった。
「散々歩き回ったんだろ。うまいぞ」
顔を上げると、穏やかな瞳があった。
「あいつらはもう戻ってるかな」
何か答える前に、
「戻ってるよな」
彼は軽くうなずき、ほんの少し軽くなった包みを持ち上げる。かさこそと中身が揺れ動く音は、風になびく草の音と溶け合った。
まばたきを繰り返し、伽夜はようやく取るべき行動を知る。
「食満先輩! ごちそうさまです!」
すでにこちらに背を向け、去りゆく留三郎に慌てて呼びかける。けれども、彼は振り向くことはなく、ただ手を軽く振り返すだけだった。みるみるうちにその背中は小さくなっていく。急いでいるのは明らかだ。
「なんなんでしょう……?」
独りごちる。
とりあえず、あたりを見回してみる。灰色の空の下、草が揺れているだけである。あれ――学園一ギンギンに忍者してる男の気配は微塵も感じられない。
干菓子を口に運ぶ。ふと、去りゆく彼の先へと視線を伸ばしてみた。
井桁模様の浮かぶ薄い青地に、若葉色の装束。それぞれに身を包んだ下級生たちが並んでいるのが見えた。留三郎が一歩を踏み出すたびに彼らの笑顔の花が咲いていく。
彼が懐へそっとしまいこんでいたあの小さな包みは、正門前で待つ下級生たちへのとびっきりのおみやげとなるのだろう。
口の中で広がっていく甘さに、伽夜も頬を思い切り緩めた。