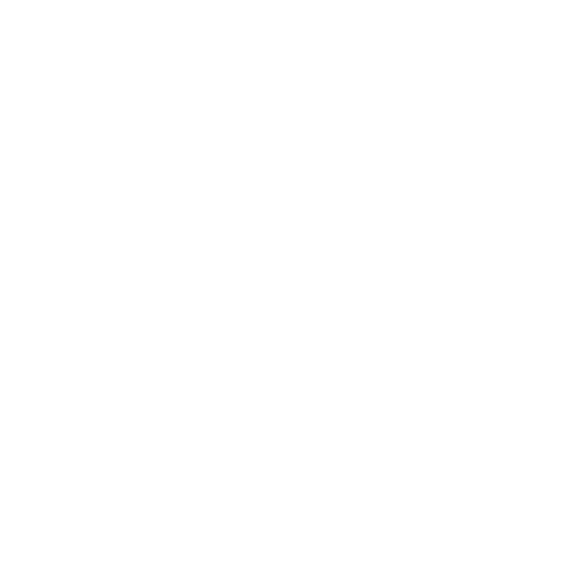アキリーズは、目を閉じた。深く呼吸して、もう一度開く。
夢でも幻でもなく、残念なことに先ほどと寸分違わぬ光景が広がっている。毛並みの良い犬二匹、否、元宮廷魔術士の見目麗しい男女二人が肩を並べて話に花を咲かせている。妙齢の男と女。色気のあるイベントが起こったり、艶めいた関係が成立したりする――などというわけではなく、とうに成人済みの男女二人が元気を爆発させ、大いにはしゃいでいる。大人しい常の二人よりも、明るく弾んだ声でテンポ速く喋っている。術法研究所の〝お使い〟を終えた記念に祝杯をあげているのだ。――水で。
「時代は、千手観音ですわ!」
「ええ、ええ! そうでしょうとも! 世はまさに大千手観音時代です!!」
華奢な拳を突き上げ、黒髪の令嬢が叫べば、淡色の三つ編みをぶんぶん揺らして激しく隣の青年が首肯する。
酔っているのではない。アルコールは一滴たりとも呑んでいない。二人とも素面だ。まことに遺憾ながらただのコップ一杯の水で酔えている。否、ノッているのだ。完全にノリノリである。だからこそ、余計手に負えない。
「必要なのは、己の拳一つ――というのがこのうえなく素晴らしいです!」
「はい! 我々魔術士は、術式を込めた呪文や歌の詠唱、もしくは媒体とする杖や小剣を手に携えて術式展開に集中するのが基本ですし、それらが封じられると、術の発動はおろか、威力も効力も発揮できません。これからの時代、千手観音習得は必須かもしれません」
「その通りです。ジェミニ先生! 私たちが前例となり、世に伝えていかねばなりません」
「なあ」
きらきらと目を輝かせる二人を見ながら、アキリーズは声をあげた。自ずと半眼になる。忠告の必要があったのだ。
「……腕立て伏せ、何回できる?」
が、余計な贅肉も必要な筋肉もない痩身の二人は聞いた様子もなかった。まったく。これっぽっちも。微塵たりとも。構わずに明るく上機嫌に笑っている。グラス一杯の水で。
「私、気弾まではなんとかマスターできました!」
「おや、ガーネットさんも? 奇遇ですね。私もです。基礎は体術ですが、理論も効果も天術と通ずる部分が大きいのが興味を引きます。それに、我々が得意とする風術とも相性が良さそうです。やはり『龍の穴通信講座』は、分かりやすく、実によい教材ですね」
「はい。あまりにも素敵な教材でしたので、私、同じ教本を追加で五冊注文してみました!」
「皆さんに布教していくのですね。素晴らしい! 素晴らしいですよガーネットさん!」
「ふふ。それはそうと、あの日のデーイダメイアさん! 素敵でしたね。とっても……!」
アキリーズは眉を上げた。思わずきょとん、としてガーネットとジェミニを見た。頤付近まで短く切った黒髪を揺らす令嬢と、淡色の細い髪を後ろで丁寧に編み込んだ青年である。絵に描いた良家の二人である。
だが、アキリーズがあっけに取られたのは、そんなことではなかった。彼の所属する傭兵隊長の名が聞こえたからだ。公爵家のお姫様が、彼の上官の名を呼んだのだ。華奢な両手を胸元で組み合わせ、目を潤ませながら。頬を薔薇色に染め、夢見るように吐息して。
「あんなにも素早く風のように舞い、素早く踏み込み、細腕からしなやかに繰り出した拳で一撃一撃を疾く鋭く打ち込むなんて!」
「ええ! 一瞬の間に千の打撃を与える高速の攻撃を放つ技とは、『龍の穴通信講座』テキストで何度も読み心躍らせたものですが、聞きしに勝る強さでした。あれほどの威力とは! 心技一体とは、まさにあの瞬間のデーイダメイアさんを指すのでしょうね! たゆまぬ努力と鍛錬が実を結ぶ。私もあの瞬間に立ち会えた喜びを忘れられそうにありません」
「ええ、私もです! バレンヌは一日にして成らず。私、それをあの瞬間、真に学ぶことができて感激しているのです。あの日以来、思い出すたび、目も胸もずっと熱いのです!」
お嬢様は、きらきらと瞳を輝かせ、うっとりと呼吸した。
「…………」
アキリーズは半眼で、首の後ろを掻いた。
ガーネットもジェミニもこちらの視線など気にせず、デーイダメイアの勇姿について熱心に語っている。アキリーズが水のおかわりを注いでやっても、見向きもせず、身振り手振りを交えて話し込んでいる。どうやら、あの日見た勇姿を忘れぬよう、千手観音の構えを取っているようなのだが、いかんせん、腕力も素早さも今ひとつの二人の動きは、わたわた、もたもた、ふらふらしており、頼りないことこのうえない。どう見積もっても、下手なジェスチャーでしりとりをしているようにしか見えない。
曰く、お化けキノコに千手観音をぶち込むデーイダメイアの勇姿を何らかの形で後世に残すべきではないか。帝都中で今も親しまれているかのジェラール帝のように、絵画に残すのが得策ではないか。皇族ではない偉人を広く知らしめるには、有志に寄付金を募るのが上策ではないか。まずは文献で過去の前例を参考にすべきだろう云々と白熱している。
デーイダメイアは、アキリーズの所属する傭兵部隊隊長だ。一言で表すならば、文武両道の傑物。血の気の多い連中がひしめき合う傭兵部隊を、持ち前の力と知恵で泰然と統率する女傑だ。
彼女を「英姿颯爽」と評したのは、「英明闊達な皇帝」と民に慕われていたマゼラン陛下そのひとである。デーイダメイアの飾らないこざっぱりとした気風には、老若男女が問わず惹きつけられている。それは部下のアキリーズもよく知っている。実際、この上司は、吹き抜ける一陣の風に似たひとだ。アキリーズが任務で剣を振るうにしろ、遠征報告書提出が遅れたにしろ、皇帝失踪事件に深く関与したにしろ――何事にも感情を混ぜることも乗せることもせずに対応してくれる上司なので部下としては非常に動きやすかった。
アバロン宮で働く若い女官の多くが、彼女のファンクラブ会員だということも知っている。「次の休みを合わせたい? デーイダメイア様の訓練を観に行くからデートなんてムリ。ぜったい」「一緒に食事? 来月の訓練場スケジュールが出てからでも良い? 私、デーイダメイア様が指導に入る公開訓練日は有休申請するから」とかなんとか、宮廷勤めのカノジョやら意中の相手とやらとの予定を、中止も延期もされた後輩共が管を巻くのに、アキリーズは何度も付き合わされたのだ。……アキリーズの財布が毎月何度も寂しいことになるので、上司殿の人気ぶりにおかれましては、そろそろ落ち着いていただきたい。
ガーネットとジェミニが、デーイダメイアの千手観音に熱を上げているのは、術法研究所の〝お使い〟が原因だ。マゼラン陛下失踪の件で、絶賛無期限謹慎中の元宮廷魔術士コンビに術法研究所発ハリア半島植物採取依頼を持って行ったのは、アキリーズだ。
術法研究所は、今でこそ広く門戸が開かれ、老若男女問わず、才あるものは貴族も平民も種族も関係なく、多くの者が研鑽に励んでいる。だが、研究資金の多くは、昔も今も貴族の寄付金頼りであるのが実情だ。それ故、建国時代からバレンヌ帝国を支えた三大公爵家出身のガーネットとジェミニが皇帝失踪事件に関わっていることは非常に重く受け止められた。それでも二人が解雇にも除名処分にもなっていないのは、所長のプロキオンと副所長のマグノリア、そして、前宰相閣下――ガーネットの父君――の尽力のおかげだ。
パトロンお貴族様の反感を買わぬよう、時折、少々厄介なフィールドワークや研究材料の採集を所長命令で依頼する体を取り、二人は首の皮が一枚繋がっているという塩梅だ。
一方、アキリーズが所属しているのは、傭兵部隊だ。帝国の正規軍とは成り立ちも在り方も異なる。ジェラール帝の御代に部隊が再編成されて以降もその在り方は変わっていないうえに、細かいことは気にしないデーイダメイアが部隊長で、それを慕う者達ばかりが従う部隊ということもあり、皇帝失踪に大いに噛んだ身ではあるが、一ヶ月の謹慎後にアキリーズはあっさりと部隊復帰を果たしている。
パトロンお貴族様から反感を買わず、謹慎処分の者への伝令役にも護衛役にもちょうどよい人材が平民出身の傭兵アキリーズ、というわけだ。今回、ガーネットとジェミニの二人に〝お使い〟を持って行ったのはアキリーズだが、彼も同行したわけではない。
アキリーズはそれとは別の商船護衛の依頼があり、二人の珍道中に同行はできなかった。代わりに二人を護衛したのは、傭兵部隊隊長デーイダメイアだ。
久しぶりの野外活動にはしゃいで注意がすっかり疎かになった二人の背後に迫るお化けキノコを、我らがデーイダメイア隊長サマは、千手観音一撃で沈めたのだという。
「ここはひとつ、やはり彫像はいかがでしょう?」
「いいですねえ! そういえばガーネットさんのご親戚の彼、彫刻家でしたね」
「ええ、まだ駆け出しなのですけれど、なかなか前衛的なものを彫ると工房でも評判なのだとか。後世に残すならば、やはり、多少前衛的で、こう、爆発する感じが」
「待て」
アキリーズは半眼でとうとう制止した。
「なんです? アキリーズ殿――」
きょとん、と示し合わせたようにガーネットとジェミニが向き直った。斜めに首を傾けたまま、澄みきった瞳でぱちぱちとまばたきを繰り返す様子は、どう見ても毛並みの良い犬二匹にしか見えない。ガーネットが両手を合わせ、こちらに跳ねてきた。ぴょん、と。
「ああ! 貴方も寄付金に一口乗りたいのですね。歓迎しますわ!」
「いや、ジャンプしてまで、元気いっぱいに盛大な勘違いをしないでほしいんだが……」
アキリーズはこめかみをさすり、うめき声をあげた。根本的な疑問を投げかける。
「いったいなにをどうしたらそーなるんだよ?」
「デーイダメイアさんに先日のお礼を兼ねた贈り物をしましょうという計画ですよ」
「彫像で?」
こっくりと二人が頷いた。農場出身のアキリーズには貴族特有の文化もしきたりも分からぬ。だが、ちょっとした礼に本人モデルの彫像をチョイスするのはナシだろうことは分かる。そもそも、贈られる相手は、デーイダメイアで、彼女もまた商家出身の平民なのだ。
「……あのな。ウチのたいちょーだって、単に自分の任務を遂行しただけだって。そもそもいきなり礼に彫像はナイだろ。ナイ」
「そうなのですか?」
丁寧に磨かれた柘榴石のような輝きを放つ大きな瞳を何度もしばたたく子犬が一匹。
「なるほど。芸術品贈与は、まだ市井ではメジャーではないのですね。まだ」
訳知り顔で妙な納得をする子犬が一匹。とりあえずそちらは無視することにする。
「あのな、お嬢」
アキリーズは少しだけかがみ、令嬢に向き直った。
「アンタだってお近づきの印によく知らん相手から、初手で自分がモデルになった彫像なんぞ貰ったら困惑するだろ? お嬢があちこちのご子息から花束貰う度、困りに困って、プロキオン爺に研究材料名目で全部押し付けてたって聞いてるぜ」
アンタの大事なマゼランお兄様から、と付け加える。うつくしい緋色の瞳が、まあるくなった。そして、それはゆっくりと弧を描いた。宵闇の天幕に灯る夕星のように。
「あら、来てくださるのです?」
こつり。ヒールを鳴らし、彼女が振り返った。身長差でどうしてもそうなるのだが、夕星に喩えられた大きな瞳が上目遣いに爛、と光る。
「…………」
とりあえず、無言で通す。
彫像ではなく、デーイダメイアの好物を礼に贈ろう、という方向で話はひとまず決着した。
ジェミニは、小さな甥っ子だか姪っ子だかの家庭教師業務がこの後あるとかで、一旦別れた。贈与品選択と購入は、ガーネットが担当することとなったのだ。
「アキリーズ殿?」
「…………」
やはり、無言で通す。
ガーネットは首を傾げたものの、疑問をそれ以上は音に乗せず、歩き始めた。彼も後から追いかける。のっそりと。
多少なりとも放っておけなかったのは――
アキリーズは、認めざるを得なかった。潮鳴りに似たあの声。あのひとのぼやき――というよりは頼み――があったからだ。
「ガーネットは叔父上の一人娘で掌中の珠というのも大いにあるんだが。アレは温室、否、大層とびきりご立派な公爵家の箱庭で大事に育てられた、やんごとなきお姫様だからなァ」
先帝マゼラン陛下が困ったように眉を下げて言ったのだ。その実、まったく困ってなどいない、慈しみに満ちた〝お兄様〟の眼差しと、潮鳴りに似た響きの穏やかな声音だった。
「好奇心が強くなったのは、本人の元々の性分と、蝶よ花よと大事に守り育てられた環境への反発もあるんだろうなァ。気になったら、己の目と手と足で徹底的に追究しないと気が済まない。とりわけ屋敷の外に興味津々でなあ。魔術士に向いていたのは、本人の関心と好奇心と探究心とが、たまたま魔術研究の本質ともぴったり合ったからだな」
あれは何度目の遠征から帰還した時だったか。あのひとの声が耳に蘇る。
親族以外の男――父親と従兄のマゼラン以外の男共――と話すのが不慣れで、随行メンバーのアキリーズともハリーとも初めはマゼラン陛下の背中越しでしか話せなかったやんごとなき公爵家のお姫様ガーネット。そんな箱入り娘は、遠征を経て随分逞しくなった。
頑固親父を絵に描いた風貌の店主相手に、公爵家のやんごとなきお嬢様が一人で値引き交渉をした。なんとか店主を説き伏せ手に入れた希少な鉱石を、まるで宝物のように手のひらに載せたご令嬢は、夕星を写し取ったうつくしい瞳を一際きらきら輝かせていた。
――その報告を兼ねて陛下と二人、城下で呑んだ夜のことだ。
帝国はますます広大に、強大に、豊かで煌びやかになった。けれども、その光が強く眩く輝きを増した分、路地裏に落ちる影は、より深く、濃くなった。露店を一人で歩かせるのは危なっかしい、と〝マゼランお兄様〟たっての依頼で、アキリーズが公爵家の箱入り娘にして、〝マゼラン皇帝陛下の愛犬お嬢〟ガーネットをそれとなく護衛した。本人には見つからぬように。後ろから。ひっそりと。そういうわけである。
「叔父上は娘可愛さに、アレを良家に嫁がせたくて仕方がないようだが、あの様子じゃあ難しいだろうな。興味の針がひとたび傾けば、帝都路地裏の怪しい露店でもハリア半島の草っ原でも、どこ吹く風、尻尾をぶんぶん振って探検したがる子犬みたいなもんだ」
「違いねえや! あのハリア半島の崖っぷちをあれほど、生き生きぴょんぴょん駆け回ることができるお嬢が、おとなしくお貴族様の奥方だなんて務まりそうもねえですよ」
アキリーズも釣られて笑った。ハリア半島山腹の崖を誰よりも颯爽と歩いていたのは、自分でも、ヌオノ出身の陛下でもない。随行員の中でいっとう若く、小柄な少女だった。
ガーネットは、やんごとなきお生まれとお育ちのご令嬢にしては、遠征で険しい道のりにも野営にも泣き言一つあげない少女だった。
母君を亡くしたばかりの少女時代に、歳の離れた従兄マゼランが住むヌオノに預けられていたということもあってか、公爵令嬢にとって、ハリア半島は遊び場も同然だったらしい。急勾配にも息切れせず、すたすた歩いていた。野宿にも目を輝かせていた。今思えば、帝都アバロンの屋敷の中で、過保護な父親や親戚との摩擦に辟易し鬱屈していたその少女は、貯めに貯めたエネルギーを、ハリア半島への遠征で爆発させていたようにも思う。
あの頃、ガーネットは料理、とりわけ、いわゆる
教本通りに自分で料理を作ったことなどないお貴族様の分際で、やれあの薬草を入れてみては、やれこのキノコを一欠片煮込んで出汁をとってみては、と大きな瞳をきらきらさせながら、やたらと謎のアレンジをしてみるようまとわりついてきた。アキリーズは宥めるのに骨を折ったものだ。
そのときばかりは、こちらが男だということもすっかり忘れ、敬愛するマゼランお兄様の背中から離れて、アキリーズの後を付いて回る好奇心旺盛な子犬のようで可愛かった。
だが、「あんたのマゼランお兄様が腹を壊しても良いのか」と言えば、ぴたりと引き下がるので、まだマシではあった。どちらかと言えば、同じくマゼラン陛下に随行していた宮廷魔術士のジェミニをあしらうのに手を焼いた。彼もまた傍系とはいえ、アバロン御三家縁のお貴族様だ。料理など一度もしたことがない坊ちゃん育ちのはずだが、その辺で採取した野草やキノコをなんとしても入れようとしてくるので、散々手を焼かされた。
アバロン御三家といえば、もう一人、先帝の孫ハリーも同行していたのだが、三人の中では対応が楽だった。涼しげな顔つき通り、あれは何事にも淡泊な男なのだ。出された食事は黙々と食べた。食事に関してのみ、御三家の連中で扱い方法がいっとう楽な存在だった。時折陛下の話に相づちを打つ、やけに綺麗な彫像みたいなものだったのだ。
ハリア半島遠征での野営メシ散々な思い出話に、あのひとは腹を抱えて笑った。
「陛下。そんなに笑わんでくださいよ。元はと言えば、陛下のせいでもあるんですからね。なんすか、あの人選は? 調理の手伝いに来ては、俺がやるなと言うことを嬉々としてやるし、やれと言うことにはちっとも聞く耳持たんし。しかもあの連中の一人は、あんたの可愛い妹分なんですから、もうちょっとこう、ちゃんと躾といてくださいよ……」
すまんすまん、と涙の浮いた目許を抑え、あのひとはますます笑った。
「ガーネットはなあ、叔母上――母君を早くに亡くしているからな。その分、叔父上の愛情も心配も倍以上に受けて育ったものだから。幸い、本人も素直で良い子に育ったのは良いことだが、それに感謝する気持ちも強い一方で、同時に重荷でもあったんだろうよ。父一人、娘一人。他に相談できる母君も息抜きに連れ出してくれる兄弟姉妹も居なかったからな。期待も愛情も心配もあの小さい背中じゃ処理しきれなくてパンク寸前だったんだよ」
本人なりに考え抜いた末、術法研究所付の宮廷魔術士に志願したそうだが、彼女の父君である宰相閣下も親戚も決して良い顔をしなかった。良家に嫁ぐよう、少女の顔を見ては、なにかと小言を繰り返したらしい。
見かねた従兄のマゼランが、自身の皇帝即位を機に、遠征随行員に少女を任命したのだ。
「……男ってのは、馬鹿な生き物だからなァ。相手が可愛くてたまらなければたまらんほど、自分に相手からの関心が向かなければ向かなくなるほど、悋気も独占欲も強くなるし、外の世界に出したくなくなる。ガーネットの場合、あのありあまるほどの好奇心だ。たとえ籠に閉じ込めるのに成功したとしても本人はおろか、相手方だって幸せにはならんだろうよ」
「難儀なことですねえ」
ぐび、とゴブレットを一気に煽れば、マゼラン皇帝陛下がまた笑った。くつり、と。
「――なあ、アキリーズ。すまんが、一つだけ頼まれてくれ。ガーネットを心の底から守りたいと希ってガーネットもそれを良しとする、ガーネットだけの王子様がまだ現れず、俺や叔父上の目も手も届かねえ時にゃあ、アキリーズ、おまえさんもあれの手綱を一本だけ握るのを手伝っちゃあくれないか?」
酔っ払いの戯れ言に自分が素直に頷いた記憶などないはずなのだが。
宮殿まで送り届けて別れる直前、あのひとはわらった。やけに安心したように。瞳に湛えた碧海をひどくやわらげて。それがまなうらに焼き付いた。きっと、そのせいだ。
「アキリーズ殿!」
「はい、はい。なんすか、お嬢」
「見てください! フライマンバ飴ですって!」
にぱ。にかっ! 上から見ても下から見ても、どう見積もっても邪悪なスマイルを真ん丸い顔面いっぱいに浮かべた有翼モンスターを象った琥珀色の棒形キャンディーが店頭に所狭しと並べられている。
ヌオノ名物を帝都でも食べられるだなんて、とはしゃぐ彼女を制止する。
「待て。何を隠そう、ウチのたいちょーはそこまで甘味が好きではない」
――というわけでもないのだが(ファンクラブ会員共から甘い焼き菓子を熱心に贈られては、訓練でしごいた傭兵部隊の部下共に山分けして誰よりも真っ先に平らげる御仁だ)、少なくともお近づきの印にふさわしい絵面の贈与品ではないだろう。貴族平民問わず、第一印象は見た目が大事だ。哀しいことだが、それが世の習いだ。
「そうなのですか? あのハリア半島の思い出にふさわしい逸品かと思いますが……」
目線も足裏も縫い止められた子犬の背を押す。名残惜しげにちらちら見るが、一切無視。
目を離すと、路地裏の怪しげな露店に行きたがるので、「うちのたいちょーは、新市街の新店舗新商品に目がない(こともない)」と情報を流し、軌道をなんとか修正する。
三歩先を行くガーネットを見る。目抜き通りを歩く足取りは、軽やかだ。頬もほんの少し、丸みが戻ったように見える。頤のラインで揺れる黒髪も、午後のやわらかな春光を受け、艶々している――南ロンギット海の彼方へ、あのひとを送った頃に比べたら、いくらか食事も睡眠も摂れるようになってきたようだ。
「ヌオノ名物の三日月と満月? 同じお酒にしか見えませんが……」
令嬢は至極真剣な眼差しになった。帝国領自慢の美酒がずらりと集められた新店舗だ。
最近アバロンで流行りの蒸留酒を贈るのはどうかと考えたらしい。〝お使い〟の道中、デーイダメイアから、仕事上がりの一杯が趣味だと聞いていたことを思い出したらしい。
「たいちょーは、どちらかというとスモーキーな方が好みだ(というわけでもないし、酒は何でもガバガバ呑む)ぞ」
「いや、それはきみの好みだろ」
そっと、静かな声。
「げ」
「まあ」
「仮にも上司に向かってご挨拶だね、アキリーズ」
すらっとした女が――我らが傭兵部隊隊長デーイダメイアそのひとが、片手をあげて声をかけてきた。碧空に似た彩りの髪を耳にかけ、笑いかけてくる。思い切り。
「私はこの調子の良すぎる部下が言うようにモルトも好きだけど、ブレンデットの方が好みだなあ。イイとこ取りだからね。ガーネット嬢は、いかが?」
にっこり。麗人のよく通る爽やかな声が空気を震わせた――いらえは、なかった。
「…………」
左後ろを振り返る。マントが強く引っ張られたのだ。
見下ろすと、ガーネットが口元を細い右手で押さえていた。左手は、アキリーズのマントを掴んでいた。ぎゅう、と。小刻みに気の毒なほどふるふる震わせながら。アキリーズの背後に素早く回り込み、身を隠したつもりらしい。
「ご、ご、ご、ごきげんよう、デーイダメイアさん! 本日はお日柄も良く至極うるわしの千手観音日和……あの、あの、失礼します! ごきげんよう!」
叫ぶなり、毛並みの良いおすましの上手な子犬、否、ガーネットが全速力で駆けて行った。気のせいでなければ、頬どころか耳まで紅潮し、緋色の双眸にはうっすら涙の膜が張っていた。予期せぬご本人登場でいっぱいいっぱいになっていらっしゃる。
ハリア半島初遠征時の競歩タイム自己ベストを更新しているのではないか。アキリーズは密かに感心した。
「おお、アキリーズよ。護衛対象に逃げられるとは情けない」
「護衛も何も、お嬢のお屋敷は、あの坂道を登ればすぐだから何の問題もねえですよ。それより、隊長が予備動作なく、足音まで消して背後からいきなり声かけるからでしょうが」
「そうか。それは悪いことをした」
デーイダメイアが、眉を下げ、頬を搔いた。
「ガーネット嬢が随分悩んでいる様子だったから、先に好みを伝えようとしたのだが」
反省しているようだが、後悔している様子は微塵もない。この上司にとって、頬を赤らめ瞳を潤ませたファンガールから逃亡されるのは、日常茶飯事なのだ。些事である。
「それにしても、アキリーズ。おぬしもなかなか悪よのう。嘘ではないが、方便にもほどってものがあるだろう」
護衛の駄賃代わりとして相伴に預かろうとしたこちらの魂胆は、ばれていたらしい。
上司は形の良い唇を緩め、くく、と声を立てて笑った。
「……なんすか?」
「いや、きみにしては、あのお嬢サマのこと、随分気に掛けてるみたいだなって」
「気に掛けてるっつーか……放っておけないんすよ」
彼はなんとなく気まずい思いを抱いて首の後ろを掻く。上司は両腕を組み直し、笑う。
「へえ」
「似てンすよ。田舎の――」
「ほう?」
「――じいちゃんが可愛がってたワンコ共に」
デーイダメイアのにんまりと吊り上がった瞳と口角が、しゅるしゅると下がった。悪いが、上司がときめくそういう方向の話ではない。いや、こちらに何も非はないが。
つい、過去形で口にしたが、実家の農場は両親と妻帯した長兄が切り盛りをし、今も傾くことなく続いている。祖父は孫が大きくなる頃には引退し、犬を可愛がりながら、趣味の庭いじりに精を出す日々を送っていた。いつも決まった時間になると、愛犬と生まれた子犬も引き連れて、夕焼けを追いかけるように農場をゆっくりと散歩するのが日課だった。
祖父は、アキリーズが帝都に出た二年後に儚くなった。だが、農場を散歩するいつもの時間になると、祖父の愛犬は、父や兄が連れ歩こうとしても、他の家族がおやつを用意しても、動こうとしない。ちらちらと家を振り返ってなかなか立ち上がってくれないのだ。それは、今でも同じだ。アキリーズが時折休暇を利用して里帰りしても、子犬たちがすっかり大きくなった今でもなかなか歩いてくれないことには変わりがない。
待っているのだ。――祖父の帰りを、ただ、今も黙したまま待っているのだ。
人魚薬を作り、あのひとを笑顔のまま南ロンギット海に送る――
そう決めたのは、随行員の中でいっとう年少の娘だった。
帝国の太陽であるあのひとが永遠に失われること、その後に自分が受ける処遇も誹りもずっと覚悟していたはずだ。それなのに、彼女の背中は今尚あんなにもか細い。あのひとを見送った日から時計の針が止まったようにさえ見えた。帰らないことをとうに知っているはずなのに、あのひとの帰りを待っているのだ。待ちぼうけしているのだ。いつまでも。
だから、放っておけないのだ。
だが、これは誰かに話すようなことでもない。アキリーズが剣を捧げたマゼラン陛下に頼まれたとはいえ、
しかめ面のままアキリーズは首の後ろをがしがし掻く。それから深く呼吸した。
「――なんすか?」
「うん」
渋面の部下などいつも通り気にすることなく、デーイダメイアは菫色の瞳を煌めかせた。訓練で部下をしごくのに何か面白いこと――大概が悪趣味な思いつきだ――を閃いたとでも言うように、悪戯っぽい光が揺らめいている。
デーイダメイアは腕組みのポーズで、右手の人差し指を立て、告げた。
「あの愛らしさは、確かに子犬を彷彿させるものだな。だが、アキリーズ、きみのほうがよっぽど似ているんじゃないか?」
目で、問う。
上司は声を立て、鷹揚に笑った。きみのご実家の優秀な番犬に、と。