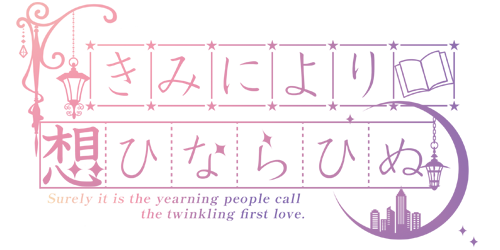物語はいつも春に始まる。
遅刻回避を願いながら食パンを咥えて走る主人公が曲がり角でヒーローや恋のお相手、ライバルと伝説的王道接触シーンを繰り広げるのも、謎の転校生が見開き大コマで突然クラスに登場するのも、日曜朝のヒーローが力に目覚めるのもたいていが春だ。始まるならば春がふさわしい季節なのだろう。
少女にとっても思い返す限り、始まりは春だった。
ドラマや漫画によると、どうやら第一話の最序盤を牽引する流星の如くスタートを切ったり、中盤のクライマックスとして大盛り上がりの音楽と共に来たり、大迫力の見開き直前ラストシーンや次話への“引き”として、ド派手にドン! とそれはそれはわかりやすく知らせてから来てくれるものらしい。
ド派手にドン! は物語世界のみに限られたものだとしても、トントン、くらいのレベルで予告なく肩を後ろから叩いてくれるものなのだと少女は考えていた。
けれども、実はそうでもないらしい。やさしく春の雨のように降ってくることもあるのだ。そのひとと出会い、そのひとのことを少しずつ知ることで、そのひとへの想いも本のページのように徐々に重なり、やがて厚くなる。それを繰り返し捲り続けていくことで、その想いが厚く熱く、あふれそうにもなる。恋とはそういうものなのだと少女は知った。
「歌川のこと好きなの?」
ひゅ。
正々堂々。威風堂々。開幕初手。搦め手なし。正面からぶち込まれた剛速球ストレートに少女は呼吸を止めた。
「……歌川のこと、好きなの?」
二回言われた。相手の肩まで届くほどの色素の薄い髪が、目の前でさらりと揺れる。首を傾げた少年がもう一度ボールを投げてくれた。聞こえていないと判断されたらしい。気怠げな表情だが、威圧感はない。髪と同じ淡い色の眉が少しだけ上がっているだけで、気を悪くした様子はない。すぐに返事ができなかったことを咎めず、嫌な素振りも見せずに同じことをもう一度言ってくれるだなんて、なかなか親切なひとである。
「……ええと」
「うん」
少年の目つきにも態度にも声にもからかうようなものは混じっていない。高校ならでは、または男子界隈特有の挨拶なのだろうか。
男の子と二人で――挨拶と天気の話以外で――面と向かって話をするだなんて、小学生ぶりのような気がする少女にとって、その質問はどういった意図によるものなのか判断が難しい。小学生の弟とは日曜日の戦隊アクションの次回予想について今朝も話したばかりだが、ノーカウントだ。父親とも学校であった出来事などについて話すものの、これもまたあまり参考にはならないだろう。
少女が大きくまばたきをすると、少年もまたゆっくりとまばたきをした。
窮した少女は「すみません」と断りを入れ、首の前で左腕を右に倒した。その真下に右腕を垂直に立て、指先も縦にピンとそろえた。まっすぐと。
タイムを願い出た少女に少年は目を丸くしたものの、うなずいてくれた。答えを急かさず待ってくれるだなんて、初めて同じクラスになったこの男子生徒はやはり親切なひとかもしれない。
放課後の図書室である。新学期が始まってから三週間が過ぎた。三年生からクラス順でスタートした図書委員会図書当番は、二年生のシフトも終わり、少女が所属する一年生にもめでたく巡ってきた。高校生活に新一年生もそろそろ慣れてきただろうという上級生の作戦だ。少女の当番の相棒は、同じC組の男子生徒だ。
一年C組は、クラス委員長の立候補制を除き、他の係と委員会はくじ引きで全て公平に決まった。提案者は担任教諭だ。担任教諭の一声で一も二もなく決まった。交流の輪も広がり親睦も深まり一石二鳥だろう、との計らいなのだ。
六頴館高校は中等部から内部進学した者が大半で、その他に高等部から外部入学してきた優秀な生徒がいる。一年C組にも外部から合流した頼もしい生徒はいるのだ。外部入学生が内部進学組と臆さずに交流できるように、一日も早く六頴館校の生活の苦楽を分かち合える友を得られるように。そうした担任教諭の心意気に生徒も快く賛成したのだ。
そういうわけで、宇田川真澄の図書当番初登板の相方は、菊地原士郎である。
同じ教室で学ぶ仲だ。挨拶くらいはしたことがあるが、クラスが一緒になるのも面と向かって話すのも初めての相手である。クラスでの席は、出席番号順によるものなので割合近い――菊地原は真澄の右斜向かいの更に一つ後ろ、つまりは右隣から二列後ろの住人だ――が、班は別々なので掃除当番も一緒になったことはない。彼はクラスでも物静かな印象の男子生徒である。真澄の隣の席の男の子と仲が良いのか、時には昼食を共に囲んだり、休み時間に話をしたりしている様子をよく見かけている。休み時間の男子と言えば、校庭で「ドッジボールしようぜ!」がメジャー(新小学二年生の弟談)らしいが、昼休みには、静かに机に伏せてヘッドホンで音楽を聴いている姿をよく見かけた。音楽をこよなく愛する者なのかもしれない。実は軽音楽部や吹奏楽部に所属しているのかもしれない。
子どもの頃から「ぼんやりしている子」だとよく言われていた真澄は、活発なグループに所属する子、とりわけ男の子と話すのは苦手だ。菊地原は男子ではあるものの、物静かなタイプであるし、話してみたら実はとっつきやすい子かもしれない。同じクラスと同じ図書委員になった同志として少しずつ仲良くなれたら嬉しいな、と挑んだ初めての図書当番である。当番日は、昼休み中の三十分間と放課後に一般下校時刻五時三十分まで図書室にて受付当番や返却書籍の整理をすることになっている。ただし、六頴館は日によっては七時限までの授業もあるので、そうした場合の当番時間は短縮が認められている。その場合は当番の生徒が到着するまで司書と司書教諭がフロント守備に回っていらっしゃるそうだ。
図書当番初登板の世間話初手は明日の天気と今日の最低気温と最高気温から攻めていこう――
決意した矢先の菊地原選手の剛速球サービスエースであった。
穏やかな晴天に恵まれた今日の図書室は空いている。予習復習や課題に励むために勉強道具を広げたり、新刊雑誌やお目当ての本を読み耽ったりしている生徒の姿もまばらだ。カウンターに着席して以来、まだ一度も新たな貸し出し客も返却客も現われなかった。カウンターの二人が会話をしていても差し障りはない。はずだ。
歌川とは、同じC組の歌川遼のことだ。宇田川真澄の右隣の席の住人だ。菊地原が昼食を囲んだり、休み時間にお喋りをしたりしている男子生徒でもある。菊地原は音楽を聴いていても歌川が話しかければ、顔をスンとさせて返事をするし、放課後も二人連れ立って教室を出る姿を見るので、昔から仲の良い友人なのだろう。友人歌川への意識調査をクラスメイトに試みるだなんて、菊地原は友だち思いで心配性なのかもしれない。
それらを踏まえ、真澄はじっくりと考える。選択肢は提示されなかったが、よくある五択形式だろう。
「あの、ええとね、『とても好き』か『やや好き』かのどちらかだと思う」
「うん?」
遅刻した真澄の返事に菊地原の語尾も眉も大きく跳ね上がった。
「『とても好き』か『やや好き』のどちらかだと思います。歌川くんのこと」
「二回も言う……聞こえてるって」
菊地原が何か言ったようだが、真澄はそのまま続けた。
「『とても好き』『やや好き』『どちらとも言えない』『やや嫌い』『とても嫌い』の五択から選ぶならば歌川くんは『とても好き』か『やや好き』のどちらかなのだけれど、正直なところよくわからないです」
きりりと眉に力を入れた真澄に、菊地原は呆れたように言った。
「へえ。三回も言っておきながらよくわからないんだ……」
「うん」
よくわからないことだけはよくわかったから三回言ったのだと自信満々にうなずくと、菊地原は右眉を上げた。それから大きく息を吐いた。ふうん、と。
「歌川くんね、すごく親切だったんだよ」
入学式。内部進学組だが高等部校舎に初めて本格的に足を踏み入れた――オープンキャンパスで来たことだけはある――真澄は、クラス発表確認後に見事に迷った。一目で迷子だとわかる真澄を見つけ、不安いっぱいの彼女に気づくなり、歌川はほんの少しかがんで話しかけてくれたのだ。
咲き誇る八重桜に見蕩れて上方ばかり見上げていたものだからなおのこと、どこからどう歩いてきたのかもわからなくなり、半ば泣きそうになっていたところを歌川は助けてくれたのだ。
教室まで案内してくれたうえに同じ一年C組でおまけに隣の席だと発覚すると、「改めてよろしく」とそのひとは明るく笑ってくれた。
「歌川くん、同い年のはずなのにとても親切だし、周りのことよく見てくれているよね」
「うん」
しっかりとうなずく菊地原に、ぱあっと目を輝かせた。
「本当に親切だよね。先週の朝、SHRで先生が黒板に模試の時間割を書いてくださったときのことなんだけど」
「うん」
「わたしの席の前列の皆さん、そろって背が高いでしょう?」
菊地原がきょとんとまたたくので、真澄は指折り数えた。
「バレー部の秋山くんと伊藤くん、バスケ部の青野さん、左斜向かい前の落語研究会佐藤くん。真ん前の吹奏楽部トロンボーン担当あゆみさん……じゃなかった市川あゆみさん。ほら、皆、背が高くてすらっとしてる」
菊地原が真澄の上から下までをざっくり目測しているのが伝わってきた。
「ああ……はい、はい」
菊地原もまた真澄よりも高身長だが、こうして席に座ると座高があまり変わらないように思える。実物と比較されるマッチ棒の気持ちがほんのりわかった気になった。息を吐きながら真澄は少しだけ椅子を引く。遠近感を強調することで格差をなんとか隠していきたい。
「それで、皆がうつむいたときを狙って、あゆみさんの後ろからぐるぐるひょいひょい顔を出してメモ取ろうとしてたらね、なんとびっくり」
「隣から歌川が……」
菊地原の合いの手に真澄は身を乗り出した。
「そう! 歌川くんがね、メモをくれたの! 時間割を全部写したメモを! こっそりと!」
その時間割メモは、やや右肩上がりだが読みやすい文字だった。自分の分だけでなく、隣人の分まで書き写してくれたのだ。とても急いでシャープペンを走らせたのだろう。
けれども、菊地原は驚きもせず、「明日の天気は今日と同じく晴れですよ」というよくある世間話を披露するノリでコメントしてくれた。
「歌川はそういうこと、息を吸うのと同じくらい当たり前にやってのけるよねえ」
「うん、うん! 歌川くん、本当にすごいよね。一時限目始まるからすぐに消されそうだったし、あゆみさんにあとで教えてもらおうかなってもう半分諦めてたのに……」
諦めたら試合終了だと言わんばかりのところで入った救いの手であった。
そのやさしさが嬉しかった。そして、少女はびっくりしたのだ。こんなにもスマートに手を差し伸べられるひとが自分と同い年で、同じクラスのすぐ隣の席にいるだなんて、と。
「すごく、すごくやさしいよね……! He has a very gentle soulだよ!」
「急に元気よく早口になるなあ……まあ、何も不思議じゃないでしょ」
「え?」
菊地原は眉一つ動かさずに言う。
「だって、歌川だよ? あいつはそういう奴だから。隣が一人ケルベロスしてたらなんとかするのは当然でしょ」
彼は気怠く背もたれに寄りかかった姿勢のままだ。真澄が身に起きた奇跡を興奮気味に伝えても、まるで明日も今日同様に晴れの天候だと雲ひとつない青空の下で聞かされたときのような、特にどうということはなくわかりきっているという反応だ。
「そ、そうかなあ……ううん、そうかも。歌川くんって、すごく本当にすごくすごくすごいね」
「すごいの飽和状態なんだよなあ」
呆れたようなコメントだが、菊地原の声のトーンは少し明るい。
ベリージェントルソウルをお持ちの隣人歌川に、少女は緊張を隠せないまま「ありがとう」と礼を言った。情けないことに絞り出せた声はどう見積もっても震えていたし、小さかった。自分から進んで男の子に話しかけるのはかなりの勇気が必要だったのだ。家にいる小学二年生男子とは毎日気負わずに話せるのに、だ。けれども、歌川は真澄の過緊張を特に指摘せず、からかいもせずに微笑んだのだ。
「初めての模試、お互いがんばろうな」
その後の記憶はひどく曖昧だ。真澄は抜かりなく返事をできたのか、正直なところ何も覚えていない。ただ、心臓がいつもより速く強く大きく鳴っていたことだけは覚えている。
親切を鼻に掛けることもなく、謙遜もすることもなく、少年は励ましの声までくれた。ベリージェントルソウル、すごい。ベリーベリーベリージェントルソウルだ。
歌川は誰にでも手を差し伸べることをためらわない少年だ。たとえば掃除時間。同じ班員が大きなゴミ袋を抱え上げるのを見たら、女子だろうが男子だろうが構わずに自分からそれを攫っていってしまう。相手が気後れしないように自分が持つ箒やモップとの交換を持ちかけるスマートさも忘れない。
たとえば休み時間。教科書や辞書を忘れた隣のクラスの友だちがしょんぼりしながら貸し出しを請えば、「次は気を付けような」と快く自分のものを差し出している。それが今日の時間割にない科目であれば、別のクラスにその友人と共に足を運びに行く姿も見えた。
たとえば朝の小テストの時間。いつも通り歌川と漢字テストを交換し、互いのものを採点し合ったときのことだ。
「途中から回答欄がずれてしまって、自分史上今まで見たこともないくらいにひどい点数になったのね。ただでさえ情けないし採点はいつも通り隣同士で交換しなくてはいけないし、恥ずかしすぎるしで家に帰りたくてたまらなかったの。けど、歌川くんは全然茶化さずにいてくれたんだ……」
いつも通り彼は淡々と採点し、「次もがんばろう」と穏やかに言ってくれた。なんとか「はい」と返事をしたものの、対する歌川の答案用紙は満点だ。情けなさが一層膨れ上がる。両手で返却するなり、がっくりと肩を落とす真澄に彼はそっと声を重ねた。
「宇田川さんの字っていつも綺麗だよな。まっすぐだし、とめ・はね・はらいとか、大きさもバランスもいつも綺麗に整ってる」
彼は真澄の書く文字を褒めてくれた。
「もしかして、書道とかペン習字とかやってる?」
「しょ、書道を少々……」
真澄は小さな頃から書道を習っている。祖母が書道教室を開いているからというのが始まりだが、四歳から始めて今年で十二年目になる。
「そうなんだ。だから答案交換すると、いつも宇田川さんは丸も罰点も点数も綺麗に書いてくれるんだな」
歌川は自身の満点の答案用紙をしげしげと見直し、感心したように言った。
「宇田川さんはいつも採点の字も綺麗だから、満点だともらえる花丸がちょっとした勲章みたいで『よし!』って嬉しくなるし、ミスして点数逃したときもシュッとした字が格好良いから『次こそはしっかり見直ししないと』って背筋が伸びるんだよな。いつも綺麗に採点してくれてありがとう」
「そんなこと…………ううん、歌川くん、いっぱい褒めてくれてありがとう」
歌川の言葉を、真澄は何度も何度も噛みしめた。それはじわじわと胸も指先も頬も温めてくれた。
書道は真澄が人生で最も長く打ち込んでいる習い事だ。彼女にとって一番胸を張ることができる特技でもある。
何事も長く打ち込むのは大変なことだ。特にこの三門市では、四年前にそれまでの生活を一変させる大きな出来事があった。だからこそ、何かに打ち込めるのは幸せで、継続するのは大変なことなのだと知っている。あの出来事以降、続けていた習い事や遊びをやめる選択をした子もいた。やめざるを得ず、そのうえ外に転校していった子もいた。
十二年間も継続できているものがあるというのは真澄にとって自信にも誇りにも繋がっている。同時に、今でも祖母が師範をしている教室に通えている自分の幸運、家族そろって平和な日常を送れていることの幸せ、それらが叶えられているのはこの街を守ってくれているひとたちがいからなのだ。少女もまたそのありがたさを忘れずにいつも大事にしたいと思っている。
歌川の言葉をじっくり反芻していると、歌川がこれは「内緒なんだけど」と声を小さくした。真澄よりも大きく筋張った指が唇を覆い隠す。
「宇田川さんが満点の時、オレの残念な採点の字で残念感が足されないといいなっていつも思ってるよ。……お互い、次もがんばろうな」
胸のあたりが、きゅう、となった。
目を細め、頬を搔きながら照れたように言う歌川の笑みが、真澄の目と心臓を焦がしたらしい。喉のあたりも熱くなって、うつむいた。
あのときも自分は返事を声にできたのか、はっきり覚えていない。ふわふわしたままの頭で何度も何度も大きくうなずいた。それだけは確かだ。
胸がいっぱいで、つっかえつっかえになる真澄の「この歌川くんがすごい! 伝説」を、菊地原はただ静かに聴いてくれていた。
話し終えると、彼はただ一言だけ告げた。
「さもありなん」
ぱちぱち、と真澄はまばたきを繰り返す。初めて聴く言葉だ。日曜朝の戦隊アクションヒーロー番組の怪人に登場しそうな響きである。
淡々とクールな調子の声が入った。
「然も有りなん。いかにも予測していたことで、今更驚くにあたらないってこと」
「へえ……! そうなんだ。すごい! 菊地原くんって物知りなんだねえ!」
「別に褒められることでもないと思うけど」
「ううん! そんなことないよ! 良いところはどんどん褒められるべきだよ!」
謙遜する少年に真澄は勢いよく横に首を振った。宇田川家の祖父母と両親はどんどん褒めて伸ばすタイプだ。それは祖母の書道教室の方針でもある。おかげで真澄も小学二年生の弟も冬の寒い日に水で毛筆を洗うのを面倒くさがることもなく、ぐんぐん書道も上達している。
「菊地原くんは物知り博士だし、すごく落ち着いているね」
「急に褒めてくる……。褒めても何も出ないのに。ぼくが落ち着いてる? 歌川ほどじゃないけど……?」
「歌川くんはベリーベリーベリージェントルソウルによる落ち着きで、菊地原くんの落ち着きは、なんというか、動かざること山の如し? という感じがする……」
「休み時間にドッジボールに興じるタイプじゃなくてすみませんねえ」
「え? ええっ!? ブショーみたいだねってゼッサンしてるのに」
「なにその発音。宇田川、武将ってちゃんと漢字で書ける? 絶賛は? それぞれの部首を説明できる?」
「う」
絶え間ない進学校入試あるあるジョークに息が止まるが、「いいひとだな」と同時に深く思う。
菊地原は言葉こそストレートで鋭いが、声音にも表情にもからかいというものが混じっていない。馬鹿にするわけでもなく、邪険にするわけでもなく、まとまらないまま話し出した真澄に相槌も否定もなしにただ耳を傾けてくれていた。
それに、元来お喋りが得意ではない真澄がなんとか一言振り絞れば、菊地原は百も二百も倍にしてテンポ良くなにやら深い言葉を返してくれる。
彼は言葉も物事も、真澄よりもずっと多く、もっと深く知っているのだろう。それらを理解して、手足に、血肉に一切を刻み込んでいなければ、ここぞという場面で速度を緩めずに最適解を引き出せるはずがない。
そのうえ真澄の「この歌川くんがすごい! 伝説」に対する律儀なコメント内容だけでなく、菊地原自身が歌川のことを話すときに少しだけ声の調子も明るいのだ。ごくごく当たり前に友だちの歌川を、彼の人柄にも親切心にも信頼を置いているのだろう。
おほん、と真澄は咳払いをした。いったい何、という風に菊地原が胡乱な目つきで先を促してくる。
「菊地原くん、知ってる? 類は友を呼ぶって」
「はあ? なに、急に? まあいいけどさあ……類を以て集まる。気の合った者や似通った者は自然に寄り集まるってことでしょ。それが何?」
「うん。あとね、知ってる? 友だちは人間に対する最高の尊称なんだよ」
菊地原の淡い色素の瞳が、まあるくなった。猫みたいだ。
昔から「友だちは人間に対する最高の尊称」で「類は友を呼ぶ」と聞く。
すごくすごくてすごい歌川とごくごく当たり前に友だちで在り続ける菊地原もまた、すごくすごくてすごいひとなのだ。「歌川くんにもすごくていい友だちがいるのだなあ」と知ったことで、またしても歌川のすごいひとポイントも上がった。そのうえ、互いにいいひとである二人が「いい友だち同士なのだな」と知ることができて、くすぐったいような気持ちになる。互いの良い部分を影響し合えるのが友だちだとよく聴くが、二人はまさにそうなのだ。
そして、そんなすごくすごくてすごい二人がいるクラスで一年を共に過ごすことができるだなんてすごくすごくてすごいだけでなく本当にすごすぎることだな、と強く実感する。
菊地原が指摘したように彼らのすごさを言い表すのに「すごい」としか言い方がわからないのが少しだけ悔しい。
昔から続けている書道のおかげで、真澄は文字を褒められることが多い。その誇れる書にふさわしい知識と落ち着きが欲しいな、と思う。
ふ、と壁の時計を見上げる。長針がまもなく六に到着しそうだ。もうすぐ五時三十分になる。開け放った窓の外の陽射しはまだ明るい。カーテンはまだ夕暮れの橙色に染まり始めていない。
「菊地原くん」
「なに?」
真澄は背をしゃんと伸ばし、菊地原に頭を下げた。
「菊地原くん、今日はたくさんお話を聴いてくれてありがとう。図書当番、これからもがんばろうね」
残念ながら歌川や菊地原のような知識も落ち着きも真澄の手元にはまだ届きそうにない。けれども、挨拶だけは、お礼だけは今からでも心をいっぱい込めて発することができる。
「また急にきりっとするし……まあいいや。こちらこそ、またよろしく」
首のあたりを搔きながら菊地原もうなずいてくれた。そして、ふ、と口角を上げた。いい暇つぶしになったよ、と。小学二年生の弟が面白そうなものをもったいぶりながら教えてくれるときに浮かべるのと似たような笑みだった。
カレンダーが進むに合わせて少しずつ増えていく日々の課題と予習復習。その先で待ち構えている定期試験に模擬試験。大学入学試験。長い長いトンネルに気持ちがめげそうになったとき、真澄は自室の机の引き出しを開ける。
お気に入りのぴかぴかした大きなクッキー缶が目に入る。菫色のふたをそっと開けると、中に入っているのは透明なクリアファイルに収めた紙だ。初めての模擬試験時間割メモ。ちょっとだけ残念な点数記録を樹立してしまった漢字小テスト答案用紙。歌川が書いてくれたものだ。
それらをもらったとき、真澄は、手を差し伸べてもらえた、と感じたのだ。隣の歌川に。同い年なのに自分よりもずっと大人びた男の子に。
右肩上がりの文字だが、読みやすく、最後の“はらい”が一番力強くて、先が僅かに丸くなっている。それがちょっとだけ可愛い。
あのとき歌川にもらったやさしさ。そっとかけてもらった言葉。
引き出しを開ければいつでも目に入るそれらが、真澄の背を押してくれている。
クッキー缶を丁寧にしまい、真澄は椅子から立ち上がった。ぽかぽか全身が温まるような気分がしたので、両腕を上げて大きく伸びをする。
少女の机の引き出しには、この春一番の宝物が眠っている。
遅刻回避を願いながら食パンを咥えて走る主人公が曲がり角でヒーローや恋のお相手、ライバルと伝説的王道接触シーンを繰り広げるのも、謎の転校生が見開き大コマで突然クラスに登場するのも、日曜朝のヒーローが力に目覚めるのもたいていが春だ。始まるならば春がふさわしい季節なのだろう。
少女にとっても思い返す限り、始まりは春だった。
ドラマや漫画によると、どうやら第一話の最序盤を牽引する流星の如くスタートを切ったり、中盤のクライマックスとして大盛り上がりの音楽と共に来たり、大迫力の見開き直前ラストシーンや次話への“引き”として、ド派手にドン! とそれはそれはわかりやすく知らせてから来てくれるものらしい。
ド派手にドン! は物語世界のみに限られたものだとしても、トントン、くらいのレベルで予告なく肩を後ろから叩いてくれるものなのだと少女は考えていた。
けれども、実はそうでもないらしい。やさしく春の雨のように降ってくることもあるのだ。そのひとと出会い、そのひとのことを少しずつ知ることで、そのひとへの想いも本のページのように徐々に重なり、やがて厚くなる。それを繰り返し捲り続けていくことで、その想いが厚く熱く、あふれそうにもなる。恋とはそういうものなのだと少女は知った。
「歌川のこと好きなの?」
ひゅ。
正々堂々。威風堂々。開幕初手。搦め手なし。正面からぶち込まれた剛速球ストレートに少女は呼吸を止めた。
「……歌川のこと、好きなの?」
二回言われた。相手の肩まで届くほどの色素の薄い髪が、目の前でさらりと揺れる。首を傾げた少年がもう一度ボールを投げてくれた。聞こえていないと判断されたらしい。気怠げな表情だが、威圧感はない。髪と同じ淡い色の眉が少しだけ上がっているだけで、気を悪くした様子はない。すぐに返事ができなかったことを咎めず、嫌な素振りも見せずに同じことをもう一度言ってくれるだなんて、なかなか親切なひとである。
「……ええと」
「うん」
少年の目つきにも態度にも声にもからかうようなものは混じっていない。高校ならでは、または男子界隈特有の挨拶なのだろうか。
男の子と二人で――挨拶と天気の話以外で――面と向かって話をするだなんて、小学生ぶりのような気がする少女にとって、その質問はどういった意図によるものなのか判断が難しい。小学生の弟とは日曜日の戦隊アクションの次回予想について今朝も話したばかりだが、ノーカウントだ。父親とも学校であった出来事などについて話すものの、これもまたあまり参考にはならないだろう。
少女が大きくまばたきをすると、少年もまたゆっくりとまばたきをした。
窮した少女は「すみません」と断りを入れ、首の前で左腕を右に倒した。その真下に右腕を垂直に立て、指先も縦にピンとそろえた。まっすぐと。
タイムを願い出た少女に少年は目を丸くしたものの、うなずいてくれた。答えを急かさず待ってくれるだなんて、初めて同じクラスになったこの男子生徒はやはり親切なひとかもしれない。
放課後の図書室である。新学期が始まってから三週間が過ぎた。三年生からクラス順でスタートした図書委員会図書当番は、二年生のシフトも終わり、少女が所属する一年生にもめでたく巡ってきた。高校生活に新一年生もそろそろ慣れてきただろうという上級生の作戦だ。少女の当番の相棒は、同じC組の男子生徒だ。
一年C組は、クラス委員長の立候補制を除き、他の係と委員会はくじ引きで全て公平に決まった。提案者は担任教諭だ。担任教諭の一声で一も二もなく決まった。交流の輪も広がり親睦も深まり一石二鳥だろう、との計らいなのだ。
六頴館高校は中等部から内部進学した者が大半で、その他に高等部から外部入学してきた優秀な生徒がいる。一年C組にも外部から合流した頼もしい生徒はいるのだ。外部入学生が内部進学組と臆さずに交流できるように、一日も早く六頴館校の生活の苦楽を分かち合える友を得られるように。そうした担任教諭の心意気に生徒も快く賛成したのだ。
そういうわけで、宇田川真澄の図書当番初登板の相方は、菊地原士郎である。
同じ教室で学ぶ仲だ。挨拶くらいはしたことがあるが、クラスが一緒になるのも面と向かって話すのも初めての相手である。クラスでの席は、出席番号順によるものなので割合近い――菊地原は真澄の右斜向かいの更に一つ後ろ、つまりは右隣から二列後ろの住人だ――が、班は別々なので掃除当番も一緒になったことはない。彼はクラスでも物静かな印象の男子生徒である。真澄の隣の席の男の子と仲が良いのか、時には昼食を共に囲んだり、休み時間に話をしたりしている様子をよく見かけている。休み時間の男子と言えば、校庭で「ドッジボールしようぜ!」がメジャー(新小学二年生の弟談)らしいが、昼休みには、静かに机に伏せてヘッドホンで音楽を聴いている姿をよく見かけた。音楽をこよなく愛する者なのかもしれない。実は軽音楽部や吹奏楽部に所属しているのかもしれない。
子どもの頃から「ぼんやりしている子」だとよく言われていた真澄は、活発なグループに所属する子、とりわけ男の子と話すのは苦手だ。菊地原は男子ではあるものの、物静かなタイプであるし、話してみたら実はとっつきやすい子かもしれない。同じクラスと同じ図書委員になった同志として少しずつ仲良くなれたら嬉しいな、と挑んだ初めての図書当番である。当番日は、昼休み中の三十分間と放課後に一般下校時刻五時三十分まで図書室にて受付当番や返却書籍の整理をすることになっている。ただし、六頴館は日によっては七時限までの授業もあるので、そうした場合の当番時間は短縮が認められている。その場合は当番の生徒が到着するまで司書と司書教諭がフロント守備に回っていらっしゃるそうだ。
図書当番初登板の世間話初手は明日の天気と今日の最低気温と最高気温から攻めていこう――
決意した矢先の菊地原選手の剛速球サービスエースであった。
穏やかな晴天に恵まれた今日の図書室は空いている。予習復習や課題に励むために勉強道具を広げたり、新刊雑誌やお目当ての本を読み耽ったりしている生徒の姿もまばらだ。カウンターに着席して以来、まだ一度も新たな貸し出し客も返却客も現われなかった。カウンターの二人が会話をしていても差し障りはない。はずだ。
歌川とは、同じC組の歌川遼のことだ。宇田川真澄の右隣の席の住人だ。菊地原が昼食を囲んだり、休み時間にお喋りをしたりしている男子生徒でもある。菊地原は音楽を聴いていても歌川が話しかければ、顔をスンとさせて返事をするし、放課後も二人連れ立って教室を出る姿を見るので、昔から仲の良い友人なのだろう。友人歌川への意識調査をクラスメイトに試みるだなんて、菊地原は友だち思いで心配性なのかもしれない。
それらを踏まえ、真澄はじっくりと考える。選択肢は提示されなかったが、よくある五択形式だろう。
「あの、ええとね、『とても好き』か『やや好き』かのどちらかだと思う」
「うん?」
遅刻した真澄の返事に菊地原の語尾も眉も大きく跳ね上がった。
「『とても好き』か『やや好き』のどちらかだと思います。歌川くんのこと」
「二回も言う……聞こえてるって」
菊地原が何か言ったようだが、真澄はそのまま続けた。
「『とても好き』『やや好き』『どちらとも言えない』『やや嫌い』『とても嫌い』の五択から選ぶならば歌川くんは『とても好き』か『やや好き』のどちらかなのだけれど、正直なところよくわからないです」
きりりと眉に力を入れた真澄に、菊地原は呆れたように言った。
「へえ。三回も言っておきながらよくわからないんだ……」
「うん」
よくわからないことだけはよくわかったから三回言ったのだと自信満々にうなずくと、菊地原は右眉を上げた。それから大きく息を吐いた。ふうん、と。
「歌川くんね、すごく親切だったんだよ」
入学式。内部進学組だが高等部校舎に初めて本格的に足を踏み入れた――オープンキャンパスで来たことだけはある――真澄は、クラス発表確認後に見事に迷った。一目で迷子だとわかる真澄を見つけ、不安いっぱいの彼女に気づくなり、歌川はほんの少しかがんで話しかけてくれたのだ。
咲き誇る八重桜に見蕩れて上方ばかり見上げていたものだからなおのこと、どこからどう歩いてきたのかもわからなくなり、半ば泣きそうになっていたところを歌川は助けてくれたのだ。
教室まで案内してくれたうえに同じ一年C組でおまけに隣の席だと発覚すると、「改めてよろしく」とそのひとは明るく笑ってくれた。
「歌川くん、同い年のはずなのにとても親切だし、周りのことよく見てくれているよね」
「うん」
しっかりとうなずく菊地原に、ぱあっと目を輝かせた。
「本当に親切だよね。先週の朝、SHRで先生が黒板に模試の時間割を書いてくださったときのことなんだけど」
「うん」
「わたしの席の前列の皆さん、そろって背が高いでしょう?」
菊地原がきょとんとまたたくので、真澄は指折り数えた。
「バレー部の秋山くんと伊藤くん、バスケ部の青野さん、左斜向かい前の落語研究会佐藤くん。真ん前の吹奏楽部トロンボーン担当あゆみさん……じゃなかった市川あゆみさん。ほら、皆、背が高くてすらっとしてる」
菊地原が真澄の上から下までをざっくり目測しているのが伝わってきた。
「ああ……はい、はい」
菊地原もまた真澄よりも高身長だが、こうして席に座ると座高があまり変わらないように思える。実物と比較されるマッチ棒の気持ちがほんのりわかった気になった。息を吐きながら真澄は少しだけ椅子を引く。遠近感を強調することで格差をなんとか隠していきたい。
「それで、皆がうつむいたときを狙って、あゆみさんの後ろからぐるぐるひょいひょい顔を出してメモ取ろうとしてたらね、なんとびっくり」
「隣から歌川が……」
菊地原の合いの手に真澄は身を乗り出した。
「そう! 歌川くんがね、メモをくれたの! 時間割を全部写したメモを! こっそりと!」
その時間割メモは、やや右肩上がりだが読みやすい文字だった。自分の分だけでなく、隣人の分まで書き写してくれたのだ。とても急いでシャープペンを走らせたのだろう。
けれども、菊地原は驚きもせず、「明日の天気は今日と同じく晴れですよ」というよくある世間話を披露するノリでコメントしてくれた。
「歌川はそういうこと、息を吸うのと同じくらい当たり前にやってのけるよねえ」
「うん、うん! 歌川くん、本当にすごいよね。一時限目始まるからすぐに消されそうだったし、あゆみさんにあとで教えてもらおうかなってもう半分諦めてたのに……」
諦めたら試合終了だと言わんばかりのところで入った救いの手であった。
そのやさしさが嬉しかった。そして、少女はびっくりしたのだ。こんなにもスマートに手を差し伸べられるひとが自分と同い年で、同じクラスのすぐ隣の席にいるだなんて、と。
「すごく、すごくやさしいよね……! He has a very gentle soulだよ!」
「急に元気よく早口になるなあ……まあ、何も不思議じゃないでしょ」
「え?」
菊地原は眉一つ動かさずに言う。
「だって、歌川だよ? あいつはそういう奴だから。隣が一人ケルベロスしてたらなんとかするのは当然でしょ」
彼は気怠く背もたれに寄りかかった姿勢のままだ。真澄が身に起きた奇跡を興奮気味に伝えても、まるで明日も今日同様に晴れの天候だと雲ひとつない青空の下で聞かされたときのような、特にどうということはなくわかりきっているという反応だ。
「そ、そうかなあ……ううん、そうかも。歌川くんって、すごく本当にすごくすごくすごいね」
「すごいの飽和状態なんだよなあ」
呆れたようなコメントだが、菊地原の声のトーンは少し明るい。
ベリージェントルソウルをお持ちの隣人歌川に、少女は緊張を隠せないまま「ありがとう」と礼を言った。情けないことに絞り出せた声はどう見積もっても震えていたし、小さかった。自分から進んで男の子に話しかけるのはかなりの勇気が必要だったのだ。家にいる小学二年生男子とは毎日気負わずに話せるのに、だ。けれども、歌川は真澄の過緊張を特に指摘せず、からかいもせずに微笑んだのだ。
「初めての模試、お互いがんばろうな」
その後の記憶はひどく曖昧だ。真澄は抜かりなく返事をできたのか、正直なところ何も覚えていない。ただ、心臓がいつもより速く強く大きく鳴っていたことだけは覚えている。
親切を鼻に掛けることもなく、謙遜もすることもなく、少年は励ましの声までくれた。ベリージェントルソウル、すごい。ベリーベリーベリージェントルソウルだ。
歌川は誰にでも手を差し伸べることをためらわない少年だ。たとえば掃除時間。同じ班員が大きなゴミ袋を抱え上げるのを見たら、女子だろうが男子だろうが構わずに自分からそれを攫っていってしまう。相手が気後れしないように自分が持つ箒やモップとの交換を持ちかけるスマートさも忘れない。
たとえば休み時間。教科書や辞書を忘れた隣のクラスの友だちがしょんぼりしながら貸し出しを請えば、「次は気を付けような」と快く自分のものを差し出している。それが今日の時間割にない科目であれば、別のクラスにその友人と共に足を運びに行く姿も見えた。
たとえば朝の小テストの時間。いつも通り歌川と漢字テストを交換し、互いのものを採点し合ったときのことだ。
「途中から回答欄がずれてしまって、自分史上今まで見たこともないくらいにひどい点数になったのね。ただでさえ情けないし採点はいつも通り隣同士で交換しなくてはいけないし、恥ずかしすぎるしで家に帰りたくてたまらなかったの。けど、歌川くんは全然茶化さずにいてくれたんだ……」
いつも通り彼は淡々と採点し、「次もがんばろう」と穏やかに言ってくれた。なんとか「はい」と返事をしたものの、対する歌川の答案用紙は満点だ。情けなさが一層膨れ上がる。両手で返却するなり、がっくりと肩を落とす真澄に彼はそっと声を重ねた。
「宇田川さんの字っていつも綺麗だよな。まっすぐだし、とめ・はね・はらいとか、大きさもバランスもいつも綺麗に整ってる」
彼は真澄の書く文字を褒めてくれた。
「もしかして、書道とかペン習字とかやってる?」
「しょ、書道を少々……」
真澄は小さな頃から書道を習っている。祖母が書道教室を開いているからというのが始まりだが、四歳から始めて今年で十二年目になる。
「そうなんだ。だから答案交換すると、いつも宇田川さんは丸も罰点も点数も綺麗に書いてくれるんだな」
歌川は自身の満点の答案用紙をしげしげと見直し、感心したように言った。
「宇田川さんはいつも採点の字も綺麗だから、満点だともらえる花丸がちょっとした勲章みたいで『よし!』って嬉しくなるし、ミスして点数逃したときもシュッとした字が格好良いから『次こそはしっかり見直ししないと』って背筋が伸びるんだよな。いつも綺麗に採点してくれてありがとう」
「そんなこと…………ううん、歌川くん、いっぱい褒めてくれてありがとう」
歌川の言葉を、真澄は何度も何度も噛みしめた。それはじわじわと胸も指先も頬も温めてくれた。
書道は真澄が人生で最も長く打ち込んでいる習い事だ。彼女にとって一番胸を張ることができる特技でもある。
何事も長く打ち込むのは大変なことだ。特にこの三門市では、四年前にそれまでの生活を一変させる大きな出来事があった。だからこそ、何かに打ち込めるのは幸せで、継続するのは大変なことなのだと知っている。あの出来事以降、続けていた習い事や遊びをやめる選択をした子もいた。やめざるを得ず、そのうえ外に転校していった子もいた。
十二年間も継続できているものがあるというのは真澄にとって自信にも誇りにも繋がっている。同時に、今でも祖母が師範をしている教室に通えている自分の幸運、家族そろって平和な日常を送れていることの幸せ、それらが叶えられているのはこの街を守ってくれているひとたちがいからなのだ。少女もまたそのありがたさを忘れずにいつも大事にしたいと思っている。
歌川の言葉をじっくり反芻していると、歌川がこれは「内緒なんだけど」と声を小さくした。真澄よりも大きく筋張った指が唇を覆い隠す。
「宇田川さんが満点の時、オレの残念な採点の字で残念感が足されないといいなっていつも思ってるよ。……お互い、次もがんばろうな」
胸のあたりが、きゅう、となった。
目を細め、頬を搔きながら照れたように言う歌川の笑みが、真澄の目と心臓を焦がしたらしい。喉のあたりも熱くなって、うつむいた。
あのときも自分は返事を声にできたのか、はっきり覚えていない。ふわふわしたままの頭で何度も何度も大きくうなずいた。それだけは確かだ。
胸がいっぱいで、つっかえつっかえになる真澄の「この歌川くんがすごい! 伝説」を、菊地原はただ静かに聴いてくれていた。
話し終えると、彼はただ一言だけ告げた。
「さもありなん」
ぱちぱち、と真澄はまばたきを繰り返す。初めて聴く言葉だ。日曜朝の戦隊アクションヒーロー番組の怪人に登場しそうな響きである。
淡々とクールな調子の声が入った。
「然も有りなん。いかにも予測していたことで、今更驚くにあたらないってこと」
「へえ……! そうなんだ。すごい! 菊地原くんって物知りなんだねえ!」
「別に褒められることでもないと思うけど」
「ううん! そんなことないよ! 良いところはどんどん褒められるべきだよ!」
謙遜する少年に真澄は勢いよく横に首を振った。宇田川家の祖父母と両親はどんどん褒めて伸ばすタイプだ。それは祖母の書道教室の方針でもある。おかげで真澄も小学二年生の弟も冬の寒い日に水で毛筆を洗うのを面倒くさがることもなく、ぐんぐん書道も上達している。
「菊地原くんは物知り博士だし、すごく落ち着いているね」
「急に褒めてくる……。褒めても何も出ないのに。ぼくが落ち着いてる? 歌川ほどじゃないけど……?」
「歌川くんはベリーベリーベリージェントルソウルによる落ち着きで、菊地原くんの落ち着きは、なんというか、動かざること山の如し? という感じがする……」
「休み時間にドッジボールに興じるタイプじゃなくてすみませんねえ」
「え? ええっ!? ブショーみたいだねってゼッサンしてるのに」
「なにその発音。宇田川、武将ってちゃんと漢字で書ける? 絶賛は? それぞれの部首を説明できる?」
「う」
絶え間ない進学校入試あるあるジョークに息が止まるが、「いいひとだな」と同時に深く思う。
菊地原は言葉こそストレートで鋭いが、声音にも表情にもからかいというものが混じっていない。馬鹿にするわけでもなく、邪険にするわけでもなく、まとまらないまま話し出した真澄に相槌も否定もなしにただ耳を傾けてくれていた。
それに、元来お喋りが得意ではない真澄がなんとか一言振り絞れば、菊地原は百も二百も倍にしてテンポ良くなにやら深い言葉を返してくれる。
彼は言葉も物事も、真澄よりもずっと多く、もっと深く知っているのだろう。それらを理解して、手足に、血肉に一切を刻み込んでいなければ、ここぞという場面で速度を緩めずに最適解を引き出せるはずがない。
そのうえ真澄の「この歌川くんがすごい! 伝説」に対する律儀なコメント内容だけでなく、菊地原自身が歌川のことを話すときに少しだけ声の調子も明るいのだ。ごくごく当たり前に友だちの歌川を、彼の人柄にも親切心にも信頼を置いているのだろう。
おほん、と真澄は咳払いをした。いったい何、という風に菊地原が胡乱な目つきで先を促してくる。
「菊地原くん、知ってる? 類は友を呼ぶって」
「はあ? なに、急に? まあいいけどさあ……類を以て集まる。気の合った者や似通った者は自然に寄り集まるってことでしょ。それが何?」
「うん。あとね、知ってる? 友だちは人間に対する最高の尊称なんだよ」
菊地原の淡い色素の瞳が、まあるくなった。猫みたいだ。
昔から「友だちは人間に対する最高の尊称」で「類は友を呼ぶ」と聞く。
すごくすごくてすごい歌川とごくごく当たり前に友だちで在り続ける菊地原もまた、すごくすごくてすごいひとなのだ。「歌川くんにもすごくていい友だちがいるのだなあ」と知ったことで、またしても歌川のすごいひとポイントも上がった。そのうえ、互いにいいひとである二人が「いい友だち同士なのだな」と知ることができて、くすぐったいような気持ちになる。互いの良い部分を影響し合えるのが友だちだとよく聴くが、二人はまさにそうなのだ。
そして、そんなすごくすごくてすごい二人がいるクラスで一年を共に過ごすことができるだなんてすごくすごくてすごいだけでなく本当にすごすぎることだな、と強く実感する。
菊地原が指摘したように彼らのすごさを言い表すのに「すごい」としか言い方がわからないのが少しだけ悔しい。
昔から続けている書道のおかげで、真澄は文字を褒められることが多い。その誇れる書にふさわしい知識と落ち着きが欲しいな、と思う。
ふ、と壁の時計を見上げる。長針がまもなく六に到着しそうだ。もうすぐ五時三十分になる。開け放った窓の外の陽射しはまだ明るい。カーテンはまだ夕暮れの橙色に染まり始めていない。
「菊地原くん」
「なに?」
真澄は背をしゃんと伸ばし、菊地原に頭を下げた。
「菊地原くん、今日はたくさんお話を聴いてくれてありがとう。図書当番、これからもがんばろうね」
残念ながら歌川や菊地原のような知識も落ち着きも真澄の手元にはまだ届きそうにない。けれども、挨拶だけは、お礼だけは今からでも心をいっぱい込めて発することができる。
「また急にきりっとするし……まあいいや。こちらこそ、またよろしく」
首のあたりを搔きながら菊地原もうなずいてくれた。そして、ふ、と口角を上げた。いい暇つぶしになったよ、と。小学二年生の弟が面白そうなものをもったいぶりながら教えてくれるときに浮かべるのと似たような笑みだった。
カレンダーが進むに合わせて少しずつ増えていく日々の課題と予習復習。その先で待ち構えている定期試験に模擬試験。大学入学試験。長い長いトンネルに気持ちがめげそうになったとき、真澄は自室の机の引き出しを開ける。
お気に入りのぴかぴかした大きなクッキー缶が目に入る。菫色のふたをそっと開けると、中に入っているのは透明なクリアファイルに収めた紙だ。初めての模擬試験時間割メモ。ちょっとだけ残念な点数記録を樹立してしまった漢字小テスト答案用紙。歌川が書いてくれたものだ。
それらをもらったとき、真澄は、手を差し伸べてもらえた、と感じたのだ。隣の歌川に。同い年なのに自分よりもずっと大人びた男の子に。
右肩上がりの文字だが、読みやすく、最後の“はらい”が一番力強くて、先が僅かに丸くなっている。それがちょっとだけ可愛い。
あのとき歌川にもらったやさしさ。そっとかけてもらった言葉。
引き出しを開ければいつでも目に入るそれらが、真澄の背を押してくれている。
クッキー缶を丁寧にしまい、真澄は椅子から立ち上がった。ぽかぽか全身が温まるような気分がしたので、両腕を上げて大きく伸びをする。
少女の机の引き出しには、この春一番の宝物が眠っている。