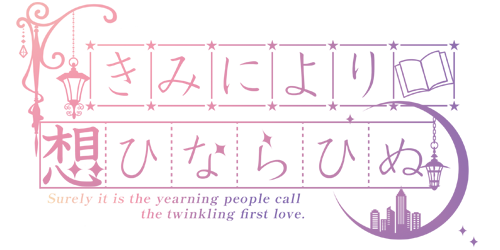白に、すうっと青い影が落ちた。その青は、滑るように白地を走って行く。燕だ。燕が空を飛び去って行ったのだ。途端、冷たい水が迸った。顔を上げると、小さく笑いながら洗い立てのタオルをこちらに差し伸べてくれるひとがいた。
「お、おばあちゃん……」
「今日のあなたは随分ぼんやりさんねえ」
真澄の手のひらと薫風を写し取ったような色合いのミントグリーン色のシャツに大きく跳ねた水を、祖母はやさしい手付きで拭っていく。ほそりとした指が、ひっくり返った水差しを、そっと静かに立たせた。
受け取ったタオルでシャツを押さえ、孫娘がまごまご姿勢を直しているうちに、祖母は障子を開け放った。明るい陽射しが、畳にも真澄にも降りる。祖母は雪に似た白いものが混じる髪を耳にかけ直し、息をついた。陽光が、その白を、淡く透かす。
「集中力、お出かけしちゃったみたいね」
「ごめんなさい」
しゅん、と肩を落とす。ポニーテールにしていた髪が、うなじで揺れた。
よい書を書くには、日々の練習だけでなく、集中力が必要だ。
身体の動きと息づかい。筆が紙をとらえる感覚。筆を動かす速度と筆圧の均衡。それらを少しずつチューニングし、吐く息と筆による線を引く身体の動きが一致した瞬間、よい書が書けるのだ。筆の墨の量と濃度、筆圧、手を動かすスピードは、練習を重ねることで身体に徐々に刻まれていく。繰り返し何度も練習を重ねることで、和紙が気持ちよく筆をとらえるようになるのだ。
真澄は、すう、と息を吸い込んだ。ほのかな墨の香りが漂い、心を落ち着かせてくれた。
指摘された通り、今日は練習する以前に気がそぞろになってしまった。連休に合わせて書道教室をお休みした祖母が、真澄の練習をゆっくり見てくれているというのに、だ。
「継続は力なり。一つの歩みを、コツコツ繰り返していく。その一歩はどんなに小さくても、どれほど地道な一歩だとしても転んでも諦めずに立ち上がって続けてみる。それが一番早くて、一番遠くまで確実に辿り着ける方法なの。書道だけでなく、何事もね」
凛と背筋を伸ばした祖母の静かで、けれどもよく通る声音。それが、小波の立った心を落ち着かせてくれる。
それから祖母は瞳をおっとりと細めた。華奢な指が、素早く孫の頬を包んでそっと摩る。
くすぐったさに身をよじれば、相手は悪戯が成功したように明るく顔をほころばせた。
「でも、高校に上がってから初めてのまとまったお休みだもの。今日はもう練習は終わりにしてゆっくりなさいな」
「はい……」
ほっそりとした指が、真澄の頬をもう一度撫でた。
「いいとこの羊羹をいただいたの。おやつに皆でいただきましょうね」
初夏の陽射しを受けて光っている祖母の瞳は、とろけそうにやわらかい。真澄もつられて頬を緩めた。
窓の外から、父と弟の声が聞こえてくる。
祖母の号令で一家そろっていいとこの羊羹をたっぷり堪能した。すっきりとした甘さに舌鼓を打って確かな満足を覚えた弟は、午前中よりも元気が回復している。母と父を誘って庭に飛び出したのだ。
「ねえ、お父さん。どんぐりって楓からも採れるよね? えっ? じゃあ、こっちの木は?」
部屋の掃除をしながら、真澄はその笑い声を聞くともなしに聞いていた。開け放した窓から弾んで響く声は、楽しげだ。庭の手入れがてら、自然観察もしているらしい。庭で芽吹く草木の名前を父がのんびりと指折り数えている声も聞こえてくる。「清らに咲けるその色めでつ」と母が上機嫌に『野ばら』を口ずさみ、父と弟も高らかにコーラスしている。ついには「太郎、そっち!」と言って愛犬と何かを追いかけ回す弟の声まで明るく響いた。元気大爆発である。はしゃぐ弟に普段はおとなしい愛犬も嬉しそうに戯れ付いているようだ。庭の笑い声が大きく寄せては賑やかに返っていく。
明るい陽射しの中に、蝶がひらめくのが見えた。
配布された課題プリントと、返却された答案用紙。週明けに提出できるもの、これから取り組むもの、もう一度取り組んで復習が必要なもの。クリアファイルに仕分けていた手を止めて、真澄はため息をついた。
高校一年生。初めての中間考査が終了した。
予想通り他の科目よりもよろしくなかった現国の成績にため息が出る。迂闊な己のケアレスミス、記述が間に合わずに空欄とした箇所、それから誤字に入った担当教諭の容赦のない赤ペンに、もう一度ため息が零れた――
返却された答案用紙にしょんぼりした気持ちが顔にはっきりと出ていたらしい。右隣の席の歌川遼は「お疲れ。またがんばろうな」と爽やかに声をかけてくれた。いつも通り大切にしたい歌川のやさしさだ。真澄はといえば、眉を下げたままうなずくことしかできなかった。もらってばかりのやさしさと応援に何も結果を出せなかった自分には、そのやさしさは嬉しいのに目にも心にも少しばかり痛いのだ。
放課後の図書当番中に日々の国語勉強の秘訣を尋ねれば、
「――国語のコツ? コツも何も掲載本文にも問題文章にも全部書いてあるでしょ?」
言葉の物知り博士こと図書委員同僚の菊地原士郎には、大きく首を傾げられてしまった。きょとんと。本降りの雨の中、手に持つ傘の差し方を知らずに歩き回る者を見つけたかのように目も丸くされた。できるひとが心の底から羨ましい。
現国と古典の先生方と書道部の先輩方が仰るには、これから現代文では小論文を自分で考えて書くという難問が登場するし(先日早速授業で小論文トレーニングもした)、古典では古語はもちろんのこと、動詞やら形容詞やらの活用表をまず身に付けなければ本文を理解することさえも難しくなっていくらしい。高校一年生スタート段階でつまずいた真澄は縮み上がった。
今日何度目かのため息をつき、椅子に座り直す。一年C組。二十二番。宇田川真澄。自分で書いた答案用紙の名前が目に入る。
とめ。はね。はらい。それらを呼吸するリズムのまま真澄がいつも書けるのは、四歳から書道を続けて十二年になるからだ。去年、学んでいる流派で最高段位も取れた。書道教室で師範をしている祖母からも、
「通い始めたばかりのあなたは半紙を前にしても気のない様子でぼんやり外を眺めてばかりいる子だったのに、思えば随分遠くまで、自分の力で歩いて来たわねえ……! 継続は力なり。いつもコツコツと、それをずっとがんばることを続けられて、ご立派!」
とびきり明るい笑顔でお褒めの言葉をもらった。
小さな頃、「ぼんやりしている子」だと周りの大人からも友だちからも真澄はよく言われていた。
よく言えば控えめ、はっきり言ってしまえばぼんやり。小学二年生の弟も同級生の子たちと比べればそちらのタイプに見えるが、姉の真澄が同じ歳だった頃よりもずっとエネルギッシュである。まだ庭を走り回っているらしい声がする。
ぼんやりしている、と言われがちだったのは、あまり喋るのが得意ではなかったからだろう。八歳離れた弟が生まれるまで、真澄は一人っ子だったのだ。周りの友だちのように兄弟や姉妹と活発に喋り合い、時には晩ご飯の唐揚げやデザートのプリンを巡って喧嘩をしたり、日曜日の行楽地お出かけおねだりに向けて仲良く作戦会議をしたり、同じ年頃の誰かと家でも日々何気なく言葉をぽんぽん交わし合って喋る経験数が少なかったのだ。そのうえ、両親と祖父母もやさしく穏やかな気性のひとたちで、小さな真澄がうまく言葉にできない気持ちも物事も笑顔で上手に汲み取ってくれていたのだ。それに甘えることを覚えてしまった少女は、ぼんやりレベルがぐんぐん上がってしまった。
その結果、高校生に上がった今も友だちとの交流では、彼女たちがテンポ良く喋るのを真澄は聴いてばかりいる。
祖母は言っていた。「継続は力なり」と。
そういえば、弟の自転車補助輪が取れたのは、転んでも転んでもめげずに弟が毎日練習していたからだ。
真澄の書道も十二年続けることで、文字の呼吸感が身に付いたのだ。現国も古典も、何事も、練習を継続することで覚えていくものなのだろう。ただし、高校は三年間という期間限定のものだ。十二年はさすがにない。留年ダメ。ぜったい。
できることからはじめよう、と真澄は気合いを入れ、まずは苦手意識しかない古典のテキストを読むことにした。
戦国武将も日曜朝に暗躍する悪の組織のえらいひともいつも言っている。「まずは敵を知り、己を知ることから始めよ」と。
それから三門市の平和を護ってくれるヒーローでお馴染みのスポーツが趣味? らしい嵐山ナントカさん? も今朝のローカル散歩番組で言っていた。
――疲れて散歩が気乗りしないときも、ひとまず運動着に着替えるんです。それからいつも走る場所まで行ってみる。すると、コロ――はい、愛犬なんです。え、写真は必要ない? そうですか可愛いのに…………コロが自分よりも先に元気に走り出してくれるので、自分もいつも通り走れるんです――
いつもと同じように準備を整えることで、気持ちも落ち着いていつも同様練習ができる、というのは真澄にも経験がある。書道だ。体育の授業が運動会やマラソン大会に向けた練習で疲れ果てた日も、畳の上で正座をし、墨を磨る。すると、いつも通り背筋がしゃきっとするのだ。
嵐山ナントカさん? は、同じクラスの歌川と菊地原も所属している街の防衛組織「ボーダー」の先輩なのだという。同じ高校一年生で学校の勉強だけでも忙しいはずなのに、いつも歌川はベリーベリーベリージェントルソウルを忘れずに周囲にやさしく声をかけてくれる。その友人の菊地原も動かざること山の如しな落ち着きで真澄やクラスメイトの話に鋭く賢いコメントをくれる。すごくすごい二人の先輩なのだ。当然この嵐山ナントカさん? のアドバイスはすごく効果がありそうだ。ついでにご利益もありそうだ。なんだかテレビの液晶画面もやけにきらきらしていた。
歌川と菊地原によると、二人の所属部隊をまとめる隊長風間なんとかさん? をはじめ、「ボーダー」にはそうした尊敬できるひとたちがたくさんいるらしい。類は友を呼ぶと言うが、すごいひとがゴロゴロ集まる組織ということは、それを創設した大人もきっと、すごくすごくものすごくすごいひとたちであふれているのだろう。更に市外からも、県外からもすごいひとたちが隊員として街の平和を護りに来てくれているのだと、朝の情報番組でも紹介していた。つまり、三門市にはすごいひとが大集合しているということになる。すごいひと選手権が開かれるかもしれない。そうしたすごいひとたちが身体を張って街の平和を護ってくれるのに恥ずかしくない市民で在りたいな、と真澄はますます気合いを入れて座り直した。
国語をがんばると決意したものの、一方で、一年生の今からつまずきかけていて、どうしたものか頭を抱えてしまう自分もいる。
風が、吹いた。からりとした爽やかな風は、レースのカーテンをそよがせ、古典の教科書を捲っていく。ぱらぱらと。五月の明るい陽光が差し、真澄を、机を明るく照らす。
風に捲られて開かれたページに真澄は目をとめた。
『伊勢物語』だ。
中学の古典でも教わったし、高等部内部入試対策の問題集でもよく登場した歌物語だ。
本文の後ろに書かれた解説冒頭文に懐かしさを覚え、「高校でもよろしくお願いします」という気持ちになる。
国語便覧の伊勢物語掲載部分を開いてみる。主人公の在原業平を描いた絵巻の写真が掲載されている。今でも充分綺麗でカラフルに見えるが、現代に残るそれは当時のものよりも少々色褪せているものらしい。描かれた当時は、きっと、おそらく、たぶん、もっと、きらきらぴかぴかしていて、手に取って読むたびに目も心も時間も奪われるうつくしい絵巻だったのだろう。
少女は、ぱちぱちとまばたきをした。
――そういえばこの在原業平ってひと、すごいなあ。
色々な女性と恋をしたという平安朝のプレイボーイの武勇伝は、こうして現代にも伝わる歌物語として、古典の教材として、中学と高校の試験問題にも気軽に顔を出してくれるくらい人々にとって親しみある歌物語として残っているのだ。数々の浮き名を流した平安朝のイタリア男は言葉の魔術師でコミュ強であった……というようなことを中学の国語でも学習した。彼は物語が最高潮に盛り上がるクライマックスシーンで毎回、「ここで一首」と歌を詠むのだ。
国語便覧の付録には、在原業平が詠んだという和歌一覧が載っていた。一覧には歌の解説だけでなく、彼がそれを詠んだシーンについても簡単に紹介されている。
「すごい……」
思わず真澄は声をあげた。
この在原業平は、すごい。毎回胸に湧き起こった気持ちを的確に素早く歌にしている。
目も口もぽかんと開いてしまった。
和歌は五・七・五・七・七の合計三十一文字に納める芸術だ。真澄は書道教室でも書道部でも昔の有名な歌人の残したものを墨で書くことがある。よりよい書にするべく、解説も歌にも込められた想いを知りたい、と師範の祖母と部活顧問に説明してもらったり、調べ学習したりしたこともある。
在原業平は、毎回きっちり三十一文字に納めている。そのうえ毎度しっかり気持ちを的確に歌にしてから贈っているのだ。そのとき湧き出た気持ちの正体を、理解しているのだ。それを表す言葉も知っているのだ。
引き出しを、静かに開ける。きらきらぴかぴかした菫色のクッキー缶が目に入る。
そこにこの春大切に仕舞ったのは、模擬試験時間割メモと自分史上最低記録を樹立した漢字テスト答案用紙だ。
どちらも歌川の右肩上がりの字が入ったものだ。
あのときもらった歌川のやさしいエール。さっと右隣からそれが届けられたあのとき、真澄はすごくすごく、ものすごく救われたのだ。暗い夜道を心細く歩いていたところに明かりを貸してもらえたくらい嬉しかった。手を差し伸べてもらえた、と思ったのだ。ほっとしたのだ。けれど、真澄にとってすごくすごくすごく親切だった歌川の思いやりは、ベリージェントルソウルをお持ちの歌川にとっては、然も有りなん、ごくごく当たり前にアサメシマエ? にできることなのだ。
「歌川くんはいつもすごいなあ。歌川くんみたいなすてきなひとに、わたしもなりたいな……なれるかな……」
歌川がベリージェントルソウルを見せてくれるたび、それを思い出すたび、真澄はきらきらした石を見つけたときのようになんだかどきどきしたし、その向けられたやさしさに恥ずかしくない自分で在りたい、と背筋がいつもしゃきっとした。
この気持ちは何だろう?
物知り博士の菊地原のように国語が得意だったならば、在原業平のように真澄がもっと言葉を知っていたら、ものの情趣を理解していたら、ぴったりの言葉で表現することができるのだろうか。
丁寧に机の引き出しを閉め直し、しゃんと姿勢を正した。
言葉にしたい。
言葉にできたらこの気持ちの正体がわかるかもしれない。
とはいえ、真澄は喋るのが得意ではない。友人と話すときだって、家族と話すときだって、相手のサーブをのろのろ受け止めて打ち返すことばかりしている。この平安朝のイタリア男よろしく朝飯前の如く、呼吸するのにも等しいリズムでここぞという歌を咄嗟に詠めるはずもない。四歳の頃から祖母の書道教室に通っていたから書写は得意だという自信はあるが、国語も作文も好成績というわけではなかった。夏休みの読書感想文や遠足と運動会などの学校行事の作文課題も毎回提出期限ギリギリまで四苦八苦していた。
先週始まった小論文のトレーニングだってそうだ。開幕戦から放課後に居残りとなってしまった。クラスメイトのほとんどが時間内に提出を済ませていて、居残り組の少なさにがっくりとしていたら、右隣からエールがあった。
「がんばれ」
歌川が励ましてくれた。
そのあたたかい応援にこたえたいと心を燃やして提出の運びとなったのであった。へとへとになって職員室まで提出に向かったが、「よくがんばりました」「宇田川さんの字は丁寧で綺麗でとても読みやすくて、いつまでも読みたくなるね」と国語教諭に花丸の笑顔をもらい、その場で赤ペンを入れられた漢字間違いの恥ずかしさも疲れも吹き飛んだ。
即興で話をするのは得意ではない。決められた時間内に文章として出力するのももっと苦手だ。
ぱらぱらと開いていた国語便覧の付録に真澄は息を呑んだ。
「あ……」
そこには、手紙の書き方が掲載されていた。拝啓。敬具。前略。前文。主文。末文。後付。どれも三年前、中等部入学試験対策で勉強したことがある手紙の基本だ。
黒ヤギさんは手紙を読まずに食べたが、白ヤギさんは黒ヤギさんに伝えたいことがあり、手紙を書いていたのだ。じっくりと伝えたい想いを言葉で書き表していたのかもしれない。
言葉を使うことでその想いを述べるのは、歌や論文、小説に限ったことではないのだ。手紙という方法もあるのだ。
――そうだ、手紙にするのはどうだろう。
自主的に取り組む手紙ならば字数制限もないし、提出期限もない。じっくりと何かに取り組むのには、書道でよく慣れている。手紙ならば言葉にできるかもしれない。そのためには現国と古典の苦手も克服せねばなるまい。ボーダーの嵐山ナントカさん? も言っていたのだ。
まずは準備をしてみることから始めよう、と。
真澄は、現国と古典を課題が出たときだけでなく、授業があった日にまずその部分の教科書とノートを読み直すことから取り組もうと決意した。それから、言葉を知るには読書が一番だろう。幸い、図書委員になってから当番のために図書室に行く習慣がある。次の当番登板では何か本を借りてみよう、と壁に掛けたカレンダーに真澄は口元を緩めた。
そして、赤ペンが大きく入れられた返却ほやほやの古典答案用紙と、ノート、教科書と向き合うことにした。
「真澄が休み時間に読書してるだなんて!」
「昼休みと言えば、窓際でのびのびぬくぬく光合成ばかりしている真澄が!」
「明日は雨?」
友人の市川あゆみと北見茉椰 が目を丸くする。
昼食後、春の陽射しに包まれる窓際で膝を丸めるのは真澄の趣味のひとつだが、そんなに驚くことだろうか。異議を申し立てねばなるまい、と真澄は四つ葉のクローバーが押し花として咲いているぴかぴかの真新しい栞を挟み直した。
読書に目覚めたきっかけは、歌川に対するきらきらした気持ちを言葉にして正体を掴みたい。ただそれだけなのだ。真澄自身よくわかっていない、この名前のない気持ちをそのまま打ち明けて、気のいい友人をこまらせるのもなんだかよろしくない気がする。
さてどうしたものか。
いつものように次の一手を選び取れずに視線を泳がせると、渦中のひと・歌川の背中が見えた。
丹波に出雲といふ所あり。
飾り気のない書体だが、誰の目から見ても誠実さを窺わせる、丁寧でどこかやわらかい文字がゆっくりと綴られていく。
五時限目は古典の授業である。今日は課題に出された教科書の古文を現代語訳することになっているのだ。担当教諭に当てられた歌川が該当箇所を黒板に書いてくれているのだ。
歌川の背中に浮いたシャツの皺。広いのにどこか硬そうにも見える背中なのに、そこに走る皺はなんだかやわらかそうだ。歌川の背中は、真澄の父と同じかそれ以上に広く見えた。まだ小学生の弟もあれほど大きくなるのだろうか。
「真澄。ねえ、真澄?」
「おーい、真澄? 真澄氏? 真澄さーん。どうしたの? ぼんやりして」
「もしもし。もしもーし。さてはおぬし、慣れない読書で知恵熱が出たな?」
ひらひら。茉椰が怪訝そうな顔つきで手のひらを振っている。あゆみも思案顔で顎をさすっている。
「ちえねつ……」
胸に湧いた気持ちをその場で三十一文字の歌にする技。それは、一長一短でできるものではない。教養や知恵が身に付いていなければ、培ったそれらを存分に磨き上げていなければまずできない芸当だ。
数々の女性との浮き名を流したという在原業平は、相手を軽んじることなく、その相手のことをよく知ったうえで、相手がそのとき一番欲しい言葉を惜しまずに贈ったということだろう。会話の達人だけでなく、気配りの名人でもあったのに違いない。
現代にも歌物語として古典の授業にまで語り継がれるほどのコミュニケーション力抜群の平安朝きってのイタリア男・在原業平を目指そうと気持ちを新たに課題も予習も済ませていることを思い出した真澄は胸を張った。
「イタリア男を目指したくて」
二対の瞳がまあるくなった。零れ落ちそうなほど、大きく、まあるく。
「真澄!?」
「真澄! なにゆえチャラ男に!?」
何故だか悲鳴をあげた茉椰とあゆみは、これまたどうしてか真澄の額にそれぞれの手のひらを代わる代わる当て始める。
「熱はないね」
「うん。発言も行動も目標もおかしいけど平熱っぽい。……読書に目覚めてイタリア生まれでイタリア育ちのチャラい男を目指すって此は如何に?」
「さあ……ジャンプで今週からそういう漫画の新連載が始まったんじゃない?」
「ジョジョ?」
「それは昔から続いてるでしょ。ほら、五部だよ五部」
「そう。それ。確かパッションフルーツみたいな名前のマフィアだかギャングだかがド派手に……」
ひそひそと、けれど、隠す気など一切ないのだろう。二人が小声で囁き合う。
真澄が小学生の弟と共同で『週刊少年ジャンプ』を購入して愛読していることを二人はよく知っているのだ。家に遊びに来たときにはそれを読むこともある。 二人がジョジョ談義を徐々に始めたところではっとした。大事な部分を省略して伝えてしまった。在原業平のようなコミュニケーション力と言葉の持つ力を身に付けたい。決意早々に失敗してしまったらしい。イタリア男・在原業平への道は険しい。そういうことだ。 歌川が板書を終えたようだ。端から端まで眺めて、彼が大きくうなずくのが見えた。誤字や脱字がないのか、また、全体のバランスも確認しているようだ。終わるなり、颯爽と前方の戸口から出て行くのが見えた。予鈴が鳴る前に手を洗いに行くのだろう。真澄がそれを見送っているうちに茉椰とあゆみの二人も徐々に奇妙なジョジョ談義も終わらせたようだ。二人は最後にもう一度だけ真澄の額の温度を確かめると、自分の席へと戻った。と言っても、あゆみは真澄の真ん前の席だが。
真澄も本を閉じ、机の中に丁寧に片付けた。ノートを開き、古語辞典と教科書、国語便覧。それからシャープペンと消しゴム、ボールペン、蛍光ペンを机に並べ、姿勢を正す。と――
「宇田川さん」
隣から澄んだ声がした。渦中のひとこと歌川遼である。席替えがまだ実施されていない現在もおとなりさんなのだ。
小テスト採点交換やペア学習でもないのに突如始まった会話イベントに真澄の心臓が騒ぎ始めた。どきどき。ばくばく。どくどく。
なにやら思案げに首を傾げた歌川が静かに言った。
「何か悩んでいることがあるのならば、一人で判断や行動する前に信頼できるご家族や友だち、先生に相談することをおすすめします」
「え、え? うん? ありがとう?」
何故だかわからないが突如歌川から静かにもたらされたアドバイス。声変わりをとうに終えたのだろう低く落ち着いた声音とあたたかな心配りに真澄は胸がいっぱいになった。 特に何かを悩んでいたわけではないのだが、彼に向けられたやさしさが、嬉しい。
胸がいっぱいになった真澄は、予習ばっちりだった古典の授業の解説が耳を素通りしてしまった。
平安朝イタリア男・在原業平への道のりは、遠い。
「お、おばあちゃん……」
「今日のあなたは随分ぼんやりさんねえ」
真澄の手のひらと薫風を写し取ったような色合いのミントグリーン色のシャツに大きく跳ねた水を、祖母はやさしい手付きで拭っていく。ほそりとした指が、ひっくり返った水差しを、そっと静かに立たせた。
受け取ったタオルでシャツを押さえ、孫娘がまごまご姿勢を直しているうちに、祖母は障子を開け放った。明るい陽射しが、畳にも真澄にも降りる。祖母は雪に似た白いものが混じる髪を耳にかけ直し、息をついた。陽光が、その白を、淡く透かす。
「集中力、お出かけしちゃったみたいね」
「ごめんなさい」
しゅん、と肩を落とす。ポニーテールにしていた髪が、うなじで揺れた。
よい書を書くには、日々の練習だけでなく、集中力が必要だ。
身体の動きと息づかい。筆が紙をとらえる感覚。筆を動かす速度と筆圧の均衡。それらを少しずつチューニングし、吐く息と筆による線を引く身体の動きが一致した瞬間、よい書が書けるのだ。筆の墨の量と濃度、筆圧、手を動かすスピードは、練習を重ねることで身体に徐々に刻まれていく。繰り返し何度も練習を重ねることで、和紙が気持ちよく筆をとらえるようになるのだ。
真澄は、すう、と息を吸い込んだ。ほのかな墨の香りが漂い、心を落ち着かせてくれた。
指摘された通り、今日は練習する以前に気がそぞろになってしまった。連休に合わせて書道教室をお休みした祖母が、真澄の練習をゆっくり見てくれているというのに、だ。
「継続は力なり。一つの歩みを、コツコツ繰り返していく。その一歩はどんなに小さくても、どれほど地道な一歩だとしても転んでも諦めずに立ち上がって続けてみる。それが一番早くて、一番遠くまで確実に辿り着ける方法なの。書道だけでなく、何事もね」
凛と背筋を伸ばした祖母の静かで、けれどもよく通る声音。それが、小波の立った心を落ち着かせてくれる。
それから祖母は瞳をおっとりと細めた。華奢な指が、素早く孫の頬を包んでそっと摩る。
くすぐったさに身をよじれば、相手は悪戯が成功したように明るく顔をほころばせた。
「でも、高校に上がってから初めてのまとまったお休みだもの。今日はもう練習は終わりにしてゆっくりなさいな」
「はい……」
ほっそりとした指が、真澄の頬をもう一度撫でた。
「いいとこの羊羹をいただいたの。おやつに皆でいただきましょうね」
初夏の陽射しを受けて光っている祖母の瞳は、とろけそうにやわらかい。真澄もつられて頬を緩めた。
窓の外から、父と弟の声が聞こえてくる。
祖母の号令で一家そろっていいとこの羊羹をたっぷり堪能した。すっきりとした甘さに舌鼓を打って確かな満足を覚えた弟は、午前中よりも元気が回復している。母と父を誘って庭に飛び出したのだ。
「ねえ、お父さん。どんぐりって楓からも採れるよね? えっ? じゃあ、こっちの木は?」
部屋の掃除をしながら、真澄はその笑い声を聞くともなしに聞いていた。開け放した窓から弾んで響く声は、楽しげだ。庭の手入れがてら、自然観察もしているらしい。庭で芽吹く草木の名前を父がのんびりと指折り数えている声も聞こえてくる。「清らに咲けるその色めでつ」と母が上機嫌に『野ばら』を口ずさみ、父と弟も高らかにコーラスしている。ついには「太郎、そっち!」と言って愛犬と何かを追いかけ回す弟の声まで明るく響いた。元気大爆発である。はしゃぐ弟に普段はおとなしい愛犬も嬉しそうに戯れ付いているようだ。庭の笑い声が大きく寄せては賑やかに返っていく。
明るい陽射しの中に、蝶がひらめくのが見えた。
配布された課題プリントと、返却された答案用紙。週明けに提出できるもの、これから取り組むもの、もう一度取り組んで復習が必要なもの。クリアファイルに仕分けていた手を止めて、真澄はため息をついた。
高校一年生。初めての中間考査が終了した。
予想通り他の科目よりもよろしくなかった現国の成績にため息が出る。迂闊な己のケアレスミス、記述が間に合わずに空欄とした箇所、それから誤字に入った担当教諭の容赦のない赤ペンに、もう一度ため息が零れた――
返却された答案用紙にしょんぼりした気持ちが顔にはっきりと出ていたらしい。右隣の席の歌川遼は「お疲れ。またがんばろうな」と爽やかに声をかけてくれた。いつも通り大切にしたい歌川のやさしさだ。真澄はといえば、眉を下げたままうなずくことしかできなかった。もらってばかりのやさしさと応援に何も結果を出せなかった自分には、そのやさしさは嬉しいのに目にも心にも少しばかり痛いのだ。
放課後の図書当番中に日々の国語勉強の秘訣を尋ねれば、
「――国語のコツ? コツも何も掲載本文にも問題文章にも全部書いてあるでしょ?」
言葉の物知り博士こと図書委員同僚の菊地原士郎には、大きく首を傾げられてしまった。きょとんと。本降りの雨の中、手に持つ傘の差し方を知らずに歩き回る者を見つけたかのように目も丸くされた。できるひとが心の底から羨ましい。
現国と古典の先生方と書道部の先輩方が仰るには、これから現代文では小論文を自分で考えて書くという難問が登場するし(先日早速授業で小論文トレーニングもした)、古典では古語はもちろんのこと、動詞やら形容詞やらの活用表をまず身に付けなければ本文を理解することさえも難しくなっていくらしい。高校一年生スタート段階でつまずいた真澄は縮み上がった。
今日何度目かのため息をつき、椅子に座り直す。一年C組。二十二番。宇田川真澄。自分で書いた答案用紙の名前が目に入る。
とめ。はね。はらい。それらを呼吸するリズムのまま真澄がいつも書けるのは、四歳から書道を続けて十二年になるからだ。去年、学んでいる流派で最高段位も取れた。書道教室で師範をしている祖母からも、
「通い始めたばかりのあなたは半紙を前にしても気のない様子でぼんやり外を眺めてばかりいる子だったのに、思えば随分遠くまで、自分の力で歩いて来たわねえ……! 継続は力なり。いつもコツコツと、それをずっとがんばることを続けられて、ご立派!」
とびきり明るい笑顔でお褒めの言葉をもらった。
小さな頃、「ぼんやりしている子」だと周りの大人からも友だちからも真澄はよく言われていた。
よく言えば控えめ、はっきり言ってしまえばぼんやり。小学二年生の弟も同級生の子たちと比べればそちらのタイプに見えるが、姉の真澄が同じ歳だった頃よりもずっとエネルギッシュである。まだ庭を走り回っているらしい声がする。
ぼんやりしている、と言われがちだったのは、あまり喋るのが得意ではなかったからだろう。八歳離れた弟が生まれるまで、真澄は一人っ子だったのだ。周りの友だちのように兄弟や姉妹と活発に喋り合い、時には晩ご飯の唐揚げやデザートのプリンを巡って喧嘩をしたり、日曜日の行楽地お出かけおねだりに向けて仲良く作戦会議をしたり、同じ年頃の誰かと家でも日々何気なく言葉をぽんぽん交わし合って喋る経験数が少なかったのだ。そのうえ、両親と祖父母もやさしく穏やかな気性のひとたちで、小さな真澄がうまく言葉にできない気持ちも物事も笑顔で上手に汲み取ってくれていたのだ。それに甘えることを覚えてしまった少女は、ぼんやりレベルがぐんぐん上がってしまった。
その結果、高校生に上がった今も友だちとの交流では、彼女たちがテンポ良く喋るのを真澄は聴いてばかりいる。
祖母は言っていた。「継続は力なり」と。
そういえば、弟の自転車補助輪が取れたのは、転んでも転んでもめげずに弟が毎日練習していたからだ。
真澄の書道も十二年続けることで、文字の呼吸感が身に付いたのだ。現国も古典も、何事も、練習を継続することで覚えていくものなのだろう。ただし、高校は三年間という期間限定のものだ。十二年はさすがにない。留年ダメ。ぜったい。
できることからはじめよう、と真澄は気合いを入れ、まずは苦手意識しかない古典のテキストを読むことにした。
戦国武将も日曜朝に暗躍する悪の組織のえらいひともいつも言っている。「まずは敵を知り、己を知ることから始めよ」と。
それから三門市の平和を護ってくれるヒーローでお馴染みのスポーツが趣味? らしい嵐山ナントカさん? も今朝のローカル散歩番組で言っていた。
――疲れて散歩が気乗りしないときも、ひとまず運動着に着替えるんです。それからいつも走る場所まで行ってみる。すると、コロ――はい、愛犬なんです。え、写真は必要ない? そうですか可愛いのに…………コロが自分よりも先に元気に走り出してくれるので、自分もいつも通り走れるんです――
いつもと同じように準備を整えることで、気持ちも落ち着いていつも同様練習ができる、というのは真澄にも経験がある。書道だ。体育の授業が運動会やマラソン大会に向けた練習で疲れ果てた日も、畳の上で正座をし、墨を磨る。すると、いつも通り背筋がしゃきっとするのだ。
嵐山ナントカさん? は、同じクラスの歌川と菊地原も所属している街の防衛組織「ボーダー」の先輩なのだという。同じ高校一年生で学校の勉強だけでも忙しいはずなのに、いつも歌川はベリーベリーベリージェントルソウルを忘れずに周囲にやさしく声をかけてくれる。その友人の菊地原も動かざること山の如しな落ち着きで真澄やクラスメイトの話に鋭く賢いコメントをくれる。すごくすごい二人の先輩なのだ。当然この嵐山ナントカさん? のアドバイスはすごく効果がありそうだ。ついでにご利益もありそうだ。なんだかテレビの液晶画面もやけにきらきらしていた。
歌川と菊地原によると、二人の所属部隊をまとめる隊長風間なんとかさん? をはじめ、「ボーダー」にはそうした尊敬できるひとたちがたくさんいるらしい。類は友を呼ぶと言うが、すごいひとがゴロゴロ集まる組織ということは、それを創設した大人もきっと、すごくすごくものすごくすごいひとたちであふれているのだろう。更に市外からも、県外からもすごいひとたちが隊員として街の平和を護りに来てくれているのだと、朝の情報番組でも紹介していた。つまり、三門市にはすごいひとが大集合しているということになる。すごいひと選手権が開かれるかもしれない。そうしたすごいひとたちが身体を張って街の平和を護ってくれるのに恥ずかしくない市民で在りたいな、と真澄はますます気合いを入れて座り直した。
国語をがんばると決意したものの、一方で、一年生の今からつまずきかけていて、どうしたものか頭を抱えてしまう自分もいる。
風が、吹いた。からりとした爽やかな風は、レースのカーテンをそよがせ、古典の教科書を捲っていく。ぱらぱらと。五月の明るい陽光が差し、真澄を、机を明るく照らす。
風に捲られて開かれたページに真澄は目をとめた。
『伊勢物語』だ。
中学の古典でも教わったし、高等部内部入試対策の問題集でもよく登場した歌物語だ。
本文の後ろに書かれた解説冒頭文に懐かしさを覚え、「高校でもよろしくお願いします」という気持ちになる。
国語便覧の伊勢物語掲載部分を開いてみる。主人公の在原業平を描いた絵巻の写真が掲載されている。今でも充分綺麗でカラフルに見えるが、現代に残るそれは当時のものよりも少々色褪せているものらしい。描かれた当時は、きっと、おそらく、たぶん、もっと、きらきらぴかぴかしていて、手に取って読むたびに目も心も時間も奪われるうつくしい絵巻だったのだろう。
少女は、ぱちぱちとまばたきをした。
――そういえばこの在原業平ってひと、すごいなあ。
色々な女性と恋をしたという平安朝のプレイボーイの武勇伝は、こうして現代にも伝わる歌物語として、古典の教材として、中学と高校の試験問題にも気軽に顔を出してくれるくらい人々にとって親しみある歌物語として残っているのだ。数々の浮き名を流した平安朝のイタリア男は言葉の魔術師でコミュ強であった……というようなことを中学の国語でも学習した。彼は物語が最高潮に盛り上がるクライマックスシーンで毎回、「ここで一首」と歌を詠むのだ。
国語便覧の付録には、在原業平が詠んだという和歌一覧が載っていた。一覧には歌の解説だけでなく、彼がそれを詠んだシーンについても簡単に紹介されている。
「すごい……」
思わず真澄は声をあげた。
この在原業平は、すごい。毎回胸に湧き起こった気持ちを的確に素早く歌にしている。
目も口もぽかんと開いてしまった。
和歌は五・七・五・七・七の合計三十一文字に納める芸術だ。真澄は書道教室でも書道部でも昔の有名な歌人の残したものを墨で書くことがある。よりよい書にするべく、解説も歌にも込められた想いを知りたい、と師範の祖母と部活顧問に説明してもらったり、調べ学習したりしたこともある。
在原業平は、毎回きっちり三十一文字に納めている。そのうえ毎度しっかり気持ちを的確に歌にしてから贈っているのだ。そのとき湧き出た気持ちの正体を、理解しているのだ。それを表す言葉も知っているのだ。
引き出しを、静かに開ける。きらきらぴかぴかした菫色のクッキー缶が目に入る。
そこにこの春大切に仕舞ったのは、模擬試験時間割メモと自分史上最低記録を樹立した漢字テスト答案用紙だ。
どちらも歌川の右肩上がりの字が入ったものだ。
あのときもらった歌川のやさしいエール。さっと右隣からそれが届けられたあのとき、真澄はすごくすごく、ものすごく救われたのだ。暗い夜道を心細く歩いていたところに明かりを貸してもらえたくらい嬉しかった。手を差し伸べてもらえた、と思ったのだ。ほっとしたのだ。けれど、真澄にとってすごくすごくすごく親切だった歌川の思いやりは、ベリージェントルソウルをお持ちの歌川にとっては、然も有りなん、ごくごく当たり前にアサメシマエ? にできることなのだ。
「歌川くんはいつもすごいなあ。歌川くんみたいなすてきなひとに、わたしもなりたいな……なれるかな……」
歌川がベリージェントルソウルを見せてくれるたび、それを思い出すたび、真澄はきらきらした石を見つけたときのようになんだかどきどきしたし、その向けられたやさしさに恥ずかしくない自分で在りたい、と背筋がいつもしゃきっとした。
この気持ちは何だろう?
物知り博士の菊地原のように国語が得意だったならば、在原業平のように真澄がもっと言葉を知っていたら、ものの情趣を理解していたら、ぴったりの言葉で表現することができるのだろうか。
丁寧に机の引き出しを閉め直し、しゃんと姿勢を正した。
言葉にしたい。
言葉にできたらこの気持ちの正体がわかるかもしれない。
とはいえ、真澄は喋るのが得意ではない。友人と話すときだって、家族と話すときだって、相手のサーブをのろのろ受け止めて打ち返すことばかりしている。この平安朝のイタリア男よろしく朝飯前の如く、呼吸するのにも等しいリズムでここぞという歌を咄嗟に詠めるはずもない。四歳の頃から祖母の書道教室に通っていたから書写は得意だという自信はあるが、国語も作文も好成績というわけではなかった。夏休みの読書感想文や遠足と運動会などの学校行事の作文課題も毎回提出期限ギリギリまで四苦八苦していた。
先週始まった小論文のトレーニングだってそうだ。開幕戦から放課後に居残りとなってしまった。クラスメイトのほとんどが時間内に提出を済ませていて、居残り組の少なさにがっくりとしていたら、右隣からエールがあった。
「がんばれ」
歌川が励ましてくれた。
そのあたたかい応援にこたえたいと心を燃やして提出の運びとなったのであった。へとへとになって職員室まで提出に向かったが、「よくがんばりました」「宇田川さんの字は丁寧で綺麗でとても読みやすくて、いつまでも読みたくなるね」と国語教諭に花丸の笑顔をもらい、その場で赤ペンを入れられた漢字間違いの恥ずかしさも疲れも吹き飛んだ。
即興で話をするのは得意ではない。決められた時間内に文章として出力するのももっと苦手だ。
ぱらぱらと開いていた国語便覧の付録に真澄は息を呑んだ。
「あ……」
そこには、手紙の書き方が掲載されていた。拝啓。敬具。前略。前文。主文。末文。後付。どれも三年前、中等部入学試験対策で勉強したことがある手紙の基本だ。
黒ヤギさんは手紙を読まずに食べたが、白ヤギさんは黒ヤギさんに伝えたいことがあり、手紙を書いていたのだ。じっくりと伝えたい想いを言葉で書き表していたのかもしれない。
言葉を使うことでその想いを述べるのは、歌や論文、小説に限ったことではないのだ。手紙という方法もあるのだ。
――そうだ、手紙にするのはどうだろう。
自主的に取り組む手紙ならば字数制限もないし、提出期限もない。じっくりと何かに取り組むのには、書道でよく慣れている。手紙ならば言葉にできるかもしれない。そのためには現国と古典の苦手も克服せねばなるまい。ボーダーの嵐山ナントカさん? も言っていたのだ。
まずは準備をしてみることから始めよう、と。
真澄は、現国と古典を課題が出たときだけでなく、授業があった日にまずその部分の教科書とノートを読み直すことから取り組もうと決意した。それから、言葉を知るには読書が一番だろう。幸い、図書委員になってから当番のために図書室に行く習慣がある。次の当番登板では何か本を借りてみよう、と壁に掛けたカレンダーに真澄は口元を緩めた。
そして、赤ペンが大きく入れられた返却ほやほやの古典答案用紙と、ノート、教科書と向き合うことにした。
「真澄が休み時間に読書してるだなんて!」
「昼休みと言えば、窓際でのびのびぬくぬく光合成ばかりしている真澄が!」
「明日は雨?」
友人の市川あゆみと北見
昼食後、春の陽射しに包まれる窓際で膝を丸めるのは真澄の趣味のひとつだが、そんなに驚くことだろうか。異議を申し立てねばなるまい、と真澄は四つ葉のクローバーが押し花として咲いているぴかぴかの真新しい栞を挟み直した。
読書に目覚めたきっかけは、歌川に対するきらきらした気持ちを言葉にして正体を掴みたい。ただそれだけなのだ。真澄自身よくわかっていない、この名前のない気持ちをそのまま打ち明けて、気のいい友人をこまらせるのもなんだかよろしくない気がする。
さてどうしたものか。
いつものように次の一手を選び取れずに視線を泳がせると、渦中のひと・歌川の背中が見えた。
丹波に出雲といふ所あり。
飾り気のない書体だが、誰の目から見ても誠実さを窺わせる、丁寧でどこかやわらかい文字がゆっくりと綴られていく。
五時限目は古典の授業である。今日は課題に出された教科書の古文を現代語訳することになっているのだ。担当教諭に当てられた歌川が該当箇所を黒板に書いてくれているのだ。
歌川の背中に浮いたシャツの皺。広いのにどこか硬そうにも見える背中なのに、そこに走る皺はなんだかやわらかそうだ。歌川の背中は、真澄の父と同じかそれ以上に広く見えた。まだ小学生の弟もあれほど大きくなるのだろうか。
「真澄。ねえ、真澄?」
「おーい、真澄? 真澄氏? 真澄さーん。どうしたの? ぼんやりして」
「もしもし。もしもーし。さてはおぬし、慣れない読書で知恵熱が出たな?」
ひらひら。茉椰が怪訝そうな顔つきで手のひらを振っている。あゆみも思案顔で顎をさすっている。
「ちえねつ……」
胸に湧いた気持ちをその場で三十一文字の歌にする技。それは、一長一短でできるものではない。教養や知恵が身に付いていなければ、培ったそれらを存分に磨き上げていなければまずできない芸当だ。
数々の女性との浮き名を流したという在原業平は、相手を軽んじることなく、その相手のことをよく知ったうえで、相手がそのとき一番欲しい言葉を惜しまずに贈ったということだろう。会話の達人だけでなく、気配りの名人でもあったのに違いない。
現代にも歌物語として古典の授業にまで語り継がれるほどのコミュニケーション力抜群の平安朝きってのイタリア男・在原業平を目指そうと気持ちを新たに課題も予習も済ませていることを思い出した真澄は胸を張った。
「イタリア男を目指したくて」
二対の瞳がまあるくなった。零れ落ちそうなほど、大きく、まあるく。
「真澄!?」
「真澄! なにゆえチャラ男に!?」
何故だか悲鳴をあげた茉椰とあゆみは、これまたどうしてか真澄の額にそれぞれの手のひらを代わる代わる当て始める。
「熱はないね」
「うん。発言も行動も目標もおかしいけど平熱っぽい。……読書に目覚めてイタリア生まれでイタリア育ちのチャラい男を目指すって此は如何に?」
「さあ……ジャンプで今週からそういう漫画の新連載が始まったんじゃない?」
「ジョジョ?」
「それは昔から続いてるでしょ。ほら、五部だよ五部」
「そう。それ。確かパッションフルーツみたいな名前のマフィアだかギャングだかがド派手に……」
ひそひそと、けれど、隠す気など一切ないのだろう。二人が小声で囁き合う。
真澄が小学生の弟と共同で『週刊少年ジャンプ』を購入して愛読していることを二人はよく知っているのだ。家に遊びに来たときにはそれを読むこともある。 二人がジョジョ談義を徐々に始めたところではっとした。大事な部分を省略して伝えてしまった。在原業平のようなコミュニケーション力と言葉の持つ力を身に付けたい。決意早々に失敗してしまったらしい。イタリア男・在原業平への道は険しい。そういうことだ。 歌川が板書を終えたようだ。端から端まで眺めて、彼が大きくうなずくのが見えた。誤字や脱字がないのか、また、全体のバランスも確認しているようだ。終わるなり、颯爽と前方の戸口から出て行くのが見えた。予鈴が鳴る前に手を洗いに行くのだろう。真澄がそれを見送っているうちに茉椰とあゆみの二人も徐々に奇妙なジョジョ談義も終わらせたようだ。二人は最後にもう一度だけ真澄の額の温度を確かめると、自分の席へと戻った。と言っても、あゆみは真澄の真ん前の席だが。
真澄も本を閉じ、机の中に丁寧に片付けた。ノートを開き、古語辞典と教科書、国語便覧。それからシャープペンと消しゴム、ボールペン、蛍光ペンを机に並べ、姿勢を正す。と――
「宇田川さん」
隣から澄んだ声がした。渦中のひとこと歌川遼である。席替えがまだ実施されていない現在もおとなりさんなのだ。
小テスト採点交換やペア学習でもないのに突如始まった会話イベントに真澄の心臓が騒ぎ始めた。どきどき。ばくばく。どくどく。
なにやら思案げに首を傾げた歌川が静かに言った。
「何か悩んでいることがあるのならば、一人で判断や行動する前に信頼できるご家族や友だち、先生に相談することをおすすめします」
「え、え? うん? ありがとう?」
何故だかわからないが突如歌川から静かにもたらされたアドバイス。声変わりをとうに終えたのだろう低く落ち着いた声音とあたたかな心配りに真澄は胸がいっぱいになった。 特に何かを悩んでいたわけではないのだが、彼に向けられたやさしさが、嬉しい。
胸がいっぱいになった真澄は、予習ばっちりだった古典の授業の解説が耳を素通りしてしまった。
平安朝イタリア男・在原業平への道のりは、遠い。