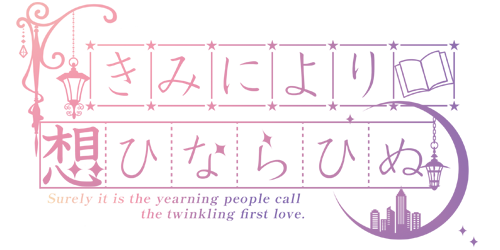「あつい」
何度目かになるそのぼやきに、古典文法の副教材から顔を上げ同意した。こっくりと。
「今日はこの夏で一番気温が高くなるって言ってたものねえ」
「知りたくなかったその情報……」
相手はうんざりした様子で、シャツの襟を摘まんでパタパタさせている。菊地原士郎は顔を不機嫌そうにしかめてこちらを見下ろしてくる。強い。圧が強い。彼はのんびりとしたこちらの相づちに、というよりも、菊地原ほど暑さに参っていない宇田川真澄の様子にご機嫌が斜めに傾いているらしい。
尻尾のように首の後ろに結わえた揺れる少し長いさらさらストレートヘアも、猫のように丸い瞳も、身体のパーツひとつひとつが淡い色彩で構成されている菊地原は、肌の色もどこか白い。俗に言う白皙だ。日焼けするよりは赤くなるタイプの肌なのだろう。「休み時間にドッジボールに興じるタイプではない」と言っていたことがあるし、夏の暑さは本当に苦手なのかもしれない。
「参るよなあ。この頃ずっと晴れ続きだし、しかも晴れてるのに蒸し暑いし……」
「今日あたりに梅雨明けするかもしれない、って嵐山ナントカ? さんが天気予報で今朝元気いっぱいに言ってたよ」
「はあ? 困るんだけど。ほんっと知りたくなかったその情報。嵐山さんが言うと本当にそうなりそうだし。困るんだよなあ。明日、防衛任務なんだけど……別に行きたくないわけじゃないけどさあ」
「そうなんだ」
ぼそぼそ呟いてくるが、菊地原はその歳の男の子にしてはどこか冷静であるというか、落ち着きがあるというか、気持ちの切り替えが上手な少年だ。その落ち着きぶりは、動かざること山の如し、だ。言葉にすることで、声に出すことでより速く気持ちの整理をしているのだろう。
「そうだ。宇田川」
じ、と菊地原が色素の薄い瞳を真澄に向けてきた。
「ちょっと、なに? なんで古典のノートなんて広げてるのさ」
「は、はい」
思わず座り直す真澄である。
「勉強なんてしてないで、もっと読書に励みなよ」
「ええ……?」
真澄はぱちぱちとまばたきをした。お母さんとは正反対のことを言う、注文が多い図書委員会同僚である。
復讐は何も生まない。という話ではなく、予習復習を邪魔してライバルを成績レースから蹴落としたい、というわけでもない。菊地原は雨乞いをしているのだ。
本好きが高じて図書委員になったわけではなく、くじ引きで公平に図書委員会所属となった真澄には、もともと読書の習慣はない。自分から喋るのも、作文も読書感想文も小論文も、漢字テストも古語小テストもどちらかといえば得意ではない。そんな真澄が、五月の中間考査後から読書を始めたのだ。中等部で慣れ親しんだ国語と道徳の教科書が何故か図書室書棚に並んでいたので、それを順番に朝読書してみることからスタートした。今は安房直子の本を読んでいる。前回の図書当番時にカウンターに返却されたものだ。真っ青な桔梗畑とそこで出会う子ギツネが作ってくれる不思議な窓のおはなしは、小学生の頃に読んだことがあるので懐かしい。
少し早めに登校して教室で本を読む真澄に、菊地原も含め、真澄の友人はぎょっとした。
「真澄が読書だなんて雨でも降るんじゃない?」と中等部からの友人・北見茉椰が言えば、高等部で初めて話すようになり、仲良くなった市川あゆみも菊地原士郎も「そうだそうだ」とうなずいた。これには真澄も抗議の声をあげたが、その日の放課後、天気予報が大いに外れて雨が降った。それ以来、〝雨を呼びし者〟〝読書で雨を降らせる能力者〟などという格好良いのに不名誉な二つ名を賜ってしまった。
それからの図書当番、真澄がカウンター席で本を広げれば、菊地原は「〝雨を呼びし者〟じゃん。調子はどう?」とか、「困るんだよね、明日防衛任務なんだから。行き帰りに濡れたくないから今日は読書中止してくれない?」などと挨拶してくれるようになった。 鋭い言葉にクールな口調ではあるが、そういう声をかけてくるときの菊地原は猫のような吊り目も平時は静かに結ばれている口角も面白そうにふんわり上がっているので、真澄も「ありがとうミスター菊地原。自分、もっとやれます! 読書がんばります!」と返した。随分仲良くなれたなあ、としみじみ思いながら。
あんなにも「珍しいことをして雨を降らせるな」などと注文していた菊地原が、今はこんなにも〝読書で雨を降らせる能力者〟のチカラに頼ろうとしている。感慨深いものを覚えた真澄は鞄をごそごそと改めた。
「歌川くんって暑さに強いのかな?」
「……はあ?」
菊地原が気怠げに返事をした。さらりと色素の薄い髪が揺れ、耳が見えた。いつもは肩に下ろしている髪を、うなじのあたりで結んでいる。彼もまた真澄と同様に夏の暑さに参っている生き物のようだ。
「期末考査の最後の日」
真澄はリュックサックから目当ての下敷きを見つけ、ちゃ、と掲げた。
「はあ」
菊地原は返事ともため息ともわからない声をあげる。
期末考査最終日。梅雨入りしているはずなのにその日は朝から、カンカン、じりじり、じわじわ、と太陽が強く地上に照りつけていて、登校するだけで真澄は体力も気持ちもごっそり削られていた。
最終日一時限目は日本史だった。早くから登校しているクラスメイト同様、帝国主義の特徴と東アジアへの波及を自分も最終確認しなければならない。けれども、あわてんぼうな夏の太陽の暑さを浴びたからか、頭がぼんやりしてうまく働かない。すると、右隣から風が吹いた。
隣の席の歌川遼だ。爽やかに微笑んでいらっしゃる。歌川が下敷きで扇いでくれたのだ。
歌川とは中間考査後に開催された席替えで隣の席から離れてしまった。しかし、定期考査も模擬試験も出席番号順の席で実施されるので、周期的に隣の席同士となるのだ。
歌川だってまだ登校したところで自分も暑いだろうに、真澄に涼風を送ってくれたのだ。ベリーベリーベリーベリージェントルソウルすぎる。善き隣人にもほどがある。夏の暑さにも負けない爽やかさに完敗、いや、乾杯。そういうひとにわたしもなりたい。
真澄は外が暑いのか、自分が熱いのかなにやらよくわからなくなったが、慌てて赤シートを取り出して頭を下げる。けれど、歌川は笑って言ってくれたのだ。
「最終日もがんばろうな」
途端、どくどくどく、と真澄の心臓が大きく音を立て始めた。歌川の風だけでは熱上昇も熱暴走も抑えられなかった真澄は、真ん前の席の友人あゆみに、ぎょっ、とされた。彼女は「え、知恵熱? 徹夜したの?」とすらりとした指で何度も真澄の額の体温を確かめ、ものすごく心配してくれた。右隣の歌川からも「つらいときは無理せずに保健室に行こう」と親切心にあふれた助言を授かった。体感温度がますますアップした。
真澄はあんなにも暑いような熱いような、謎の熱暴走に弱ったというのに、歌川の様子は平時と変わらず落ち着いていた。
真澄よりも身長が高く、より太陽に近い位置から照らされているはずなのに額に汗は浮かんでいない。むしろ顔に浮かんでいるのは穏やかな笑みだ。短く切られた髪は、いつも通り清潔感があって爽やかだ。ベリーベリーベリーベリージェントルソウルだけでなく、良い冷却システムもお持ちしているのかもしれない。
期末考査での一幕を伝えると、菊地原のクールを通り越した声が耳に届いた。いいご身分だね、と。
ぱちぱち。真澄がまばたきを返す。
こちらの反応が予想通りではなかったからか、菊地原が鼻を鳴らした。そのまま彼は、怠そうにずるずると背もたれに寄りかかった。わからずに声も出せなかっただけなのだが、菊地原は雨にも負けず風にも負けずいつも律儀でいいひとである。夏の暑さには負けているようだが。
「扇いでもらったんだ。歌川に。苦しゅうないって。まったくいいご身分だね、宇田川は」
今日のありがたいお言葉をもう一度わかりやすく丁寧に包み直してお見舞いするなり、彼は机に突っ伏してしまった。どことなく、彼の切れ味が今日は損なわれている。
そういえば、図書室カウンターは設置された冷房から遠い。つまり、やや暑いのだ。
体育を終えて一年C組の教室へ。火照りを抱えたままSHRに臨み、教室から図書当番のために図書室に向かう道のりですっかり身体が茹で上がったらしい。そういえば、男子は外でサッカーだった。女子は体育館でバレーであったが、夏の元気いっぱいの直射日光がない分、暑さはいくらかましだろう。
真澄は下敷きと赤シートを取り出し、お疲れ気味の菊地原に風を送った。二刀流なので風も通常の二倍だ。
「あー……生き返る」
低く唸る声がした。机の表面もほどよく冷たくて気持ちが良いのか、ぺったりと頬も額も付けてしまった。廊下でよく見る夏の風物詩、長毛種にゃんこのようだ。
風を送りながらもう一度確かめるように呟く。歌川くんって暑さに強いのかな、と。
「登校するだけでも暑いのに、教室の涼しさが身体になじむまで待たずにあんなにもやさしい笑顔で周りにエールも風も爽やかさも送れる。やっぱり歌川くん、心頭滅却すれば火もまた涼しマインドをお持ちのような気がする」
「また急に早口になる……心頭滅却って戦国猛将メカじゃないんだからさあ」
緩慢に姿勢を戻した菊地原が大きく息を吐いた。
「歌川は昔から根っからのスポーツ少年というか、身体を動かすのが好きな奴だからさあ、暑さにも慣れてるんでしょ。梅雨入り前まで昼休みにサッカーとかバスケとかしてたじゃん」
真澄が目をぽかんと開ければ、菊地原もまた色素の薄い瞳をまあるくさせた。
「五月の球技大会だって活躍してたじゃん。観てたでしょ。同じクラスなんだから」
ぱかり。口も大きく開いた真澄に、菊地原が半眼になった。
「覚えてない」
「はあ?」
「ま、待って! だって歌川くん、なんだかよくわからないくらいすごくきらきらしてたから! こう、きらきらぴかぴかするエフェクトがとんでもなくかかっていたことまでは覚えてる……!」
前のめりになって両手をひらひら振る真澄に、菊地原が思い切り全身を引いた。
「なにその早口の割にふんわりした形容……」
「なにって、きらきら……?」
ふう、と巨大なため息交じりに「眩しかったってこと?」と返され、真澄はコクコクと首を縦に動かした。さすが物知り博士の菊地原プロだ。言葉にならないあれこれを呆れつつも的確に捉えてくれる。いいひとである。
「まあ、歌川はバスケだけじゃなく、サッカーにも卓球にも引っ張りだこだったよね。クラスで一二を争う運動量エグすぎ戦士だったはずなのに、全然疲れてないのにはちょっと引いたよなあ……」
なんなんだあれ、と零す菊地原に真澄はにこにこしながら右手を挙げた。言ってみろ、と色素の薄い双眸が促してくる。
「現代に舞い降りしスポーツを司る神の御子と言っても過言ではない?」
「過言でしょ」
「そ、そうかな……」
菊地原の冷房の冷風にも負けないクールな声に真澄はすごすごと座り直した。
だって、そう。物知り博士菊地原が言う通り、まぶしかった。いや、まぶしすぎたのだ。新緑を透かす初夏の明るい陽射しを受けてなお、歌川遼はまぶしかった。目がチカチカしてしまったから真澄はきっと球技大会の記憶がそれ以外に残っていないのだろう。そうに違いない。
「……まあ、よかったね」
「え?」
目をぱちくりとさせる真澄に、菊地原の吊り気味の瞳が、ふ、と緩んだ。カウンターに頬杖をつき、じっと真澄を見る。
「現国と古典。成績、上がったんでしょ。中間よりも」
「え? うん? うん! ありがとう菊地原くん……!」
真澄はこくこく、と力いっぱいうなずく。ポニーテールにした髪がぶんぶん揺れた。
菊地原は猫目を細めて、口の両端を吊った。にんまりと。
「春先より爆発的に語彙が増えてるし。さすが読書で〝雨を呼びし者〟のチカラに目覚めただけある……。冷たいにわか雨にぼくらが濡れた甲斐もあったよなあ」
「おとーさん、それはいわないやくそくでしょう……」
朝読書に慣れたからか、国語の予習復習に進んで取り組むようになったからか。はたまたその両方か。期末考査の現国と古典は中間考査よりも成績がアップした。教卓で担当教諭から返された答案用紙には、「よくがんばりましたね」と赤ペンで書かれていて、真澄は思わず、ぴょん、とその場で跳ねてしまった。学年首席を勝ち獲ったわけでも、全国模試で一位に輝いたわけでもない。けれども、どちらの科目にも苦手意識しかなかった真澄にとって、それは金メダルにも負けないくらい嬉しいものだった。
あのときの真澄の喜びを彼もまた祝福してくれている……のだ。たぶん。おそらくは。
と――
「ふっ」
正面で誰かが大きく吹き出した。菊地原の声ではない。彼はまだそこまでの元気を取り戻せていないのだ。今日の図書当番が始まった頃の菊地原はぐにゃぐにゃ溶けてバターになったトラのように伏せていたが、今はまだ背もたれに寄りかかれるほどの元気しか手元に戻っていないはずだ。
今日初めての図書室の客だ。期末考査後の図書室もやはりガラガラ空いているのだ。
真澄は座り直して顔を上げ、息を呑んだ。ひゅ、と。
「ごめん。盗み聞きするつもりはなかったんだ」
歌川遼がすまなそうに眉を下げ、真澄の正面に立っていた。
「二人のやりとりが面白……ごめん、楽しくて」
筋張った大きな手のひらで口元を覆うと、歌川は笑い出した。歌川の微笑みはよく見ている。けれどもそれは、いつも目にする落ち着いた穏やかな笑みとは違って、近しいひとに見せるような幼い表情だった。笑うと、切れ長の眦の角が取れて、きゅう、と丸くなるらしい。
予想外の展開に、口をぱくぱく閉じては開き、左右の手のひらを、ぐ、ぱ。ぐ、ぱ、と結んでは開くことしか、真澄の脳みその処理が追いつかない。ようやっと真澄が弾き出した第一声は――
「歌川くん! いらっしゃいませこんにちは!」
威勢の良いコンビニ店員のような挨拶だった。
「こんにちは」
歌川もいつも通り朗らかに挨拶を返してくれたが、整えられた笑みの端、口角がほのかに震えていた。ひくり、と。
「うわっ、うるさ……」
溶けたバターから固形バターにまで形が戻った菊地原のコメントに真澄は我に返った。
「う、歌川くん、もしかして、菊地原くんになにかご用事かな? ボーダーの、緊急のお仕事とか」
つっかえながらなんとか言い終えた真澄は、「あ」と目を開いた。そして、ざっと血の気が引いた。
彼らが緊急の仕事で呼ばれるということは、街になにかが起きたのかもしれない。弟は学校からまっすぐ家に帰れただろうか。今日は母もパートに出ていて留守にしている。祖母も書道教室に出ている。愛犬が庭にいるとはいえ、家にいるのは弟独りだ。
おろおろと歌川と菊地原に視線をぐるぐる往復させてしまう。
隣で、ふう、と巨大なため息が落ちた。
「……急ぎならぼくにも風間さんから直接連絡入るし。そうじゃないんでしょ? 歌川、なに?」
「なにってひどいな菊地原。図書室なんだから本を借りに来たんじゃないか」
「ふうん」
菊地原は言葉こそよそよそしいが、口調も目つきも静かだ。対する歌川も慣れたように口元を緩めている。二人にとって、いつものやりとりらしい。
「宇田川さん、すまない。びっくりさせたよな。菊地原の言う通り、街では何も起きてないよ。大丈夫」
歌川は少しかがんで真澄の瞳を覗き込むと、安心させるように大きくうなずいた。
「う、ううん……だいじょうぶ」
大丈夫ではない。入学式の日のように歌川は真澄をびっくりさせないよう、かがんで目線を合わせてくれたのだ。大丈夫なのに大丈夫ではない。
「うわ……うるさ! 全然大丈夫じゃないでしょ。そろそろ壊れるんじゃないの」
図書室の冷房で涼しくなってきたからか、冷蔵庫で保存されたバターのように、かなり通常のカクカク鋭い角も戻ってきた菊地原がなにやら言っているようだが、真澄には窓の外の音はよく聞こえなかった。
ばくばく。どきどき。どくどく。どっどっ!
心臓の音がうるさくてそれどころではなかったのだ。
本当は、オウム返しみたいな返答だけでなく、いつも教室で親切にしてくれていること、日夜勉学に励む傍らで街を護ってくれていることに感謝している気持ちを伝えたかった。「ここで一首」などと平安朝のイタリア男・在原業平の如く、三十一文字に感謝を込めて歌をさらさらと流暢に詠めるはずもなく、真澄はおずおずと歌川の様子を窺うことしかできなかった。
ちらりと見えた歌川が抱えた本は、今年から読書に目覚めた真澄が読むものよりも三倍は厚そうだった。けれども、なにやら難しそうなタイトルが書かれた本の表紙とは正反対に、彼の表情はいつも通り穏やかだ。
「え、と……、なんだっけ。ほん。ほんを、かりる? うたがわくんが……」
「急に世界の理も言葉も忘れるし……。歌川だって読むでしょ本くらい。それから宇田川、もういいから早くカード作ってよ、そうこれから歌川のをちゃちゃっと」
突然ライムを刻み始めた菊地原の顔を、真澄は、ぼう、と見上げる。
「言っとくけど、ラップじゃないから。ライム刻むならもっとうまく真面目にやるし……ああもう。そもそもきみたち二人の苗字が似過ぎてややこしいせいなんだからね。どっちが漢字三文字でどっちに濁点足すのか喋ってるとわけわかんなくなる」
菊地原はいたってクールに言った。内容は辛辣だが、声のトーンはいつも通りのツンと澄ました産地直送クール便だ。そして、胡乱な目つきで真澄に紙をひらり、と差し出してきた。まっさらな図書室利用カード申請書だ。
「宇田川。歌川の代わりに書いてよ。歌川の名前」
「エ!」
思い切り声が引きつる真澄に、菊地原は目線も合わせずに言う。
「そっちの方がずっと見やすいから、ぼくの入力仕事がすぐ終わるでしょ。ほら、さっさとしてよね」
「心外だなあ菊地原。もうオレの日本史ノート、貸さないぞ」
歌川が眉を上げた。でも、唇も声も緩んだままだ。
「はあ? 心外も何も事実を言っただけだし。昼休み直後の日本史が眠くなるのは夏の風物詩なんだから惜しまずにこれからもぼくに貸してよね」
「今日も強気にわがままだなあ」
二人の気安いやりとりをバックミュージックに、真澄は息を整えた。深く吸い、深く吐く。繰り返すこと三度。
それから姿勢を正した。もう一度息を吐き、ボールペンを握る。
とめ。はね。はらい。一切の文字に、全霊を、心を込める。
書き終えて、バランスを確認する。それから、ふう、と詰めていた息を深く深く出した。と――
完成した申請書に「すごいな」と感嘆の声があがった。
「代筆ありがとう。やっぱり綺麗だな。宇田川さんの書く字。見ているこっちまで襟を正したくなる」
「う、ううん。こちらこそ、ありがとう……」
深々と歌川にお辞儀をする真澄から、菊地原が申請書を攫ってしまった。入力作業をしてくれるらしい。さらりとした髪は、うなじのあたりで結ばれている。そのせいか、彼の横顔がよく見えた。目も口も何故だかにやにや緩んでいるのもよく見えた。
「でも、宇田川さん、よく間違えなかったな」
菊地原の作業を待つ間、目を輝かせた歌川が話しかけてきた。
真澄は、息を止めた。彼の瞳が、悪戯めいていたのだ。それは、いいことを思いついたときの小学二年生の弟が浮かべる光によく似ていた。
わからずに首を傾げれば、歌川がふっと口元に笑みを浮かべた。
「りょうだよ、りょう」
「りょう……」
ぱちぱちとまばたきを繰り返す真澄に歌川は微笑んだ。
「そう、『遼』の字。よく間違われるんだ。良しの『良』か、なべぶたの『亮』が多いかな。だから、間違われなかったのもめったにないから嬉しいし、宇田川さんの整った字で書いてもらえたのも嬉しいよ。見慣れた自分の名前なのに、額縁に飾られたみたいに立派に見えるな」
「……歌川くんの『遼』は、はるか、遠いを意味する『遼』だよね。心も器もずっと広くて、周りのことを遠くからもよく見てくれていて、いつも手を差し伸べてくれる歌川くんらしい、素敵な字だよね」
ぽろっと、そう言うと、歌川は目を瞠った。それから、そのひとは困ったようにきゅう、と眉を下げ――笑った。
歌川の大人びて落ち着いたいつもの微笑みではなく、少年らしくまぶしい笑みだった。
「ありがとう。漢字までは正しく書いてもらえても、つくりとか、この単語と同じ文字とかいう説明で終わることが大半だし、かといって、自分から意味まで説明するのは恥ずかしいから、なんだか照れるな」
かッ!
途端、全身が燃えるように熱くなった。
反射的に、真澄は立ち上がっていた。がたん、と椅子が音を立てて倒れる。怪訝な目つきで菊地原がこちらを振り返るが、彼はまた申請書と液晶画面の確認作業に戻ってしまった。
「え、と、たしかに自分の口から名前に使われている漢字を説明するのって照れるよね。生まれて初めてもらった贈り物だから、大切にしたいのに」
真澄もそうだ。両親から贈られた名前は大切だし、その名にふさわしいひとになりたいと常々願っているが、自分から「この意味の字ですよろしく」と口にするのはなんだか面はゆいものがあった。
「うん。そうだよな。オレも照れくさいけど、宇田川さんみたいにその気持ち、大事にしたいな。宇田川さんは良い子だなあ」
まるで祖父母が褒めてくれるときのように歌川がやわらかに微笑んだ。
「あまり使われない漢字だからか、間違われずに書いてもらえたのも説明してもらえたのもやっぱり嬉しい。宇田川さん、きちんと書道を嗜んでいるひとだからかな、漢字をよく知ってるんだな」
歌川が真澄に向かって微笑んでいる。朗らかにやわらかに。まっすぐと。
どくどくと耳の内側からも、心臓の音がダイレクトに伝わってきたが、なんとか声も勇気も絞り出す。
「う、ううん。そんなことないよ」
物知り博士ならば、真澄の隣の席で今も黙々と利用者カードの登録確認作業をしてくれている。
自分の名の説明をするのは照れくさい。けれど、自分のものでなければ胸を張って言える。真澄はふにゃりと頬を緩めた。
「弟がね、弟の名前が歌川くんの『遼』と同じ漢字なの」
「そうなんだ。弟さん、名前もそのままオレと同じ遼くん?」
「ううん。うちの遼くんは、司馬遼太郎とおそろいの『遼太』です。一年お兄さんの太郎――うちの柴犬の太郎と二人合わせて初めてそっくりおそろいの『遼太郎』となります」
小学二年生の弟・遼太はまだ小さくて可愛い。クラスでも背の順では前から数えた方が早いらしい。八学年も歳が離れているというのを差し引いても、素直でよく笑い、真澄にも全身で甘えてくれる弟はとても可愛い。弟も同じ字を持つ歌川のように、両親の願いのように、大きくなったら心も器も広くて大きい立派なひとになれるだろうか。
真澄がつっかえながら詰まりながら弟のことを話すのを、歌川はどこかまぶしげに目を細めてくれた。
「……そうか。宇田川さんちもけっこう歳が離れてるんだな」
「うん。いつもその日学校であったことも給食のメニューで何が一番美味しかったのかも全部教えてくれてね、それが一生懸命で可愛いの」
「それは宇田川さんが聞き上手で良いお姉さんだからだよ」
なんでも話したくなる、と微笑む歌川の顔がなんだか直視できず、と目を泳がせた。
「そ、んなこと……! ううん、そうかな。そうだといいな。ありがとう歌川くん」
頼みの菊地原はまだパソコンとにらみ合っている。己にも他者にも確認作業にも厳しい仕事のプロフェッショナルのようだ。情熱大陸にも使われそうないつになく真剣な横顔に背中である。
おろり、と少女は視線を彷徨わせた。少年の笑顔をずっと見ていたいのに、まぶしくて、あまりにもまぶしくて、なんだか見ていられないのだ。
入り口と窓に目線を逃がそうにも、書棚のタイトルを一から数えようと企てようとしてもだめだった。だって、正面に光源があるのだ。歌川がまっすぐ見られないからちょうどよい視線の先を探しているのだ。何もかも歌川越しでないと目にできないものしか思いつかない。期末考査が終わったばかりなのに、終わったばかりだからなのか。図書室を新たに訪れる生徒も、後にしようとする生徒もいない。うろうろ。机と、目下プロフェッショナルに情熱大陸中の菊地原とを往復した真澄の瞳がようやく足下を捉えた。そうだ。倒したままだった。
音を立てないように椅子を持ち上げて位置を正す。震える膝も、指先にも正面で微笑むひとに気づかれませんように。そう祈りながら。
ぎしぎしと鈍い動きで首を真正面に戻した真澄にも歌川は変わらず穏やかな声で話してくれた。気を悪くした様子はない。
「それにしてもその名乗り、遼太くんの、いいなあ。司馬遼太郎とおそろいとは盲点だった。シンプルにわかりやすくて格好良い。オレも今度からそうやって名乗っても良いか?」
歌川の悪戯めいた瞳が、まっすぐと真澄に向けられている。
「あ、ありがとうございます喜んで!」
ふは、と歌川が吹き出した。誰がどう聞いても威勢の良い飲食店アルバイターの挨拶だったのだ。
ベリーベリーベリージェントルソウルをお持ちの歌川は、実は笑い上戸らしい。切れ長の眦の角が取れて、きゅう、と丸くなるそれに、真澄の心臓がまたしても勢いよく早鐘を鳴らし始めた。今日だけで何種類の笑顔がリリースされたのだろう。
「うわっ、すご。……なんか、久々に『風の又三郎』読みたくなったかも」
歌川のカードの作成と貸し出し手続きに全身全霊を注いでいるプロフェッショナルで情熱大陸中の菊地原が何故だか左右両方の耳を押さえ始めた。
安房直子のシリーズを読み終えたら、次は宮沢賢治の作品を読むのも良いかもしれない。真澄が心にそっとメモすると、歌川も目を輝かせた。
「いいな、それ。懐かしい。オレも読んでみようかな」
言うなり、彼は朗らかに笑う。思いがけず、歌川と貸し出し記録がおそろいになるかもしれない未来の予感に、真澄は口元をあわあわさせた。
どっどど どどうど どどうど どどう!
あまいざくろもすっぱいざくろも、世界の理も言葉も、歌川と今日ゆっくりと話せた思い出も、今日だけでいくつも見られたそのひとのまぶしい笑顔も吹き飛ばしてしまいそうな激しいリズムで心臓が鳴り響いていた。
じりじりと太陽が照りつける前の道と、太陽が傾いて橙色に街が染まる頃の道。真澄は毎日の朝と夕方に弟と犬と歩く。
真澄と小学二年生の弟にとって、散歩は夏休みの日課だ。愛犬の散歩は、弟の夏休み課題のひとつだ。「小さなことからでかまいません。毎日つづけられるお手つだいを一つはじめましょう」と夏休みに配布されるワークブックの最初の課題としてカレンダーと共に大きく書かれていたのだ。
弟の成績表と夏休みワークブック、課題案内のプリントを見て、父は長いこと顎をさすっていた。小学二年生一学期の成績や授業態度が悪かったわけではない。弟が得意げに許可してくれたので真澄も中身を知っている。
弟は素直で聞き分けが良い子だ。朝と夕にポストに届いた新聞を取りに行くのも、食事の前にテーブルを拭くのも、家族の皿と箸を並べるのも、自分で食べた皿をシンクの洗い桶にまで運ぶのも毎日していた。更なるお手伝い、そのうえ危なげもなく弟の成長にも繋がるもの――眉を寄せて思案していた父が、あっ、と大きな声をあげた。扇風機にあたっていた真澄は、レモンシャーベットをひっくり返しそうになった。
「いいじゃないか。こういうのでいいんだよこういうので」
輸入雑貨商がひたすら食事するグルメ漫画のような台詞に真澄は首を傾げる。
下に落ちる前にスプーンをキャッチした娘も見ていたのか、父は笑いながら言った。真澄にも宿題を出そうかな、と。
それが、夏休みの日課「朝夕に太郎と散歩に行くこと」の始まりであった。
庭の向日葵と背比べをする遼太と、それを静かに見守る太郎の背中からヒントを得たらしい。太郎は宇田川家の愛犬の名前だ。遼太よりも一年早く生まれた柴犬のお兄さんである。その自覚があるからか、弟よりも落ち着きのある子だ。今も後ろを時折振り返っては遼太を見上げている。遼太がまっすぐ道を歩いているか、確認しているようだ。ちなみに二人合わせると、司馬遼太郎の「遼太郎」とぴったりおそろいだ。
今日も宇田川姉弟は肩を並べて川縁の道を歩く。朝は姉と弟と愛犬の三人きりだが、夕方には書道教室終わりの祖母、仕事帰りの父と母も合流することがある。夕焼けを探しながら歩くのがもうひとつの日課だ。
澄んだ青空が広がっている。朝方には緩く固まっていた雲だったのに、夕方の今は夏祭りの夜店でちぎって食べ合ったときの綿飴に似た大きさで分かれ、空のあちこちに散らばっている。ほんのりと淡い橙色が混じっているのが見えた。
暑さと日々の復習と課題とに気をとられて気づかずにいたが、空はもう秋にさしかかっている。
そういえば、日が暮れてくるのも、道に影が伸びるのも早くなってきた。
橋にさしかかったところで、「あっ」と弟が声を弾ませた。ぱちぱちと真澄が目をまばたいているうちに、弟は太郎と仲良く連れ立って走り出した。
真澄もびっくりしたまま追いかける。先に家を出発した弟を、自転車に乗った兄が追いかける。なんだか数学の課題で何度も見たことがあるシチュエーションだ。残念ながらここに自転車はない。なので、自分で速度を上げるしかない。橋の向こうにいる弟に真澄は息を切らして叫ぶ。
「遼ちゃん!」
弟を抱きしめて目線を合わせたうえで「急に走ったら危ないでしょう」ときちんと伝えねばなるまい。なんとか橋を渡りきり、ゴール直前で腕を伸ばしかけた真澄は、息が止まった。ひゅ、と。
「はい」
返事があったのだ。随分低い声で。上方から。
そこには、同級生がいた。宇田川遼太と太郎の頭を代わる代わる撫で回すそのひとは、はにかみながら顔をこちらに向けてくれた。
「ごめん。オレじゃないってわかってはいるんだ。わかってはいるんだが、びっくりしたよ。宇田川さんが必死に呼ぶから」
教室で見せてくれるのと同じ穏やかな笑顔のまま、そのひとは頬を搔く。
そうだ。このひとの名は、歌川遼だ。このひともまた「遼ちゃん」と呼ばれても不思議ではないのだ。
「こ、んばんは。うたがわくん。ごめんね。びっくりさせてしまって……」
声が上擦ったものの、なんとか挨拶できた自分を、褒めてあげたい。一年C組に五百点。怒って大声で叫んだことも、叫びながら走ったから息切れしていることも、汗が噴き出しているうえに髪が大きくほつれているだろうことも、何もかもが恥ずかしくて顔を上げられない。
「大丈夫だよ宇田川さん」
落ち着いた声が、真澄の耳を震わせる。
「こんばんは」
そのひとは少女の息が整うのも、心臓が落ち着きを取り戻すのも、顔を上げる心の準備が整うのも、そっと待ってくれている。
「あと、ただいま」
はにかむように頬を搔く歌川から目を反らさずに、唇を開く。
「お、おつかれさまです。おかえりなさい」
なんとか出せた。ほっとした真澄の眉が、へにゃんと下がった。「遠征」から帰ってきた彼を労う言葉を直接贈ることができたのもなんだか嬉しい。
「うん。ただいま」
声というものは、実にそのひとのひととなりをよく表していることがわかる。相手の言葉に耳を澄ませようとするひとは、よく通る声を持っていて、表現もやわらかい。そして、歌川もそうした例から漏れず、よく澄んでいて、包み込むようなやさしさとあたたかさも持ち合わせた声をしている。
「ねえねえ遼くん! 聞いて聞いて!」
小学二年生は姉の緊張になどまったく気づかず、歌川の足下に全身で戯れ付いている。きらきらと目を輝かせながら。太郎もふかふかの尻尾を大きく振り、二人の前で足踏みしている。
「こら、遼太。太郎。お姉ちゃんをあまり心配させるなよ」
歌川は少しかがむと、遼太と太郎の目を、じ、と見下ろした。
「う。すーちゃん、ごめんなさい」
上目遣いで真澄をちらちら見上げてくる弟を、真澄はつい甘やかしたくなる。遼太は、言葉を覚え始めたとき、「お姉ちゃん」と覚えるよりも先に、真澄の名前を覚えた。祖父母と両親が名を呼ぶのをよく聞いていたらしい。けれども、うまく発音できなくて、真澄のことを「すーちゃん」と呼び始めた。そして、今もそのまま呼び慕ってくれている。舌足らずで甘えたような声は可愛い。だが、ぐっと我慢した。耐えねばならない。心を鬼にして、きりりと眉を引き締める。その潤んだ瞳にまっすぐ目線を合わせ、真澄は声を出した。
「……急に走ったら危ないでしょう。誰かにぶつかって怪我をさせてしまうかもしれないし誰かの大事なものを壊してしまうかもしれない。それに、遼ちゃんが怪我することだってあるかもしれない。だから、急に走るのは危ないんだよ」
「はい。きをつけます」
「うん。次からがんばろうね」
しおしおと肩を落とす弟は、素直で可愛かった。真澄は頬をふにゃふにゃ緩め、弟のやわらかい髪と小さな頭を右手で撫でる。
「……宇田川さん、そうしてると、ほんとうにお姉ちゃんなんだな」
ぽつり、と落とされた声に、肩が跳ねた。
「遼くんなに言ってるの? すーちゃんはずーっとずーっと、ぼくのお姉ちゃんだよ? レベルだってもうすぐ八に上がるんだから! すごいんだ!」
もうすぐ八歳になる小学二年生が、えへん、と胸を張った。
「そうなんだ。すごいな」
「そうでしょうそうでしょう。この間だって、カブトムシの一番大きくて格好良いの採ってくれたんだ! すーちゃんはすごいんだよ! いいでしょう! もっと褒めてもいいよ!」
にこにこと笑い合う二人がまぶしい。太郎のリードを握る弟の手に力が入る。太郎はといえば、静かに座っている。遼太の足下にどっしりと腰を下ろしている。飛び出し禁止と言っているのだ。おりこうさんである。
歌川に会うのは少しだけ久しぶりだ。
終業式と、夏休み直後の課外授業の学校教室。それから課外授業が終わった翌日にも橋を渡りきったこの場所で会った。
太郎の散歩兼カブトムシ狩りに出かけた日の早朝だ。課外授業で学校に向かっていた日よりも早く弟に起こされた真澄は、うつらうつらしていた。堪えきれずに大きな欠伸をしたところで会ったのだ。爽やかな笑みを浮かべる歌川と。
ぱちん。思わず両手で口を押さえる真澄に、歌川は「おはよう」と声をかけてくれた。
しゃがみ込んで、落としたリードを拾い上げてくれた。夢の中でも彼はベリージェントルソウルをお持ちだ。
「だあれ?」
シャツの裾を後ろに引っ張られる。ぎゅう、とシャツを小さな指で力いっぱいに引っ張ってくる弟と、真澄のスニーカーの上に座り込んだ太郎の重みとあたたかさで、これが夢ではないことに気づいた。口をあわあわさせながら両手でリードを受け取る真澄と、真澄の後ろからそっと顔を出す弟に、歌川は笑いかけてくれた。にっこりと。安心させるようにやわらかく。
「はじめまして。遼太くん。太郎くん。オレは歌川遼と言います。司馬遼太郎の遼太郎とおそろいの遼と書きます」
「うたがわ遼くん? ぼくたちおそろいだね!」
ぱあっと目を輝かせた弟は、一気に歌川に懐いてしまった。「三人合わせたら上から読んでも下から読んでも遼太郎遼だねえ!」と胸を張っている。
「そうだな」
屈託のない小学二年生の笑みにも負けず、歌川がやわらかく笑ってくれている。やはり夢かな。夢かもしれない。ほう、と息をつく真澄である。と――
ちらちら、そわそわ、と歌川がこちらにせわしなく目線を送ってきた。真澄はピンときた。皆まで言わずともわかる。言ってくれるな、と真澄は右手を前に掲げた。
「ごめんね歌川くん。時間をもらってしまって。なにか急いでいるのでしょう? ボーダーのお仕事かな?」
「ごめん宇田川さん! 撫でさせてもらってもいいかな!?」
「エ」
乞われた真澄は今度こそ心臓が壊れたかと思った。どこか緊張した顔つきの歌川が視界いっぱいに広がる。身を乗り出してきたのだ。近い。そして、半ば叫ぶような勢いで放たれた宣言。押し寄せる怒濤の情報に脳みその処理能力が追いつかない。ぎゅう、とリードを握りしめ、震える唇を開いた。
「ど、どうぞ。ひと思いにお願いします!」
「ありがとう!」
ぱああっと目を輝かせた歌川が、その筋張った大きな手のひらをまっすぐ伸ばし――――真澄の真ん前でしゃがみ込んだ。
「よーしよしよし。いい子だねえ。太郎はものすごく、ふわふわふかふかふくふくしてるなあ!」
いつになく、やさしい声だ。歌川は真澄の――宇田川家の愛犬――太郎に握った拳を差し出し、太郎が鼻を近づけて心を開くのを待った。彼の許しを得るなり頭と背を思い切り撫で回す。頬も眉も眦も大きく緩ませ、とろけきったような顔つきで、ふわふわふさふさもふもふした黄金色の被毛を広い手のひらでわしわしと撫で、太郎に話しかけている。
「…………」
まだ夏のぎらつく太陽は昇りきっていないのに、暑い。そして、熱い。朱く染まった顔を両手で覆い、真澄はしゃがみ込んだ。
「すーちゃん、どうしたの? だいじょうぶ? 麦茶飲む?」
隣にしゃがみ、おずおずと水筒を差し出してくれる弟は、今日もやさしくて可愛い。
ここでまた歌川と顔を合わせることになるとは。嬉しい。だが、すごく恥ずかしい。嬉しくてそわそわするのに恥ずかしい。
あの夏季課外授業翌日の朝と同じく、歌川は太郎に思い切り笑いかけ、遼太と仲良く、代わる代わる太郎の黄金に輝く毛皮をわしゃわしゃ撫で回している。太郎もご満悦といったように気持ちよさそうに口を緩めている。顔はとろけきっていた。
リードを握る指に力が入る。そうでもしないと、あの日の盛大な勘違いの思い出で胸がいっぱいいっぱいになり、心臓も全身も爆発しそうになるのだ。まさか弟を注意した手前、急に全速力で走り出すわけにも行かず、ぐんぐん上昇していく体感温度に真澄はくらくらする思いがした。
「遼太、背が伸びたんじゃないか?」
「うん! そうだよ。よくわかったねえ。遼くん、すごい!」
前に会ったときと目線の高さが違う、と歌川が遼太の頭を撫でる。
「さすが遼くんお目が高い! 背も高い! でもねえ――」
むん、と胸を張り、遼太が笑った。
「まだまだ大きくなるよ。すーちゃんよりもずっとずーっと大きくなるんだ」
背筋をぴんと伸ばして宣言する弟に、歌川は、ふは、と吹き出した。 「あっ、遼くん! 笑ったな! いいよ、べつに信じてくれなくても。遼くんよりもビッグになっても遼くんのこと撫でてあげないからね!」
上目遣いになる弟に、歌川は笑みを堪えつつ謝った。
「ごめん。格好良いこと言うなあって思ったんだよ」
歌川は遼太と目線を合わせ、小さく言った。どこかまぶしげに、なにかを懐かしむように眦をふわりと緩めながら。
「わかればよろしい」
両腕を組むポーズで鷹揚にうなずく遼太に、歌川は再び吹き出した。乞うご期待だな、と。
屈託なく笑い合う二人を見つめ、真澄は素直に感心した。
一学期に朝読書を始めたことで、夏休みの今でも読書の習慣は続いていたが、まだまだ平安朝のイタリア男・在原業平への道は遠い。まずは小学二年生の弟のコミュニケーション能力に弟子入りするべきかもしれない。
遼太の頭をやさしい手付きで撫でながら、歌川が、ふっとこちらを見上げてきた。
とくとくとく、と心臓が音を立て始めた。
真澄はおろおろとリードを持ち上げては、下ろすことを繰り返した。
挨拶は先ほど交わしたばかりだし、真澄の近況を話そうにもカブトムシ狩りの話を弟が先に披露してしまった。無事に終えた「遠征」というものについて聞くのはタブーだろうな、と真澄は開きかけた口を閉じ、右手で押さえた。「機密は人命より重いのだ。ゆめ忘れるな」と先週の日曜朝、戦隊番組の博士がヒーローに言っていた。
ぐらぐらと頭が茹で上がってきた真澄を、口を開いたものの言葉が出ない真澄を、歌川は急かそうともせず、静かに笑んで待ってくれている。いつでもどこでもベリージェントルソウルを忘れない歌川は、今日もすごくすごくすごい。
「――歌川くんは、いつもすごいね」
三対の瞳が真澄に集中した。
声に出てしまっていたらしい。あっ、と声をあげ、真澄は視線を泳がせた。慌てて太郎の頭に手を伸ばす。あたたかく、やわらかい黄金色に波立った気持ちが凪いでいく。
夏休みの序盤にここで会った歌川は、「これから『遠征』に行くんだ」と言っていた。ボーダーには全国大会があるのだな、と納得をした真澄は、心の底から感心したのだ。すごいなあ、と。
日々の防衛と訓練だけでなく、高校一年生の学校生活を送りながら勉学にも励んでいるのだ。そのうえ、いつもはるか高いところから、遠いところまで気を配り、誰にでもいつもいつだって快く手を差し伸べてくれる。このひとは、草鞋を何足同時に履いているのだろう。立ち上がって、息を整えて、言う。
「歌川くんのこと、いつもひたむきですごいなあって思ってるよ」
こちらをまっすぐ見上げていた歌川は、きゅう、と眦を緩めて、笑った。ありがとう、と。それから笑いを堪えるように筋張った手のひらで口元を覆い、顔をうつむけた。初めてつむじが見えた。いつもはこちらが見上げてばかりなのでなんだか新鮮だ。
「――宇田川さんも守備は上々?」
なんのことかわからず真澄は目を大きくしばたたいた。「読書感想文」と笑みを含んだ声で言われ、両手をぽんと打つ。この間ここで会ったときにも彼は尋ねてくれたのだ。夏休みの課題の進みはどうか、と。
歌川は遠征前に読書感想文を除き、すべて済ませたらしい。所属チームの隊長からのお達しでもあったそうだが、それでもすごい。「遠征」前日まで課外授業で毎日通学していたのに、その合間にも防衛任務があっただろうに、夏休み序盤のうちに済ませるだなんてすごい。すごくすごく本当にすごい。同じチームの菊地原も終わらせていると教えてもらい、二人の伝説に新たな一ページが加わった。すごくべらぼうにブラボーにとてつもなく尋常でなくすごい。
対して、真澄は溜め込んで終盤に泣きながら取り組むタイプでもないが、彼らのように序盤に一気に攻め崩すスピードスタータイプでもない。淡々と毎日少しずつ取り組む派だ。夏休みの終わりにゴールに辿り着けず泣くことはなかったが、読書感想文だけは別だ。毎年うんうん頭を抱えるのが夏の風物詩であった。
だが、今年は違う!
ギュッ! と、眉を自分史上最高に引き締めて、言う。
「無事に終わりました!」
「すごい! よくがんばったな! 宇田川さん、教室でもよく本を読んでるものなあ。レベルアップも当然だよ」
真澄は頬が緩むのを抑えきれない。ベリージェントルソウルをお持ちの歌川からまっすぐと向けられた微笑み。他愛ない会話を覚えてくれていたこと。そして、歌川に直接惜しみない称賛を贈られたこと。何もかもが照れくさく、くすぐったくて。胸のあたりが、じわじわ、ふわふわ、きらきら、どきどきした。
さあ、と風が渡った。真澄のポニーテールが、ふわ、と揺れた。太郎が三角形の耳を立て、心地よさそうに耳を澄ませている。ちりん、とかすかに風鈴の音がした。
綿飴のような雲は、いつの間にか橙色に染まり始めていた。そういえば太陽が山の端に沈みきるまでの時間も、夏休みの始めの頃よりもぐっと短くなった。
山の端に太陽が傾き、橋と丘の向こうでは家々の灯りがともるのが見えた。
「歌川くん」
「うん」
夏の果ての風に、歌川の短く切り揃えられた髪もそよそよ揺れている。
「あのね、わたし……」
唇を開いては閉じ、閉じては開くことを繰り返す真澄を、歌川は待ってくれている。
「わたし、いつもこの道を散歩するたびに思うんだ」
「うん」
喋るのが得意ではない真澄にとって、自分から話を始めるのは覚悟が必要なことだ。けれど、今、この瞬間、歌川は真澄の隣で同じ景色を見ている。夏の終わりの夕焼けに染まるこの街を共に見てくれているそのひとに、真澄にはどうしても伝えたいことがあった。
「あの……」
「うん」
真澄のつたないお喋りが始まるのを、そのひとは待ってくれた。そのひとは静かに相づちを打って耳を傾けてくれている。
「ボーダーのひとたちがこの町を護ってくれているから遼太も太郎もわたしも、ううん、街の皆も。皆が安心しながらこうして散歩できるんだなって。ここで街の灯を見るたびに思ってる」
だから、と真澄は言葉を切った。息を吸い――言う。
「いつもありがとう。街を護ってくれて」
頬が、ほころんだ。なんとか言えたのにほっとしたのだ。それを一番に伝えたい歌川に、同じ夏の灯を隣で見ながら言えたのも嬉しい。嬉しくて、たまらなかった。
「……宇田川さんは、いつもまっすぐ言葉をくれるね」
その日最後の太陽の光を受け止めた歌川の瞳はまぶしかった。落ち着いたトーンの瞳をほのかに細めて、そのひとは笑う。なんだかまっすぐ見ていられなくて、少女は耳に髪をかけ直しては下ろし、耳から下ろしてはかけ直した。
正面から吹く秋の気配が混じる風に、そっと目を伏せた。
何度目かになるそのぼやきに、古典文法の副教材から顔を上げ同意した。こっくりと。
「今日はこの夏で一番気温が高くなるって言ってたものねえ」
「知りたくなかったその情報……」
相手はうんざりした様子で、シャツの襟を摘まんでパタパタさせている。菊地原士郎は顔を不機嫌そうにしかめてこちらを見下ろしてくる。強い。圧が強い。彼はのんびりとしたこちらの相づちに、というよりも、菊地原ほど暑さに参っていない宇田川真澄の様子にご機嫌が斜めに傾いているらしい。
尻尾のように首の後ろに結わえた揺れる少し長いさらさらストレートヘアも、猫のように丸い瞳も、身体のパーツひとつひとつが淡い色彩で構成されている菊地原は、肌の色もどこか白い。俗に言う白皙だ。日焼けするよりは赤くなるタイプの肌なのだろう。「休み時間にドッジボールに興じるタイプではない」と言っていたことがあるし、夏の暑さは本当に苦手なのかもしれない。
「参るよなあ。この頃ずっと晴れ続きだし、しかも晴れてるのに蒸し暑いし……」
「今日あたりに梅雨明けするかもしれない、って嵐山ナントカ? さんが天気予報で今朝元気いっぱいに言ってたよ」
「はあ? 困るんだけど。ほんっと知りたくなかったその情報。嵐山さんが言うと本当にそうなりそうだし。困るんだよなあ。明日、防衛任務なんだけど……別に行きたくないわけじゃないけどさあ」
「そうなんだ」
ぼそぼそ呟いてくるが、菊地原はその歳の男の子にしてはどこか冷静であるというか、落ち着きがあるというか、気持ちの切り替えが上手な少年だ。その落ち着きぶりは、動かざること山の如し、だ。言葉にすることで、声に出すことでより速く気持ちの整理をしているのだろう。
「そうだ。宇田川」
じ、と菊地原が色素の薄い瞳を真澄に向けてきた。
「ちょっと、なに? なんで古典のノートなんて広げてるのさ」
「は、はい」
思わず座り直す真澄である。
「勉強なんてしてないで、もっと読書に励みなよ」
「ええ……?」
真澄はぱちぱちとまばたきをした。お母さんとは正反対のことを言う、注文が多い図書委員会同僚である。
復讐は何も生まない。という話ではなく、予習復習を邪魔してライバルを成績レースから蹴落としたい、というわけでもない。菊地原は雨乞いをしているのだ。
本好きが高じて図書委員になったわけではなく、くじ引きで公平に図書委員会所属となった真澄には、もともと読書の習慣はない。自分から喋るのも、作文も読書感想文も小論文も、漢字テストも古語小テストもどちらかといえば得意ではない。そんな真澄が、五月の中間考査後から読書を始めたのだ。中等部で慣れ親しんだ国語と道徳の教科書が何故か図書室書棚に並んでいたので、それを順番に朝読書してみることからスタートした。今は安房直子の本を読んでいる。前回の図書当番時にカウンターに返却されたものだ。真っ青な桔梗畑とそこで出会う子ギツネが作ってくれる不思議な窓のおはなしは、小学生の頃に読んだことがあるので懐かしい。
少し早めに登校して教室で本を読む真澄に、菊地原も含め、真澄の友人はぎょっとした。
「真澄が読書だなんて雨でも降るんじゃない?」と中等部からの友人・北見茉椰が言えば、高等部で初めて話すようになり、仲良くなった市川あゆみも菊地原士郎も「そうだそうだ」とうなずいた。これには真澄も抗議の声をあげたが、その日の放課後、天気予報が大いに外れて雨が降った。それ以来、〝雨を呼びし者〟〝読書で雨を降らせる能力者〟などという格好良いのに不名誉な二つ名を賜ってしまった。
それからの図書当番、真澄がカウンター席で本を広げれば、菊地原は「〝雨を呼びし者〟じゃん。調子はどう?」とか、「困るんだよね、明日防衛任務なんだから。行き帰りに濡れたくないから今日は読書中止してくれない?」などと挨拶してくれるようになった。 鋭い言葉にクールな口調ではあるが、そういう声をかけてくるときの菊地原は猫のような吊り目も平時は静かに結ばれている口角も面白そうにふんわり上がっているので、真澄も「ありがとうミスター菊地原。自分、もっとやれます! 読書がんばります!」と返した。随分仲良くなれたなあ、としみじみ思いながら。
あんなにも「珍しいことをして雨を降らせるな」などと注文していた菊地原が、今はこんなにも〝読書で雨を降らせる能力者〟のチカラに頼ろうとしている。感慨深いものを覚えた真澄は鞄をごそごそと改めた。
「歌川くんって暑さに強いのかな?」
「……はあ?」
菊地原が気怠げに返事をした。さらりと色素の薄い髪が揺れ、耳が見えた。いつもは肩に下ろしている髪を、うなじのあたりで結んでいる。彼もまた真澄と同様に夏の暑さに参っている生き物のようだ。
「期末考査の最後の日」
真澄はリュックサックから目当ての下敷きを見つけ、ちゃ、と掲げた。
「はあ」
菊地原は返事ともため息ともわからない声をあげる。
期末考査最終日。梅雨入りしているはずなのにその日は朝から、カンカン、じりじり、じわじわ、と太陽が強く地上に照りつけていて、登校するだけで真澄は体力も気持ちもごっそり削られていた。
最終日一時限目は日本史だった。早くから登校しているクラスメイト同様、帝国主義の特徴と東アジアへの波及を自分も最終確認しなければならない。けれども、あわてんぼうな夏の太陽の暑さを浴びたからか、頭がぼんやりしてうまく働かない。すると、右隣から風が吹いた。
隣の席の歌川遼だ。爽やかに微笑んでいらっしゃる。歌川が下敷きで扇いでくれたのだ。
歌川とは中間考査後に開催された席替えで隣の席から離れてしまった。しかし、定期考査も模擬試験も出席番号順の席で実施されるので、周期的に隣の席同士となるのだ。
歌川だってまだ登校したところで自分も暑いだろうに、真澄に涼風を送ってくれたのだ。ベリーベリーベリーベリージェントルソウルすぎる。善き隣人にもほどがある。夏の暑さにも負けない爽やかさに完敗、いや、乾杯。そういうひとにわたしもなりたい。
真澄は外が暑いのか、自分が熱いのかなにやらよくわからなくなったが、慌てて赤シートを取り出して頭を下げる。けれど、歌川は笑って言ってくれたのだ。
「最終日もがんばろうな」
途端、どくどくどく、と真澄の心臓が大きく音を立て始めた。歌川の風だけでは熱上昇も熱暴走も抑えられなかった真澄は、真ん前の席の友人あゆみに、ぎょっ、とされた。彼女は「え、知恵熱? 徹夜したの?」とすらりとした指で何度も真澄の額の体温を確かめ、ものすごく心配してくれた。右隣の歌川からも「つらいときは無理せずに保健室に行こう」と親切心にあふれた助言を授かった。体感温度がますますアップした。
真澄はあんなにも暑いような熱いような、謎の熱暴走に弱ったというのに、歌川の様子は平時と変わらず落ち着いていた。
真澄よりも身長が高く、より太陽に近い位置から照らされているはずなのに額に汗は浮かんでいない。むしろ顔に浮かんでいるのは穏やかな笑みだ。短く切られた髪は、いつも通り清潔感があって爽やかだ。ベリーベリーベリーベリージェントルソウルだけでなく、良い冷却システムもお持ちしているのかもしれない。
期末考査での一幕を伝えると、菊地原のクールを通り越した声が耳に届いた。いいご身分だね、と。
ぱちぱち。真澄がまばたきを返す。
こちらの反応が予想通りではなかったからか、菊地原が鼻を鳴らした。そのまま彼は、怠そうにずるずると背もたれに寄りかかった。わからずに声も出せなかっただけなのだが、菊地原は雨にも負けず風にも負けずいつも律儀でいいひとである。夏の暑さには負けているようだが。
「扇いでもらったんだ。歌川に。苦しゅうないって。まったくいいご身分だね、宇田川は」
今日のありがたいお言葉をもう一度わかりやすく丁寧に包み直してお見舞いするなり、彼は机に突っ伏してしまった。どことなく、彼の切れ味が今日は損なわれている。
そういえば、図書室カウンターは設置された冷房から遠い。つまり、やや暑いのだ。
体育を終えて一年C組の教室へ。火照りを抱えたままSHRに臨み、教室から図書当番のために図書室に向かう道のりですっかり身体が茹で上がったらしい。そういえば、男子は外でサッカーだった。女子は体育館でバレーであったが、夏の元気いっぱいの直射日光がない分、暑さはいくらかましだろう。
真澄は下敷きと赤シートを取り出し、お疲れ気味の菊地原に風を送った。二刀流なので風も通常の二倍だ。
「あー……生き返る」
低く唸る声がした。机の表面もほどよく冷たくて気持ちが良いのか、ぺったりと頬も額も付けてしまった。廊下でよく見る夏の風物詩、長毛種にゃんこのようだ。
風を送りながらもう一度確かめるように呟く。歌川くんって暑さに強いのかな、と。
「登校するだけでも暑いのに、教室の涼しさが身体になじむまで待たずにあんなにもやさしい笑顔で周りにエールも風も爽やかさも送れる。やっぱり歌川くん、心頭滅却すれば火もまた涼しマインドをお持ちのような気がする」
「また急に早口になる……心頭滅却って戦国猛将メカじゃないんだからさあ」
緩慢に姿勢を戻した菊地原が大きく息を吐いた。
「歌川は昔から根っからのスポーツ少年というか、身体を動かすのが好きな奴だからさあ、暑さにも慣れてるんでしょ。梅雨入り前まで昼休みにサッカーとかバスケとかしてたじゃん」
真澄が目をぽかんと開ければ、菊地原もまた色素の薄い瞳をまあるくさせた。
「五月の球技大会だって活躍してたじゃん。観てたでしょ。同じクラスなんだから」
ぱかり。口も大きく開いた真澄に、菊地原が半眼になった。
「覚えてない」
「はあ?」
「ま、待って! だって歌川くん、なんだかよくわからないくらいすごくきらきらしてたから! こう、きらきらぴかぴかするエフェクトがとんでもなくかかっていたことまでは覚えてる……!」
前のめりになって両手をひらひら振る真澄に、菊地原が思い切り全身を引いた。
「なにその早口の割にふんわりした形容……」
「なにって、きらきら……?」
ふう、と巨大なため息交じりに「眩しかったってこと?」と返され、真澄はコクコクと首を縦に動かした。さすが物知り博士の菊地原プロだ。言葉にならないあれこれを呆れつつも的確に捉えてくれる。いいひとである。
「まあ、歌川はバスケだけじゃなく、サッカーにも卓球にも引っ張りだこだったよね。クラスで一二を争う運動量エグすぎ戦士だったはずなのに、全然疲れてないのにはちょっと引いたよなあ……」
なんなんだあれ、と零す菊地原に真澄はにこにこしながら右手を挙げた。言ってみろ、と色素の薄い双眸が促してくる。
「現代に舞い降りしスポーツを司る神の御子と言っても過言ではない?」
「過言でしょ」
「そ、そうかな……」
菊地原の冷房の冷風にも負けないクールな声に真澄はすごすごと座り直した。
だって、そう。物知り博士菊地原が言う通り、まぶしかった。いや、まぶしすぎたのだ。新緑を透かす初夏の明るい陽射しを受けてなお、歌川遼はまぶしかった。目がチカチカしてしまったから真澄はきっと球技大会の記憶がそれ以外に残っていないのだろう。そうに違いない。
「……まあ、よかったね」
「え?」
目をぱちくりとさせる真澄に、菊地原の吊り気味の瞳が、ふ、と緩んだ。カウンターに頬杖をつき、じっと真澄を見る。
「現国と古典。成績、上がったんでしょ。中間よりも」
「え? うん? うん! ありがとう菊地原くん……!」
真澄はこくこく、と力いっぱいうなずく。ポニーテールにした髪がぶんぶん揺れた。
菊地原は猫目を細めて、口の両端を吊った。にんまりと。
「春先より爆発的に語彙が増えてるし。さすが読書で〝雨を呼びし者〟のチカラに目覚めただけある……。冷たいにわか雨にぼくらが濡れた甲斐もあったよなあ」
「おとーさん、それはいわないやくそくでしょう……」
朝読書に慣れたからか、国語の予習復習に進んで取り組むようになったからか。はたまたその両方か。期末考査の現国と古典は中間考査よりも成績がアップした。教卓で担当教諭から返された答案用紙には、「よくがんばりましたね」と赤ペンで書かれていて、真澄は思わず、ぴょん、とその場で跳ねてしまった。学年首席を勝ち獲ったわけでも、全国模試で一位に輝いたわけでもない。けれども、どちらの科目にも苦手意識しかなかった真澄にとって、それは金メダルにも負けないくらい嬉しいものだった。
あのときの真澄の喜びを彼もまた祝福してくれている……のだ。たぶん。おそらくは。
と――
「ふっ」
正面で誰かが大きく吹き出した。菊地原の声ではない。彼はまだそこまでの元気を取り戻せていないのだ。今日の図書当番が始まった頃の菊地原はぐにゃぐにゃ溶けてバターになったトラのように伏せていたが、今はまだ背もたれに寄りかかれるほどの元気しか手元に戻っていないはずだ。
今日初めての図書室の客だ。期末考査後の図書室もやはりガラガラ空いているのだ。
真澄は座り直して顔を上げ、息を呑んだ。ひゅ、と。
「ごめん。盗み聞きするつもりはなかったんだ」
歌川遼がすまなそうに眉を下げ、真澄の正面に立っていた。
「二人のやりとりが面白……ごめん、楽しくて」
筋張った大きな手のひらで口元を覆うと、歌川は笑い出した。歌川の微笑みはよく見ている。けれどもそれは、いつも目にする落ち着いた穏やかな笑みとは違って、近しいひとに見せるような幼い表情だった。笑うと、切れ長の眦の角が取れて、きゅう、と丸くなるらしい。
予想外の展開に、口をぱくぱく閉じては開き、左右の手のひらを、ぐ、ぱ。ぐ、ぱ、と結んでは開くことしか、真澄の脳みその処理が追いつかない。ようやっと真澄が弾き出した第一声は――
「歌川くん! いらっしゃいませこんにちは!」
威勢の良いコンビニ店員のような挨拶だった。
「こんにちは」
歌川もいつも通り朗らかに挨拶を返してくれたが、整えられた笑みの端、口角がほのかに震えていた。ひくり、と。
「うわっ、うるさ……」
溶けたバターから固形バターにまで形が戻った菊地原のコメントに真澄は我に返った。
「う、歌川くん、もしかして、菊地原くんになにかご用事かな? ボーダーの、緊急のお仕事とか」
つっかえながらなんとか言い終えた真澄は、「あ」と目を開いた。そして、ざっと血の気が引いた。
彼らが緊急の仕事で呼ばれるということは、街になにかが起きたのかもしれない。弟は学校からまっすぐ家に帰れただろうか。今日は母もパートに出ていて留守にしている。祖母も書道教室に出ている。愛犬が庭にいるとはいえ、家にいるのは弟独りだ。
おろおろと歌川と菊地原に視線をぐるぐる往復させてしまう。
隣で、ふう、と巨大なため息が落ちた。
「……急ぎならぼくにも風間さんから直接連絡入るし。そうじゃないんでしょ? 歌川、なに?」
「なにってひどいな菊地原。図書室なんだから本を借りに来たんじゃないか」
「ふうん」
菊地原は言葉こそよそよそしいが、口調も目つきも静かだ。対する歌川も慣れたように口元を緩めている。二人にとって、いつものやりとりらしい。
「宇田川さん、すまない。びっくりさせたよな。菊地原の言う通り、街では何も起きてないよ。大丈夫」
歌川は少しかがんで真澄の瞳を覗き込むと、安心させるように大きくうなずいた。
「う、ううん……だいじょうぶ」
大丈夫ではない。入学式の日のように歌川は真澄をびっくりさせないよう、かがんで目線を合わせてくれたのだ。大丈夫なのに大丈夫ではない。
「うわ……うるさ! 全然大丈夫じゃないでしょ。そろそろ壊れるんじゃないの」
図書室の冷房で涼しくなってきたからか、冷蔵庫で保存されたバターのように、かなり通常のカクカク鋭い角も戻ってきた菊地原がなにやら言っているようだが、真澄には窓の外の音はよく聞こえなかった。
ばくばく。どきどき。どくどく。どっどっ!
心臓の音がうるさくてそれどころではなかったのだ。
本当は、オウム返しみたいな返答だけでなく、いつも教室で親切にしてくれていること、日夜勉学に励む傍らで街を護ってくれていることに感謝している気持ちを伝えたかった。「ここで一首」などと平安朝のイタリア男・在原業平の如く、三十一文字に感謝を込めて歌をさらさらと流暢に詠めるはずもなく、真澄はおずおずと歌川の様子を窺うことしかできなかった。
ちらりと見えた歌川が抱えた本は、今年から読書に目覚めた真澄が読むものよりも三倍は厚そうだった。けれども、なにやら難しそうなタイトルが書かれた本の表紙とは正反対に、彼の表情はいつも通り穏やかだ。
「え、と……、なんだっけ。ほん。ほんを、かりる? うたがわくんが……」
「急に世界の理も言葉も忘れるし……。歌川だって読むでしょ本くらい。それから宇田川、もういいから早くカード作ってよ、そうこれから歌川のをちゃちゃっと」
突然ライムを刻み始めた菊地原の顔を、真澄は、ぼう、と見上げる。
「言っとくけど、ラップじゃないから。ライム刻むならもっとうまく真面目にやるし……ああもう。そもそもきみたち二人の苗字が似過ぎてややこしいせいなんだからね。どっちが漢字三文字でどっちに濁点足すのか喋ってるとわけわかんなくなる」
菊地原はいたってクールに言った。内容は辛辣だが、声のトーンはいつも通りのツンと澄ました産地直送クール便だ。そして、胡乱な目つきで真澄に紙をひらり、と差し出してきた。まっさらな図書室利用カード申請書だ。
「宇田川。歌川の代わりに書いてよ。歌川の名前」
「エ!」
思い切り声が引きつる真澄に、菊地原は目線も合わせずに言う。
「そっちの方がずっと見やすいから、ぼくの入力仕事がすぐ終わるでしょ。ほら、さっさとしてよね」
「心外だなあ菊地原。もうオレの日本史ノート、貸さないぞ」
歌川が眉を上げた。でも、唇も声も緩んだままだ。
「はあ? 心外も何も事実を言っただけだし。昼休み直後の日本史が眠くなるのは夏の風物詩なんだから惜しまずにこれからもぼくに貸してよね」
「今日も強気にわがままだなあ」
二人の気安いやりとりをバックミュージックに、真澄は息を整えた。深く吸い、深く吐く。繰り返すこと三度。
それから姿勢を正した。もう一度息を吐き、ボールペンを握る。
とめ。はね。はらい。一切の文字に、全霊を、心を込める。
書き終えて、バランスを確認する。それから、ふう、と詰めていた息を深く深く出した。と――
完成した申請書に「すごいな」と感嘆の声があがった。
「代筆ありがとう。やっぱり綺麗だな。宇田川さんの書く字。見ているこっちまで襟を正したくなる」
「う、ううん。こちらこそ、ありがとう……」
深々と歌川にお辞儀をする真澄から、菊地原が申請書を攫ってしまった。入力作業をしてくれるらしい。さらりとした髪は、うなじのあたりで結ばれている。そのせいか、彼の横顔がよく見えた。目も口も何故だかにやにや緩んでいるのもよく見えた。
「でも、宇田川さん、よく間違えなかったな」
菊地原の作業を待つ間、目を輝かせた歌川が話しかけてきた。
真澄は、息を止めた。彼の瞳が、悪戯めいていたのだ。それは、いいことを思いついたときの小学二年生の弟が浮かべる光によく似ていた。
わからずに首を傾げれば、歌川がふっと口元に笑みを浮かべた。
「りょうだよ、りょう」
「りょう……」
ぱちぱちとまばたきを繰り返す真澄に歌川は微笑んだ。
「そう、『遼』の字。よく間違われるんだ。良しの『良』か、なべぶたの『亮』が多いかな。だから、間違われなかったのもめったにないから嬉しいし、宇田川さんの整った字で書いてもらえたのも嬉しいよ。見慣れた自分の名前なのに、額縁に飾られたみたいに立派に見えるな」
「……歌川くんの『遼』は、はるか、遠いを意味する『遼』だよね。心も器もずっと広くて、周りのことを遠くからもよく見てくれていて、いつも手を差し伸べてくれる歌川くんらしい、素敵な字だよね」
ぽろっと、そう言うと、歌川は目を瞠った。それから、そのひとは困ったようにきゅう、と眉を下げ――笑った。
歌川の大人びて落ち着いたいつもの微笑みではなく、少年らしくまぶしい笑みだった。
「ありがとう。漢字までは正しく書いてもらえても、つくりとか、この単語と同じ文字とかいう説明で終わることが大半だし、かといって、自分から意味まで説明するのは恥ずかしいから、なんだか照れるな」
かッ!
途端、全身が燃えるように熱くなった。
反射的に、真澄は立ち上がっていた。がたん、と椅子が音を立てて倒れる。怪訝な目つきで菊地原がこちらを振り返るが、彼はまた申請書と液晶画面の確認作業に戻ってしまった。
「え、と、たしかに自分の口から名前に使われている漢字を説明するのって照れるよね。生まれて初めてもらった贈り物だから、大切にしたいのに」
真澄もそうだ。両親から贈られた名前は大切だし、その名にふさわしいひとになりたいと常々願っているが、自分から「この意味の字ですよろしく」と口にするのはなんだか面はゆいものがあった。
「うん。そうだよな。オレも照れくさいけど、宇田川さんみたいにその気持ち、大事にしたいな。宇田川さんは良い子だなあ」
まるで祖父母が褒めてくれるときのように歌川がやわらかに微笑んだ。
「あまり使われない漢字だからか、間違われずに書いてもらえたのも説明してもらえたのもやっぱり嬉しい。宇田川さん、きちんと書道を嗜んでいるひとだからかな、漢字をよく知ってるんだな」
歌川が真澄に向かって微笑んでいる。朗らかにやわらかに。まっすぐと。
どくどくと耳の内側からも、心臓の音がダイレクトに伝わってきたが、なんとか声も勇気も絞り出す。
「う、ううん。そんなことないよ」
物知り博士ならば、真澄の隣の席で今も黙々と利用者カードの登録確認作業をしてくれている。
自分の名の説明をするのは照れくさい。けれど、自分のものでなければ胸を張って言える。真澄はふにゃりと頬を緩めた。
「弟がね、弟の名前が歌川くんの『遼』と同じ漢字なの」
「そうなんだ。弟さん、名前もそのままオレと同じ遼くん?」
「ううん。うちの遼くんは、司馬遼太郎とおそろいの『遼太』です。一年お兄さんの太郎――うちの柴犬の太郎と二人合わせて初めてそっくりおそろいの『遼太郎』となります」
小学二年生の弟・遼太はまだ小さくて可愛い。クラスでも背の順では前から数えた方が早いらしい。八学年も歳が離れているというのを差し引いても、素直でよく笑い、真澄にも全身で甘えてくれる弟はとても可愛い。弟も同じ字を持つ歌川のように、両親の願いのように、大きくなったら心も器も広くて大きい立派なひとになれるだろうか。
真澄がつっかえながら詰まりながら弟のことを話すのを、歌川はどこかまぶしげに目を細めてくれた。
「……そうか。宇田川さんちもけっこう歳が離れてるんだな」
「うん。いつもその日学校であったことも給食のメニューで何が一番美味しかったのかも全部教えてくれてね、それが一生懸命で可愛いの」
「それは宇田川さんが聞き上手で良いお姉さんだからだよ」
なんでも話したくなる、と微笑む歌川の顔がなんだか直視できず、と目を泳がせた。
「そ、んなこと……! ううん、そうかな。そうだといいな。ありがとう歌川くん」
頼みの菊地原はまだパソコンとにらみ合っている。己にも他者にも確認作業にも厳しい仕事のプロフェッショナルのようだ。情熱大陸にも使われそうないつになく真剣な横顔に背中である。
おろり、と少女は視線を彷徨わせた。少年の笑顔をずっと見ていたいのに、まぶしくて、あまりにもまぶしくて、なんだか見ていられないのだ。
入り口と窓に目線を逃がそうにも、書棚のタイトルを一から数えようと企てようとしてもだめだった。だって、正面に光源があるのだ。歌川がまっすぐ見られないからちょうどよい視線の先を探しているのだ。何もかも歌川越しでないと目にできないものしか思いつかない。期末考査が終わったばかりなのに、終わったばかりだからなのか。図書室を新たに訪れる生徒も、後にしようとする生徒もいない。うろうろ。机と、目下プロフェッショナルに情熱大陸中の菊地原とを往復した真澄の瞳がようやく足下を捉えた。そうだ。倒したままだった。
音を立てないように椅子を持ち上げて位置を正す。震える膝も、指先にも正面で微笑むひとに気づかれませんように。そう祈りながら。
ぎしぎしと鈍い動きで首を真正面に戻した真澄にも歌川は変わらず穏やかな声で話してくれた。気を悪くした様子はない。
「それにしてもその名乗り、遼太くんの、いいなあ。司馬遼太郎とおそろいとは盲点だった。シンプルにわかりやすくて格好良い。オレも今度からそうやって名乗っても良いか?」
歌川の悪戯めいた瞳が、まっすぐと真澄に向けられている。
「あ、ありがとうございます喜んで!」
ふは、と歌川が吹き出した。誰がどう聞いても威勢の良い飲食店アルバイターの挨拶だったのだ。
ベリーベリーベリージェントルソウルをお持ちの歌川は、実は笑い上戸らしい。切れ長の眦の角が取れて、きゅう、と丸くなるそれに、真澄の心臓がまたしても勢いよく早鐘を鳴らし始めた。今日だけで何種類の笑顔がリリースされたのだろう。
「うわっ、すご。……なんか、久々に『風の又三郎』読みたくなったかも」
歌川のカードの作成と貸し出し手続きに全身全霊を注いでいるプロフェッショナルで情熱大陸中の菊地原が何故だか左右両方の耳を押さえ始めた。
安房直子のシリーズを読み終えたら、次は宮沢賢治の作品を読むのも良いかもしれない。真澄が心にそっとメモすると、歌川も目を輝かせた。
「いいな、それ。懐かしい。オレも読んでみようかな」
言うなり、彼は朗らかに笑う。思いがけず、歌川と貸し出し記録がおそろいになるかもしれない未来の予感に、真澄は口元をあわあわさせた。
どっどど どどうど どどうど どどう!
あまいざくろもすっぱいざくろも、世界の理も言葉も、歌川と今日ゆっくりと話せた思い出も、今日だけでいくつも見られたそのひとのまぶしい笑顔も吹き飛ばしてしまいそうな激しいリズムで心臓が鳴り響いていた。
じりじりと太陽が照りつける前の道と、太陽が傾いて橙色に街が染まる頃の道。真澄は毎日の朝と夕方に弟と犬と歩く。
真澄と小学二年生の弟にとって、散歩は夏休みの日課だ。愛犬の散歩は、弟の夏休み課題のひとつだ。「小さなことからでかまいません。毎日つづけられるお手つだいを一つはじめましょう」と夏休みに配布されるワークブックの最初の課題としてカレンダーと共に大きく書かれていたのだ。
弟の成績表と夏休みワークブック、課題案内のプリントを見て、父は長いこと顎をさすっていた。小学二年生一学期の成績や授業態度が悪かったわけではない。弟が得意げに許可してくれたので真澄も中身を知っている。
弟は素直で聞き分けが良い子だ。朝と夕にポストに届いた新聞を取りに行くのも、食事の前にテーブルを拭くのも、家族の皿と箸を並べるのも、自分で食べた皿をシンクの洗い桶にまで運ぶのも毎日していた。更なるお手伝い、そのうえ危なげもなく弟の成長にも繋がるもの――眉を寄せて思案していた父が、あっ、と大きな声をあげた。扇風機にあたっていた真澄は、レモンシャーベットをひっくり返しそうになった。
「いいじゃないか。こういうのでいいんだよこういうので」
輸入雑貨商がひたすら食事するグルメ漫画のような台詞に真澄は首を傾げる。
下に落ちる前にスプーンをキャッチした娘も見ていたのか、父は笑いながら言った。真澄にも宿題を出そうかな、と。
それが、夏休みの日課「朝夕に太郎と散歩に行くこと」の始まりであった。
庭の向日葵と背比べをする遼太と、それを静かに見守る太郎の背中からヒントを得たらしい。太郎は宇田川家の愛犬の名前だ。遼太よりも一年早く生まれた柴犬のお兄さんである。その自覚があるからか、弟よりも落ち着きのある子だ。今も後ろを時折振り返っては遼太を見上げている。遼太がまっすぐ道を歩いているか、確認しているようだ。ちなみに二人合わせると、司馬遼太郎の「遼太郎」とぴったりおそろいだ。
今日も宇田川姉弟は肩を並べて川縁の道を歩く。朝は姉と弟と愛犬の三人きりだが、夕方には書道教室終わりの祖母、仕事帰りの父と母も合流することがある。夕焼けを探しながら歩くのがもうひとつの日課だ。
澄んだ青空が広がっている。朝方には緩く固まっていた雲だったのに、夕方の今は夏祭りの夜店でちぎって食べ合ったときの綿飴に似た大きさで分かれ、空のあちこちに散らばっている。ほんのりと淡い橙色が混じっているのが見えた。
暑さと日々の復習と課題とに気をとられて気づかずにいたが、空はもう秋にさしかかっている。
そういえば、日が暮れてくるのも、道に影が伸びるのも早くなってきた。
橋にさしかかったところで、「あっ」と弟が声を弾ませた。ぱちぱちと真澄が目をまばたいているうちに、弟は太郎と仲良く連れ立って走り出した。
真澄もびっくりしたまま追いかける。先に家を出発した弟を、自転車に乗った兄が追いかける。なんだか数学の課題で何度も見たことがあるシチュエーションだ。残念ながらここに自転車はない。なので、自分で速度を上げるしかない。橋の向こうにいる弟に真澄は息を切らして叫ぶ。
「遼ちゃん!」
弟を抱きしめて目線を合わせたうえで「急に走ったら危ないでしょう」ときちんと伝えねばなるまい。なんとか橋を渡りきり、ゴール直前で腕を伸ばしかけた真澄は、息が止まった。ひゅ、と。
「はい」
返事があったのだ。随分低い声で。上方から。
そこには、同級生がいた。宇田川遼太と太郎の頭を代わる代わる撫で回すそのひとは、はにかみながら顔をこちらに向けてくれた。
「ごめん。オレじゃないってわかってはいるんだ。わかってはいるんだが、びっくりしたよ。宇田川さんが必死に呼ぶから」
教室で見せてくれるのと同じ穏やかな笑顔のまま、そのひとは頬を搔く。
そうだ。このひとの名は、歌川遼だ。このひともまた「遼ちゃん」と呼ばれても不思議ではないのだ。
「こ、んばんは。うたがわくん。ごめんね。びっくりさせてしまって……」
声が上擦ったものの、なんとか挨拶できた自分を、褒めてあげたい。一年C組に五百点。怒って大声で叫んだことも、叫びながら走ったから息切れしていることも、汗が噴き出しているうえに髪が大きくほつれているだろうことも、何もかもが恥ずかしくて顔を上げられない。
「大丈夫だよ宇田川さん」
落ち着いた声が、真澄の耳を震わせる。
「こんばんは」
そのひとは少女の息が整うのも、心臓が落ち着きを取り戻すのも、顔を上げる心の準備が整うのも、そっと待ってくれている。
「あと、ただいま」
はにかむように頬を搔く歌川から目を反らさずに、唇を開く。
「お、おつかれさまです。おかえりなさい」
なんとか出せた。ほっとした真澄の眉が、へにゃんと下がった。「遠征」から帰ってきた彼を労う言葉を直接贈ることができたのもなんだか嬉しい。
「うん。ただいま」
声というものは、実にそのひとのひととなりをよく表していることがわかる。相手の言葉に耳を澄ませようとするひとは、よく通る声を持っていて、表現もやわらかい。そして、歌川もそうした例から漏れず、よく澄んでいて、包み込むようなやさしさとあたたかさも持ち合わせた声をしている。
「ねえねえ遼くん! 聞いて聞いて!」
小学二年生は姉の緊張になどまったく気づかず、歌川の足下に全身で戯れ付いている。きらきらと目を輝かせながら。太郎もふかふかの尻尾を大きく振り、二人の前で足踏みしている。
「こら、遼太。太郎。お姉ちゃんをあまり心配させるなよ」
歌川は少しかがむと、遼太と太郎の目を、じ、と見下ろした。
「う。すーちゃん、ごめんなさい」
上目遣いで真澄をちらちら見上げてくる弟を、真澄はつい甘やかしたくなる。遼太は、言葉を覚え始めたとき、「お姉ちゃん」と覚えるよりも先に、真澄の名前を覚えた。祖父母と両親が名を呼ぶのをよく聞いていたらしい。けれども、うまく発音できなくて、真澄のことを「すーちゃん」と呼び始めた。そして、今もそのまま呼び慕ってくれている。舌足らずで甘えたような声は可愛い。だが、ぐっと我慢した。耐えねばならない。心を鬼にして、きりりと眉を引き締める。その潤んだ瞳にまっすぐ目線を合わせ、真澄は声を出した。
「……急に走ったら危ないでしょう。誰かにぶつかって怪我をさせてしまうかもしれないし誰かの大事なものを壊してしまうかもしれない。それに、遼ちゃんが怪我することだってあるかもしれない。だから、急に走るのは危ないんだよ」
「はい。きをつけます」
「うん。次からがんばろうね」
しおしおと肩を落とす弟は、素直で可愛かった。真澄は頬をふにゃふにゃ緩め、弟のやわらかい髪と小さな頭を右手で撫でる。
「……宇田川さん、そうしてると、ほんとうにお姉ちゃんなんだな」
ぽつり、と落とされた声に、肩が跳ねた。
「遼くんなに言ってるの? すーちゃんはずーっとずーっと、ぼくのお姉ちゃんだよ? レベルだってもうすぐ八に上がるんだから! すごいんだ!」
もうすぐ八歳になる小学二年生が、えへん、と胸を張った。
「そうなんだ。すごいな」
「そうでしょうそうでしょう。この間だって、カブトムシの一番大きくて格好良いの採ってくれたんだ! すーちゃんはすごいんだよ! いいでしょう! もっと褒めてもいいよ!」
にこにこと笑い合う二人がまぶしい。太郎のリードを握る弟の手に力が入る。太郎はといえば、静かに座っている。遼太の足下にどっしりと腰を下ろしている。飛び出し禁止と言っているのだ。おりこうさんである。
歌川に会うのは少しだけ久しぶりだ。
終業式と、夏休み直後の課外授業の学校教室。それから課外授業が終わった翌日にも橋を渡りきったこの場所で会った。
太郎の散歩兼カブトムシ狩りに出かけた日の早朝だ。課外授業で学校に向かっていた日よりも早く弟に起こされた真澄は、うつらうつらしていた。堪えきれずに大きな欠伸をしたところで会ったのだ。爽やかな笑みを浮かべる歌川と。
ぱちん。思わず両手で口を押さえる真澄に、歌川は「おはよう」と声をかけてくれた。
しゃがみ込んで、落としたリードを拾い上げてくれた。夢の中でも彼はベリージェントルソウルをお持ちだ。
「だあれ?」
シャツの裾を後ろに引っ張られる。ぎゅう、とシャツを小さな指で力いっぱいに引っ張ってくる弟と、真澄のスニーカーの上に座り込んだ太郎の重みとあたたかさで、これが夢ではないことに気づいた。口をあわあわさせながら両手でリードを受け取る真澄と、真澄の後ろからそっと顔を出す弟に、歌川は笑いかけてくれた。にっこりと。安心させるようにやわらかく。
「はじめまして。遼太くん。太郎くん。オレは歌川遼と言います。司馬遼太郎の遼太郎とおそろいの遼と書きます」
「うたがわ遼くん? ぼくたちおそろいだね!」
ぱあっと目を輝かせた弟は、一気に歌川に懐いてしまった。「三人合わせたら上から読んでも下から読んでも遼太郎遼だねえ!」と胸を張っている。
「そうだな」
屈託のない小学二年生の笑みにも負けず、歌川がやわらかく笑ってくれている。やはり夢かな。夢かもしれない。ほう、と息をつく真澄である。と――
ちらちら、そわそわ、と歌川がこちらにせわしなく目線を送ってきた。真澄はピンときた。皆まで言わずともわかる。言ってくれるな、と真澄は右手を前に掲げた。
「ごめんね歌川くん。時間をもらってしまって。なにか急いでいるのでしょう? ボーダーのお仕事かな?」
「ごめん宇田川さん! 撫でさせてもらってもいいかな!?」
「エ」
乞われた真澄は今度こそ心臓が壊れたかと思った。どこか緊張した顔つきの歌川が視界いっぱいに広がる。身を乗り出してきたのだ。近い。そして、半ば叫ぶような勢いで放たれた宣言。押し寄せる怒濤の情報に脳みその処理能力が追いつかない。ぎゅう、とリードを握りしめ、震える唇を開いた。
「ど、どうぞ。ひと思いにお願いします!」
「ありがとう!」
ぱああっと目を輝かせた歌川が、その筋張った大きな手のひらをまっすぐ伸ばし――――真澄の真ん前でしゃがみ込んだ。
「よーしよしよし。いい子だねえ。太郎はものすごく、ふわふわふかふかふくふくしてるなあ!」
いつになく、やさしい声だ。歌川は真澄の――宇田川家の愛犬――太郎に握った拳を差し出し、太郎が鼻を近づけて心を開くのを待った。彼の許しを得るなり頭と背を思い切り撫で回す。頬も眉も眦も大きく緩ませ、とろけきったような顔つきで、ふわふわふさふさもふもふした黄金色の被毛を広い手のひらでわしわしと撫で、太郎に話しかけている。
「…………」
まだ夏のぎらつく太陽は昇りきっていないのに、暑い。そして、熱い。朱く染まった顔を両手で覆い、真澄はしゃがみ込んだ。
「すーちゃん、どうしたの? だいじょうぶ? 麦茶飲む?」
隣にしゃがみ、おずおずと水筒を差し出してくれる弟は、今日もやさしくて可愛い。
ここでまた歌川と顔を合わせることになるとは。嬉しい。だが、すごく恥ずかしい。嬉しくてそわそわするのに恥ずかしい。
あの夏季課外授業翌日の朝と同じく、歌川は太郎に思い切り笑いかけ、遼太と仲良く、代わる代わる太郎の黄金に輝く毛皮をわしゃわしゃ撫で回している。太郎もご満悦といったように気持ちよさそうに口を緩めている。顔はとろけきっていた。
リードを握る指に力が入る。そうでもしないと、あの日の盛大な勘違いの思い出で胸がいっぱいいっぱいになり、心臓も全身も爆発しそうになるのだ。まさか弟を注意した手前、急に全速力で走り出すわけにも行かず、ぐんぐん上昇していく体感温度に真澄はくらくらする思いがした。
「遼太、背が伸びたんじゃないか?」
「うん! そうだよ。よくわかったねえ。遼くん、すごい!」
前に会ったときと目線の高さが違う、と歌川が遼太の頭を撫でる。
「さすが遼くんお目が高い! 背も高い! でもねえ――」
むん、と胸を張り、遼太が笑った。
「まだまだ大きくなるよ。すーちゃんよりもずっとずーっと大きくなるんだ」
背筋をぴんと伸ばして宣言する弟に、歌川は、ふは、と吹き出した。 「あっ、遼くん! 笑ったな! いいよ、べつに信じてくれなくても。遼くんよりもビッグになっても遼くんのこと撫でてあげないからね!」
上目遣いになる弟に、歌川は笑みを堪えつつ謝った。
「ごめん。格好良いこと言うなあって思ったんだよ」
歌川は遼太と目線を合わせ、小さく言った。どこかまぶしげに、なにかを懐かしむように眦をふわりと緩めながら。
「わかればよろしい」
両腕を組むポーズで鷹揚にうなずく遼太に、歌川は再び吹き出した。乞うご期待だな、と。
屈託なく笑い合う二人を見つめ、真澄は素直に感心した。
一学期に朝読書を始めたことで、夏休みの今でも読書の習慣は続いていたが、まだまだ平安朝のイタリア男・在原業平への道は遠い。まずは小学二年生の弟のコミュニケーション能力に弟子入りするべきかもしれない。
遼太の頭をやさしい手付きで撫でながら、歌川が、ふっとこちらを見上げてきた。
とくとくとく、と心臓が音を立て始めた。
真澄はおろおろとリードを持ち上げては、下ろすことを繰り返した。
挨拶は先ほど交わしたばかりだし、真澄の近況を話そうにもカブトムシ狩りの話を弟が先に披露してしまった。無事に終えた「遠征」というものについて聞くのはタブーだろうな、と真澄は開きかけた口を閉じ、右手で押さえた。「機密は人命より重いのだ。ゆめ忘れるな」と先週の日曜朝、戦隊番組の博士がヒーローに言っていた。
ぐらぐらと頭が茹で上がってきた真澄を、口を開いたものの言葉が出ない真澄を、歌川は急かそうともせず、静かに笑んで待ってくれている。いつでもどこでもベリージェントルソウルを忘れない歌川は、今日もすごくすごくすごい。
「――歌川くんは、いつもすごいね」
三対の瞳が真澄に集中した。
声に出てしまっていたらしい。あっ、と声をあげ、真澄は視線を泳がせた。慌てて太郎の頭に手を伸ばす。あたたかく、やわらかい黄金色に波立った気持ちが凪いでいく。
夏休みの序盤にここで会った歌川は、「これから『遠征』に行くんだ」と言っていた。ボーダーには全国大会があるのだな、と納得をした真澄は、心の底から感心したのだ。すごいなあ、と。
日々の防衛と訓練だけでなく、高校一年生の学校生活を送りながら勉学にも励んでいるのだ。そのうえ、いつもはるか高いところから、遠いところまで気を配り、誰にでもいつもいつだって快く手を差し伸べてくれる。このひとは、草鞋を何足同時に履いているのだろう。立ち上がって、息を整えて、言う。
「歌川くんのこと、いつもひたむきですごいなあって思ってるよ」
こちらをまっすぐ見上げていた歌川は、きゅう、と眦を緩めて、笑った。ありがとう、と。それから笑いを堪えるように筋張った手のひらで口元を覆い、顔をうつむけた。初めてつむじが見えた。いつもはこちらが見上げてばかりなのでなんだか新鮮だ。
「――宇田川さんも守備は上々?」
なんのことかわからず真澄は目を大きくしばたたいた。「読書感想文」と笑みを含んだ声で言われ、両手をぽんと打つ。この間ここで会ったときにも彼は尋ねてくれたのだ。夏休みの課題の進みはどうか、と。
歌川は遠征前に読書感想文を除き、すべて済ませたらしい。所属チームの隊長からのお達しでもあったそうだが、それでもすごい。「遠征」前日まで課外授業で毎日通学していたのに、その合間にも防衛任務があっただろうに、夏休み序盤のうちに済ませるだなんてすごい。すごくすごく本当にすごい。同じチームの菊地原も終わらせていると教えてもらい、二人の伝説に新たな一ページが加わった。すごくべらぼうにブラボーにとてつもなく尋常でなくすごい。
対して、真澄は溜め込んで終盤に泣きながら取り組むタイプでもないが、彼らのように序盤に一気に攻め崩すスピードスタータイプでもない。淡々と毎日少しずつ取り組む派だ。夏休みの終わりにゴールに辿り着けず泣くことはなかったが、読書感想文だけは別だ。毎年うんうん頭を抱えるのが夏の風物詩であった。
だが、今年は違う!
ギュッ! と、眉を自分史上最高に引き締めて、言う。
「無事に終わりました!」
「すごい! よくがんばったな! 宇田川さん、教室でもよく本を読んでるものなあ。レベルアップも当然だよ」
真澄は頬が緩むのを抑えきれない。ベリージェントルソウルをお持ちの歌川からまっすぐと向けられた微笑み。他愛ない会話を覚えてくれていたこと。そして、歌川に直接惜しみない称賛を贈られたこと。何もかもが照れくさく、くすぐったくて。胸のあたりが、じわじわ、ふわふわ、きらきら、どきどきした。
さあ、と風が渡った。真澄のポニーテールが、ふわ、と揺れた。太郎が三角形の耳を立て、心地よさそうに耳を澄ませている。ちりん、とかすかに風鈴の音がした。
綿飴のような雲は、いつの間にか橙色に染まり始めていた。そういえば太陽が山の端に沈みきるまでの時間も、夏休みの始めの頃よりもぐっと短くなった。
山の端に太陽が傾き、橋と丘の向こうでは家々の灯りがともるのが見えた。
「歌川くん」
「うん」
夏の果ての風に、歌川の短く切り揃えられた髪もそよそよ揺れている。
「あのね、わたし……」
唇を開いては閉じ、閉じては開くことを繰り返す真澄を、歌川は待ってくれている。
「わたし、いつもこの道を散歩するたびに思うんだ」
「うん」
喋るのが得意ではない真澄にとって、自分から話を始めるのは覚悟が必要なことだ。けれど、今、この瞬間、歌川は真澄の隣で同じ景色を見ている。夏の終わりの夕焼けに染まるこの街を共に見てくれているそのひとに、真澄にはどうしても伝えたいことがあった。
「あの……」
「うん」
真澄のつたないお喋りが始まるのを、そのひとは待ってくれた。そのひとは静かに相づちを打って耳を傾けてくれている。
「ボーダーのひとたちがこの町を護ってくれているから遼太も太郎もわたしも、ううん、街の皆も。皆が安心しながらこうして散歩できるんだなって。ここで街の灯を見るたびに思ってる」
だから、と真澄は言葉を切った。息を吸い――言う。
「いつもありがとう。街を護ってくれて」
頬が、ほころんだ。なんとか言えたのにほっとしたのだ。それを一番に伝えたい歌川に、同じ夏の灯を隣で見ながら言えたのも嬉しい。嬉しくて、たまらなかった。
「……宇田川さんは、いつもまっすぐ言葉をくれるね」
その日最後の太陽の光を受け止めた歌川の瞳はまぶしかった。落ち着いたトーンの瞳をほのかに細めて、そのひとは笑う。なんだかまっすぐ見ていられなくて、少女は耳に髪をかけ直しては下ろし、耳から下ろしてはかけ直した。
正面から吹く秋の気配が混じる風に、そっと目を伏せた。