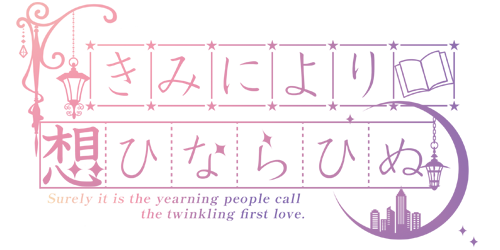顔を上げると雲ひとつなく、澄み切った青空が見えた。開け放った窓からは、透明な風がそよぎ、カーテンを揺らしている。二度咲きした金木犀の香りがほのりと教室を包んだ。
ほう、と少女はため息を零した。秋を知らせてくれる清らかで甘やかでやわらかい香りをもう一度味わえるだなんて、今年の秋はなんだか豪華だ。
ふ、と机に影が差した。
「なに? なんでさっきから顔で独り大運動会してるの?」
「菊地原くん……」
顔を上げると、友人が胡乱な目つきでこちらを見下ろしていた。
善き隣人、菊地原士郎の声かけはいつも藪からスティックだ。けれども、雨の日も風の日も隣の席歴を二ヶ月も重ねれば、親しみも慣れもレベルアップするものである。同じ図書委員になったことがきっかけで話すようになり、席替えで隣同士になってからそれなりに会話をしてくれるようになった。「おはよう」と挨拶して、「おはよう」と挨拶が返ってくるのはやはり気持ちがよい。
彼の語り口は歯に衣着せぬもので直球だ。しかしながら、小粒の山椒よりもぴりりと辛味の効いた菊地原語は聞いていて楽しいし、冷え冷えとした指摘もやんわり落とす苦言も語彙のレパートリーが豊かで勉強になる。機知に富むとは彼のようなひとのことを言うのだろう。
「聴いて驚かないでいただきたい。ううん、聴いて共に驚いていただきたい」
「なに? どっちなわけ? ぼくだって暇じゃないんだから早く言ってくれる?」
目を伏せ、息を吸って整える。そして、震える指を組み直し、告げる――
「歌川くんに『綺麗だね』とお言葉を賜りました」
相手は「……ふぅん」とだけ返してくれた。素っ気ない。けれど、口元はにやにや緩んでいる。祝福の意を素直に示してくれる彼はやはり善き隣人だ。他者の喜びに耳を傾け、共に喜んで分かち合ってくれる。なんとできたひとであろうか。自分もかく在りたいものだ。しみじみとそう思い、少女は馳せるように吐息した。
「やってて良かった書道塾……」
「は?」
「今日の選択書道はDVD観る都合で教室が視聴覚室に移動になったのですよ。でも先生から連絡があったのは昼休み中で、選択者全員が教室にいたわけではなくて。それで、教室にも書道室にもわかるように黒板に書き置きを残そうとなったのです。で、僭越ながらわたし、宇田川真澄が教室分を担当いたしました。それでねっ、そっ、がっ!?」
核心に迫ったところで、げほごほがほと真澄は盛大にむせた。
「はあ、言われたんだ。歌川に」
菊地原は嫌そうに思い切り眉を寄せたものの、息も絶え絶えな真澄の遺志を引き継いでくれた。ここで無視することも黙殺することもしないあたり、彼は大変ひとがよい。
「ごほ。失礼しました。うん。それを見てくれた歌川名人が『綺麗だね』と! 褒められたんですよ! わたしの字が! 歌川くんに! 微笑みを添えられて!」
「はあ。よかったね」
先人が残した「継続は力なり」という格言はまさにイグザクトリーであった。
きゃー、どうしよう! と小声でエキサイトする真澄とは正反対に、ロウテンションな菊地原である。一応、そう言ってくれるあたり、菊地原プロもまたひとがよい。
「ていうか、何なの歌川が名人って」
実によい質問である。
真澄は大きくゆっくりとうなずいた。よくぞ聞いてくれました、と。
「人生の名人」
同じ高校一年生なのに歌川遼名人の察しの良さ、細やかな気遣い、いつでも漂う爽やかさは、歌川が人生七周目の人間だからだろうとクラスでもまことしやかに流れている説である。ちなみにいつでもどこでも誰にでも丁寧に的確にツッコミを入れてくれる菊地原も「菊地原プロ」としてクラスメイトにこっそり慕われている。彼だけが知らない公然の秘密である。
「どうしよう。この今日の佳き日を祝日に制定したい。今すぐ半切に行書体で書いて飾りたい。これは全国展で賞をいただくよりも空前絶後の史上最高に誉れのある出来事だと言っても過言ではないと思う」
「はあ? 過言でしょ」
「芸は身を助けるって本当だったんだねえ。きっと、小学一年生の冬休みに凍らないようにカイロと一緒にポケットであたためた毛筆が恩返ししてくれたんだ……」
「急に早口になる……」
「歌川くん基金がますます捗ります。ありがたやありがたや」
「はあ? 基金?」
ぱちくりと驚いた猫のように目をまあるくさせた菊地原に、真澄もまばたきを返した。
「先月から〝歌川くん基金〟を始めまして」
「は?」
「あれ、まだ菊地原くんに話したことなかったかな?」
「はあ」
「発起人わたし、賛同者わたしという体制で始めたんだ。歌川名人がクラスの子たちに施す素晴らしい瞬間を刮目したとき、歌川くんから素敵な笑顔や言葉を賜ったときの記念にその良さを噛みしめながら財布の小銭を基金箱に移して貯金していくというとても画期的な基金で、もうすでにけっこうな金額が貯まりまして……」 「…………」
コンセプトと達成金額を説明していく。すると、菊地原が何故か疲れたような顔つきで言ってくる。
「その〝歌川基金〟ってさあ、貯めて何に使うわけ?」
そのとき、世界が止まった。
菊地原プロと歌川名人は、三門市の平和を護る界境防衛機関「ボーダー」に所属する隊員だ。テレビや街のポスターで嵐山隊はよく見かけるが、二人の所属する隊は朝の情報番組に登場することはないらしい。街の防衛は同じでも、担う専門任務が違うのだそうだ。当然、テレビや街のイベントに登壇する嵐山隊のようにマグネットやタオル、ポスターなどの関連グッズ(?)というものが発売される未来はないらしい。残念な気もするし、助かった気もするし、なんとも複雑な心境である。
「……歌川くんが経済的に困ったときに紫の薔薇の花束と共に『応援しています』と匿名で贈る、とか?」
何故か険しい顔つきになった菊地原プロが犬歯を見せてきた。
「重い……」
「え、まだまだだよ? 自分もっといけます!! やらせてください!!」
真澄が瞳に炎を灯すと、菊地原プロは何故かこめかみを押さえた。
「あのさあ、歌川はぼくと同じ隊で任務についているからきみよりよっぽど収入はあるし、よほどのことがない限り困窮しないでしょ」
「た、たしかに」
「それよりさあ、宇田川。きみさあ、テスト期間はいつも歌川と隣の席になるんだからわけわかんないことしないでもっと普通に仲良くしたら?」
宇田川真澄は女子の中で、歌川遼は男子の中でその名の通り、出席番号が早い。その都合で今のクラスではよほどのことがない限り、出席番号順の座席で受ける定期試験期間と模擬試験日は彼と真澄は隣の席同士の関係なのだ。
だが、緊張の余り、真澄は歌川名人が隣にいらっしゃる右半身の挙動が毎回小刻みに振動したり、挙動がおかしくなったりするのだ。自然な会話など生まれるはずがない。それなのに、歌川は特にどうということもなく、爽やかに微笑んで「がんばろう」とあたたかい励ましを送ってくれるのだ。
「も、もったいなくてそうそう話せないよ。覚えた単語が緊張で溶けちゃいそうになるもん」
へにゃりと情けなく眉の力を抜いた真澄に、菊地原プロは何故か大きく吹き出した。
「まあ、せいぜいがんばりなよね」
「う、うん。今日の古典の小テスト、がんばろうね。菊地原くん、いつも聴いてくれてありがとう」
真澄は、菊地原のことを、歌川と話す口実にしているわけではない。ただ歌川のやさしさと素晴らしさを直撃し、爆発しそうで持て余してしまうどうしようもない真澄の気持ちを、彼はいつも呆れながら耳を傾けてくれるのだ。
歌川に抱く真澄の気持ちには、きっと、まだ、はっきりとした名前はない。
分類するのならば、「憧れ」だ。けれども、模擬試験のスケジュールが見えなくて背伸びを繰り返す真澄にこっそり彼が隣から渡してくれたメモ。掃除時間に彼が同じ班の生徒の代わりに大きなゴミ袋を持つ姿。そうした彼の何気ないやさしさに出逢うたびに、日増しに憧れの気持ちは大きくなっていく。膨れ上がる気持ちの成長は、〝歌川くん基金〟でみるみる数値化されている。
「菊地原くんが困ったときにもこの貯めに貯めた基金を紫の薔薇と共に贈るからいつでも力が、財力が必要なときは言ってね」
「……歌川の彼女枠は正直わからないけど、おもしれークラスメイト枠なら宇田川もいい線狙えるかもね」
なにやら菊地原プロが告げた気もするが、真澄はラ行変格活用で頭がいっぱいでそれどころではなかった。
「えへへへ」
にこにこと頬を朝から緩むのに任せている真澄に、登校したばかりの菊地原士郎が目を丸くした。
醒めた調子で言う。
「……朝からおめでたい奴だね、宇田川は」
「おはよう! 菊地原くん!」
律儀に朝の挨拶をしてくれる菊地原である。真澄も頬を緩ませたまま、元気いっぱいに会釈する。
「菊地原くん聴いて!」
「はいはい」
「ありがとう!」
「はいはい。で? なに? 早く話しなよ」
菊地原プロは今日も元気だ、絶好調に言葉が辛 い。クールな口調ではあるが、そういうツンツン澄ました声をかけてくるときの菊地原は、猫に似た吊り目も平時は静かに一文字に結んでいる口角も面白そうにふんわり上がっているので、なんだかんだ聴いてくれるのだ。いいひとである。
「長期目標を用意すると良いって、昨日の集会で進路指導の鈴木先生からお話があったでしょう?」
それがどうしたのだ、という胡乱な目つきに先を促され、真澄は両手を合わせて笑いかける。
「そういうわけで、例の〝歌川くん基金〟は、将来歌川くんの結婚祝いにお贈りするためのフラワースタンドに使うことにしました! 備えあれば憂いなしだね」
真澄は菊地原に宣言し、いそいそと今日の朝読書の友だちを紹介した。じゃん、と。
『Flower Shop 楓』からもらった花のカタログだ。昨日の進路集会のありがたい講話に深く感銘を受けた宇田川真澄は、そのあとに出発した夕方の愛犬太郎の散歩コースを蔵先町に変更したのだ。
「うわ、絵に描いたような晴れやかな顔と曇りなき眼 だ。いったい何なの宇田川が時々びっくりするほど発揮する謎の行動力……」
「ありがとう!」
「褒めてないから」
何故か犬歯を見せてくれる菊地原である。きょとんとまばたきを返し、真澄は付箋を貼っておいたページを開いた。
「どんなフラワースタンドがいいかな?」
フラワースタンドとは、立派なスタンドに優雅に華麗に大胆に飾られたアレンジ花のことだ。店の新規オープン時などに入り口で飾られているのを見かけるあれのことだ。
朝のローカル情報番組と祖母の話からヒントを得たのだ。お祝いや応援にはこれだ。
真澄の祖母は書家だ。仕事の傍ら、子ども向けの書道教室を開いている。つい先日、児童館がリニューアルオープンした。そのセレモニーに協賛企業からフラワースタンドが贈られた。それぞれの贈り主の名札とセレモニー式次表を担当したのが祖母だ。
そのセレモニーの様子を、朝のローカル情報番組が紹介してくれた。お天気情報によくゲスト出演してくれる嵐山ナントカさん? と部隊が同じだという、艶やかな黒髪をショートボブにした女の子がリポートしてくれていた。そのリポート中、黒髪の乙女は祖母の題字に微笑んだのだ。「とても美しい字ですね」と。
その一言に祖母は舞い上がった。普段は穏やかでたおやかで物静かな祖母ではあるが、何を隠そう、大の宝塚歌劇団ファンなのであった。〝ご贔屓さん〟〝贔屓ジェンヌ〟似のそのひと、つまりは一番好きな歌劇団俳優に似たその少女に褒められて、祖母は有頂天になったのだ。それ以来、祖母はにこにこと楽しげに微笑みながら、その少女――涼しげで大人びている面差しだがまだ中学三年生らしい――木虎さんがローカル情報番組に出るときは欠かさずチェックする日々を送っている。
嵐山隊が三門市のイベントに登場する機会があれば、祖母はうきうきと申し込みをする。はがきに記載する住所氏名もアンケート内容も番組感想も応援メッセージも、何度も何度も入念に筆で練習してから挑むという気合いの入り用だ。隊長の嵐山ナントカ? さんをはじめ、彼らの嵐山隊ファンは多いと聞く。祖母の流麗な書が入ったはがきでさえ、抽選にはなかなか当たらない。力の限りペンライトを握りしめアイドルのステージを応援しに行くファンの如く瞳を煌めかせながら、嵐山ナントカ? さんの掲載雑誌や出演情報番組について熱心に教えてくれるファンガールやファンボーイもこの一年C組にだっている。けれども、祖母のファン活動は彼らのようなファンガール・ファンボーイのそれとは少し違っていた。彼らがテレビやラジオに登場しない日でも、彼らがゲスト出演してくれるイベントに当選しなくても、街で彼らの取材や撮影に遭遇せずとも、街を防衛してくれている彼らがすぐそばにいてもいなくても、ただ静かに背筋を伸ばし襟を正し、まっすぐ書に向かい、楚楚と日常生活を送るのだ。
――街をいつも護ってくれている木虎さんに恥じないファンで在りたいの。それは、木虎さんたちボーダーの方々が、身も心もひたむきに注いでこの三門市と私たちを護りたいと思ってくれる善き心もそのまま大切にしたいということなのよ。それには私たち大人がそれに値する街を作らなくてはいけないわ。そう思ってくれる街に住むのにふさわしい素敵な大人で在り続けるには、品行方正を心がけないとね。
木虎さんのサイン色紙を納めた額縁を見せてくれた祖母は、真澄たち姉弟にそっと耳打ちしてくれた。木虎さんの活躍を、木虎さんが護ってくれている日常を、街を護りたいと願ってくれているその想いを大切に護るのがファンの務めなのだ、と。夢見る少女のようにはにかむ祖母の笑みは、やわらかくてやさしくて、とびきり可愛らしかった。
歌川遼に対して宇田川真澄が抱いている気持ちに、名前はまだない。
けれども、誰よりもはるか何千里も先に進んでいるのに、誰よりも遠くにいるのにずっと周りをよく見てくれているところも、快く誰にでも分け隔てなく手を差し伸べてくれる気配り上手でやさしいところも、大人びているのに実は笑いの沸点が低くてすぐに笑ってくれるところも、笑い声を堪えきれないときや近しいひとに見せるときの笑みは切れ長の眦が、きゅう、と丸くなって幼く見えるところも、それから小テストの最後の欄はいつも〝はらい〟が伸び伸びとしているのに先がほんのり丸くなっていて可愛いところも。そして、真澄の字を見ると「綺麗だな」とやわらかに目を細めてくれることも。
それらを思うだけで、真澄はいつも胸のあたりがきゅう、となる。痛むのではなく、そわそわ、ふわふわ、きらきらしているし、どくどく、どきどきもした。言葉にならないこうした不思議な気持ちも、歌川と出逢い、歌川と少しずつ交流をしていくなかで全部知っていったものだ。それまでは知らなかったものだ。
川縁でぴかぴかの石を拾ったときのようにわくわくどきどきするこの素敵な気持ちを、真澄はもっと知りたくて、この気持ちも言葉にしたくて、歌川の素晴らしいところも引き出しの宝箱に仕舞っておきたい一方で世界中に教えたくなったのだ。平安朝のイタリア男・在原業平のように「ここで一首」と歌を詠むのはとてもできそうにはないが、手紙ならばできるかもしれない。苦手だった本も読み始めるようになった。国語の予習復習にも取り組むようになった。居残り常習組だった小論文も時間内に提出できるようになったし、国語の成績も上がってきた。
歌川の結婚式にお贈りするフラワースタンドには、歌川のおかげでできるようになったことをぜひとも来場者の皆様にも広く知らしめてその感動を分かち合いたい。便箋では伝えきれないだろうから、小冊子を作る方法について今から勉強する必要があるだろう。
そう説明すると、半眼でご静聴くださっていた菊地原がぽつりと零した。
「冊子じゃなくて巻物にしたら?」
「そのこころは?」
「五メートルもあれば足りるんじゃない。知らないけど」
不確かな情報であることを忘れるな、ときっちり言い添えてくれる菊地原はやはりいいひとだ。
「直江状だね」
ふむふむ、と真澄はうなずいた。徳川家康が上杉景勝に送った書状に対する返事を、景勝の重臣直江兼続が代理として送ったことで有名なベリーベリーロング書状である。
書展でお馴染みの二×八尺つまりは六〇×二四〇センチメートルの画仙紙もなかなかのお値段がするものだ。それよりも長い長い直江状クラスを目指すとなると、もっと費用がかかるだろう。本番だけでなく練習用だって必要なのだ。今日は放課後に書道部部室のカタログを確認させてもらわねばなるまい。〝歌川くん基金〟にもますます力を入れねばなるまい。歌川は呼吸するのと等しいリズムで毎日善行をしている。同じ一年C組の教室で真澄がそれを刮目する機会も、それを見た真澄が財布から小銭を基金箱に移すのも毎日あるということだ。入学してから半年。毎日見てきたのだ。
鼓動がドラムと木霊する勢いで、どきどき、どくどくと音を立て始めた。胸を押さえ、真澄が目にも心に炎を燃やせば、
「うわ、うるさ……」
思い切り菊地原に顔を引かれた。
いつも通り皆がめいめいに好きなように過ごしている朝の教室である。寝ぼけ眼をこすりながら授業で当てられる担当箇所を見直している子もいるし、英単語小テスト対策に赤シートと単語帳を広げたままうつらうつらしている子も見える。むしろ昼休みよりはずっと静かである。
真澄は首を傾げつつ、『Flower Shop 楓』のカタログを掲げる。
「それでね。まず目標を定めておきたくて……。どんなフラワースタンドがいいかな?」
あらん限りのありがとうとおめでとうを込めてお贈りする所存だが、結婚披露宴は生涯で一度の晴れ舞台だろう。歌川とそのお相手の方にぜひとも喜んでいただける至高にして究極のフラワースタンドをお贈りしたいものだ。児童館セレモニーの紹介番組で木虎さんがリポートしてくれていたスタンドは何色だっただろうか。祖母がDVDにダビングしていたものを見せてもらおう。そういえばこのほど新装開店した駅前のラーメン店にも飾られていた。どんな形でどれくらいの高さだっただろうか。部活後に寄ってみようか。
真澄はそんなことを話しながらフラワースタンド見本の一番目に掲載されているものを指差し、菊地原に助言を求める。
菊地原は顔をしかめた。猫に似た吊り気味の瞳が少しだけ閉じられている。
「すごく饒舌になる……どれも同じでしょ」
「う、ん……?」
真澄は目をしばたたく。
少なくとも飾る花の種類に本数、それから段数。スタンドの大きさや材質で値段も予約に必要となる日数も異なるようなのだが。特に特大サイズとSサイズとでは値段のゼロの数が違う。だが、真澄と同じ高校一年生にして学業の傍らに防衛機関ボーダーの隊員として、日々、この三門市の防衛任務を担って収入を得ている菊地原からしたら些細な違いでしかないのかもしれない。そんな菊地原と同じ部隊で日夜働いていらっしゃる歌川にとっても。
残念ながら親戚の結婚披露宴にまだお呼ばれしたことがない真澄にはフラワースタンドのスタンダードがわからない。彼らの収入を参考に一番高い値段から絞り込めばよいのだろうか。効率的だが、それはそれでいと味気なしのような――と首を傾げたところで、後ろから声がした。
「それ。サンダーソニアって名前なんだな」
歌川遼が菊地原の真後ろからカタログを覗き込んでいる。
つまり、真澄のすぐ斜め後ろにいる。歌川が、すぐそばに。
「ひゅ」
真澄の息が止まった。
歌川が「知らなかった」と切れ長の眉と目を上げている。歌川が。歌川の端正な顔が。ものすごく近くに。真澄の斜め後ろに。ある。歌川遼が。すぐそばに。いる!
かッ!
理解した途端、全身に火が走る。
がたん。椅子が倒れた。立ち上がって左に避けた真澄に菊地原がコメントした。
「やかましい」
「ごめんなさい……」
顔が熱い。というよりも、全身が熱い。身体中から煙がしゅうしゅう上ることを自覚しながら真澄は頭を大きく下げた。
「宇田川さん! ごめん! 大丈夫か? すまない。驚かせるつもりはなかったんだ。でも、びっくりするよな急に声かけたら」
歌川が、こちらに手を伸ばしているのが見えた。が、彼は、はっと両目を開き、すぐに身体を引いた。彼は腕を伸ばしながらかがむ。そして、ゆっくりと丁寧な所作で椅子を立たせた。音はひとつもしなかった。真澄を驚かせないよう注意してくれたらしい。
切れ長の眉と瞳。この秋一番の近さで見た歌川のそれは、朝からとても爽やかだ。veryどころかamazingly爽やかである。そして、朝でも夕方でもいつでも今朝も惜しまずに振る舞ってくれるベリージェントルソウル。どうしよう。どうしたらよい。どうしてくれようか。走り出すわけにも行かず――予鈴が鳴るまで十分は切っている。だが、チャイムの前に――
どっどど どどうど どどうど どどう!
猛烈な勢いで心臓がドラムを叩いた。
口元があわあわしてしまう。ひとまず震える右手で髪を耳にかけ直した。それから左手で脈打つ左胸をぎゅうと押さえる。震えに気づかれませんように、激しいビートが音漏れしませんように、と祈るような思いで真澄はなんとか席に座り直した。
「あ、の、ありがとう歌川くん……おはようございます」
上目遣いに挨拶をして、自身の左手に右手を重ねる。ぎゅう、と。
眉を少し下げ、すまなそうな表情をした歌川がそっとうなずいてくれた。
「おはよう。宇田川さん。菊地原。急にごめんな。ボーダー近くのパチンコ店でよく見る黄色い花が見えたから、つい」
「そろそろ条例に明記してくれないかなあ。朝から轟音にもほどがあるんだけど……おはよう、歌川」
菊地原が言った。何故か机にぺったりと顔を突っ伏しながら。
「はは。そうかもな。でも、あの店は夜勤明けの二時限目講義まで寝落ちないよう遅刻防止ですぐ入れるから便利だって諏訪さんたちが言ってたぞ?」
「需要があるから閉店してもすぐ次の新規店舗が入るってことだよなあ」
「そうだなあ。リニューアルなのか新規参入なのか、オレもよくは知らないけど、あの店はよく入り口でお祝いの花を飾ってるものな。おまえの言うように需要と供給が成り立っているんだろう」
「諏訪さんたち、いいお客様なんだろうね。でも、うちの風間さんは諏訪さんちで一旦仮眠してから大学に行く方が集中できるし効率的だって言ってたけど」
「こら。言い方……うん。でも、なんというか、さすが風間さんだよな」
「うん。風間さんだからね。然も有りなん」
自隊の隊長風間さんの話をする二人は、いつもまぶしげで、誇らしげな声と顔つきになる。きらきらしたまぶしいものを見るときの瞳をしている。同級生の中でも大人びている彼らが、少しだけ幼い少年のような顔つきなるのがなんだか微笑ましい。真澄も頬が緩んだ。と――
歌川がこちらを見下ろしてきた。まっすぐと。
「何かお祝い事?」
「う、うん。あ、ありがとうとおめでとうを、おくりたくて……」
つっかえながら真澄は答えた。まさか「将来歌川くんに日頃の感謝と人生の門出とこれからの新しいステージへの祝福をお祈りしたフラワースタンドをお贈りするので今から一番良いものを探しています! よろしくゥ!」などと、きらりと白い歯を見せて元気よく笑いかける度胸も余裕もご用意できるはずもない。
「じゃあ、とびきり豪華にしないとな」
歌川は朗らかに笑った。にっこりと。そして、「どれどれ」といった風に、菊地原の後ろから再びカタログを覗き込んだ。
すい。硬そうで筋張った長い指が、目の前で、動く。
「へえ。紫の薔薇もあるんだ。綺麗だなあ……。確か、薔薇は青色遺伝子を持っていないから、青い色の花を咲かせるまでのプロジェクトが長く険しい道のりだったって中学の理科で先生が言ってたよな」
「うん」
菊地原が緩やかに首を動かした。
「そうかも。でも、赤と青を混ぜると紫になるってことは、紫のものは青よりも咲かせやすいんじゃない? 昔から漫画でもあるくらいだし」
「ああ。紫のバラのひと……!」
ぎょっ、と目を開いた。
「う、たがわくん!?」
しってるの、と真澄は脊椎反射の勢いで声をあげた。
「うわ」
菊地原が顔をしかめた。
またしても椅子を倒してしまった。がたんと音を立てていた。勢いよく。「しつれいしました」と声をかけて椅子を粛々と戻す。
漫画『ガラスの仮面』の紫のバラのひと、速水真澄は、主人公北島マヤを応援してくれる御曹司のことである。彼が〝紫のバラのひと〟と呼ばれる理由は、マヤの演技にかける情熱に心打たれ、素性を隠した速水が贈り続けるファンレターに添える花が、紫色の薔薇だからだ。速水は、影ながらひっそりと、夜道を照らす月明かりのように、心くじけそうなマヤを時には励まし、時には叱咤してくれる、まさしくファンの鑑のようなひとである。彼は、名を明かさずに「あなたのファンより」と紫の薔薇を贈り、マヤもまた駆け出しの頃から応援してくれるそのひとに〝紫のバラのひと〟と感謝し続け、今日もまた演技の道に情熱を注ぐのだ。
宇田川真澄の〝歌川くん基金〟のプロジェクト目標のひとつは、歌川が経済的に困ったときには紫の薔薇の花束と共に「あなたを応援しています」と匿名で贈ることが決まっているのだ……つい一昨日からだが。
「うん。姉さんと母さんが熱心に読んでるのを、オレも借りて読むんだ」
面白いよな、と照れたように頬を搔く歌川の眦の角が、丸くなっている。きゅう、と。
「宇田川。歌川にも見てもらえば?」
「エ!?」
またしても真澄の呼吸が止まった。ひゅ、と。
「え、と」
プロジェクト目標である本人が、将来お祝いをお贈りすることになる結婚式披露宴の主役である、フラワースタンドの贈りびと……ではなかった、贈られびと(?)のそのひとが、カタログをセレクトしてくれる。極秘プロジェクトが始めから歌川本人に知られるのではないか。それはつまり、極秘プロジェクト終了のお知らせなのではないか。
しかし、サプライズプレゼントは相手の好みを熟知していないと失敗に終わる学説があると聞く。故 きを温 ねて新しきを知る。失敗は成功のもと。しかし、歌川の好みの色や花を学べる絶好の機会でもあるのではないか。歌川と菊地原と真澄。あとは友人のあゆみと茉椰に願えば、意見をくれるだろう。三人寄れば文殊の知恵。五人寄れば五人衆。合議制。十三人の合議制にはあと八人足りない。多数決の原理と少数派の権利。ぐるぐる。ぐつぐつ。ぐらぐら。真澄の頭が沸騰し始めた。
と――
「恐ろしい子……」
菊地原が迷惑そうに眉を寄せ、左右の耳を塞いだ。
「お、菊地原も読むんだな。次のコミックス発売が待ち遠しいよな」
歌川が笑っている。にこにこと。朗らかに。爽やかに。真澄のすぐ目の前で。
どっどっ、どどうど、と激しく鼓動を打つ真澄の心臓は、まだ鎮まりそうにない。こんなにも予鈴が鳴るのを待ち遠しく思った朝はあっただろうか。いや、ない。
ほう、と少女はため息を零した。秋を知らせてくれる清らかで甘やかでやわらかい香りをもう一度味わえるだなんて、今年の秋はなんだか豪華だ。
ふ、と机に影が差した。
「なに? なんでさっきから顔で独り大運動会してるの?」
「菊地原くん……」
顔を上げると、友人が胡乱な目つきでこちらを見下ろしていた。
善き隣人、菊地原士郎の声かけはいつも藪からスティックだ。けれども、雨の日も風の日も隣の席歴を二ヶ月も重ねれば、親しみも慣れもレベルアップするものである。同じ図書委員になったことがきっかけで話すようになり、席替えで隣同士になってからそれなりに会話をしてくれるようになった。「おはよう」と挨拶して、「おはよう」と挨拶が返ってくるのはやはり気持ちがよい。
彼の語り口は歯に衣着せぬもので直球だ。しかしながら、小粒の山椒よりもぴりりと辛味の効いた菊地原語は聞いていて楽しいし、冷え冷えとした指摘もやんわり落とす苦言も語彙のレパートリーが豊かで勉強になる。機知に富むとは彼のようなひとのことを言うのだろう。
「聴いて驚かないでいただきたい。ううん、聴いて共に驚いていただきたい」
「なに? どっちなわけ? ぼくだって暇じゃないんだから早く言ってくれる?」
目を伏せ、息を吸って整える。そして、震える指を組み直し、告げる――
「歌川くんに『綺麗だね』とお言葉を賜りました」
相手は「……ふぅん」とだけ返してくれた。素っ気ない。けれど、口元はにやにや緩んでいる。祝福の意を素直に示してくれる彼はやはり善き隣人だ。他者の喜びに耳を傾け、共に喜んで分かち合ってくれる。なんとできたひとであろうか。自分もかく在りたいものだ。しみじみとそう思い、少女は馳せるように吐息した。
「やってて良かった書道塾……」
「は?」
「今日の選択書道はDVD観る都合で教室が視聴覚室に移動になったのですよ。でも先生から連絡があったのは昼休み中で、選択者全員が教室にいたわけではなくて。それで、教室にも書道室にもわかるように黒板に書き置きを残そうとなったのです。で、僭越ながらわたし、宇田川真澄が教室分を担当いたしました。それでねっ、そっ、がっ!?」
核心に迫ったところで、げほごほがほと真澄は盛大にむせた。
「はあ、言われたんだ。歌川に」
菊地原は嫌そうに思い切り眉を寄せたものの、息も絶え絶えな真澄の遺志を引き継いでくれた。ここで無視することも黙殺することもしないあたり、彼は大変ひとがよい。
「ごほ。失礼しました。うん。それを見てくれた歌川名人が『綺麗だね』と! 褒められたんですよ! わたしの字が! 歌川くんに! 微笑みを添えられて!」
「はあ。よかったね」
先人が残した「継続は力なり」という格言はまさにイグザクトリーであった。
きゃー、どうしよう! と小声でエキサイトする真澄とは正反対に、ロウテンションな菊地原である。一応、そう言ってくれるあたり、菊地原プロもまたひとがよい。
「ていうか、何なの歌川が名人って」
実によい質問である。
真澄は大きくゆっくりとうなずいた。よくぞ聞いてくれました、と。
「人生の名人」
同じ高校一年生なのに歌川遼名人の察しの良さ、細やかな気遣い、いつでも漂う爽やかさは、歌川が人生七周目の人間だからだろうとクラスでもまことしやかに流れている説である。ちなみにいつでもどこでも誰にでも丁寧に的確にツッコミを入れてくれる菊地原も「菊地原プロ」としてクラスメイトにこっそり慕われている。彼だけが知らない公然の秘密である。
「どうしよう。この今日の佳き日を祝日に制定したい。今すぐ半切に行書体で書いて飾りたい。これは全国展で賞をいただくよりも空前絶後の史上最高に誉れのある出来事だと言っても過言ではないと思う」
「はあ? 過言でしょ」
「芸は身を助けるって本当だったんだねえ。きっと、小学一年生の冬休みに凍らないようにカイロと一緒にポケットであたためた毛筆が恩返ししてくれたんだ……」
「急に早口になる……」
「歌川くん基金がますます捗ります。ありがたやありがたや」
「はあ? 基金?」
ぱちくりと驚いた猫のように目をまあるくさせた菊地原に、真澄もまばたきを返した。
「先月から〝歌川くん基金〟を始めまして」
「は?」
「あれ、まだ菊地原くんに話したことなかったかな?」
「はあ」
「発起人わたし、賛同者わたしという体制で始めたんだ。歌川名人がクラスの子たちに施す素晴らしい瞬間を刮目したとき、歌川くんから素敵な笑顔や言葉を賜ったときの記念にその良さを噛みしめながら財布の小銭を基金箱に移して貯金していくというとても画期的な基金で、もうすでにけっこうな金額が貯まりまして……」 「…………」
コンセプトと達成金額を説明していく。すると、菊地原が何故か疲れたような顔つきで言ってくる。
「その〝歌川基金〟ってさあ、貯めて何に使うわけ?」
そのとき、世界が止まった。
菊地原プロと歌川名人は、三門市の平和を護る界境防衛機関「ボーダー」に所属する隊員だ。テレビや街のポスターで嵐山隊はよく見かけるが、二人の所属する隊は朝の情報番組に登場することはないらしい。街の防衛は同じでも、担う専門任務が違うのだそうだ。当然、テレビや街のイベントに登壇する嵐山隊のようにマグネットやタオル、ポスターなどの関連グッズ(?)というものが発売される未来はないらしい。残念な気もするし、助かった気もするし、なんとも複雑な心境である。
「……歌川くんが経済的に困ったときに紫の薔薇の花束と共に『応援しています』と匿名で贈る、とか?」
何故か険しい顔つきになった菊地原プロが犬歯を見せてきた。
「重い……」
「え、まだまだだよ? 自分もっといけます!! やらせてください!!」
真澄が瞳に炎を灯すと、菊地原プロは何故かこめかみを押さえた。
「あのさあ、歌川はぼくと同じ隊で任務についているからきみよりよっぽど収入はあるし、よほどのことがない限り困窮しないでしょ」
「た、たしかに」
「それよりさあ、宇田川。きみさあ、テスト期間はいつも歌川と隣の席になるんだからわけわかんないことしないでもっと普通に仲良くしたら?」
宇田川真澄は女子の中で、歌川遼は男子の中でその名の通り、出席番号が早い。その都合で今のクラスではよほどのことがない限り、出席番号順の座席で受ける定期試験期間と模擬試験日は彼と真澄は隣の席同士の関係なのだ。
だが、緊張の余り、真澄は歌川名人が隣にいらっしゃる右半身の挙動が毎回小刻みに振動したり、挙動がおかしくなったりするのだ。自然な会話など生まれるはずがない。それなのに、歌川は特にどうということもなく、爽やかに微笑んで「がんばろう」とあたたかい励ましを送ってくれるのだ。
「も、もったいなくてそうそう話せないよ。覚えた単語が緊張で溶けちゃいそうになるもん」
へにゃりと情けなく眉の力を抜いた真澄に、菊地原プロは何故か大きく吹き出した。
「まあ、せいぜいがんばりなよね」
「う、うん。今日の古典の小テスト、がんばろうね。菊地原くん、いつも聴いてくれてありがとう」
真澄は、菊地原のことを、歌川と話す口実にしているわけではない。ただ歌川のやさしさと素晴らしさを直撃し、爆発しそうで持て余してしまうどうしようもない真澄の気持ちを、彼はいつも呆れながら耳を傾けてくれるのだ。
歌川に抱く真澄の気持ちには、きっと、まだ、はっきりとした名前はない。
分類するのならば、「憧れ」だ。けれども、模擬試験のスケジュールが見えなくて背伸びを繰り返す真澄にこっそり彼が隣から渡してくれたメモ。掃除時間に彼が同じ班の生徒の代わりに大きなゴミ袋を持つ姿。そうした彼の何気ないやさしさに出逢うたびに、日増しに憧れの気持ちは大きくなっていく。膨れ上がる気持ちの成長は、〝歌川くん基金〟でみるみる数値化されている。
「菊地原くんが困ったときにもこの貯めに貯めた基金を紫の薔薇と共に贈るからいつでも力が、財力が必要なときは言ってね」
「……歌川の彼女枠は正直わからないけど、おもしれークラスメイト枠なら宇田川もいい線狙えるかもね」
なにやら菊地原プロが告げた気もするが、真澄はラ行変格活用で頭がいっぱいでそれどころではなかった。
「えへへへ」
にこにこと頬を朝から緩むのに任せている真澄に、登校したばかりの菊地原士郎が目を丸くした。
醒めた調子で言う。
「……朝からおめでたい奴だね、宇田川は」
「おはよう! 菊地原くん!」
律儀に朝の挨拶をしてくれる菊地原である。真澄も頬を緩ませたまま、元気いっぱいに会釈する。
「菊地原くん聴いて!」
「はいはい」
「ありがとう!」
「はいはい。で? なに? 早く話しなよ」
菊地原プロは今日も元気だ、絶好調に言葉が
「長期目標を用意すると良いって、昨日の集会で進路指導の鈴木先生からお話があったでしょう?」
それがどうしたのだ、という胡乱な目つきに先を促され、真澄は両手を合わせて笑いかける。
「そういうわけで、例の〝歌川くん基金〟は、将来歌川くんの結婚祝いにお贈りするためのフラワースタンドに使うことにしました! 備えあれば憂いなしだね」
真澄は菊地原に宣言し、いそいそと今日の朝読書の友だちを紹介した。じゃん、と。
『Flower Shop 楓』からもらった花のカタログだ。昨日の進路集会のありがたい講話に深く感銘を受けた宇田川真澄は、そのあとに出発した夕方の愛犬太郎の散歩コースを蔵先町に変更したのだ。
「うわ、絵に描いたような晴れやかな顔と曇りなき
「ありがとう!」
「褒めてないから」
何故か犬歯を見せてくれる菊地原である。きょとんとまばたきを返し、真澄は付箋を貼っておいたページを開いた。
「どんなフラワースタンドがいいかな?」
フラワースタンドとは、立派なスタンドに優雅に華麗に大胆に飾られたアレンジ花のことだ。店の新規オープン時などに入り口で飾られているのを見かけるあれのことだ。
朝のローカル情報番組と祖母の話からヒントを得たのだ。お祝いや応援にはこれだ。
真澄の祖母は書家だ。仕事の傍ら、子ども向けの書道教室を開いている。つい先日、児童館がリニューアルオープンした。そのセレモニーに協賛企業からフラワースタンドが贈られた。それぞれの贈り主の名札とセレモニー式次表を担当したのが祖母だ。
そのセレモニーの様子を、朝のローカル情報番組が紹介してくれた。お天気情報によくゲスト出演してくれる嵐山ナントカさん? と部隊が同じだという、艶やかな黒髪をショートボブにした女の子がリポートしてくれていた。そのリポート中、黒髪の乙女は祖母の題字に微笑んだのだ。「とても美しい字ですね」と。
その一言に祖母は舞い上がった。普段は穏やかでたおやかで物静かな祖母ではあるが、何を隠そう、大の宝塚歌劇団ファンなのであった。〝ご贔屓さん〟〝贔屓ジェンヌ〟似のそのひと、つまりは一番好きな歌劇団俳優に似たその少女に褒められて、祖母は有頂天になったのだ。それ以来、祖母はにこにこと楽しげに微笑みながら、その少女――涼しげで大人びている面差しだがまだ中学三年生らしい――木虎さんがローカル情報番組に出るときは欠かさずチェックする日々を送っている。
嵐山隊が三門市のイベントに登場する機会があれば、祖母はうきうきと申し込みをする。はがきに記載する住所氏名もアンケート内容も番組感想も応援メッセージも、何度も何度も入念に筆で練習してから挑むという気合いの入り用だ。隊長の嵐山ナントカ? さんをはじめ、彼らの嵐山隊ファンは多いと聞く。祖母の流麗な書が入ったはがきでさえ、抽選にはなかなか当たらない。力の限りペンライトを握りしめアイドルのステージを応援しに行くファンの如く瞳を煌めかせながら、嵐山ナントカ? さんの掲載雑誌や出演情報番組について熱心に教えてくれるファンガールやファンボーイもこの一年C組にだっている。けれども、祖母のファン活動は彼らのようなファンガール・ファンボーイのそれとは少し違っていた。彼らがテレビやラジオに登場しない日でも、彼らがゲスト出演してくれるイベントに当選しなくても、街で彼らの取材や撮影に遭遇せずとも、街を防衛してくれている彼らがすぐそばにいてもいなくても、ただ静かに背筋を伸ばし襟を正し、まっすぐ書に向かい、楚楚と日常生活を送るのだ。
――街をいつも護ってくれている木虎さんに恥じないファンで在りたいの。それは、木虎さんたちボーダーの方々が、身も心もひたむきに注いでこの三門市と私たちを護りたいと思ってくれる善き心もそのまま大切にしたいということなのよ。それには私たち大人がそれに値する街を作らなくてはいけないわ。そう思ってくれる街に住むのにふさわしい素敵な大人で在り続けるには、品行方正を心がけないとね。
木虎さんのサイン色紙を納めた額縁を見せてくれた祖母は、真澄たち姉弟にそっと耳打ちしてくれた。木虎さんの活躍を、木虎さんが護ってくれている日常を、街を護りたいと願ってくれているその想いを大切に護るのがファンの務めなのだ、と。夢見る少女のようにはにかむ祖母の笑みは、やわらかくてやさしくて、とびきり可愛らしかった。
歌川遼に対して宇田川真澄が抱いている気持ちに、名前はまだない。
けれども、誰よりもはるか何千里も先に進んでいるのに、誰よりも遠くにいるのにずっと周りをよく見てくれているところも、快く誰にでも分け隔てなく手を差し伸べてくれる気配り上手でやさしいところも、大人びているのに実は笑いの沸点が低くてすぐに笑ってくれるところも、笑い声を堪えきれないときや近しいひとに見せるときの笑みは切れ長の眦が、きゅう、と丸くなって幼く見えるところも、それから小テストの最後の欄はいつも〝はらい〟が伸び伸びとしているのに先がほんのり丸くなっていて可愛いところも。そして、真澄の字を見ると「綺麗だな」とやわらかに目を細めてくれることも。
それらを思うだけで、真澄はいつも胸のあたりがきゅう、となる。痛むのではなく、そわそわ、ふわふわ、きらきらしているし、どくどく、どきどきもした。言葉にならないこうした不思議な気持ちも、歌川と出逢い、歌川と少しずつ交流をしていくなかで全部知っていったものだ。それまでは知らなかったものだ。
川縁でぴかぴかの石を拾ったときのようにわくわくどきどきするこの素敵な気持ちを、真澄はもっと知りたくて、この気持ちも言葉にしたくて、歌川の素晴らしいところも引き出しの宝箱に仕舞っておきたい一方で世界中に教えたくなったのだ。平安朝のイタリア男・在原業平のように「ここで一首」と歌を詠むのはとてもできそうにはないが、手紙ならばできるかもしれない。苦手だった本も読み始めるようになった。国語の予習復習にも取り組むようになった。居残り常習組だった小論文も時間内に提出できるようになったし、国語の成績も上がってきた。
歌川の結婚式にお贈りするフラワースタンドには、歌川のおかげでできるようになったことをぜひとも来場者の皆様にも広く知らしめてその感動を分かち合いたい。便箋では伝えきれないだろうから、小冊子を作る方法について今から勉強する必要があるだろう。
そう説明すると、半眼でご静聴くださっていた菊地原がぽつりと零した。
「冊子じゃなくて巻物にしたら?」
「そのこころは?」
「五メートルもあれば足りるんじゃない。知らないけど」
不確かな情報であることを忘れるな、ときっちり言い添えてくれる菊地原はやはりいいひとだ。
「直江状だね」
ふむふむ、と真澄はうなずいた。徳川家康が上杉景勝に送った書状に対する返事を、景勝の重臣直江兼続が代理として送ったことで有名なベリーベリーロング書状である。
書展でお馴染みの二×八尺つまりは六〇×二四〇センチメートルの画仙紙もなかなかのお値段がするものだ。それよりも長い長い直江状クラスを目指すとなると、もっと費用がかかるだろう。本番だけでなく練習用だって必要なのだ。今日は放課後に書道部部室のカタログを確認させてもらわねばなるまい。〝歌川くん基金〟にもますます力を入れねばなるまい。歌川は呼吸するのと等しいリズムで毎日善行をしている。同じ一年C組の教室で真澄がそれを刮目する機会も、それを見た真澄が財布から小銭を基金箱に移すのも毎日あるということだ。入学してから半年。毎日見てきたのだ。
鼓動がドラムと木霊する勢いで、どきどき、どくどくと音を立て始めた。胸を押さえ、真澄が目にも心に炎を燃やせば、
「うわ、うるさ……」
思い切り菊地原に顔を引かれた。
いつも通り皆がめいめいに好きなように過ごしている朝の教室である。寝ぼけ眼をこすりながら授業で当てられる担当箇所を見直している子もいるし、英単語小テスト対策に赤シートと単語帳を広げたままうつらうつらしている子も見える。むしろ昼休みよりはずっと静かである。
真澄は首を傾げつつ、『Flower Shop 楓』のカタログを掲げる。
「それでね。まず目標を定めておきたくて……。どんなフラワースタンドがいいかな?」
あらん限りのありがとうとおめでとうを込めてお贈りする所存だが、結婚披露宴は生涯で一度の晴れ舞台だろう。歌川とそのお相手の方にぜひとも喜んでいただける至高にして究極のフラワースタンドをお贈りしたいものだ。児童館セレモニーの紹介番組で木虎さんがリポートしてくれていたスタンドは何色だっただろうか。祖母がDVDにダビングしていたものを見せてもらおう。そういえばこのほど新装開店した駅前のラーメン店にも飾られていた。どんな形でどれくらいの高さだっただろうか。部活後に寄ってみようか。
真澄はそんなことを話しながらフラワースタンド見本の一番目に掲載されているものを指差し、菊地原に助言を求める。
菊地原は顔をしかめた。猫に似た吊り気味の瞳が少しだけ閉じられている。
「すごく饒舌になる……どれも同じでしょ」
「う、ん……?」
真澄は目をしばたたく。
少なくとも飾る花の種類に本数、それから段数。スタンドの大きさや材質で値段も予約に必要となる日数も異なるようなのだが。特に特大サイズとSサイズとでは値段のゼロの数が違う。だが、真澄と同じ高校一年生にして学業の傍らに防衛機関ボーダーの隊員として、日々、この三門市の防衛任務を担って収入を得ている菊地原からしたら些細な違いでしかないのかもしれない。そんな菊地原と同じ部隊で日夜働いていらっしゃる歌川にとっても。
残念ながら親戚の結婚披露宴にまだお呼ばれしたことがない真澄にはフラワースタンドのスタンダードがわからない。彼らの収入を参考に一番高い値段から絞り込めばよいのだろうか。効率的だが、それはそれでいと味気なしのような――と首を傾げたところで、後ろから声がした。
「それ。サンダーソニアって名前なんだな」
歌川遼が菊地原の真後ろからカタログを覗き込んでいる。
つまり、真澄のすぐ斜め後ろにいる。歌川が、すぐそばに。
「ひゅ」
真澄の息が止まった。
歌川が「知らなかった」と切れ長の眉と目を上げている。歌川が。歌川の端正な顔が。ものすごく近くに。真澄の斜め後ろに。ある。歌川遼が。すぐそばに。いる!
かッ!
理解した途端、全身に火が走る。
がたん。椅子が倒れた。立ち上がって左に避けた真澄に菊地原がコメントした。
「やかましい」
「ごめんなさい……」
顔が熱い。というよりも、全身が熱い。身体中から煙がしゅうしゅう上ることを自覚しながら真澄は頭を大きく下げた。
「宇田川さん! ごめん! 大丈夫か? すまない。驚かせるつもりはなかったんだ。でも、びっくりするよな急に声かけたら」
歌川が、こちらに手を伸ばしているのが見えた。が、彼は、はっと両目を開き、すぐに身体を引いた。彼は腕を伸ばしながらかがむ。そして、ゆっくりと丁寧な所作で椅子を立たせた。音はひとつもしなかった。真澄を驚かせないよう注意してくれたらしい。
切れ長の眉と瞳。この秋一番の近さで見た歌川のそれは、朝からとても爽やかだ。veryどころかamazingly爽やかである。そして、朝でも夕方でもいつでも今朝も惜しまずに振る舞ってくれるベリージェントルソウル。どうしよう。どうしたらよい。どうしてくれようか。走り出すわけにも行かず――予鈴が鳴るまで十分は切っている。だが、チャイムの前に――
どっどど どどうど どどうど どどう!
猛烈な勢いで心臓がドラムを叩いた。
口元があわあわしてしまう。ひとまず震える右手で髪を耳にかけ直した。それから左手で脈打つ左胸をぎゅうと押さえる。震えに気づかれませんように、激しいビートが音漏れしませんように、と祈るような思いで真澄はなんとか席に座り直した。
「あ、の、ありがとう歌川くん……おはようございます」
上目遣いに挨拶をして、自身の左手に右手を重ねる。ぎゅう、と。
眉を少し下げ、すまなそうな表情をした歌川がそっとうなずいてくれた。
「おはよう。宇田川さん。菊地原。急にごめんな。ボーダー近くのパチンコ店でよく見る黄色い花が見えたから、つい」
「そろそろ条例に明記してくれないかなあ。朝から轟音にもほどがあるんだけど……おはよう、歌川」
菊地原が言った。何故か机にぺったりと顔を突っ伏しながら。
「はは。そうかもな。でも、あの店は夜勤明けの二時限目講義まで寝落ちないよう遅刻防止ですぐ入れるから便利だって諏訪さんたちが言ってたぞ?」
「需要があるから閉店してもすぐ次の新規店舗が入るってことだよなあ」
「そうだなあ。リニューアルなのか新規参入なのか、オレもよくは知らないけど、あの店はよく入り口でお祝いの花を飾ってるものな。おまえの言うように需要と供給が成り立っているんだろう」
「諏訪さんたち、いいお客様なんだろうね。でも、うちの風間さんは諏訪さんちで一旦仮眠してから大学に行く方が集中できるし効率的だって言ってたけど」
「こら。言い方……うん。でも、なんというか、さすが風間さんだよな」
「うん。風間さんだからね。然も有りなん」
自隊の隊長風間さんの話をする二人は、いつもまぶしげで、誇らしげな声と顔つきになる。きらきらしたまぶしいものを見るときの瞳をしている。同級生の中でも大人びている彼らが、少しだけ幼い少年のような顔つきなるのがなんだか微笑ましい。真澄も頬が緩んだ。と――
歌川がこちらを見下ろしてきた。まっすぐと。
「何かお祝い事?」
「う、うん。あ、ありがとうとおめでとうを、おくりたくて……」
つっかえながら真澄は答えた。まさか「将来歌川くんに日頃の感謝と人生の門出とこれからの新しいステージへの祝福をお祈りしたフラワースタンドをお贈りするので今から一番良いものを探しています! よろしくゥ!」などと、きらりと白い歯を見せて元気よく笑いかける度胸も余裕もご用意できるはずもない。
「じゃあ、とびきり豪華にしないとな」
歌川は朗らかに笑った。にっこりと。そして、「どれどれ」といった風に、菊地原の後ろから再びカタログを覗き込んだ。
すい。硬そうで筋張った長い指が、目の前で、動く。
「へえ。紫の薔薇もあるんだ。綺麗だなあ……。確か、薔薇は青色遺伝子を持っていないから、青い色の花を咲かせるまでのプロジェクトが長く険しい道のりだったって中学の理科で先生が言ってたよな」
「うん」
菊地原が緩やかに首を動かした。
「そうかも。でも、赤と青を混ぜると紫になるってことは、紫のものは青よりも咲かせやすいんじゃない? 昔から漫画でもあるくらいだし」
「ああ。紫のバラのひと……!」
ぎょっ、と目を開いた。
「う、たがわくん!?」
しってるの、と真澄は脊椎反射の勢いで声をあげた。
「うわ」
菊地原が顔をしかめた。
またしても椅子を倒してしまった。がたんと音を立てていた。勢いよく。「しつれいしました」と声をかけて椅子を粛々と戻す。
漫画『ガラスの仮面』の紫のバラのひと、速水真澄は、主人公北島マヤを応援してくれる御曹司のことである。彼が〝紫のバラのひと〟と呼ばれる理由は、マヤの演技にかける情熱に心打たれ、素性を隠した速水が贈り続けるファンレターに添える花が、紫色の薔薇だからだ。速水は、影ながらひっそりと、夜道を照らす月明かりのように、心くじけそうなマヤを時には励まし、時には叱咤してくれる、まさしくファンの鑑のようなひとである。彼は、名を明かさずに「あなたのファンより」と紫の薔薇を贈り、マヤもまた駆け出しの頃から応援してくれるそのひとに〝紫のバラのひと〟と感謝し続け、今日もまた演技の道に情熱を注ぐのだ。
宇田川真澄の〝歌川くん基金〟のプロジェクト目標のひとつは、歌川が経済的に困ったときには紫の薔薇の花束と共に「あなたを応援しています」と匿名で贈ることが決まっているのだ……つい一昨日からだが。
「うん。姉さんと母さんが熱心に読んでるのを、オレも借りて読むんだ」
面白いよな、と照れたように頬を搔く歌川の眦の角が、丸くなっている。きゅう、と。
「宇田川。歌川にも見てもらえば?」
「エ!?」
またしても真澄の呼吸が止まった。ひゅ、と。
「え、と」
プロジェクト目標である本人が、将来お祝いをお贈りすることになる結婚式披露宴の主役である、フラワースタンドの贈りびと……ではなかった、贈られびと(?)のそのひとが、カタログをセレクトしてくれる。極秘プロジェクトが始めから歌川本人に知られるのではないか。それはつまり、極秘プロジェクト終了のお知らせなのではないか。
しかし、サプライズプレゼントは相手の好みを熟知していないと失敗に終わる学説があると聞く。
と――
「恐ろしい子……」
菊地原が迷惑そうに眉を寄せ、左右の耳を塞いだ。
「お、菊地原も読むんだな。次のコミックス発売が待ち遠しいよな」
歌川が笑っている。にこにこと。朗らかに。爽やかに。真澄のすぐ目の前で。
どっどっ、どどうど、と激しく鼓動を打つ真澄の心臓は、まだ鎮まりそうにない。こんなにも予鈴が鳴るのを待ち遠しく思った朝はあっただろうか。いや、ない。