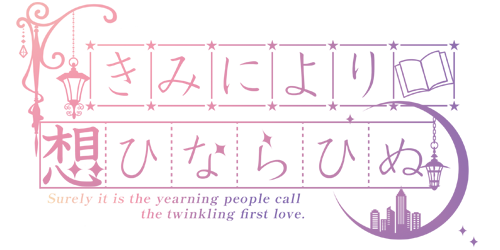そよぐ風はまだ冷たい。
少女は指先に息を吹きかけた。吐く息はあたたかいが、空気を白く染めはしない。風邪の予防対策で換気された窓から届く風は、少しだけ冷たいが、底冷えのするようなものではない。校庭では梅がやわらかに花開いている。すぐそばまで春が来ているのだ。
少女はしみじみとした思いで呟く。
「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」
一生懸命覚えた『おくのほそ道』の序文が今はとても懐かしい。覚えたのはちょうど一年前の今頃の季節だ。中等部三年の特別考査課題のひとつだった。
一月の特別考査がようやく終わったと思ったら、二月には英語検定試験TOEFLが手招きしている。三月には学年末考査が両腕を組んで待ち構えている。まさに一月は行き、二月は逃げ、三月は去って行く。あれからもう一年。光陰矢の如し。月日が経つのは、本当に早い。
二月である。暦の上では立春を迎えた。換気中の窓から産地直送で届く風も冷たいものの、降り注ぐ陽光の彩度や温もりはあたたかい。冬の窓際席組の特権である。昼休みの日光浴はまさに天国と言えた。
「草の戸も住替 る代 ぞひなの家 」
前列の物知り博士こと菊地原士郎が合いの手を入れてくれた。いいひとである。
「面 八句を庵 の柱に懸置 」
少女も返し、ぺこりと頭を下げた。
「ありがとう菊地原くん。去年は覚えるのに苦労したのに、一度覚えたらなかなか忘れないものだねえ」
「まあ、後ろから聞こえたらね。口ずさみたくなるでしょ」
菊地原士郎が眠たげな目つきで言ってきた。三学期の席替えで菊地原とは隣同士の間柄ではなくなった。しかし、窓際特等列、前後の配置となったので今でもほのぼのとした交流は続いている。
「うん。祇園精舎の鐘の声とか、春はあけぼのとか。聞こえ始めるといつのまにか皆で合唱しちゃうよね、食う寝るところに住むところ~って」
「それは寿限無」
さすが菊地原プロである。いつでもどこでも誰にでも丁寧に的確にツッコミを入れてくれるプロフェッショナル意識を忘れない。進学校生あるある事項のチェックにも厳しい。
「それにしても一年が過ぎるのって本当に早いよねえ。二月ももう半分終わっちゃうねえ」
しみじみとした思いで言う真澄を、菊地原がまじまじと見つめてくる。
「……あのさあ。宇田川。やる気あるの?」
「え」
ぱちぱち。真澄は目を大きくしばたたいた。
やる気ならばある。TOEFLは明日二月十五日が本番だ。窓から降りる午後の陽射しに微睡みを誘われかけている情勢ではあるが、今も過去問題プリントを読み直している最中だ。
「いや、ない」
「はい……」
醒めた口調の反語表現に真澄は姿勢を正した。なんとなく気まずいものを感じたのだ。プリントを広げてはいるものの、あたたかな陽光をたっぷりと浴び、ひなたぼっこをしている猫のような心地を存分に味わっていることは否めない。
ため息交じりに菊地原が口を開いた。
「今日は何日」
「二月十四日金曜日です」
「……今日は何の日」
「TOEFL前日です」
突如始まった口頭試問に真澄は内心焦ったが、机からプリントを持ち上げてみせた。
「はあ」
またしても果てしない巨大なため息をお見舞いされた。猫に似た菊地原プロの吊り目がなにやら険しくなっている。そうじゃない、と。
弾かれたように真澄は叫んだ。
「えっ、明日だよね?」
検定試験は明日の土曜日に行われるはずだ。先週は登校しなくて良い休日だった。はずだ。真澄が口をぱくぱくさせると、菊地原がげんなりと言った。
「だから、そうだけどそうじゃない」
二回言った。
「?」
さっぱりわからずに、真澄は菊地原に目で問いかける。じ、と見上げる。
菊地原の猫目が信じられないものを見たときのように険しくなった。極寒の日に半袖で遊びに来た友だちを見つめる、あれだ。
「だから。そうだけどそうじゃないって」
眉間に皺を寄せたまま、彼はのたまった。いつも通りのクールな調子で。
「宇田川、本当にやる気あるの? 歌川のことがそんなに気になるならバレンタインに便乗して贈ってみるとかしたら? 今日は休み時間のたびに歌川が呼ばれて教室から出て行くのも戻って来るたび荷物増えてるのも、ずっと目で追いかけてはしょんぼりしてるじゃん。朝からずっと。この繰り返し。このあとクラス替えだってあるわけだし贈ってみるチャレンジをしたら? ちなみにTOEFLはちゃんと明日だよ。よかったね」
ぎょっと目を剥いた。今、なにやらすごいことを一息に指摘された気がする。TOEFLは明日。よかったよかった! よかった? よくない!
かッ!
火が、走った。
脊椎反射の勢いで真澄は立ち上がった。弾かれたように。がたんと。後ろで椅子が大きな音を立てた。
「ナ、ナンデ!?」
「うるさ……」
菊地原がクールに言う。にべもない。だが、ざっついぐざくとりーすぎるお言葉である。真澄は頭を下げ、椅子を戻すべくしゃがんだ。どっどっどっどっ、と心臓が激しくドラムを叩いていた。
「歌川とクリスマスにイルミネーションだって見たんでしょ」
「う」
菊地原刑事の追及に宇田川真澄は息を止める。
取調室ではなく、昼休みの教室である。デスクライトの代わりに春の初めのやわらかな陽光が窓際席族の二人を照らしている。ほこほこと。
「あんなにきらきらした街の灯は見たことがないってぼくに教えてくれたじゃん。敢えて。わざわざ。ご丁寧に目をきらっきらさせながらさあ。二学期最後の図書当番。エアコンの電源がなかなか反応しなかった寒い図書室でさあ。とっておきの心温まるエピソードがあるんだって、やけににこにこして」
「うう……」
真澄は更なる追い打ちに頭を抱えた。
歌川遼と宇田川真澄がクリスマスの時季にイルミネーションを見た。
それは事実だ。真 である。命題である。嘘ではない。まことだ。夢でもない。夢だけど、夢じゃなかった!
ただし、愛犬太郎の散歩コースのひとつである駅前通りをクリスマスシーズンに歩いたところ、偶然にもコンビニ前で歌川と会った。真澄の小学二年生の弟もいたし、当然、宇田川家の柴犬太郎も一緒に居た。そういうことである。 そして、その翌週にシフトがあった図書当番当日は、エアコンのリモコンスイッチの調子が悪かった。何度ボタンを押しても反応してくれなかった。コートを着込み、マフラーをぐるぐる巻いた二人は、司書教諭が定例職員会議から帰還されるのを待った。そういうときに限って、貸し出しにも返却にも生徒が代わる代わる現れるものである。彼らも交えて小学二年生のように押しくらまんじゅうやドッジボールをして暖を取るわけにもいかず、カウンター席に座った菊地原と真澄の一年C組図書委員は、歯をカチカチ震わせながら代わる代わる六角鉛筆を転がしてクロストーークを交わすことで寒さを忘れる努力に励んだのであった。
ちなみに各面それぞれに割り振ったテーマは確か、一の目が出たら「冬の定番! 至高にして究極のメニュー!」で、六が出たら「とっておきの冬の心温まるエピソード」というような内容であった。長引いた職員会議を終え、使い捨てカイロとホットレモンを司書教諭が差し入れに来てくれるまで、二人は鉛筆を転がし続けた。
半泣きのまま菊地原警部補と向き合う真澄であるが、やはり救援はまだ来そうにない。そう。今日は二月十四日金曜日。TOEFL前日。バレンタインデー当日である。進学校といえど、この六頴館高校一年C組の教室も、どこかうきうき、そわそわ、ふわふわ、きらきらというような華やいだ空気が朝から醸し出され、昼休みの今は飽和状態となっていた。
二月から本格的な受験シーズンに入り、三年生も自由登校になった。けれど、今日は偶然にも三年生の登校日だ。「日頃のお礼を伝えよう」「卒業前に感謝や想いを伝えよう」とクラスメイトが鼻息荒く三年生の校舎に向かう姿を何度も見送ったし、反対に、教室まで足を運んでくださった三年生がニコニコしながらクラスメイトを手招きしている光景も見かけた。要するに、休み時間のたびに教室内人口密度が著しく減るのである。真澄の元へ友による増援はまだ届きそうにない。
「歌川にさあ、『風邪に気を付けような』って微笑まれて、思いやりあふれる笑顔とまぶしさとあたたかさとやさしさに感激して、火傷しそうになったって言ってたじゃん」
菊地原が静かに言う。
「コンビニ前で半分こにした中華まんを喉に詰まらせかけて。きみ、あの日の熱さをもう忘れたんだ?」
忘れていない。忘れようがない。忘れるはずがない。むしろ思い出しては爆発しそうになる。たとえば、たった今。今、この瞬間も菊地原が丁寧にあの日の会話を再現してくれるので心臓が爆発しそうなほど音を立てているのだ。どくどく。どんどん。どっどっどっどっ。そろそろ本格的に弾け飛ぶに違いない。
「は、半分こじゃないよ。不均等三分割だもん。弟も一緒にいたもん……」
のろのろと弁明する真澄に、菊地原は口の端をにんまりと吊り上げた。
「ふうん?」
あれは本当に熱かった。あの日はとても寒かったはずなのに、とびきり熱い思い出となった。思い出すだけで、胸のあたりがきゅう、となるし、頬だけでなく、耳も首も熱くなる。
弟が目を潤ませて「お腹空いたよう」とおねだりしてきた。しかし、真澄はすぐに返事ができなかった。その晩は祖母が弟の好物クリームシチューを作ってくれる日だったのだ。中華まんを真澄と折半するにしても、小学二年生の弟からすれば夕飯前に食べるには多い分量だ。どうしたものかな、と真澄が窮して弟の頭を撫でていたら、歌川が提案してくれたのだ。こちらに思い切り笑いかけながら。
――一緒に悪いことしないか。
歌川は中華まんを真っ二つに割り、更にその片方だけを折半した。小さく二分割したものをまず真澄の弟へ、続いて真澄に差し出してくれた。最後に残った大きいものは歌川自身が担当してくれた。弟だけでなく、真澄の分量も、祖母のクリームシチューを姉弟がどれだけ楽しみにしているのかを汲み取ってくれたのだ。
三人で食べた中華まんは、熱かった。とても熱かった。歌川から受け取るとき、指先がほんのり触れ合った。瞬間、真澄の頭から狼煙が上がった。熱かった。今年一番の冷え込みを記録した日なのにものすごく熱かった。弟がおろおろと水筒の麦茶を差し出してくれなければ確実に火傷していた。弟に感謝。そもそも歌川が「風邪に気を付けような」と声をかけてくれたのも、弟の学年で風邪が大流行しているという話題がきっかけであった。そのひとと駅前通りの煌めくイルミネーションを眺め、中華まんをシェアするこの冬最大の幸運が巡ってきたのも弟の遼太と愛犬太郎と一緒に散歩に出向いたおかげである。感謝しかない。
「宇田川。ちょっと、顔貸してくれない?」
「え」
カツアゲだ。これは俗に言うカツアゲなのでは? カツアゲだろう! 菊地原警部がカツアゲをしようとしている!
目も口もあんぐり開いたまま凍りつく真澄に、菊地原プロは巨大なため息をついた。
「ちゃんと見たら? 現実」
「はい」
「まあ、いいや。これから見せてあげる。ほら、早く来なよね」
「はい」
真澄は肩を落とし、どこまでも醒めた口調と顔つきの菊地原警部に連行された。さながら刑の執行に向かう咎人の心地だ。
「菊地原、現着」
菊地原警視正が醒めた口調のまま言う。小声で先導してくれる彼に導かれ、真澄は口のファスナーを閉じ、両手で口を覆ったまま一年B組の靴箱陰に身を潜めた。
「はい、宇田川。これが現実だよ。一言どうぞ」
真澄は息を止めた。目を見開いて――さすがに冷や汗を落とさずにはいられなかった――、真澄は、こちらを見下ろしてくる菊地原に、目も口もぽかんと開いたまま向き直った。
「…………」
体育館裏や屋上、校門などといった、学ランに立派な刺繍が入った人々によるクローズでZEROな展開が始まることはなさそうだ。生徒玄関は靴箱コーナーである。
す、と右の人差し指で一点を示す彼に、なにをどう言えばいいものか――というよりもあまりにもすごくすごくすごすぎる光景に呼吸も思考も停止した。
彼の指が指し示したのは、一年C組の靴箱男子列だった。間違い探しをするとしたら、誰もが真っ先に指を差すであろう靴箱があった。ぎっしり。いや、みっしり。所狭しと直方体に立方体、円柱形の箱。クッション性のある大きくて可愛らしいふわふわもこもこきらきらした封筒。それらが所狭しと大集結していた。
そう、ネームプレートに書かれていたのは、歌川遼そのひとの名前であった。皆、歌川に贈られたチョコレートギフトとやらだ。
菊地原が丁寧に言い直した。
「ほら、宇田川。これが現実。今の心境を一言」
「…………」
はくはく、と唇をわななかせるしかない。震える膝を叱咤し、両の手を開いては、握る。結んでは、ほどく。ごくり、と唾を飲む。そして――
「げ」
「げ?」
「げ、芸術点たか~い……?」
しばらく間を置いてから、ひとまず首を傾げる。
「……どうしたの菊地原くん。歩いてもないのにどうしてつまずくの?」
「……いや、現実見ろとは言ったけどさあ、こうも現実を拡大解釈して受け入れるとは思わなかっただけ」
うめき声をあげながら、のろのろと起き上がる菊地原に、真澄はうなずいた。
「歩くときは注意したほうがいいかも」
「わかってるけど」
ようやく姿勢を正した彼は、なぜか怒っているようにも見えた。八拍分の沈黙を挟んでから言ってくる。
「あのさあ、気づいてなかったわけ?」
「気づいてるよ」
即答する。歌川遼は、クラスで一番、いや、少なくとも学年でいっとうベリーベリーベリージェントルソウルをお持ちで、誰にでもいつでもやさしく手を差し伸べてくれるひとなのだ。憧れの気持ちを抱かない方がきっと難しい。これは、真澄よりも勇気のあるひとたちの気持ちの結晶なのだ。自分には出せなかったその一歩は、まぶしくて、まぶしくて、少しだけ苦い。
菊地原の口から、長々とした嘆息が漏れるのが聞こえてきた。
「ならいいけどさあ。で?」
どうするの、と言いたげな目つきに、真澄は眉を下げた。どうもしないよ、と――
「その声は我が後輩きくっちー! きくっちーではないか!」
「菊地原くんと愉快なおともだち、かな。こんにちは~」
やけに澄んだ明るい声とどこかのんびりした声音が玄関いっぱいに響いた。
現れたのは、艶やかな黒髪を靡かせた眼鏡の美少女と、曖昧に微笑みながら淡い色素の髪をサイドで子犬の尻尾のように結わえた少女だった。
上履きの学年色を見る限り、どちらも一年生ではない。長いストレート黒髪の先輩が二年生で、子犬めいた――この中で一番小柄だ――サイドテールをふわふわ揺らす方が三年生らしい。その最年長の先輩は二年生に後ろ襟を掴まれている。「しおりちゃん、ぎぶぎぶ。しまるしまる」となにやら苦しげにうめいている。
「いやはやきくっちーよ、よくぞ来てくれた! いや、キミが来てくれることは信じていたとも! しかも活きの良いゲストを産地直送で連れてくるとは! さっすがデキる風間隊エースの中のエースよ!」
澄んだ声で快活に笑う二年生が、ぐ、と左右両方の親指を立てた。
小さな三年生の大きな深呼吸が聞こえてくる。無事に解放されたらしい。
「うわ、なんでいるの。暇なの?」
一転して、嫌そうな顔で犬歯まで見せて、菊地原が言う。
「心外だなあ、きくっちー。なんでも何も、今日はバレンタインデーだ。うってぃーのテトリス実況に駆けつけたに決まってるじゃん」
「絵に描いた暇人じゃん」
菊地原プロは首を傾げる二年生をひとまず無視し、半眼で三年生を見やる。が、三年生は厳かな表情で、きっぱりとかぶりを振ってきた。サイドテールが利口な子犬の尾の如く、凛々しく揺れた。ぶん、と。
「待って。菊地原くん。これにはわけがある」
「なに?」
「栞ちゃんは言いました」
「?」
「明日またここに来てください。本物のバレンタインってやつを見せてあ――」
「いや、もういいから。受験生は早く帰って勉強しなよ」
「えー」
二年生と三年生が口をそろえた。
「はいはい、かえったかえった」
菊地原が醒めた口調でぞんざいに、手で追い払い始めるが、どちらも全然気にしていない。上級生、すごい。黒髪の二年生が額に拳を作って当てた。てへ、と。
「いや、まあ、アタシが先輩を呼んだのは本当。パズルゲーム得意な先輩に〝ドキッ☆うってぃーのバレンタインだよ! チキチキチョコレートギフト詰め放題レース〟模様を解説してもらおうと来てもらっただけ。やっぱり一年生はうってぃーが一等賞かなあ。もうぎゅうぎゅうじゃん」
肩をすくめてみせる二年生とは正反対に、小柄な三年生は奇妙な表情を浮かべていた。眉根を寄せて、なにやら考え込んでいる。
「はい」
三年生が「整いました」と右手を挙げる。じ、と淡い色素の大きな瞳を、〝ドキッ☆うってぃーのバレンタインだよ! チキチキチョコレートギフト詰め放題レース〟の詰め放題レース現場に向けたまま、ゆっくりと唇を開いた。
「まだ完全なみっしりではないかな。五〇グラムの板型ミルクチョコレートパッケージならあと七枚、いや、六枚はいけるはず。ハイミルクチョコレートのボックスなら四箱はギリギリ入る。どちらを入れるか次第で攻略法はだいぶ変わるけれど。一旦そのふわふわの封筒を出して、この円柱を右に寄せれば赤い立方体の隣に板型がまず二枚いける……。それぞれ箱から取り出して、個包装のみの勝負ならばもっといけるよ」
「うわ……」
「おおー! さっすが先輩! だからゲスト解説にお呼びしたんですよう!」
思い切り嫌そうに頬を引きつらせる菊地原に対し、二年生のナントカ栞先輩は、ぱちぱちぱちぱちぱち、とたまらずに感激した様子で拍手を送った。三年生はぐったりとうめく。
「犬飼くんにも結束さんにも朝からしょっちゅう三年A組の現場に直行するよう急かされたからね……だいたいの形状は見たから。何回も何個も見ましたので……」
どうやらこの小柄な先輩は、チョコレート博士らしい。チョコレートのメジャーな箱サイズを完全に把握していらっしゃるようである。
「蔵内くんのところ、もう本当に凄かったよ。靴箱はまだ序の口。机とロッカーと鞄がどえらいことになってた。万国びっくりチョコレート詰め放題選手権とか、人類の新たな空間処理ワザマエへの挑戦を見た気がする。でも、丈夫そうな紙袋もたくさん寄せられていてねえ。ファンの対応も凄い。さすが蔵内かいちょーは日頃の人徳レベルが神がかってるなってそう思った……」
「…………」
示し合わせたわけではないが、元生徒会長・蔵内和紀が所属する三年A組靴箱の方角に向かってそっと十字を切る一同であった。
「一年生のときの蔵内くんの靴箱もそれはそれは凄かったんだよ。紙袋の到着が一刻も早く待たれてた」
内緒話をするように、三年生の先輩が細い両手で筒を作った。それからふわり、と頬の力を抜いた。
「今日の靴箱を見る限り、歌川くんにもそうした伸びしろがありそうだねえ。どの贈り主も他の箱を邪魔しないように、落とさないように、壊さないようにって丁寧に入れてるよね。気遣いの名人歌川くん相手に恥じない真っ向勝負を、贈りびとそれぞれが真摯に挑んでいる気がする」
「さッすが先輩! 歴戦のバレンタイン詰め放題選手権解説を担当しただけある! 先輩、来年も、うってぃーの解説をゼヒゼヒお願いしますよ~!」
「いや、来月卒業するから」
「ゆっくりしていってもいいんですよう?」
「留年だめ、ゼッタイ」
「一緒に最後の高校生活を送りましょうよ~!」
「受験生おかわりはいやだ受験生おかわりはいやだ!」
二年生は三年生に思い切り戯れ付いている。二年生に揺さぶられていた三年生が、ふ、とこちらを見た。右手で拳を作り、左の手のひらをぽんと叩いた。
「そういえば、そちらのお嬢さん、十二月に歌川くんと金の豚まん食べてた子だよね。ほら、小学生の男の子と、金色のふわふわした立派な柴犬さんと仲良く駅前通りで美味しそうに頬張って……」
ひゅ、と真澄は息を呑んだ。見られていた。あの日の思い出を見られていた。何故中華まんの種類をしっかり覚えているのか。
「あと、今日の二限後の休み時間、書道室から帰る歌川くんが三年生に呼……おっと」
書道教室は三年生の校舎にあるのだ。同じ選択書道の真澄も今日のその場面は当然見た。見てしまった。上級生はもちろん、クラスメイトにも他のクラスの子を前にしても、歌川はベリージェントルソウルを忘れずににこやかに対応していた。どこに出しても恥ずかしくない、誰が見ても微笑みたくなる、今日彼に贈り物をした者はよき思い出として生涯その胸をあたためてくれるであろう神対応であった。
それを見るたび、胸のあたりが、もやもやするような、ざわざわするような心地がした。
昼休み。菓子作りの得意なクラスメイトが作ってきてくれたチョコレートケーキのご相伴に与ろうと、友人に誘われても、真澄は辞退した。なんだか食欲がしなかった。ざわざわ波立つ思いは、TOEFLの問題プリントを解き直すことで一旦保留にしたのだ。
ごほん。
三年生はわざとらしく大きく咳を払い、言い直した。
「ええと、そう! 選択書道の行き帰り、歌川くんの背中をそっと見守っている奥ゆかしい宇田川さん!」
「ちょっと」
菊地原プロの制止が入った。思い切り眉と頬を引きつらせながら。
「あっ、ごめんなさい。もう一回言い直しても?」
「遅いでしょ」
待たずに入ったツッコミに二年生の先輩も沈痛の面持ちを浮かべた。
「ウン。遅いです。さすがにアタシもフォローできません……」
「ごめんね。みんなが知ってるひみつなのかな、って」
三年生がしおしおと頭を下げる。やわらかそうなサイドテールが弱り果てた子犬の尾のようにその動きに沿って垂れ落ちた。しおしおと。
「はいはーい! 先輩は今日の発言一旦お休みしましょう」
ぱん、と二年生の先輩が両の手を合わせた。それから細い指で眼鏡のフレームをかけ直すと、すい、と真澄の正面に来た。それから、彼女は顔をうつむけた真澄の頭を、そっと撫でてくれた。あたたかい手のひらが、頭を、髪を、滑っていく。
「まあ、これは大きな独り言なんだけど」
二年生の先輩の澄んだ声が、真澄の耳に届く。
「先月、大きな出来事があったでしょう」
それが起きたのは一月二十日のことだ。四年半前にも起きた。三門市に住む者が、もう二度と忘れられない日。もう二度と忘れてはいけない日。
「この街の防衛組織側のアタシが言うのもなんだけど――ううん、そうならないように最善を尽くすのが務めだってわかってるけど、ね」
その先輩は、笑みを落とした。
「明日が必ずしも来ること、いつでも誰にでも保証はされてないんだよね。だからこそ、『また明日』って挨拶を交わせる関係も瞬間も大事にしていきたいよね」
雲間からほそりと月の明かりが差したような静かな笑みだった。
菊地原は、黙したまま歌川の靴箱を見つめていた。それからつと目線をこちらに向けて、口を開いた。
「宇田川」
「うん」
「歌川に言いたいことがあるなら、言えるうちに言った方がいい」
「うん……」
ありがとう、と唇を動かす。よろしい、というように菊地原はうなずいてくれた。
先月三門市に起きた二度目の大規模侵攻。明日を変わらずに迎えられることのありがたさ。いつも通りの明日が来る幸せを、日々わかっているはずなのに、わかっているつもりでしかなかったことを思い知らされた。一月二十日、それを改めて強く痛感したはずだ。わかっているはずなのに、わかっていたつもりで全然理解できていなかった。
最前線で身体を張ってくれている彼らに、身も心もこの街の防衛に注いでくれている彼らにその言葉を言わせてしまった。それが情けなくて、切なくて。哀しかった。
目尻に浮いた涙をそっと指の腹で拭う。栞先輩はわしゃわしゃと乱暴に頭を撫でた。そして――
「ダイジョーブ! 皆が知っているキミのひみつは、ひみつにしますよ。ちゃあんとね」
右目をぱちん、と閉じ、先輩は細い人差し指を艶やかな唇の前で立てる。
「大丈夫だ! 未来はもう動き出してる!」
「うわ」
どこかの誰かさんの台詞丸パクリじゃん、と顔をしかめる菊地原に、栞先輩は両手をわきわき広げ、
「先輩の決めシーンを邪魔したきくっちーよ、神妙に致せ! わしゃわしゃの刑に処す!」
笑いながら菊地原に突進し、頭をかき回した。
「……ありがとうございます」
真澄がそっと頭を下げると、栞先輩は「いえいえ」と晴れやかに笑い返してくれた。菊地原は心を無にしてわしゃわしゃ髪と頭をシェイクされていた。
「へい、宇田川ちゃん! きくっちーによる現実確認も現場検証も済んだことだし、いっそのこと今年のバレンタインデーのうちに動かしてみないかい? 未来」
びしっ、と右の親指を立て、白い歯にきらりと星を煌めかせた。「大将、未来一丁!」と。
きらりと眼鏡のレンズを――目を煌めかせ、笑う。
「我らが六頴館高売店にも板型ミルクチョコレートは常備されてるんだぜ! なんと、今なら六枚は、〝ドキッ☆うってぃーのバレンタインだよ! チキチキチョコレートギフト詰め放題レース〟会場でも堂々と入り込める算段だ! 若干の余裕があると、こちらの歴戦解説の先輩お墨付きだ!」
子犬めいた先輩が、ぎゃっ、と跳ねた。
「こら! 栞ちゃん!」
「やだな〜! 善き先輩としての助言とアタシ個人としてのアドバイスは別腹ですよゥ!」
「も〜!」
胸を張る二年生に、三年生が鳴いた。牛のように。
「失言連発したわたしが言うのも大変アレですが」
子犬めいた先輩が言う。背伸びして、両の手のひらをいっぱいに広げて栞先輩の口を塞ぎながら。
「友だちは人間に対する最高の尊称なんだよ」
真澄には、まばたきを返すことしかできない。
ふわり。先輩が、思い切り頬を緩めた。
大丈夫だよ、と。
「菊地原くんを見ているとよくわかるもの。いい友だちは善きひとのもとに集うって。類は友を呼ぶとも言うよね。いい友だちを持つ歌川くんが宇田川さんにとっていい子であるように、歌川くんから見た宇田川さんもきっとそうだと思うよ。大丈夫。なるようになる」
「おみくじじゃないんだから」
「そうそう。それが付くとなーんか怪しいぞって思います、アタシ」
後輩二人から冷静に指摘され、子犬めいた三年生は肩を落とした。
「いえ、あの、ありがとうございます……」
「いえいえ。生きとし生けるものに等しく春は来る! もちろん宇田川ちゃんのもとにもね!」
「ね!」
栞先輩と三年生が顔を思い切りほころばせた。
「先輩にもね。テトリス解説するくらいだからさぞかし余裕なんだね。本命受験」
「…………」
菊地原の指摘に三年生がしゅるしゅると肩を下げた。心なしかサイドテールも一回り萎んだように見える。栞先輩がしんみりとした口調で言う。
「そっかあ、今日がバレンタインデーだからあと十日ですよねえ。前期日程」
「それは、そうなんですが……」
この場に呼び出した張本人からの指摘に三年生は思い切り頬を引きつらせていた。
自己紹介なんてしたかな、と真澄は首を傾げた。
油性ペンで上履きにでかでかとクラスも名前も書いていることを思い出したのは、先輩方と別れて教室に戻ってからだった。
学年末考査が終わった。まもなく三学期のゴールが近づいている。高校一年生も終幕が近い。
思えば、あんなこと、こんなこと、いっぱいあった。
この一年C組のクラスの一員になってから過ごした日々が、本のページのようにふわ、と浮き上がっては、次々と捲(めく)れていく。
苦手意識の強かった国語の成績が徐々に上がっていったのも、予習復習も、本を読むことも楽しいと思えるようになったのも高校一年生になってからの出来事だった。
ベリージェントルソウルをお持ちの歌川遼に抱く気持ちには、まだ、名前は付けていない。けれど、その輪郭は、歌川に対する気持ちの正体を知りたいと願うようになった初夏よりもずっと色濃く見えるようになっていた。
「菊地原くん、眠そうだね」
「春休みの試……」
ばっ! 素早く真澄が腕でTの字を作る。タイム要求に気づいてくれた菊地原は、欠伸をしながら「どうぞ」と目つきで言った。
「菊地原くん。機密は人命より重い。大事なところはぼかし、お願いします!」
日曜朝の戦隊番組で一年間、小学二年生の弟指導の下で真澄は学習したのだ。知りすぎる者は組織に消される。きりりと眉を引き締めた。
「はい、はい」
菊地原が緩慢にうなずき、背もたれに寄りかかった。
「まあ、風間さんの期待に応えようって歌川が張り切ってるから、うるさいんだよね。連携の確……まあ、その、学年末考査が終わってから、ああ、そう。練習、の拘束時間が増えてる。順調に」
いつも的確に鋭い言葉を授けてくれる菊地原にしては、珍しくふんわりとした内容だ。こちらのリクエストに全力で応えようとしてくれているのだ。いいひとである。
「春はそういうものだね」
ボーダーには「遠征」があると聞いたことがある。春の全国大会も近いのだろう。真澄がうんうん、とうなずけば、
「……宇田川のそういう拡大解釈、ある意味すごいよね」
「ありがとう」
「褒めてない。あの記者会見だって毎日報道されてたのにさあ。……人間ってやっぱりわかり合えない生き物だよね」
なにやら哀しいことを言ってくる。春の菊地原プロのSentimentalismeであろう。春なので。
「春だねえ」
菊地原は目を伏せたまま、ぐったりと同意してくれた。三月の窓から注ぐ春光こそ、いとあはれ。
今年度最後の図書当番は昨日をもって終了した。進級後もクラスが一緒にならない限り、菊地原とこうしてゆっくり会話できる機会はなくなるかもしれない。
思えば、菊地原にはいつも話を聴いてもらっていた。歌川のやさしさと素晴らしさを直撃し、爆発しそうで持て余してしまうどうしようもない真澄の気持ちを、彼はいつも呆れながらも耳を傾けてくれた。現実の再確認ツアーにも連れて行ってくれた。やはり、友だちは人間最高の尊称だ。
「菊地原くん。いつもお話をたくさん聴いてくれてありがとう」
ありがとうだけでは足りないな、と思いながらも深々と頭を下げれば、菊地原は猫目と口元をほんのり緩めてくれた。
「どういたしまして。なかなかいい退屈しのぎになったかな」
そういえば、と菊地原が欠伸をしながら言ってくる。
「この際だから聞いておく。宇田川、四月にあった校外オリエンテーションもさぞかし楽しかったんでしょ? あの頃の班分け、出席番号順だったよね。歌川と一緒だったんじゃん」
ぎょっ、と真澄は目を見開いた。それを受けた菊地原も目をまあるくさせた。
「四月ってあの四月?」
「そう。たぶんその四月」
他に何があるのか、菊地原は淡い色素の片眉を上げた。
じ、と猫に似た吊り目が真澄に注がれる。口元をあわあわさせ、目線をおろおろ泳がせるが、正面の圧はますます強くなった。
観念して、告げる。
「い、いっぱいいっぱいすぎて、心臓が爆発しなかったことくらいしか覚えてない」
「はあ? やる気あるの?」
「ひっ」
声に凄みが入り、真澄は縮み上がった。やる気も何も、現実の確認をしたのはつい先月のバレンタインデーである。菊地原がその証人になっているのだ。彼は既にそれをよくご存じのはずなのだが。真澄は思い切り眉を下げる。と――
「ストーップ!」
「二人ともどうどう。どうどう」
願いが、届いた。助け船が二艘も来た。来てくれた!
「なにその止め方……」
げんなりとした目つきを隠さずに菊地原が声を出す。さすが菊地原プロ、どんなときでも誰が相手でもあくなきツッコミ心を忘れない。真澄が市川あゆみにわしゃわしゃ頭を撫でられている瞬間でも冴え渡るツッコミに真澄はため息を出す。
「昨日観た『生き物びっくり紀行』を参考にしてみました。荒ぶる羊が羊飼いの少年の一声で鎮まってたから効くかなって」
「はあ? 暴れてないけど?」
「比喩だよ比喩。暴風警報発令間近の予感がしたからさあ。STOP THE春疾風 」
凄みを増した菊地原の声に怯みもせず、北見茉椰が「あっはっはっ」と笑う。
バレンタインデー当日の危急存亡の秋 には部活と委員会の用事で留守にしていた二人だが、今回は駆けつけてくれた。持つべきものは友だちだ。友だちこそ人間に対する最高の尊称なり!
「すまないねえ。菊地原くん。この子、入学直後はまだアップデートどころか、恋心インストール完了してなかったから」 あゆみと茉椰がにやにやする。敵は本能寺にあり。
「ナンデ!?」
弾かれたように立ち上がると、真澄は全身をわななかせた。菊地原がうるさそうに顔をしかめている。椅子を派手に倒したことは事実なので陳謝したい。二人から出された謎が解き明かせたら。
「話したことないのに! なんで!? なんで知ってるの!? ふたりはエスパー!?」
頭から湯気を上げて叫ぶ真澄を見下ろしたまま、二人は特にどうということもなくうなずいた。
「エスパーアユミよ、かつてこれほどわかりやすいものはあっただろうか」
「いや、ない。そうだろう、エスパーマヤよ」
反語表現をさらりと使いこなす二人に真澄は「ああああ……!」と頭を抱えた。
「見てればわかるって。やってて良かったマーガレット塾!」
「あたしは花ゆめ塾!」
晴れやかに朗らかに笑い、二人は親指を立てた。びし、と。ちなみに真澄は『LaLa』塾と『週刊少年ジャンプ』教室出身だ。
真澄の出席番号よりひとつ早いあゆみが目を細めた。にんまりと。
「真澄、朝読書するために早く登校するようになったでしょ? 歌川くんも、まあ、さすがというか、むしろそうでない方が不思議というか……いつも早く登校するひとじゃない? 真澄、毎日がんばってるよね。歌川くんへの挨拶。真澄が挨拶する前に大きく深呼吸してるのよく見えるよ。あたしも朝練あるから最後まではなかなか観戦できないのが残念なんだけど」
「あ……」
「うんうん。あゆみさんの分は私が見てるから安心して! 真澄、出席番号順の席ではない日でも歌川くんへの挨拶運動がんばっているのがいじらしいよねえ。歌川くんに挨拶するときの真澄、見てるこっちまでどきどきするくらいものすごく緊張してるのに、声がやわらかいの。それに終わった後に手のひら白くなるほどぎゅうって握りしめてるんだよね。それがもう可愛くて可愛くて!」
「う」
茉椰もうんうん、とうなずいている。微笑みを堪えきれないといったように、口元をほころばせながら。
「歌川くんが授業で当てられたとき、教科書机に立てて、口元隠しながらきらきらした目で窺ってるの、あたしの席からよく見えるんだよねえ」
「それそれ! こっちからもよく見えるよ~。真澄の百面相がもう面白可愛くて……! 歌川くん、次も先生に当てられないかなあってついつい期待しちゃうよね」
「うんうん。防衛任務で忙しい歌川くんには悪いけど」
「あ……う……」
あうあうとしか音にならず、言語と熱処理能力の限界を迎えた真澄を、三人が見守る。
黙していた菊地原プロが、ついに動いた。彼はさっと席を立つと廊下側に赴き、クラスメイトと談笑しているそのひとに声をかけた。
「歌川」
「うん? どうした菊地原」
「下敷き借りるよ」
「うん? いいぞ」
「ほら」
席に座り直した菊地原がこちらに下敷きを差し出してきた。歌川の下敷きを。
「ナンデ!?」
菊地原の顔がまっすぐ見られない。「見えてるよ、狼煙」と口元を緩めながら言ってくるあたり、菊地原プロも少女漫画を知る者らしい。
ますます頭からしゅうしゅう、もくもく、どんどこ、と狼煙をあげた真澄を宥め、茉椰が「いつもすまないねえ」と下敷きを恭しくキャッチした。真澄の下敷きと赤シートを机からいつの間にか取り出していたあゆみも「菊地原先生、いつもありがとう。次もクラスご一緒の暁には、うちの真澄ちゃんのフォローとツッコミと見守り活動のご協力をどうぞよろしくね」などと言い、ゆったりと扇ぎ始める。
風が、左右の頬にガンガンぶつかり始める。
春の陽光のあたたかさと晩冬の名残の冷たい空気を孕んだ風が、ぶつかり稽古の如く、真澄に思い切り当たっている。けれども、のぼせた頬の熱はまだ下がりそうにない。
少女は指先に息を吹きかけた。吐く息はあたたかいが、空気を白く染めはしない。風邪の予防対策で換気された窓から届く風は、少しだけ冷たいが、底冷えのするようなものではない。校庭では梅がやわらかに花開いている。すぐそばまで春が来ているのだ。
少女はしみじみとした思いで呟く。
「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」
一生懸命覚えた『おくのほそ道』の序文が今はとても懐かしい。覚えたのはちょうど一年前の今頃の季節だ。中等部三年の特別考査課題のひとつだった。
一月の特別考査がようやく終わったと思ったら、二月には英語検定試験TOEFLが手招きしている。三月には学年末考査が両腕を組んで待ち構えている。まさに一月は行き、二月は逃げ、三月は去って行く。あれからもう一年。光陰矢の如し。月日が経つのは、本当に早い。
二月である。暦の上では立春を迎えた。換気中の窓から産地直送で届く風も冷たいものの、降り注ぐ陽光の彩度や温もりはあたたかい。冬の窓際席組の特権である。昼休みの日光浴はまさに天国と言えた。
「草の戸も
前列の物知り博士こと菊地原士郎が合いの手を入れてくれた。いいひとである。
「
少女も返し、ぺこりと頭を下げた。
「ありがとう菊地原くん。去年は覚えるのに苦労したのに、一度覚えたらなかなか忘れないものだねえ」
「まあ、後ろから聞こえたらね。口ずさみたくなるでしょ」
菊地原士郎が眠たげな目つきで言ってきた。三学期の席替えで菊地原とは隣同士の間柄ではなくなった。しかし、窓際特等列、前後の配置となったので今でもほのぼのとした交流は続いている。
「うん。祇園精舎の鐘の声とか、春はあけぼのとか。聞こえ始めるといつのまにか皆で合唱しちゃうよね、食う寝るところに住むところ~って」
「それは寿限無」
さすが菊地原プロである。いつでもどこでも誰にでも丁寧に的確にツッコミを入れてくれるプロフェッショナル意識を忘れない。進学校生あるある事項のチェックにも厳しい。
「それにしても一年が過ぎるのって本当に早いよねえ。二月ももう半分終わっちゃうねえ」
しみじみとした思いで言う真澄を、菊地原がまじまじと見つめてくる。
「……あのさあ。宇田川。やる気あるの?」
「え」
ぱちぱち。真澄は目を大きくしばたたいた。
やる気ならばある。TOEFLは明日二月十五日が本番だ。窓から降りる午後の陽射しに微睡みを誘われかけている情勢ではあるが、今も過去問題プリントを読み直している最中だ。
「いや、ない」
「はい……」
醒めた口調の反語表現に真澄は姿勢を正した。なんとなく気まずいものを感じたのだ。プリントを広げてはいるものの、あたたかな陽光をたっぷりと浴び、ひなたぼっこをしている猫のような心地を存分に味わっていることは否めない。
ため息交じりに菊地原が口を開いた。
「今日は何日」
「二月十四日金曜日です」
「……今日は何の日」
「TOEFL前日です」
突如始まった口頭試問に真澄は内心焦ったが、机からプリントを持ち上げてみせた。
「はあ」
またしても果てしない巨大なため息をお見舞いされた。猫に似た菊地原プロの吊り目がなにやら険しくなっている。そうじゃない、と。
弾かれたように真澄は叫んだ。
「えっ、明日だよね?」
検定試験は明日の土曜日に行われるはずだ。先週は登校しなくて良い休日だった。はずだ。真澄が口をぱくぱくさせると、菊地原がげんなりと言った。
「だから、そうだけどそうじゃない」
二回言った。
「?」
さっぱりわからずに、真澄は菊地原に目で問いかける。じ、と見上げる。
菊地原の猫目が信じられないものを見たときのように険しくなった。極寒の日に半袖で遊びに来た友だちを見つめる、あれだ。
「だから。そうだけどそうじゃないって」
眉間に皺を寄せたまま、彼はのたまった。いつも通りのクールな調子で。
「宇田川、本当にやる気あるの? 歌川のことがそんなに気になるならバレンタインに便乗して贈ってみるとかしたら? 今日は休み時間のたびに歌川が呼ばれて教室から出て行くのも戻って来るたび荷物増えてるのも、ずっと目で追いかけてはしょんぼりしてるじゃん。朝からずっと。この繰り返し。このあとクラス替えだってあるわけだし贈ってみるチャレンジをしたら? ちなみにTOEFLはちゃんと明日だよ。よかったね」
ぎょっと目を剥いた。今、なにやらすごいことを一息に指摘された気がする。TOEFLは明日。よかったよかった! よかった? よくない!
かッ!
火が、走った。
脊椎反射の勢いで真澄は立ち上がった。弾かれたように。がたんと。後ろで椅子が大きな音を立てた。
「ナ、ナンデ!?」
「うるさ……」
菊地原がクールに言う。にべもない。だが、ざっついぐざくとりーすぎるお言葉である。真澄は頭を下げ、椅子を戻すべくしゃがんだ。どっどっどっどっ、と心臓が激しくドラムを叩いていた。
「歌川とクリスマスにイルミネーションだって見たんでしょ」
「う」
菊地原刑事の追及に宇田川真澄は息を止める。
取調室ではなく、昼休みの教室である。デスクライトの代わりに春の初めのやわらかな陽光が窓際席族の二人を照らしている。ほこほこと。
「あんなにきらきらした街の灯は見たことがないってぼくに教えてくれたじゃん。敢えて。わざわざ。ご丁寧に目をきらっきらさせながらさあ。二学期最後の図書当番。エアコンの電源がなかなか反応しなかった寒い図書室でさあ。とっておきの心温まるエピソードがあるんだって、やけににこにこして」
「うう……」
真澄は更なる追い打ちに頭を抱えた。
歌川遼と宇田川真澄がクリスマスの時季にイルミネーションを見た。
それは事実だ。
ただし、愛犬太郎の散歩コースのひとつである駅前通りをクリスマスシーズンに歩いたところ、偶然にもコンビニ前で歌川と会った。真澄の小学二年生の弟もいたし、当然、宇田川家の柴犬太郎も一緒に居た。そういうことである。 そして、その翌週にシフトがあった図書当番当日は、エアコンのリモコンスイッチの調子が悪かった。何度ボタンを押しても反応してくれなかった。コートを着込み、マフラーをぐるぐる巻いた二人は、司書教諭が定例職員会議から帰還されるのを待った。そういうときに限って、貸し出しにも返却にも生徒が代わる代わる現れるものである。彼らも交えて小学二年生のように押しくらまんじゅうやドッジボールをして暖を取るわけにもいかず、カウンター席に座った菊地原と真澄の一年C組図書委員は、歯をカチカチ震わせながら代わる代わる六角鉛筆を転がしてクロストーークを交わすことで寒さを忘れる努力に励んだのであった。
ちなみに各面それぞれに割り振ったテーマは確か、一の目が出たら「冬の定番! 至高にして究極のメニュー!」で、六が出たら「とっておきの冬の心温まるエピソード」というような内容であった。長引いた職員会議を終え、使い捨てカイロとホットレモンを司書教諭が差し入れに来てくれるまで、二人は鉛筆を転がし続けた。
半泣きのまま菊地原警部補と向き合う真澄であるが、やはり救援はまだ来そうにない。そう。今日は二月十四日金曜日。TOEFL前日。バレンタインデー当日である。進学校といえど、この六頴館高校一年C組の教室も、どこかうきうき、そわそわ、ふわふわ、きらきらというような華やいだ空気が朝から醸し出され、昼休みの今は飽和状態となっていた。
二月から本格的な受験シーズンに入り、三年生も自由登校になった。けれど、今日は偶然にも三年生の登校日だ。「日頃のお礼を伝えよう」「卒業前に感謝や想いを伝えよう」とクラスメイトが鼻息荒く三年生の校舎に向かう姿を何度も見送ったし、反対に、教室まで足を運んでくださった三年生がニコニコしながらクラスメイトを手招きしている光景も見かけた。要するに、休み時間のたびに教室内人口密度が著しく減るのである。真澄の元へ友による増援はまだ届きそうにない。
「歌川にさあ、『風邪に気を付けような』って微笑まれて、思いやりあふれる笑顔とまぶしさとあたたかさとやさしさに感激して、火傷しそうになったって言ってたじゃん」
菊地原が静かに言う。
「コンビニ前で半分こにした中華まんを喉に詰まらせかけて。きみ、あの日の熱さをもう忘れたんだ?」
忘れていない。忘れようがない。忘れるはずがない。むしろ思い出しては爆発しそうになる。たとえば、たった今。今、この瞬間も菊地原が丁寧にあの日の会話を再現してくれるので心臓が爆発しそうなほど音を立てているのだ。どくどく。どんどん。どっどっどっどっ。そろそろ本格的に弾け飛ぶに違いない。
「は、半分こじゃないよ。不均等三分割だもん。弟も一緒にいたもん……」
のろのろと弁明する真澄に、菊地原は口の端をにんまりと吊り上げた。
「ふうん?」
あれは本当に熱かった。あの日はとても寒かったはずなのに、とびきり熱い思い出となった。思い出すだけで、胸のあたりがきゅう、となるし、頬だけでなく、耳も首も熱くなる。
弟が目を潤ませて「お腹空いたよう」とおねだりしてきた。しかし、真澄はすぐに返事ができなかった。その晩は祖母が弟の好物クリームシチューを作ってくれる日だったのだ。中華まんを真澄と折半するにしても、小学二年生の弟からすれば夕飯前に食べるには多い分量だ。どうしたものかな、と真澄が窮して弟の頭を撫でていたら、歌川が提案してくれたのだ。こちらに思い切り笑いかけながら。
――一緒に悪いことしないか。
歌川は中華まんを真っ二つに割り、更にその片方だけを折半した。小さく二分割したものをまず真澄の弟へ、続いて真澄に差し出してくれた。最後に残った大きいものは歌川自身が担当してくれた。弟だけでなく、真澄の分量も、祖母のクリームシチューを姉弟がどれだけ楽しみにしているのかを汲み取ってくれたのだ。
三人で食べた中華まんは、熱かった。とても熱かった。歌川から受け取るとき、指先がほんのり触れ合った。瞬間、真澄の頭から狼煙が上がった。熱かった。今年一番の冷え込みを記録した日なのにものすごく熱かった。弟がおろおろと水筒の麦茶を差し出してくれなければ確実に火傷していた。弟に感謝。そもそも歌川が「風邪に気を付けような」と声をかけてくれたのも、弟の学年で風邪が大流行しているという話題がきっかけであった。そのひとと駅前通りの煌めくイルミネーションを眺め、中華まんをシェアするこの冬最大の幸運が巡ってきたのも弟の遼太と愛犬太郎と一緒に散歩に出向いたおかげである。感謝しかない。
「宇田川。ちょっと、顔貸してくれない?」
「え」
カツアゲだ。これは俗に言うカツアゲなのでは? カツアゲだろう! 菊地原警部がカツアゲをしようとしている!
目も口もあんぐり開いたまま凍りつく真澄に、菊地原プロは巨大なため息をついた。
「ちゃんと見たら? 現実」
「はい」
「まあ、いいや。これから見せてあげる。ほら、早く来なよね」
「はい」
真澄は肩を落とし、どこまでも醒めた口調と顔つきの菊地原警部に連行された。さながら刑の執行に向かう咎人の心地だ。
「菊地原、現着」
菊地原警視正が醒めた口調のまま言う。小声で先導してくれる彼に導かれ、真澄は口のファスナーを閉じ、両手で口を覆ったまま一年B組の靴箱陰に身を潜めた。
「はい、宇田川。これが現実だよ。一言どうぞ」
真澄は息を止めた。目を見開いて――さすがに冷や汗を落とさずにはいられなかった――、真澄は、こちらを見下ろしてくる菊地原に、目も口もぽかんと開いたまま向き直った。
「…………」
体育館裏や屋上、校門などといった、学ランに立派な刺繍が入った人々によるクローズでZEROな展開が始まることはなさそうだ。生徒玄関は靴箱コーナーである。
す、と右の人差し指で一点を示す彼に、なにをどう言えばいいものか――というよりもあまりにもすごくすごくすごすぎる光景に呼吸も思考も停止した。
彼の指が指し示したのは、一年C組の靴箱男子列だった。間違い探しをするとしたら、誰もが真っ先に指を差すであろう靴箱があった。ぎっしり。いや、みっしり。所狭しと直方体に立方体、円柱形の箱。クッション性のある大きくて可愛らしいふわふわもこもこきらきらした封筒。それらが所狭しと大集結していた。
そう、ネームプレートに書かれていたのは、歌川遼そのひとの名前であった。皆、歌川に贈られたチョコレートギフトとやらだ。
菊地原が丁寧に言い直した。
「ほら、宇田川。これが現実。今の心境を一言」
「…………」
はくはく、と唇をわななかせるしかない。震える膝を叱咤し、両の手を開いては、握る。結んでは、ほどく。ごくり、と唾を飲む。そして――
「げ」
「げ?」
「げ、芸術点たか~い……?」
しばらく間を置いてから、ひとまず首を傾げる。
「……どうしたの菊地原くん。歩いてもないのにどうしてつまずくの?」
「……いや、現実見ろとは言ったけどさあ、こうも現実を拡大解釈して受け入れるとは思わなかっただけ」
うめき声をあげながら、のろのろと起き上がる菊地原に、真澄はうなずいた。
「歩くときは注意したほうがいいかも」
「わかってるけど」
ようやく姿勢を正した彼は、なぜか怒っているようにも見えた。八拍分の沈黙を挟んでから言ってくる。
「あのさあ、気づいてなかったわけ?」
「気づいてるよ」
即答する。歌川遼は、クラスで一番、いや、少なくとも学年でいっとうベリーベリーベリージェントルソウルをお持ちで、誰にでもいつでもやさしく手を差し伸べてくれるひとなのだ。憧れの気持ちを抱かない方がきっと難しい。これは、真澄よりも勇気のあるひとたちの気持ちの結晶なのだ。自分には出せなかったその一歩は、まぶしくて、まぶしくて、少しだけ苦い。
菊地原の口から、長々とした嘆息が漏れるのが聞こえてきた。
「ならいいけどさあ。で?」
どうするの、と言いたげな目つきに、真澄は眉を下げた。どうもしないよ、と――
「その声は我が後輩きくっちー! きくっちーではないか!」
「菊地原くんと愉快なおともだち、かな。こんにちは~」
やけに澄んだ明るい声とどこかのんびりした声音が玄関いっぱいに響いた。
現れたのは、艶やかな黒髪を靡かせた眼鏡の美少女と、曖昧に微笑みながら淡い色素の髪をサイドで子犬の尻尾のように結わえた少女だった。
上履きの学年色を見る限り、どちらも一年生ではない。長いストレート黒髪の先輩が二年生で、子犬めいた――この中で一番小柄だ――サイドテールをふわふわ揺らす方が三年生らしい。その最年長の先輩は二年生に後ろ襟を掴まれている。「しおりちゃん、ぎぶぎぶ。しまるしまる」となにやら苦しげにうめいている。
「いやはやきくっちーよ、よくぞ来てくれた! いや、キミが来てくれることは信じていたとも! しかも活きの良いゲストを産地直送で連れてくるとは! さっすがデキる風間隊エースの中のエースよ!」
澄んだ声で快活に笑う二年生が、ぐ、と左右両方の親指を立てた。
小さな三年生の大きな深呼吸が聞こえてくる。無事に解放されたらしい。
「うわ、なんでいるの。暇なの?」
一転して、嫌そうな顔で犬歯まで見せて、菊地原が言う。
「心外だなあ、きくっちー。なんでも何も、今日はバレンタインデーだ。うってぃーのテトリス実況に駆けつけたに決まってるじゃん」
「絵に描いた暇人じゃん」
菊地原プロは首を傾げる二年生をひとまず無視し、半眼で三年生を見やる。が、三年生は厳かな表情で、きっぱりとかぶりを振ってきた。サイドテールが利口な子犬の尾の如く、凛々しく揺れた。ぶん、と。
「待って。菊地原くん。これにはわけがある」
「なに?」
「栞ちゃんは言いました」
「?」
「明日またここに来てください。本物のバレンタインってやつを見せてあ――」
「いや、もういいから。受験生は早く帰って勉強しなよ」
「えー」
二年生と三年生が口をそろえた。
「はいはい、かえったかえった」
菊地原が醒めた口調でぞんざいに、手で追い払い始めるが、どちらも全然気にしていない。上級生、すごい。黒髪の二年生が額に拳を作って当てた。てへ、と。
「いや、まあ、アタシが先輩を呼んだのは本当。パズルゲーム得意な先輩に〝ドキッ☆うってぃーのバレンタインだよ! チキチキチョコレートギフト詰め放題レース〟模様を解説してもらおうと来てもらっただけ。やっぱり一年生はうってぃーが一等賞かなあ。もうぎゅうぎゅうじゃん」
肩をすくめてみせる二年生とは正反対に、小柄な三年生は奇妙な表情を浮かべていた。眉根を寄せて、なにやら考え込んでいる。
「はい」
三年生が「整いました」と右手を挙げる。じ、と淡い色素の大きな瞳を、〝ドキッ☆うってぃーのバレンタインだよ! チキチキチョコレートギフト詰め放題レース〟の詰め放題レース現場に向けたまま、ゆっくりと唇を開いた。
「まだ完全なみっしりではないかな。五〇グラムの板型ミルクチョコレートパッケージならあと七枚、いや、六枚はいけるはず。ハイミルクチョコレートのボックスなら四箱はギリギリ入る。どちらを入れるか次第で攻略法はだいぶ変わるけれど。一旦そのふわふわの封筒を出して、この円柱を右に寄せれば赤い立方体の隣に板型がまず二枚いける……。それぞれ箱から取り出して、個包装のみの勝負ならばもっといけるよ」
「うわ……」
「おおー! さっすが先輩! だからゲスト解説にお呼びしたんですよう!」
思い切り嫌そうに頬を引きつらせる菊地原に対し、二年生のナントカ栞先輩は、ぱちぱちぱちぱちぱち、とたまらずに感激した様子で拍手を送った。三年生はぐったりとうめく。
「犬飼くんにも結束さんにも朝からしょっちゅう三年A組の現場に直行するよう急かされたからね……だいたいの形状は見たから。何回も何個も見ましたので……」
どうやらこの小柄な先輩は、チョコレート博士らしい。チョコレートのメジャーな箱サイズを完全に把握していらっしゃるようである。
「蔵内くんのところ、もう本当に凄かったよ。靴箱はまだ序の口。机とロッカーと鞄がどえらいことになってた。万国びっくりチョコレート詰め放題選手権とか、人類の新たな空間処理ワザマエへの挑戦を見た気がする。でも、丈夫そうな紙袋もたくさん寄せられていてねえ。ファンの対応も凄い。さすが蔵内かいちょーは日頃の人徳レベルが神がかってるなってそう思った……」
「…………」
示し合わせたわけではないが、元生徒会長・蔵内和紀が所属する三年A組靴箱の方角に向かってそっと十字を切る一同であった。
「一年生のときの蔵内くんの靴箱もそれはそれは凄かったんだよ。紙袋の到着が一刻も早く待たれてた」
内緒話をするように、三年生の先輩が細い両手で筒を作った。それからふわり、と頬の力を抜いた。
「今日の靴箱を見る限り、歌川くんにもそうした伸びしろがありそうだねえ。どの贈り主も他の箱を邪魔しないように、落とさないように、壊さないようにって丁寧に入れてるよね。気遣いの名人歌川くん相手に恥じない真っ向勝負を、贈りびとそれぞれが真摯に挑んでいる気がする」
「さッすが先輩! 歴戦のバレンタイン詰め放題選手権解説を担当しただけある! 先輩、来年も、うってぃーの解説をゼヒゼヒお願いしますよ~!」
「いや、来月卒業するから」
「ゆっくりしていってもいいんですよう?」
「留年だめ、ゼッタイ」
「一緒に最後の高校生活を送りましょうよ~!」
「受験生おかわりはいやだ受験生おかわりはいやだ!」
二年生は三年生に思い切り戯れ付いている。二年生に揺さぶられていた三年生が、ふ、とこちらを見た。右手で拳を作り、左の手のひらをぽんと叩いた。
「そういえば、そちらのお嬢さん、十二月に歌川くんと金の豚まん食べてた子だよね。ほら、小学生の男の子と、金色のふわふわした立派な柴犬さんと仲良く駅前通りで美味しそうに頬張って……」
ひゅ、と真澄は息を呑んだ。見られていた。あの日の思い出を見られていた。何故中華まんの種類をしっかり覚えているのか。
「あと、今日の二限後の休み時間、書道室から帰る歌川くんが三年生に呼……おっと」
書道教室は三年生の校舎にあるのだ。同じ選択書道の真澄も今日のその場面は当然見た。見てしまった。上級生はもちろん、クラスメイトにも他のクラスの子を前にしても、歌川はベリージェントルソウルを忘れずににこやかに対応していた。どこに出しても恥ずかしくない、誰が見ても微笑みたくなる、今日彼に贈り物をした者はよき思い出として生涯その胸をあたためてくれるであろう神対応であった。
それを見るたび、胸のあたりが、もやもやするような、ざわざわするような心地がした。
昼休み。菓子作りの得意なクラスメイトが作ってきてくれたチョコレートケーキのご相伴に与ろうと、友人に誘われても、真澄は辞退した。なんだか食欲がしなかった。ざわざわ波立つ思いは、TOEFLの問題プリントを解き直すことで一旦保留にしたのだ。
ごほん。
三年生はわざとらしく大きく咳を払い、言い直した。
「ええと、そう! 選択書道の行き帰り、歌川くんの背中をそっと見守っている奥ゆかしい宇田川さん!」
「ちょっと」
菊地原プロの制止が入った。思い切り眉と頬を引きつらせながら。
「あっ、ごめんなさい。もう一回言い直しても?」
「遅いでしょ」
待たずに入ったツッコミに二年生の先輩も沈痛の面持ちを浮かべた。
「ウン。遅いです。さすがにアタシもフォローできません……」
「ごめんね。みんなが知ってるひみつなのかな、って」
三年生がしおしおと頭を下げる。やわらかそうなサイドテールが弱り果てた子犬の尾のようにその動きに沿って垂れ落ちた。しおしおと。
「はいはーい! 先輩は今日の発言一旦お休みしましょう」
ぱん、と二年生の先輩が両の手を合わせた。それから細い指で眼鏡のフレームをかけ直すと、すい、と真澄の正面に来た。それから、彼女は顔をうつむけた真澄の頭を、そっと撫でてくれた。あたたかい手のひらが、頭を、髪を、滑っていく。
「まあ、これは大きな独り言なんだけど」
二年生の先輩の澄んだ声が、真澄の耳に届く。
「先月、大きな出来事があったでしょう」
それが起きたのは一月二十日のことだ。四年半前にも起きた。三門市に住む者が、もう二度と忘れられない日。もう二度と忘れてはいけない日。
「この街の防衛組織側のアタシが言うのもなんだけど――ううん、そうならないように最善を尽くすのが務めだってわかってるけど、ね」
その先輩は、笑みを落とした。
「明日が必ずしも来ること、いつでも誰にでも保証はされてないんだよね。だからこそ、『また明日』って挨拶を交わせる関係も瞬間も大事にしていきたいよね」
雲間からほそりと月の明かりが差したような静かな笑みだった。
菊地原は、黙したまま歌川の靴箱を見つめていた。それからつと目線をこちらに向けて、口を開いた。
「宇田川」
「うん」
「歌川に言いたいことがあるなら、言えるうちに言った方がいい」
「うん……」
ありがとう、と唇を動かす。よろしい、というように菊地原はうなずいてくれた。
先月三門市に起きた二度目の大規模侵攻。明日を変わらずに迎えられることのありがたさ。いつも通りの明日が来る幸せを、日々わかっているはずなのに、わかっているつもりでしかなかったことを思い知らされた。一月二十日、それを改めて強く痛感したはずだ。わかっているはずなのに、わかっていたつもりで全然理解できていなかった。
最前線で身体を張ってくれている彼らに、身も心もこの街の防衛に注いでくれている彼らにその言葉を言わせてしまった。それが情けなくて、切なくて。哀しかった。
目尻に浮いた涙をそっと指の腹で拭う。栞先輩はわしゃわしゃと乱暴に頭を撫でた。そして――
「ダイジョーブ! 皆が知っているキミのひみつは、ひみつにしますよ。ちゃあんとね」
右目をぱちん、と閉じ、先輩は細い人差し指を艶やかな唇の前で立てる。
「大丈夫だ! 未来はもう動き出してる!」
「うわ」
どこかの誰かさんの台詞丸パクリじゃん、と顔をしかめる菊地原に、栞先輩は両手をわきわき広げ、
「先輩の決めシーンを邪魔したきくっちーよ、神妙に致せ! わしゃわしゃの刑に処す!」
笑いながら菊地原に突進し、頭をかき回した。
「……ありがとうございます」
真澄がそっと頭を下げると、栞先輩は「いえいえ」と晴れやかに笑い返してくれた。菊地原は心を無にしてわしゃわしゃ髪と頭をシェイクされていた。
「へい、宇田川ちゃん! きくっちーによる現実確認も現場検証も済んだことだし、いっそのこと今年のバレンタインデーのうちに動かしてみないかい? 未来」
びしっ、と右の親指を立て、白い歯にきらりと星を煌めかせた。「大将、未来一丁!」と。
きらりと眼鏡のレンズを――目を煌めかせ、笑う。
「我らが六頴館高売店にも板型ミルクチョコレートは常備されてるんだぜ! なんと、今なら六枚は、〝ドキッ☆うってぃーのバレンタインだよ! チキチキチョコレートギフト詰め放題レース〟会場でも堂々と入り込める算段だ! 若干の余裕があると、こちらの歴戦解説の先輩お墨付きだ!」
子犬めいた先輩が、ぎゃっ、と跳ねた。
「こら! 栞ちゃん!」
「やだな〜! 善き先輩としての助言とアタシ個人としてのアドバイスは別腹ですよゥ!」
「も〜!」
胸を張る二年生に、三年生が鳴いた。牛のように。
「失言連発したわたしが言うのも大変アレですが」
子犬めいた先輩が言う。背伸びして、両の手のひらをいっぱいに広げて栞先輩の口を塞ぎながら。
「友だちは人間に対する最高の尊称なんだよ」
真澄には、まばたきを返すことしかできない。
ふわり。先輩が、思い切り頬を緩めた。
大丈夫だよ、と。
「菊地原くんを見ているとよくわかるもの。いい友だちは善きひとのもとに集うって。類は友を呼ぶとも言うよね。いい友だちを持つ歌川くんが宇田川さんにとっていい子であるように、歌川くんから見た宇田川さんもきっとそうだと思うよ。大丈夫。なるようになる」
「おみくじじゃないんだから」
「そうそう。それが付くとなーんか怪しいぞって思います、アタシ」
後輩二人から冷静に指摘され、子犬めいた三年生は肩を落とした。
「いえ、あの、ありがとうございます……」
「いえいえ。生きとし生けるものに等しく春は来る! もちろん宇田川ちゃんのもとにもね!」
「ね!」
栞先輩と三年生が顔を思い切りほころばせた。
「先輩にもね。テトリス解説するくらいだからさぞかし余裕なんだね。本命受験」
「…………」
菊地原の指摘に三年生がしゅるしゅると肩を下げた。心なしかサイドテールも一回り萎んだように見える。栞先輩がしんみりとした口調で言う。
「そっかあ、今日がバレンタインデーだからあと十日ですよねえ。前期日程」
「それは、そうなんですが……」
この場に呼び出した張本人からの指摘に三年生は思い切り頬を引きつらせていた。
自己紹介なんてしたかな、と真澄は首を傾げた。
油性ペンで上履きにでかでかとクラスも名前も書いていることを思い出したのは、先輩方と別れて教室に戻ってからだった。
学年末考査が終わった。まもなく三学期のゴールが近づいている。高校一年生も終幕が近い。
思えば、あんなこと、こんなこと、いっぱいあった。
この一年C組のクラスの一員になってから過ごした日々が、本のページのようにふわ、と浮き上がっては、次々と捲(めく)れていく。
苦手意識の強かった国語の成績が徐々に上がっていったのも、予習復習も、本を読むことも楽しいと思えるようになったのも高校一年生になってからの出来事だった。
ベリージェントルソウルをお持ちの歌川遼に抱く気持ちには、まだ、名前は付けていない。けれど、その輪郭は、歌川に対する気持ちの正体を知りたいと願うようになった初夏よりもずっと色濃く見えるようになっていた。
「菊地原くん、眠そうだね」
「春休みの試……」
ばっ! 素早く真澄が腕でTの字を作る。タイム要求に気づいてくれた菊地原は、欠伸をしながら「どうぞ」と目つきで言った。
「菊地原くん。機密は人命より重い。大事なところはぼかし、お願いします!」
日曜朝の戦隊番組で一年間、小学二年生の弟指導の下で真澄は学習したのだ。知りすぎる者は組織に消される。きりりと眉を引き締めた。
「はい、はい」
菊地原が緩慢にうなずき、背もたれに寄りかかった。
「まあ、風間さんの期待に応えようって歌川が張り切ってるから、うるさいんだよね。連携の確……まあ、その、学年末考査が終わってから、ああ、そう。練習、の拘束時間が増えてる。順調に」
いつも的確に鋭い言葉を授けてくれる菊地原にしては、珍しくふんわりとした内容だ。こちらのリクエストに全力で応えようとしてくれているのだ。いいひとである。
「春はそういうものだね」
ボーダーには「遠征」があると聞いたことがある。春の全国大会も近いのだろう。真澄がうんうん、とうなずけば、
「……宇田川のそういう拡大解釈、ある意味すごいよね」
「ありがとう」
「褒めてない。あの記者会見だって毎日報道されてたのにさあ。……人間ってやっぱりわかり合えない生き物だよね」
なにやら哀しいことを言ってくる。春の菊地原プロのSentimentalismeであろう。春なので。
「春だねえ」
菊地原は目を伏せたまま、ぐったりと同意してくれた。三月の窓から注ぐ春光こそ、いとあはれ。
今年度最後の図書当番は昨日をもって終了した。進級後もクラスが一緒にならない限り、菊地原とこうしてゆっくり会話できる機会はなくなるかもしれない。
思えば、菊地原にはいつも話を聴いてもらっていた。歌川のやさしさと素晴らしさを直撃し、爆発しそうで持て余してしまうどうしようもない真澄の気持ちを、彼はいつも呆れながらも耳を傾けてくれた。現実の再確認ツアーにも連れて行ってくれた。やはり、友だちは人間最高の尊称だ。
「菊地原くん。いつもお話をたくさん聴いてくれてありがとう」
ありがとうだけでは足りないな、と思いながらも深々と頭を下げれば、菊地原は猫目と口元をほんのり緩めてくれた。
「どういたしまして。なかなかいい退屈しのぎになったかな」
そういえば、と菊地原が欠伸をしながら言ってくる。
「この際だから聞いておく。宇田川、四月にあった校外オリエンテーションもさぞかし楽しかったんでしょ? あの頃の班分け、出席番号順だったよね。歌川と一緒だったんじゃん」
ぎょっ、と真澄は目を見開いた。それを受けた菊地原も目をまあるくさせた。
「四月ってあの四月?」
「そう。たぶんその四月」
他に何があるのか、菊地原は淡い色素の片眉を上げた。
じ、と猫に似た吊り目が真澄に注がれる。口元をあわあわさせ、目線をおろおろ泳がせるが、正面の圧はますます強くなった。
観念して、告げる。
「い、いっぱいいっぱいすぎて、心臓が爆発しなかったことくらいしか覚えてない」
「はあ? やる気あるの?」
「ひっ」
声に凄みが入り、真澄は縮み上がった。やる気も何も、現実の確認をしたのはつい先月のバレンタインデーである。菊地原がその証人になっているのだ。彼は既にそれをよくご存じのはずなのだが。真澄は思い切り眉を下げる。と――
「ストーップ!」
「二人ともどうどう。どうどう」
願いが、届いた。助け船が二艘も来た。来てくれた!
「なにその止め方……」
げんなりとした目つきを隠さずに菊地原が声を出す。さすが菊地原プロ、どんなときでも誰が相手でもあくなきツッコミ心を忘れない。真澄が市川あゆみにわしゃわしゃ頭を撫でられている瞬間でも冴え渡るツッコミに真澄はため息を出す。
「昨日観た『生き物びっくり紀行』を参考にしてみました。荒ぶる羊が羊飼いの少年の一声で鎮まってたから効くかなって」
「はあ? 暴れてないけど?」
「比喩だよ比喩。暴風警報発令間近の予感がしたからさあ。STOP THE
凄みを増した菊地原の声に怯みもせず、北見茉椰が「あっはっはっ」と笑う。
バレンタインデー当日の危急存亡の
「すまないねえ。菊地原くん。この子、入学直後はまだアップデートどころか、恋心インストール完了してなかったから」 あゆみと茉椰がにやにやする。敵は本能寺にあり。
「ナンデ!?」
弾かれたように立ち上がると、真澄は全身をわななかせた。菊地原がうるさそうに顔をしかめている。椅子を派手に倒したことは事実なので陳謝したい。二人から出された謎が解き明かせたら。
「話したことないのに! なんで!? なんで知ってるの!? ふたりはエスパー!?」
頭から湯気を上げて叫ぶ真澄を見下ろしたまま、二人は特にどうということもなくうなずいた。
「エスパーアユミよ、かつてこれほどわかりやすいものはあっただろうか」
「いや、ない。そうだろう、エスパーマヤよ」
反語表現をさらりと使いこなす二人に真澄は「ああああ……!」と頭を抱えた。
「見てればわかるって。やってて良かったマーガレット塾!」
「あたしは花ゆめ塾!」
晴れやかに朗らかに笑い、二人は親指を立てた。びし、と。ちなみに真澄は『LaLa』塾と『週刊少年ジャンプ』教室出身だ。
真澄の出席番号よりひとつ早いあゆみが目を細めた。にんまりと。
「真澄、朝読書するために早く登校するようになったでしょ? 歌川くんも、まあ、さすがというか、むしろそうでない方が不思議というか……いつも早く登校するひとじゃない? 真澄、毎日がんばってるよね。歌川くんへの挨拶。真澄が挨拶する前に大きく深呼吸してるのよく見えるよ。あたしも朝練あるから最後まではなかなか観戦できないのが残念なんだけど」
「あ……」
「うんうん。あゆみさんの分は私が見てるから安心して! 真澄、出席番号順の席ではない日でも歌川くんへの挨拶運動がんばっているのがいじらしいよねえ。歌川くんに挨拶するときの真澄、見てるこっちまでどきどきするくらいものすごく緊張してるのに、声がやわらかいの。それに終わった後に手のひら白くなるほどぎゅうって握りしめてるんだよね。それがもう可愛くて可愛くて!」
「う」
茉椰もうんうん、とうなずいている。微笑みを堪えきれないといったように、口元をほころばせながら。
「歌川くんが授業で当てられたとき、教科書机に立てて、口元隠しながらきらきらした目で窺ってるの、あたしの席からよく見えるんだよねえ」
「それそれ! こっちからもよく見えるよ~。真澄の百面相がもう面白可愛くて……! 歌川くん、次も先生に当てられないかなあってついつい期待しちゃうよね」
「うんうん。防衛任務で忙しい歌川くんには悪いけど」
「あ……う……」
あうあうとしか音にならず、言語と熱処理能力の限界を迎えた真澄を、三人が見守る。
黙していた菊地原プロが、ついに動いた。彼はさっと席を立つと廊下側に赴き、クラスメイトと談笑しているそのひとに声をかけた。
「歌川」
「うん? どうした菊地原」
「下敷き借りるよ」
「うん? いいぞ」
「ほら」
席に座り直した菊地原がこちらに下敷きを差し出してきた。歌川の下敷きを。
「ナンデ!?」
菊地原の顔がまっすぐ見られない。「見えてるよ、狼煙」と口元を緩めながら言ってくるあたり、菊地原プロも少女漫画を知る者らしい。
ますます頭からしゅうしゅう、もくもく、どんどこ、と狼煙をあげた真澄を宥め、茉椰が「いつもすまないねえ」と下敷きを恭しくキャッチした。真澄の下敷きと赤シートを机からいつの間にか取り出していたあゆみも「菊地原先生、いつもありがとう。次もクラスご一緒の暁には、うちの真澄ちゃんのフォローとツッコミと見守り活動のご協力をどうぞよろしくね」などと言い、ゆったりと扇ぎ始める。
風が、左右の頬にガンガンぶつかり始める。
春の陽光のあたたかさと晩冬の名残の冷たい空気を孕んだ風が、ぶつかり稽古の如く、真澄に思い切り当たっている。けれども、のぼせた頬の熱はまだ下がりそうにない。