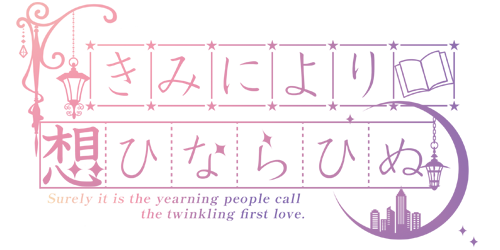ふわり。カーテンが浮き、揺れた。風が渡ったのだ。日本文学の書棚から顔を上げた少女は目を細めた。窓の向こうで、校庭の新緑が揺れ、陽光を周囲に散らしている。春だ。春が来た。
陽射しを受けて春光を弾くスカートのプリーツはまっすぐだ。クリーニング店から共に引き取ってきたばかりの二度目の春を迎えたブレザーもネクタイもぴかぴかしている。
無事に二年生に進級した。宇田川真澄は洗い立てぴかぴかまっさらな制服のように新鮮な気持ちいっぱいのまま、頬を緩めた。
「菊地原くん、今年も一緒に図書委員会がんばろうね」
受付台に戻るなりにこにこと声をかけた真澄に、菊地原士郎はアルカイック・スマイルを浮かべた。
「ふうん。宇田川はそれでいいんだ?」
「うん?」
ぱちぱちぱちとまばたきを返す。
今年も同じクラス、同じ委員会になった菊地原に差し出されたなぞなぞに真澄は首を傾げるしかない。
「委員長に異議を申し立てなかったから」
「いぎ? 意義?」
さすが菊地原だ。委員会活動の意義を常に追い求めるハンターにして、いつでも全力投球で取り組む生徒。その心意気、あっぱれである。
一方、真澄は「今年もそのまま図書委員になれたし、一年間当番を共に務めた菊地原くんと一緒だから安心安心。よかったなあ」などとほのぼのした気持ちで今日も図書室に向かった次第である。春の恒例行事、自己紹介の緊張も差し障りのない世間話の台本選びも必要ない。
幸運にも春特有の緊張する必要がなくなったので、緩みきっている。気合いなど一切ない。クラス替えは行われたが、受験選択科目、文理選択の都合でクラスメイトがほぼ持ち上がりだったのだ。進路選択の都合で移動して行った者、代わりに移動して来た者は片手で数える程度だ。
持ち上がりクラスの良いところは、クラス替え特有のメンバーシャッフルのどきどき感がそれほどないということだ。
自分から進んで誰かと喋るのがあまり得意ではない真澄にとって、クラス替えほど緊張を強いられるイベントはそうない。進学校ではあるので皆勉学には積極的だが、常に成績トップをキープし続ける精鋭のA組やB組よりも、このC組というクラスはどこかのんびりとした雰囲気がある。英語担当の担任教諭がおおらかでのんびりとした気風のひとだというのも大いに影響している気がする。
「違う違う。異議だよ、異議。ぼくが言ってるのは、不賛成・反対意見を指す『異議』だよ。宇田川のは、そのものではなければ果たすことのできないの『意義』でしょ? てっきり歌川と同じ係目指して、宇田川が反対するかと思ったって言ったんだよ」
突如出た歌川遼の名に、一気に沸騰した真澄は図書室利用カード申請書を取り落とした。
「な、なんで!?」
「はあ? なんではこっちの台詞なんだけど? お約束にもほどがあるでしょ、その反応」
呆れた口調ではあるものの、少年は真澄が頭から湯気をくゆらせているうちに、ばらまいた申請書をさくさく拾い上げ、学年・クラス・五十音順に並び替えては差し出してくれた。
「ありがとう……」
「どういたしまして。で、その心は? なんで反対しなかったの?」
さすが菊地原プロ。新学期でもその言葉のナイフは速くて鋭い。
「は、反対だなんてとんでもない!」
気の利いた三十一文字などその場ですらすら詠めるはずもなく、真澄は声も頬も引きつらせた。
菊地原がじっとりと眼差しを向けてくれているのが痛い。聞いてくれるやさしさはプライスレスなのに、視線で心が痛い。
二年C組の係と委員会は、昨年のものがほぼそのまま引き継がれた。委員長――今年も進んでクラス委員長の座に就いてくれた頼もしい者だ――の一声に一も二もなく決定した。今年からC組に加わった生徒もあっさりうなずいてくれた。拝命されたのがそれほど活動のない教科係だったからかもしれない。
「……あのね、この前、お礼参りに行ってきたんだ」
「はあ」
受け取った図書室利用カード申請書の高さを机で整えつつ、ぐらぐら沸騰した脳みそから伝えたい言葉を引き出す。
「今年も歌川くんと一緒のクラスになれたのは奇跡だから」
進学校に通う以上、気を緩めずに成績上昇を目指すのが正しい学生の姿だと真澄だってわかっている。
街の防衛任務を担ってくれている菊地原や歌川をはじめとしたボーダー所属隊員、全国大会優勝やコンクール入選を目指して部活動に励む学友たち。真澄も書道部には所属しているが、活動は火曜日と金曜日だけだ。彼らよりもその拘束時間はずっと緩い。つまり、自由に使える時間が多いということだ。要するに、街を護ってくれているボーダー隊員や活発な部活動に所属する人々が注いでいる時間と情熱と比較したら、ぐっと短いものなのだ。総時間はまばたきにも等しいかもしれない。よい書にしたいという気持ちこそ負けてはいないとは思う。けれども、真澄よりも情熱も時間も絶え間なく注ぎ、ひたむきに街の防衛任務や部活動に励む彼らに頭が上がりそうにはない。
彼らよりも勉学に回せる時間は多いはずなのに、真澄が晴れてA組生になれたというわけではない。真澄の成績がアップしたように、A組生やB組生、同じC組生だって怠けることなどなく、自身の成績にあぐらを搔くことなく、日夜勉学に励んでいるのだ。
「なに? なんで話し始めた途端へこむわけ?」
「……高みを共に目指す頼もしい友への畏敬の念を噛みしめてる」
「はあ?」
菊地原が眉を上げた。
六頴館高等学校のクラス分けは成績順だと言われている。トップクラスの難関大学合格を目指すA組には、学校側も彼らが望むカリキュラムを編成し応えてくれるのだ。A組だけが特別扱いをされているというわけではない、もちろん他のクラス編成にも配慮が為されている。個人の文理選択だけでなく、それぞれが目指す国公立や私立大学、専門学校といった進路の受験に必要な選択科目、生徒が悔いなく存分に学べるよう万全のカリキュラムを用意してくれているのだ。
そうした色々が加味された上でのクラス替えであることは重々承知している。それでも、歌川と進路について気軽に話せる仲ではなく、彼の進路選択を知らなかった真澄にとって、進級しても歌川と同じクラスに割り振られたのは嬉しいのだ。奇跡だと感謝せずにいられないのは、出席番号もそのまま持ち上がりだったことだ。ありがたいことに出席番号順では今年も歌川と席が隣同士なのだ。授業を担当する教諭が変更される科目もあり、「席替えはしばらくお預け」と担任教諭から宣言があったのだ。小テスト採点交換や定期試験、模擬試験での緊張は強いられる。歌川のちょっとした表情の変化にどきどきするし、毎日朝と夕方に交わす挨拶のまぶしさに目を焼かれ胸のあたりが焦げつきそうにもなる。けれども、歌川の左隣で送る日々は輝いている。奇跡としか言いようのないほど、毎日がきらきらしている。ますます〝歌川くん基金〟も捗るというものだ。歌川への尊敬と感謝は日々、積み重なっているのだ。
この奇跡と幸運はクラス分けの業務的処理の都合が大変大きいことは理解している。けれども、まさか学校に感謝状を贈るわけにもいかず、まして歌川本人に感謝の一首を詠めるはずもない。歌川への感謝の気持ちもいっぱいだが、まだ朝と夕に挨拶を交わすのでいっぱいいっぱいなのだ。
あふれかえる感謝の気持ちを持て余した結果、真澄は近所の神社にお礼に行くことにした。そういうわけである。
「感謝は減るものではないでしょう? お手洗いにも神様がいるのならば、クラス分けにも神様はいると思う。でも、祭られている神社を知らないから、家から一番近い神社に行ってみました」
そうしたことを、ぽつりぽつりと語る真澄に、菊地原は耳をじっと傾けてくれていた。いいひとだなあ、と心から思う。
参拝を終え、ぐるりと見回した神社は清々しい空気に包まれていた。新緑が芽吹き始め、吹く風も緑の匂いがした。訪れた春にうきうきとした心地のまま、真澄はおみくじを引いてみたのだ。
おみくじは、小吉だった。可もなく不可もなく、欲張らずに日々を送れという啓示だ。
手帳に挟んでいたそれと、今読んでいる本を広げ、菊地原にそっと見せた。菊地原は目を丸くしたものの、目を通してくれている。
「相変わらず宇田川はまっすぐとわけわかんないことするなあ」
あっさりと返された感想に真澄は口元を緩めるしかない。
「でも」
菊地原が言葉を切った。真澄は申請書を机に置き、膝に手を載せた。
「よかったね」
一年次にくじ引きで決まった図書委員。国語に苦手意識のあった真澄は豊富な蔵書を誇る高等部図書室に恐れをなしていたが、今では返却された本を手に取りページを捲ってみたり、タイトルやあらすじが面白そうだと心惹かれたら棚に戻さずにそのまま借りてみたりすることもあった。 ちなみに今、机の上で広げているのは、和歌の本だ。今までおみくじには運勢とアドバイスにしか目が向かなかった。忠告が難しいときは、祖母にいつも教えを請うていた。けれども、平安のイタリア男にして和歌の魔術師、在原業平をリスペクトするようになって以来、わずか三十一文字に色々を込められた和歌の内容を知りたいと思うようになったのだ。とはいえ、授業のサポートなしに『伊勢物語』や『古今和歌集』と向き合うのはまだハードルが高すぎる。手始めに先週手に入れた小吉のおみくじに書かれた和歌の謎を解こう、と司書の先生に相談することにした。先生はニコニコ微笑みながら、おみくじに書かれた歌を紹介する本を教えてくれたのだ。
「うん。ありがとう」
ひとの幸運を妬むことなく、僻むことなく、素直に相手を祝福し、その喜びに傾聴する姿勢を忘れない菊地原はやはりひとが良い。そうした良い友人を持てることもまた同じクラスで二年目の高校生活を送ることができるのも嬉しい。かけがえのない友人ができたことが嬉しくてたまらない。真澄は眉も頬も口角もふにゃりと緩めた。
晴れわたる月の光にうれしくもゆくての道のさやかなりけり
ひらり、とおみくじが捲れそうになった。そっと手帳に挟み直し、換気のために開け放っていた窓を閉めに行く。咲き染めの花と新緑の匂いが鼻をくすぐった。春のやわらかな風がゆっくりと図書室のカーテンを揺らしていた。
さらさらと砂時計の砂が流れていくように。日々を繰り返しているうちに、春が終わり、定期考査が来て、全国模試に小論文模試、やがて学期末考査も訪れた。巡ってきた高校二年生の夏もいつの間にか過ぎ去ろうとしている。
この夏も真澄は、太陽がじりじり照りつけるよりも早い時刻の道と、太陽が街を橙色に染める頃の道の散歩を、弟と犬と共に続けていた。
「すーちゃん……」
呆れた果てた弟の声が、届いた。
「ごめんね。もう一回。ワン・モア!」
気合いを入れ直し、呼吸を整える。
「行くよ!」
大きく振りかぶって投げる――
ボールは大きく放物線を描いた。真正面の遼太と大きく離れた左前方へ。丘の向こう目がけて。
「…………」
黄金の稲穂に似た尾が揺れた。二人のキャッチボールを観戦していた柴犬の太郎が、立ち上がり、駆けて行く。彼はボールを追いかけに行ってくれたのだ。さすが宇田川家が誇る優秀なセンターである。
緩やかな速度のボールはすぐに捕らえられた。センターこと太郎は咥えたボールを見せながらこちらに尾を振った。ぶんぶんと雄々しく風を切る尾は、得意げである。二人も笑いながら手を振り返す。太郎のつぶらな瞳は更に輝きを増し――
「あ」
走り出した。丘の向こう側へ。
「すーちゃんより太郎の方が上手いね!」
「うん! 太郎を獲得しようと次のドラフト会議は大いに荒れるね……!」
姉弟もその太郎を追いかけて、走る。三歩分先を行く弟の背を、真澄も懸命に追う。小学三年生になった遼太は、去年よりも背が伸びた。走るのも速くなった。距離がぐんぐん開いていく。先に出発した弟を、後から追いかけた姉が追いつくのに必要な速度は――
算数の問題が一瞬過ったが、そういう問題ではない。いや、そういう問題なのだが。
息を切らせながら走る。丘の頂上で黄金の稲穂が大きく揺れているのが見えた。嬉しそうにぶんぶんと太郎が尾を振っている。
「遼ちゃん!」
最後の力を振り絞り、駆け上がる。そして、ゴール直前で真澄は呼吸が止まった。ひゅ、と。
「はい」
返事があったのだ。
随分低い声で。去年よりもずっと聞き慣れたその声で。
そこには、同級生がいた。宇田川遼太と太郎の頭を代わる代わるやさしい手付きで撫で回すそのひとは、教室で会うのと変わりない穏やかな笑顔をこちらに向けてくれている。
「う、歌川くん……」
「はい」
震える膝を押さえて息を整える真澄を、呆れもせず笑い飛ばしもせずに歌川は待ってくれている。登校後と下校前に彼に声をかける際、真澄が声を震わせながらもなんとか言い終わるのを、彼はいつも待ってくれる。ありったけの勇気をかき集めた真澄が二年C組の教室で挨拶をするときと変わらずに、そのひとはただ穏和な微笑みをたたえて、真澄のことを待ってくれている。
意識した途端、胸のあたりが、きゅう、となる。目と喉のあたりが熱くなる。それでもなんとか言葉を探す。
「こ、こんにちは……」
「うん。宇田川さん、こんにちは。少しだけ久しぶりかな」
夏休み開始と同時に行われた夏季課外授業。それが終わるなり彼はボーダーの「遠征」に行くと聞いていたので、会うのはそれ以来だ。
「うん。久しぶりだね。歌川くん、お疲れ様です」
歌川の目線が少しだけ遠い。夏の間にまた背が伸びたようだ。と――
「遼くんおつかれさま! すーちゃんゴールできてえらい!」
腰に遼太が飛びついてきた。少しぐらついたものの、姉の威厳で踏みとどまる。真澄も両手を伸ばし、弟の頭と頬を撫でる。丸みを帯びた頬は、すべすべもちもちしてやわらかい。遼太はくすぐったそうに全身を揺らし、笑った。力いっぱい甘えてくれる小学三年生の弟の可愛さに真澄もつい頬が緩んでしまう。
「ありがとう。仲いいなあ」
わちゃわちゃ戯れ合う姉弟に目を細め、歌川が笑った。太郎が尾を大きく振った。「そうだろう」というように黒目をきらきら輝かせながら。
「宇田川さん、手を貸してもらえるかな」
「は、はい」
真澄はぱちぱちとまばたきをしながら両手を広げた。
「オレも見たかったな。宇田川さんの消える魔球」
落とされたのは、つるつるしたオレンジ色のカラーボール。そして、歌川の笑みを含んだ声だった。
「遼ちゃん!」
真澄は悲鳴をあげた。取り落としたボールを、弟の遼太が素早くキャッチしてくれた。震える手のひらで、弟の両肩を、握る。ぎゅう、と。
キャッチボールをしていたことも、姉のノーコントロールぶりもドラフト会議で太郎獲得に各チーム監督が動き出すだろうことも、弟は歌川に全部話してしまったらしい。真澄の球技全般センスが大変アレなのは、同じクラスで二回も挑んだ球技大会で歌川にも知られている。知られているかな。知られているといいな。知ってもらえていたら嬉しい――ような恥ずかしいような。
ぐるぐる。ぐらぐら。ぐつぐつ。沸騰する真澄の頭をよそに弟が元気よく言った。
「すーちゃんはボール投げるのは下手だけど、飛行機作って飛ばすのはうちで一番上手なんだよ! いっちばん遠くまで飛ぶんだ!」
弟は目を輝かせながら歌川にプレゼンテーションを始めた。夏休みの工作課題に弟は紙の模型飛行機を選んだ。それを真澄も父と一緒に少しだけ手伝ったのだ。
手と表情だけでなく、全身まで使って懸命に模型飛行機について語る遼太の話に耳を傾けてくれていた歌川の瞳が、ふ、と和んだ。はるか遠くをも透かすような澄んだ切れ長の瞳が、まっすぐとこちらを向いている――
「すごいなあ」
まぶしい。彼の笑顔は、まぶしい。とても。すごく。とてつもなく。とびきり。それが、彼のまぶしい笑顔が、今、この瞬間、自分に向けられている。まっすぐと。
理解した途端、心臓が、ふるえた。
やっとのことで「わたしも数学と理科の道を選びし子なので」と紡げば、彼はくつくつと笑った。違いない、と。
文理選択で真澄は理系コースを選んだのだ。六頴館高校では、生徒一人一人が適性や興味を考えながら深く幅広い学力を身に付けることができるように、二年時次から緩やかな文・理コース制が導入されている。同じクラスの二年C組に所属していても英語などの共通科目の他の選択科目は、文系コースを選んだクラスメイトとは科目内容も教室も分かれて行われるのだ。彼もまた同じ理系コースにいるのだが、今はそれどころではない。
上機嫌に笑う歌川に、まっすぐと向けられたその笑顔のまぶしさに、胸の奥から色々な感情がまぜこぜになり、熱を帯びて込み上げてくる。
顔を覆った両手に伝わるその熱さ。傾きそうでまだ沈まない晩夏の太陽の暑さ。歌川の笑顔のまばゆさ。真澄の頭はくらくらするほかなかった。
それから歌川は、遼太と太郎を交えてキャッチボールをしてくれた。残暑の中、全力で走った後で顔色を慌ただしく変えている真澄を見かねたのか、「お姉ちゃんには少しだけ休んでもらおうな」と提案してくれたのだ。
二年生に進級してますますベリージェントルソウルに磨きを掛けた歌川がまぶしい。
弟にボールを投げるフォームをコーチしてくれている横顔も大変凜々しくてまぶしくて、ますます真澄の体感温度がアップした。今日だけで〝歌川くん基金〟はかなりの額になる。このあと真澄の財布から大いに移動することが決定しているので。
山の端に太陽が隠れかかるのを追いかけるように、道を行く。街には灯りが少しずつともり始めた。夜の帳と共に少しずつ姿を見せる、星の輝きと重なり、ほんのり明るいそれに、歌川が目を細めた。
「オレ、街の灯を見るたびに思い出すことがあって」
秋隣の風に、歌川の清潔感あふれる爽やかな髪が、靡いている。
「皆が安心しながらこうして散歩できるのは、オレたちボーダーが護ってくれるからだって宇田川さんがまっすぐ言ってくれたことがあっただろう? 去年」
「うん……」
もちろん覚えている。
一年前の今頃。夏と秋とのあわいに包まれたこの道を、歌川と真澄はゆっくり歩いた。もちろん弟も愛犬も一緒に居た。ふたりきりだなんて途方もない。けれども、教室の外で彼と長い時間、話をする権利も関係も約束も持っているわけではない真澄にとって、忘れられない夏の思い出だ。
嬉しかったんだ、と彼は目を細めた。
「街の灯を見るたびに思うって。まっすぐ言ってもらえたの、嬉しかったんだ」
「うん」
「ボーダーに入ることを選んだのも続けることを決めたのもオレ自身だ。でも、やっぱりなんというか、その、うん。時々、そういうまっさらな気持ちを忘れそうになる日もあって……」
「…………」
一月の第二次大規模侵攻で近界民に攫われた三十二人。五年前の第一次大規模侵攻で行方不明となった四〇〇人以上の三門市民。そうした人々を見つけて連れ戻すために界境防衛機関「ボーダー」は「遠征」計画を進めているのだ。
組織に所属する歌川もまたその計画に携わっていると聞く。高校で勉学に励む傍らボーダーで訓練に励み、街の防衛任務も担い、「遠征」にも赴く。それだけではなく、歌川遼はその名に冠せられた「遼」の通り、はるか遠い先を見据えながらも、はるか遠い先に進んでいながらも、心も器もずっと広く、周りのことをよく見てくれていて、いつもいつでもいつだって誰にでも手を差し伸べてくれるやさしさを持つひとなのだ。
このひとは、一人でいったい何足もの草鞋を履いているのだろう。
「ごめん。なんだか聞いていて楽しい言い方じゃなかったよな……」
「う、ううん! こっちこそごめんね。そんなことない。そんなこと、ないから……」
また気遣わせてしまった。真澄は大きく首を振った。
歌川だって同じ高校二年生だ。疲れる日だってもちろんあるだろう。そうしたごく当たり前のことに気づけなかったことが、目を向けられなかったことが恥ずかしくて、情けない。
それでも少女は、じっと彼の顔を見上げた。
「そういうとき、いつも宇田川さんがあの日話してくれたことを思い出すんだ」
それから少年は、そっと彼女を見つめて唇を開いてくれた。
「防衛任務に向かう夜に。任務や訓練を終えて本部や家に帰る道で。そういうとき、街の灯が、あのとき宇田川さんがかけてくれた言葉が、いつもオレの心を静かに照らしてくれてる。嬉しかったんだ。とても」
はるか、遠い空を見晴るかすかのような眼差しで。そのひとは、笑う。
「だから、ありがとう」
じわりと染み入るような声に乗せられた言葉だった。
徐々に傾いていく陽の光が、彼の精悍な顔つきも短く切り揃えられた栗色の髪も明るく照らしている。それがまぶしくて。見ていられなくて。ずっと見ていたいのに、それがなんだか難しくて。真澄は、そうっと目を伏せた。
笑い合う声がする。太郎の尾が大きく揺れ、遼太の弾ける笑い声が辺りを包む。弟を中心に愛犬がくるくる走っては、互いに飛びつき戯れ合っている。遼太に振り返した手のひらを、結ぶ。ぎゅう、と。
「あのね」
「うん」
「……歌川くんが、ボーダーの方々が、いつもわたしたちのことを大切に護ってくれているから、こうしてのんびり散歩できるのも本当だから。いつも感謝しているのも本当だよ」
「うん」
なんだか小学三年生のような言い方になってしまった。歌川のやさしい声がする。ずっと聴いていたいのに、その返事をもらうたびに心臓がどくどく音を立てるのも聞こえてくる。その声をずっと聴くのは危険な気がする。一日の摂取量をオーバーしているかもしれない。
手のひらに握るものがない。真澄は、おろり、と目を泳がせた。凜々しく黄金色の尻尾を立てて歩く太郎と仲良く弟も歩いている。小学三年生に上がると、遼太はまた背が伸びて、体つきも少しずつ立派になってきた。父からの許可も下り、今年の夏休みの散歩から太郎のリードは遼太に任せている。手持ち無沙汰の真澄は、おろおろと、耳に髪をかけては下ろし、下ろしてはかけ直す意味のない動作を繰り返してしまう。
歌川が待ってくれている。
あわあわと唇を開いては閉じ、閉じては開くことを繰り返す真澄を、歌川は待ってくれている。
「あのね、わたしの家は五年前も八ヶ月前のときも無事だったの。でも、おばあちゃんのお家が五年前に警戒区域に指定されてしまって……」
「…………」
「あっ、ええと! その、おばあちゃんは無事です。お家は壊れたけれど、怪我も全然なかったし、『命あっての物種よね』って笑いながら今日も元気に書道教室で先生をしています……!」
わたわたと真澄が両手を振ると、ほっとしたように歌川が息を落としてくれた。こまらせたいわけではないのに、やはり彼をこまらせてばかりいる。「ここで一首」とここぞというシーンで歌を詠める平安のイタリア男・在原業平への道はやはり険しい。
「街の灯を見るたびにね、おばあちゃんが話してくれるの」
祖母が、真澄がボーダーのひとたちにありがとうと伝えたいきっかけが、そこにはある。
「『ボーダーの子たちはね、家に私が残してきたものを、かけがえのない宝物を、決してないがしろにしなかったのよ』って」
――警戒区域の自宅に残してきた夫からの手紙を取りに行きたい。
祖母の申請が通ったのは、真澄が高等部に上がる直前の春休みだった。
夫から昔もらった大切な手紙を、かけがえのない宝物であるそれを、ボーダーの彼らは代わりに取りに行くでもなく、祖母自身がその手で大事に持ち帰るのを最初から最後までサポートしてくれたのだ。
――危なくないようにずっとそばに付き添ってくれたのももちろん嬉しかったわ。でもね、私の手であのひとの手紙を持ち帰りたい。そういう気持ちを大切にしてくれる子たちが、同じこの街に居てくれることが、この街を護ろうとしてくれていることが、何よりもずっと嬉しかったのよ。
祖母はその話をするとき、いつもまぶしげに目を細めて笑うのだ。
「わたしね、その話を初めておばあちゃんから聴いたとき、すごく嬉しかったの。警戒区域への行き帰り、緊張しているおばあちゃんにも色々とお話ししてくれたんだって。ちょうど『この春から高校一年生になるんです』って風間隊の男の子二人が道中話してくれたって」
一人は淡い色素の髪とおそろいの眉に猫と似た吊り目がちの男の子。もう一人は短く栗色の髪を切り揃えて額に大きく上げたスポーツマンのような男の子。まだあどけない横顔を見せる少年たちは、黒髪の精悍な顔つきをした隊長の一声一声に耳を澄まし、祖母がつまずかないように、怪我をしないように行きから帰りまでサポートしてくれたのだという。
「わたし、その話を初めて聴いたとき、嬉しかったの。とても。誰かが何かを大切に想う気持ちを、大切にしてくれるひとが居てくれるんだなって。そういうひとたちが、同じ街に居ることも同い年に居ることも嬉しくて、街を護ってくれているのもすごいなって」
頬が緩むのに任せて、言う。
「そういうやさしいひとたちに恥じない自分で在りたいなって、街の灯を見るたびに思うよ」
大きく、息を零した。なんとか言葉にできてほっとしたのだ。一番に伝えたい歌川に、夏の灯を見ながら言えたのも嬉しい。この夏も同じ灯を前に歌川の隣で話せたのが、嬉しくて嬉しくてたまらなかった。
「……宇田川さんは、いつもまっすぐ言葉をくれるね」
太陽が山の端に隠れる直前の強い光を帯びた歌川の瞳はまぶしかった。落ち着いた彩度の瞳をやわらかくして、そのひとは笑んだ。
やはりまっすぐ見ていられなくて、少女は耳に髪をかけ直しては下ろし、耳にかけては下ろした。
横から吹く夏の名残の暑さと秋の初めの涼を孕んだ風が、彼のシャツを、少女のポニーテールを、黄金に染まる太郎の尾を、大きく揺らした。