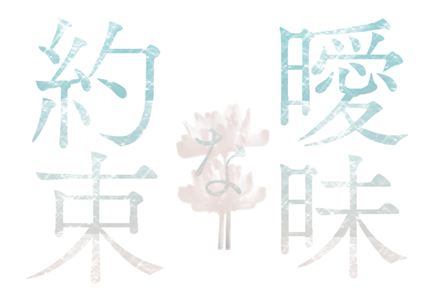
ススキの穂が風に揺れ、なびいている。透明な風に自身の髪を流し、竹谷八左ヱ門は深呼吸をした。吸い込んだ空気はひんやりとしていて、胸の奥まで沁みとおるような心地がした。夏の頃とは大分空気の質が変わってきたのを実感する。
空気の冴え冴えとした秋晴れの日である。
――無理もないだろ。
くっきりと白い鰯雲の浮かぶ空を仰ぎ、独りごちる。
――こんなにいい天気なんだぜ? あれだって外に行きたいよなあ。野山を彷徨いたいという野生の血が騒いだんだって。
捜索終了。めでたし、めでたし。さて飼育小屋に引き上げようか、と振り返る。風が渡り、ススキの穂波がさざめいた。
ふと、後輩の泣き顔が脳裏をよぎった。
頭巾越しに頭をがしがしと掻き、嘆息する。彼は再び周囲へと視線を投じた。
咲き誇るススキの尾花を道なりに進んでいくと、草の根で繰り広げられている虫の合唱もいよいよ大きくなってきた。
「ひとつ、ふたつ、みっつ」
合唱に交じって、か細く情けない声が聞こえてきた。彼は訝しく思って眉根をぐ、と寄せる。
「よっつ……いつつ、むーっつ。…………ああ、ひとつ足りません」
声はすれども姿はない。
彼はなにやら背筋に冷たいものが通り過ぎるのを感じていた。
落ち着かせるように目を伏せる。呼吸しながら、ゆっくりと開く。
と――
ふと、地面に穴がぽっかりと空いているのを発見する。
彼は二、三度まばたきをしてから、しばし虚空を見上げ、そして、身を屈めて、その穴の中をのぞき込んだ。
見慣れたくのいち教室の鴇色の装束が目に入った。よく見知った少女である。彼女の邪魔にならぬように紐で纏めているはずの髪はぼさぼさと乱れ、葉っぱが絡んでいるのが見える。そして、まだ少し子供のような丸みを残した頬は、ほのかに泥で汚れていた。
だが、そんなことはこれっぽっちも気にした風もなく、少女は手足を丸めていた。
「――何だ上月じゃないか。何してるんだ、そんなところで」
「わかりませんか」
同学年のくのたま生徒、上月伽夜はこちらをちらりと見上げ、何かを指折り数える作業へと舞い戻った。すっと眇めた双眸には、睫毛の影が落ちている。いつになく真剣なその表情に、八左ヱ門は少々たじろいだ。
「……まあ、見ればわかるけどさ。なんでそんなとこに落ちてるんだ?」
確認するように呟けば、彼女は座り込んだままの姿勢で飛び上がった。
「うわっ! タコ壺ですか、ここは!? やけにほの暗いと思ったら!」
八左ヱ門は肩をコケさせた。たまらず、ひきつりまくった表情で叫び返す。
「待て待て待て! とりあえず、どこから突っ込めばいいんだ!?」
太陽の光がススキの尾花を照らして、風に寄せては返る波がその光を反射させる。
「引っ張り上げてくれて、どうもありがとうございました」
ぺこりと頭を下げ、彼女はためらいがちな声音で感謝の言葉を紡いできた。
八左ヱ門は、通りがかっただけだから気にするな――と手をひらひらと振ってやる。ついでに、この件は口外しないから安心しろ――とも付け加える。
途端、相手は泥のついた頬をほっと緩めた。
――失せものを探しているはずが、まったく別の、ばかでかい失せものを拾ってしまった……。
八左ヱ門は、大きく嘆息した。隠しもしなかったため、相手が不快に思うかと、一瞬慌てる。だが――彼女はまったく気づかずに、再び眉を八の字に下げ、精一杯真剣な表情を作っている。
「なでしこ、尾花、葛の花、女郎花、朝顔、萩……。うーん、やっぱりひとつ足りません……」
今度は小さくため息をつく。
そして、唐突に理解する。
――何だ。そんなことで悩んで穴に落ちたのか……。
苦笑をにじませて、静かに呼びかける。
「上月」
八左ヱ門の声に伽夜は目をぱちくりさせた。
「? なんです?」
「あれだろ。七草に足りないのは」
「え?」
「ほら。そこに咲いてるぞ、藤袴」
言って、指で示す。淡い紫紅色の花弁が、風に小さく揺れていた。
虚を突かれ、ぱちくり、とまばたきをする少女に、八左ヱ門はにっと口の両端をつり上げる。そのまま諳んじてみせる。
「萩の花尾花葛花なでしこの花女郎花また藤袴朝顔の花、ってな。昔から言うだろ」
「あ。そうか。その歌でしたっけ」
口の中で確かめるように歌を転がすと、少女の瞳は大きく弧を描いた。その動きに従って、眉は下がっていく。何だか見ているこちらまで大きく力が抜けてしまうような笑みだった。
「何なんだ、その笑顔は……」
「いえ、竹谷くんっていいお父さんだなあと思いまして」
にこにこと邪気のない笑みを深め、今度は彼女がそっと指さした。その方向へつられたように八左ヱ門も視線を伸ばす。
「竹谷せんぱーい!」
「きみこ、無事に捕獲しました……!」
ススキの穂波の向こうで、水色の地に井桁模様の浮かんだ装束に身を包んだ後輩たちが、わたわたと虫取り網を振っている。
「よーし、よくやった!」
頭上に両手を掲げて、大きな丸を作る。すると、後輩たちはうれしそうに息を弾ませてこちらへと駆け出した。
「こら。転ぶから、慌てて走るな、走るな!」
太陽の光を反射し、眩しいくらいにきらめく黄金の穂波。青く、蒼く、碧く、透けるような空。虫の音が耳を撫でて、風の渡るススキの音が心地よく響く。
それはあまりにも美しい光景だった。
隣に立つ少女と同じように、自身の目も柔らかな弧を描いて細まっているんだろうなあ――と何となく八左ヱ門は、思った。