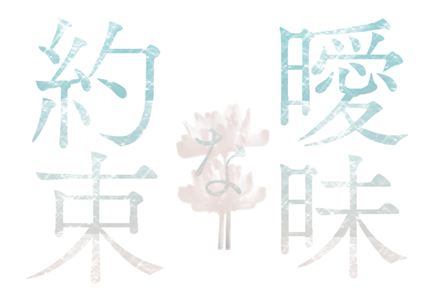
知っているのだ、本当は。この手を離す日がきたのだということを。
忍術学園の校庭は今日も活気やざわめきであふれている。ただ一つだけいつもと違うのは、すすり泣くような声や嗚咽を堪えるような声、そして大きな泣き声が、笑い声に混じって聞こえてくることだろう。
ひらり。ひらり。
ほの白い花びらが降っている。
大地を桜の海に沈めるように、世の中一帯を桜一色で埋め尽くすかのように、花びらは降り続いていた。
空も山も大地も何もかもが桜一色に仕立て上げられていた。
満開の桜の下で、少女の視野はただじっと一点を捉えている。
空色に若葉色、茄子紺色の装束をまとった生徒が輪を作っている。彼らは輪の中心人物の静かな語りを、身動き一つせずに聞き入っていた。輪の中心には草色の装束をまとった六年生が、背筋をぴんと伸ばして立っていた。
少女は、大きな瞳を絞った。そのひとの輪郭が、際立った。
草色の装束は、くたびれているようにくすんで見える。ところどころ引っかけたように糸がほつれている。離れていても、目の下の隈ははっきりと見えた。けれども、その表情はひどく穏やかだ。
振ろうとしていた手のひらを、ゆっくりと降ろした。無意識に力が込もる。覚悟していたはずの心が、今更になって震えた。
ついにそのひとが、口を閉じた。話は終いだ、と片手をひらりと振る。
それが、合図だった。
井桁模様の浮かんだ制服に身を包んだ一年生たちが、そのひとに飛びついた。そのひとは微苦笑のようなものを漏らす。しょうがねぇなあ、というように唇を短く動かして、両手で一年生二人の頭を乱暴に撫でた。たまらずに三年生も四年生も一年生ごと彼めがけて飛び込んでいく。
「おめでとうございます」
文次郎ちゃん――少女はそう続けたつもりだったのだが、語尾はあたりのざわめきに吸い込まれるように消えて行った。
視界の先が、ゆらゆらと揺れている。――眩しすぎるのだ。それぞれが太陽の光を一身に浴び、それを地上へと振り撒いている。
背中から風が吹き抜け、大地を覆う花びらが舞い上がった。
止むことを知らないかのように、一枚、また一枚と花びらは天から降りてくる。
雪のようだ、と少女は思った。降り積もってはどんどん重なっていく思い出とおんなじだ、と。