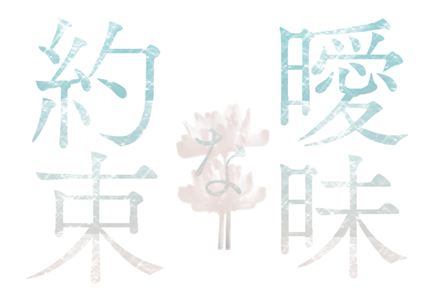
陽だまりの満ちた縁側に腰を降ろして――
ただ伽夜はじっと庭へと視線を注いでいた。雲の切れ間から陽の光が差し込んで、空へと背伸びした草が明滅している。
上へ視界をずらすと、薄い朱の混じったようなほの白いものが山のあちこちに見えた。あれも桜の木だったのだなと思い出す。あと数日もすれば、空も山も大地も桜色一色で満杯になるだろう。
さあ、と風が頬を撫でた。寒くはない。心地よいくらいであった。降りてくる陽射しが暖かいのだ。芽吹いたばかりの草花の香りが鼻を掠めた。
大きく嘆息をして、膝の上にほおづえをする。
「伽夜」
顔を上げる。
まさか笑う気にもなれず、憮然とした目つきで伽夜は振り返った。従兄殿が立っていた。浅葱色の筒袖に紺青色の括袴。染め抜いたばかりのように色鮮やかで、皺どころか埃一つさえ見当たらない。黒髪も奇妙なくらいに整っていた。今日は丁寧に櫛を入れたらしい。――いつもはいくら言っても聞かないくせに。
知りません。伽夜は胸中で独りごちる。知りません知りません。こんなひと知りません。
苛々と眉が寄っていくのを自覚しながら睨みつけていると、彼の右手に何やら小さな包みが見えた。
「あー、その……、な」
無言のまま見つめると、従兄殿は眉を寄せて、ため息を吐き出した。重くはないはずなのに、彼は不自然なくらいその右手をゆっくりと下ろしていく。拳からはみ出した若葉色が揺れる。伽夜の大好きな菓子屋の包みだ。
「いいかげん機嫌直せ」
「…………」
伽夜は顔を背けると、息を止めた。座っていた縁側から、飛び降りる。足が届かないほどの高さがあるわけではないのだが、気分の問題である。意識してゆっくりと体勢を整える。相手の方に向き直ったのは十を数え終えた後のことだったが、彼は表情を変えることもなく、こちらを見下ろしてきていた。
そろそろ黙っていることもできなくなって――悔しいけれど――伽夜は、口を開いた。
「……ひどいじゃないですか!」
身体の前で腕を組んで、続ける。
「どうして教えてくれなかったんですか!?」
「だって、おまえ、聞かなかったじゃないか」
仕方ないだろう、というように文次郎はこちらを見下ろしてくる。
眉間にぐっと力を入れて、伽夜は一気にまくし立てた。
「知らないんだから聞けるわけないじゃないですか! 文次郎ちゃんが潮江のお家を出て遠くの学校とやらに行っちゃうなんて! しかもここへ寄った足でそのまま行っちゃうなんて! なんで教えてくれなかったんですか! ずるいですよ!」
「おーおー。おまえの言うとーりだ」
適当に返事をしながら、彼は包みを持ち上げた。
「ほら、土産の団子だぞ。おまえ、好きだろう? 一緒に食おう。な?」
「ごまかさないで下さい! 父上にも母上にも知らせていたのに、わたしにだけ教えてくれなかったのでしょう? ずるいですよう!」
「……なんでそう言い切れるんだよ。お二人にもついさっき報告したばかりだぞ」
「うそです」
じっとりと半眼で包みを見つめる。
「だって、文次郎ちゃんがわたしにわざわざお土産を持ってくるなんて天地がひっくり返ってもないですもん。伯母上か母上の入れ知恵に決まってますよ、ぜったい」
非難の声を一気に投げつける間、文次郎から目線をずらしていたわけだが――
気づかれないように横目で見やると、彼は気まずそうに眉を下げて頬を掻いていた。顔を上げれば、素早くいつもの無愛想な顔に戻っていたが。
苦虫をかみつぶしたような目つきで文次郎がうめいた。
「素直に食えばいいのに。……っとにおまえは可愛くねぇ奴だな」
「意地悪文次郎ちゃんには言われたくありません」
口を尖らせて返すと、文次郎は大きく息をついた。
「意地悪なんかじゃねぇよ。つくづく無礼な奴だな」
じゃあなんでですか――と、じっと睨みつける。文次郎も呆れたようにこちらを半眼で見下ろしてくる。
そのまま二十は数えた頃だろうか。とうとう観念したように、文次郎は再び大きくため息をついた。
「…………おれが行くことを教えたら、おまえ――」
微妙に視線を外す文次郎を、伽夜は真正面から見上げる。
と――
「――文次郎くん、お昼ごはんができましたよ。早くお上がりなさい」
聞き慣れた間延びしたような声が聞こえた。視線を向けると、廊下の向こうへと遠ざかる母の背中が見えた。
視線を戻せば、ほっとしたように文次郎が息をついた。
「……だとよ。じゃあな」
縁側の上にいる気配が、足音と共に離れていってしまう。
伽夜はぽかんとその背中を見つめる。
二人の距離がゆっくりと開いていく。その間を、春の穏やかな風が撫でるように通り抜けていった。
「……あ」
声が、乾いたように、喉が引きつる。上手く声が出せない。
文次郎ちゃんが、忍術学園とやらに行ってしまったら、もう遊んでもらえない。話もできない。喧嘩だってできない。
――もう会えない。
急に思い知らされた現実に愕然としているうちにも相手は緩やかに歩みを進めていく。遠ざかる足音。文次郎が、そのまま離れていくような気がした。思い出も、温もりも、何もかもが手のひらからすり抜けて遠くへと。
ずっと遠い終わりが始まったのだと、知った。
気がつけば、駆けだしていた。片方の草履が脱げて、走りにくかった。心臓の音が、うるさい。それでも伽夜は足を止めなかった。
ちょうど文次郎が角を曲がろうと、更に歩みを緩めた時だった。縁側に転がるように上がり込む。ついに彼に追いついた伽夜は、走ってきた勢いのまま、縋るように彼の袂を引っ張った。
文次郎が振り返った。驚きを含んだ視線が、上からじっと注がれた。
相手を見上げると、じわりと視界が滲んだ。
まだ息の整わない唇を、伽夜はそれでもこじ開ける。
けれども、いろんな感情が混ざり合ってしまい、上手く言葉にならない。
ただ願うことしかできなかった。おいていかないでください――と。
沈黙が、耳に痛く響いた。
「ばかたれ」
ぽすん。額に硬い何かを押し当てられた。
「?」
思わず目を閉じた伽夜は、文次郎の袂を離して額を押さえる。指の間から文次郎が、菓子の包みを持ち上げるのが見えた。
「なんて情けない顔してやがる。……っとに伽夜はばかだな」
文次郎はやけに大きな声音で告げてきた。
「あのな。今生の別れじゃねぇんだから。休みになったら飽きるくらいまた遊んでやるよ」
文次郎の目線が先ほどよりも近い。気のせいでなければ、少し眉の力を抜いているようだ。
「それに時々――本当に時々だけど、新しく覚える遊びも文で教えてやる」
それが笑みだと気づいたのは、こちらの目線に合わせて彼が身体を折るようにしてくれていることを知ったのと同時だった。
「だから、おまえも返事を書くこと。宿題だ」
「……しゅくだい?」
初めて耳にする言葉に、伽夜は首をひねった。
「学んだことが身につくように先生が、おれたち生徒に出す問題のことだ。学校ってそういうものが出されるところなんだと。おまえにも特別におすそ分けだ」
普段通りの文次郎のぶっきらぼうな物言いを聞いていると、急に恥ずかしくなってくる。何だか目を合わせていられなくて、伽夜は小さくうなずいた。
「ほら、行くぞ」
文次郎が再び踵を返す。けれども、立ち尽くしたままの伽夜を気遣ったのか、体半分だけ振り返る。
「さっさと飯食って団子も食うぞ。食い終わったらおれはここを出るんだからな。早くしないとゆっくり味わえんぞ」
握るものが何もなくなった空っぽの手のひらは、支えを失くしたようでひどく落ち着かなかった。けれども、それを堪えるように、手のひらをぎゅっと結ぶ。
黙したまま少し急ぎ足で彼の背中に追いつく。
歩調を合わせているうちに、伽夜は自分の眉が下がっているのを感じていた。
「……ゆっくりするのに急ぐんですか。おかしなこと言うなあ、文次郎ちゃんは」
深く深く息を吐きながら、手のひらをゆっくりとほどく。
縁側は、春の穏やかな日差しに包まれていた。