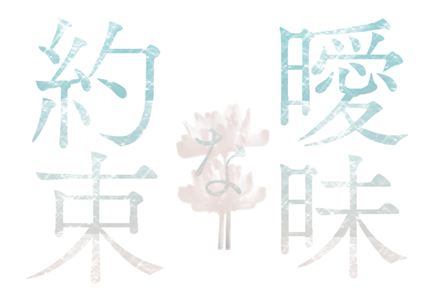
藪を割ると、広い場所に出た。
ようやく開けた視界に安堵し、深く深く呼吸する。途端、鼻につくような草の匂いがした。
視線をぐるりと巡らせる。伸びたばかりの芝草が、鮮やかに映った。やわらかな青緑の芝草に埋もれながら、白色に青色、黄色……と小さな花が点々と見える。
一周させたところで、力が抜けた。
――やっぱり見つかりません。
ため息とともに、へたり込んだ。甲高い鳥の声が耳を突いた。仰ぎ見れば、遥か上空をひばりが泳いでいる。
「この不良迷子娘!」
「わああああっ!?」
唐突に響いた怒鳴り声に、伽夜は飛び上がった。
恐る恐る振り返ると、鬼が立っていた。否、仁王立ちしてこちらを見下ろしている従兄殿――潮江文次郎がいた。眉間には深い皺が刻まれ、目の下にはくっきりと隈が浮いていた。全身からはおどろおどろしい気配があふれ出ている。
緊張した声で呼びかける。
「……もんじろー、ちゃん?」
「馬鹿たれ!」
有無を言わさず怒鳴り返された。先ほどよりも大きく空気が震えた。脊椎反射のような速度で、まっすぐと背筋を伸ばす。拍子に痺れるような痛みが走った。眉が寄ったが、ぐっと力を入れて座り直した。
うなるような声音が、全身を刺すように響き渡る。
「下級生の分際で演習場をうろつくんじゃねえ」
「……一個とちょっとだけしか年食ってない文次郎ちゃんには言われたくないです」
ささやかに抵抗を試みる。が、敵にぴしゃりと反撃された。
「俺はいいんだよ。お前はまだ入学したてのひよっこだろーが」
何も返せず、言葉に詰まった。頬を膨らませて見上げていると、目線がぐっと近くなった。
「……なんでこんな所をうろついてたんだ?」
文次郎がしゃがんで自分を覗き込んでいた。伽夜は少しだけ視線を外す。何だかまっすぐ目を合わせていられない。
耳に痛い沈黙に耐えられず、呟いた。
「……れんげそう」
文次郎は一瞬、虚をつかれたように目を白黒させた。
「レンゲソウ……、蓮華草か。それがどうした?」
「見たかったんです……蓮華草。いっぱい咲くころだから。おうちの庭に」
断片的な言葉しか出てこない。
しょうがねぇなあ、というようなかすれた声音が聞こえた。
文次郎の肩が僅かに上がり、下がった。
「……家が恋しくなったんだな」
そうなのかなあ――と口の中で転がした。
不意に文次郎がこちらの頭へと手を伸ばしてきた。けれども、弾かれることはなく、撫でられることもなく、息を詰めている間にその手はゆっくりと離れていった。じっと見つめていると、その手には葉っぱの切れ端が掴まれていた。いつのまにか頭に付いていたらしい。
そっと指先から放す。春風にさらわれ、空に吸い込まれていった。
耳を通ったのは、大げさに呆れたようなため息だった。
深い色の双眸がこちらをまっすぐと見つめていた。けれども、隈の浮いた目許はかすかに和んでいる。
「……帰るぞ。怪我はしてねえな」
「大丈夫です」
へらり。口元に弧を描いて宣言した。
「……お前の『大丈夫』ほど信用ならんものはない」
その声とともに右腕が引っぱられ、身体が宙に浮いた気がした。けれども、決して気のせいではなかった。文次郎の背中に担ぎあげられていた。
降ろしてもらおうと、足をばたつかせて抵抗を試みる。が、痛い。足首の痺れにそれを阻まれた。
文次郎は落ちないように伽夜を背負いなおした。ついでのように短く吐き捨ててくる。ばかたれ、と。
彼はそのまま歩き始める。
何も言い返せず、伽夜は唇を噛んだ。頬が熱いのを自覚しながら、相手をにらむ。目の前に映る頭巾が、じわりと滲んでいく。
見覚えがあるようでないような道を文次郎は黙々と進んでいく。
空が近い。まだ陽射しは明るかったが、夕暮れの予感がした。頬に当たる風の冷たさや空の片隅に浮かぶ赤みがかった雲が、それを漂わせていた。
「伽夜」
おもむろに文次郎が口を開いた。顔は前を向いたままだった。
夕陽色に包まれた頭巾を見つめ、じっと耳を傾ける。
「一人で演習場をふらつくのは止めろ。お前が怪我でもしたら、叔父上も叔母上もみんな心配するだろうが」
そっと、呟いた。
「……文次郎ちゃんも?」
「…………ばかたれ」
ぞんざいな一言だったが、不器用な彼なりの答えに聞こえた。
「わかりました。代わりに文次郎ちゃんも約束して下さい」
言って、右手をそっと伸ばした。左腕を彼の首に回し、落ちないように体重を預ける。伸ばした方の右手の小指で相手のそれに軽く触れた。伸ばすだけで精いっぱいで、かけ合わせることまではできなかった。だから、祈るように呟いた。
「あまり無理はしないで下さい」
「……してないことまでは約束できんぞ」
「説得力がないので却下です」
戻した右手の人差し指で、彼の目の下をトンと押した。
返事はなかった。けれども、彼の頭が上下に揺れ動くのが見えた。
文次郎の足取りに迷いはない。しかし、その歩みはとても静かなものだった。
彼は、伽夜の足首に震動が伝わらないように気遣ってくれていたのだ。
理解した瞬間、息が詰まった。
思わず彼の両肩をぎゅっと掴む。それでも――目のふちに盛り上がったものがあふれてしまいそうで、伽夜は顔を伏せた。
頬を撫でる風が、強くなった。その冷たさに眉が寄る。けれども、伝わってくる文次郎の背中のぬくもりが、心地よい。
「伽夜。……寝たのか」
聞きとれるか聞き取れないかぐらいの小さな呼びかけだった。
顔を上げると、見たこともない風景が広がっていた。
紅紫色の小さな花が、天に向かって一斉に背伸びをしていた。一面の蓮華畑であった。
呼吸を忘れて、その光景に見とれていた。
「わあ……」
傾く太陽の光を集め、蓮華草の輪郭は淡く揺れている。
「校舎からここまで来る途中、気づかなかったのか」
「はい」
即答した。
「だって、私、あっちの方から来ましたから」
言って、伽夜は指さした。つられたように文次郎が顔を向けた。
彼は、しばし生い茂る緑の隙間を見つめ――
そして、肩を大きく上げ、そのまま下げた。
「一体どこをどう通ったらあんな道に出るんだよ」
「……ありがとうございます」
「褒めてねえぞ」
夕陽に照らされた横顔は、口元にやわらかなものを浮かべていた。
肩に乗せた手に力を込めて、もう一度だけ呟く。
ありがとうございます――と。