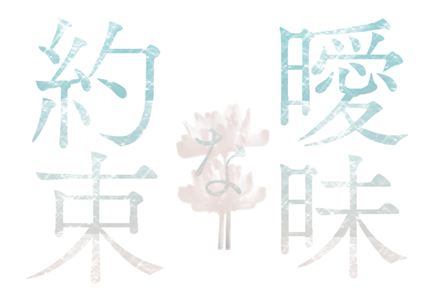
障子に差し込む光は白く眩しかった。外の青天井の下で寝転がりたくなるような、うららかな放課後である。
静かに、けれども、確かに床を踏み鳴らす音がした。それは徐々にこちらへと近づいてくる。
伽夜は向き合っていた綴りから顔を上げた。
正面に座り、同じように本へと視線を落としていた善法寺伊作の視線とぶつかった。彼は怪訝そうに少し眉を寄せると、何も言わずに入口の方へ首を巡らせた。伽夜もまたつられたように戸口へ目線を飛ばす。
戸口の向こうに一瞬沈黙が走った。
「失礼します。新野先生、傷の手当てをお願いできますか」
ぱちぱち、と伽夜はまばたきをする。気のせいでなければ、やけに聞き慣れた声だった。
首をひねる間もなく、戸が開いた。
「あ」
「や」
「げ」
見事にそろわなかった声音が消える間もなく――引き戸がばたんと閉じた。素早く扉にかじりつく。
「なんでですかー!?」
「やかましい!」
即座に怒鳴り返された。
ぎしぎしと異様に軋む音を立てる戸を渾身の力で引っ張りながら、伽夜は非難の声をあげた。
「そっちの方がでっかいです!」
「うるさい!」
「文次郎ちゃんには言われたくありません! ここに用事があるくせにーっ!」
「ない! たった今片付いた! だから俺は帰る!」
「えーっ!?」
「だ・ま・れ!」
「文次郎」
唐突に――
伊作が口をはさんでくる。
「何だ伊作! 後にしろ!」
そっと静かな声。
落ち着いた、抑揚のない言葉で伊作が呟くのが耳に入った。
「……あんまり力むと広がるんじゃないかな、その傷口」
沈黙が、降りた。
「……」
すっかり静まり、そして、手ごたえのなくなった戸を開く。
しんぞうが、はねあがった――変色した血糊が点々と床の上に落ちていた。
顔を上げると、文次郎がうずくまっていた。痛みを思い出したのか、片手を押さえて歯を食いしばっている。
彼の顔から片手へと視線を落とす。
溢れた血を吸って、変色した布のようなものが巻かれていた。自分で巻いたらしい。――完全に、乾いている。
深呼吸のようなものが零れた。
「……よかったね」
込み上げるものを見透かしたかのように伊作に言われ、自分の眉が下がるのが伽夜にはわかった。震えを悟られないように、そっと手のひらを握る。
「そうですね」
わざと軽い声を出して付け加えた。
「よかったです。扉が壊れなくて」
へらりと口元に弧を描けば、伊作は優しい光を宿した瞳を眇めて微笑んだ。
ぱっと手を離し、部屋の中へ足を運ぶ。何やら文次郎がほっと深くため息をついたようだが、無視をした。伽夜は口の両端を緩め、手招きをしてやる。一瞬、彼の瞳が死んだ魚のそれとそっくりな色になったようだが、やはり無視した。相手は何も言わず、ぐったりともう一つ嘆息し、室内に足を踏み入れた。
よくそんな傷のまま手当てせずに帰る気になるなあ――と伊作の呆れたような声が聞こえた。
いらえはなかった。文次郎は憮然としたまま沈黙を吐き続けていた。
天井までそびえ立つ薬品棚を見上げ、伽夜は立ち尽くした。鼻にしみるような消毒薬や湿布、煎じたばかりの薬草の臭いに眉が寄る。
「善法寺先輩。消毒薬はどの引き出しでしたっけ?」
「確かその棚の右から三段目じゃなかったっけ?」
「あ。ありましたありました。……あれ? 胃薬って書いてありますよ」
「え? おかしいなあ。こっちの方かな」
隣の棚の三段目に手をかけ、伊作が首をひねる。
「……おい」
伽夜は半眼で、声の方へと顔を向けた。
「何です? 今忙しいんですけど」
文次郎がひきつりまくった表情でうめいてくる。
「手当てって……」
「病気やけがの処置を施すこと。もしくは、その処置のことだけど」
まさか知らないのかい、と伊作が苦笑した。
「違う。お前ら不運委員のしかも下級生なんかに手当てができるのかよ?」
文次郎の疑問に伊作は目を丸くした。面白い冗談だ、とでもいうようにすぐに相好を崩す。
「馬鹿だなあ、文次郎。大丈夫だって。保健委員を務めてから伽夜ちゃんは二年目、僕は三年目に突入したんだから」
「そうですよ。大船に乗ったつもりでどーんとお任せ下さいよ」
「できるかっ!」
目を見開き、文次郎は怒鳴り声をあげた。びしとこちらを指さして
「お気楽能天気思考のお前ら二人だから余計に不安なんだろーが! 新野先生はともかく他の委員はどうしたんだよ。全くいねーのか?」
睨んでくる。気のせいでなければ、指先はかすかに震えていた。
「はい。今日は新野先生とみんなで裏々山まで薬草摘みに行っているので、まるッと出払ってますよ」
「……なんでよりにもよってお前らが留守番する必要があるんだよ」
ひたすら疲れたように文次郎がうめく。
伽夜は無言で足元を指さした。文次郎がつられたように視線を落とす。彼の目線が、部屋いっぱいに紐で大きく描かれた円をゆっくりとなぞるのを確認してから伽夜は肩をすくめた。
「さあ? 何故だかわかりませんが、先輩と私はこの線から出ないようにって委員長から指示を出されたので」
「委員長もつくづく不思議な活動命令を言い渡すよねえ?」
首をかしげながら伊作もうなずいてくる。
「……そーいえば、学園きっての不運小僧と方向音痴だったよな、お前ら」
完全に半眼で、文次郎がうめいた。
文次郎は、ひとしきり沈黙を吐き出してから――
すた、と立ち上がった。
「……邪魔したな」
彼は顔いっぱいに不自然な笑顔を浮かべ、ひきつったような声で会釈をしてくる。
主賓が立ち去ろうとしたところを、二人は見逃さなかった。素早く手を伸ばし、彼の衿首と袂をそれぞれ引っ張り上げる。
「ちょっと待ったー!」
「!?」
悲鳴のようなものが聞こえたが、それは無視して、もがく文次郎をずるずると引き寄せた。
空いている方の拳を、軽く上げた。
「私たちがその傷をまんまと見逃すという間抜けな芸当ができると思ったら大間違いですよっ!」
「そうだよ! せっかくの練習台……じゃなかった、怪我人は誰であれ放っておくわけにはいかない!」
「目を輝かせながら不穏なことを言うな!」
「言ってない、言ってない」
「嘘つけぇぇぇぇっ!」
全力で叫び返す文次郎の声が、空気を震わせた。むなしく震わせただけだった。
ぜいぜいと荒い呼吸を繰り返す彼の背中をそっと撫でた。
「苦しそうですね。というわけでここで休んでいきますかいきますよねいくに決まってますよね!」
「……どうにでもしろ」
彼は半分あきらめたような表情でぐったりと座り込んだ。
「いやです」
きっぱりと宣言した。
「何だと?」
伽夜はかぶりを振って、大仰に嘆息した。吐息とともに沈痛な面持ちで告げる。
「肝心の一言が足りないのでちょっと……」
ちっ、と苛立たしげに舌打ちをすると、文次郎は半眼になった。
「……頭下げろってか」
相手はますます険悪な表情へと変わっていく。それは無視し、彼女は、ちっちっと音をたてて人差し指を振ってみせた。
「いやだなあ。全然違いますよ。ねえ、先輩?」
「うんうん。あれを言ってくれないと。どうも調子が出ないよ。ねえ、伽夜ちゃん?」
「ですよねえ」
互いに目許を和らげ、視線を交わす。にやりと口の両端を緩めながら、伽夜は文次郎の様子をうかがう。彼は依然としたまま冷たく突き刺さるような視線をこちらに投げてくる。
伊作の様子を横目でちらりと盗み見る。彼もまたにこにこと微笑むばかりで、口を開く気配はなかった。
そのまま静かな時間が流れた。
沈黙に耐えかねたのか、とうとう文次郎が疲れたような声でぽつりとうめいた。
「…………お前らがそんなに手当てに必死になるのはなんでだ?」
「それは私たちが、保健委員だから」
一字一句漏れることなく、返事はぴたりと重なった。
清冽な白に包まれた手のひらを見下ろし、文次郎が感心したように息をついた。
「見事なもんだな。お前にしては……」
「どーいたしまして。でも」
「無理はするな?」
「……はい」
伽夜は苦笑を零した。理解しているのに実行はしないのだ、この従兄殿は。
引こうとした手を取ったのは、無意識だった。
乾いた広い手のひらの感触に、はっと我に返る。
「……文次郎ちゃんの手、大きいですねえ」
聞こえないように小さく嘆息し、そっと重ねた。きょとん、と形容したくなるような沈黙を文次郎が吐き出した。
「…………お前のが小さいだけだろ」
「そんなことありませんよ」
重ねた手のひらは伽夜よりも一回りは広かった。どう見積もっても、記憶の中のそれよりもずっと大きくなっている。
「どうでもいいが、そんなに見るもんじゃねえぞ。きれいじゃねえんだからよ……」
眉根は僅かに寄せられ、瞳には形容できない悲しい色がにじんでいた。けれども、手のひらはそのままだった。声音もずっと穏やかだ。
胸の奥の色んなものが溶け出してしまいそうで、伽夜は大きく吸い込んだ息を吐き出した。
「……私は好きですよ」
指先は少し冷たかったけれど、包帯に巻かれたその手のひらはとてもあたたかい。
「豆だらけでごつごつしていて。皮が厚くって、がさがさしていますし」
胸が締め付けられるのに耐えきれず、言葉を切った。小さく息を吸いこんで、紡ぐ。
「格好悪いくらいがむしゃらで。そのくせ、笑っちゃいたくなるくらい不器用で」
重ねた手のひらから伝わってくる、じわりと染みるようなあたたかさ。泣きたくなるようなあたたかさだ。
「でも、この手のひらは他の誰にも負けないくらい、ずっとひたむきなものですから。私は好きです」
「……ばかたれ」
軽い音と共に、額に痛みが走った。咄嗟にまぶたを閉じて、開く。
額を押さえ、伽夜は頬が緩んでいくのに任せながら返した。文次郎ちゃんには言われたくありません――と。
開いたばかりの瞳に映り込む日の光が、明るい。