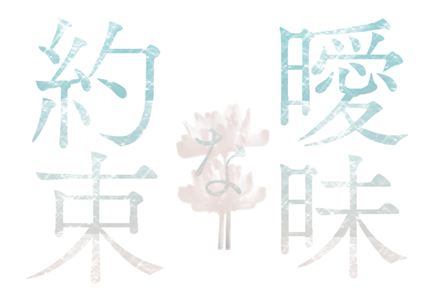
歩みに合わせた呼吸に、少し湿った空気が肺に取り込まれる。
やわらかな風が、ゆったりと渡っていく。
外と校舎との境目である渡り廊下で伽夜は足を止めた。視線をぐるりとめぐらせば、中庭にはところ構わず草花が生え、陽の光を一身に浴びていた。
白い蝶が、花から花へと舞う。光を弾く蝶の動きが、目に眩しい。
「すっかり春ですねえ」
馳せるように息をつく。
「何してやがる」
嘆息と共に、呆れたような声が降りそそいだ。同行者の声音とは似ても似つかない響きであった。けれども、振り返らずとも声の正体は分かる。伽夜は思わず苦笑した。
「こんにちは。文次郎ちゃん。いつもながら無愛想なご挨拶ですね」
振り向けば、そこには従兄殿の姿があった。「険悪」を絵に描いたような顔つきで、こちらを見下ろしている。
彼は少し考え込むかのように沈黙を吐き出した。そして、眉一つ動かさずに紡いだ。
「ごきげんよう」
聞き慣れぬ猫なで声が、空気を震わせ、耳を通って行く。挨拶だったのだと認識した途端、全身の血の気がざっと引いた。
「…………」
長い沈黙を吐き出して、伽夜がとった行動は――たったひとつのことだった。
「無理を言って申し訳ありませんでした」
顔をひきつらせたまま、ただひたすらに頭を下げた。
両腕をしっかりと組んで、文次郎が言ってきた。
「で、一体お前は何をしているんだ?」
「見て分かりませんか?」
文次郎はじっと、真顔でこちらを見下ろす。伽夜も笑んだまま、見上げる。黙したまま二人は睨み合った。――片方は笑顔だが。
やや間を置いてから、相手が閃いたように手をぽんと叩いた。
「また迷子か」
「……断じて違います。注文していた本が大量に届いたので、それを図書室へ運ぶところですよ」
塔のようにうず高く積んだ本を抱えたまま、誇らしげに吐息する。息を吸い込むと、新しい紙と墨の匂いが鼻腔をくすぐった。
文次郎が少しだけ片眉を上げた。その動きに従って、目の下にうっすらと残る隈が、ぴくりと上下した。
「ほう。新入りが一人で働くとはなかなか謙虚な心掛けだな」
「私一人じゃないですよ。図書委員みんなで分担しているんです。ほら、不破くんはもっとたくさん持って――」
へらりと笑んで、視線を隣へ飛ばす。
吸いかけた息が、喉の奥で止まる。
あれ?
――隣にいたはずの不破雷蔵の姿はかき消えていた。
「……やっぱり迷子になったんじゃねえか」
すっかり呆れ果てた文次郎の声に、何も返せない。
伽夜は心の底から嘆息すると、へなへなとその場に座り込んだ。
「ほら」
顔を上げる。文次郎が右手を差し伸べていた。こちらへ。
ごつごつとした、皮の厚ぼったい大きな手のひらをまじまじと見つめ、伽夜は嘆息した。
「……ずいぶん図太くて長い生命線ですねえ」
がす。
目の前で星が飛び交った。同時に弾けるような衝撃の走った頭を押さえる。
涙の浮いた瞳で、文次郎をじっと見上げた。
拳を固めたまま、彼は吐き捨てるように答えてくる。
「バカタレ。誰が手相を見ろと言った」
「へ?」
じゃあ何で、と目をぱちくりさせる。けれども、彼はこちらには目もくれずに踵を返す。そのまま廊下の向こうへと歩きだしていた。
角にさしかかる手前で彼の歩みは急に止まった。身体半分だけ振り返り、無愛想な眼差しをこちらに注いでくる。
「ほら、さっさとしろ。日が暮れちまうぞ」
待って下さい――と言いかけて。
伽夜は息を止めた。
従兄殿がとても見覚えのある装丁の本を抱えているのが見えた。伽夜が先ほどまで抱えていたものとそっくり同じであった。手元にあったはずの本の塔がすっかり消えていたことを、唐突に理解する。
開いたままの唇は何の言葉も発せずに、ぱくぱくと金魚のように開閉させるに留まった。
「伽夜」
名を、呼ばれる。
黙したまま、一歩ずつ、一歩ずつ廊下を踏みしめてその背中を追いかける。足を動かすうちに徐々に笑いが込み上げてきた。
震える唇を手で押さえ、吸い込んだ空気と一緒に笑いを呑みこむ。
けれども、どうしようもなく頬が緩むのだけは止められなかった。