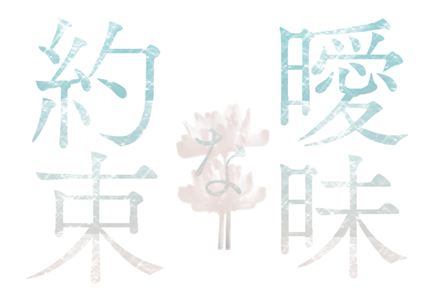風が止んだ。ふわりと花びらが舞い降りる。
彼がゆっくりと振り返った。
花びらが何枚も散った。
顔を見せないように空を仰ぎ、無理矢理に笑みを作る。
雲ひとつない空はどこまでも高く、そこには太陽が白く輝いている。
伽夜は目を瞑った。そのまま小さく息をつく。
こんなにも目が沁みるのは、眩しすぎる太陽の光のせいなのだ、と。
まぶたを上げると、目の前に文次郎が立っていた。
「……全く。なんて顔してるんだこのばかたれ」
言うべき言葉が見つからず、伽夜はただただ従兄殿を見上げた。
「どうした。言わないのか? 文次郎ちゃんには言われたくありませんって」
お前の悪態はそれしかねえからなあ――と云って、文次郎は頭を掻いた。
その所作に従って、花びらがまた一枚、また一枚と散っていく。
「……今生の別れじゃないだろうが。なんで泣きそうなんだよ」
「わかりません」
「なら、泣くな。笑え」
呆れたような声とひとつの温もりが頭上に落ちた。彼が自分の頭に手を乗せたのだと知った。
ぽんぽん。ぽんぽん。大きな手のひらは、まるで幼子をあやすかのように一定のリズムを刻み始める。
めったにないくらいの従兄殿の優しさに、伽夜は少しだけ微笑った。しかし、その笑みが、いつもと違って上手く保てない。笑おうとすればするほど、どんどんと視界が滲んでいく。
けれども、文次郎の瞳が、ふっと柔らかなものとなった。
昔も言ったが――と落とすような声音で紡がれた。
「そっちの方が、ずっと伽夜に似合ってる」
ほんの一瞬だった。
桜色の花びらが舞い落ちる中で、その淡さに溶け入るかのように彼は小さく笑った。
涙を零すまいと懸命に彼を見上げていた伽夜は、目を瞠った。
まばたきを返せば、いつものように眉間に皺を寄せ、まるでそれが当たり前みたいな顔で、文次郎は伽夜を見下ろしていた。
思い出と重なるその光景に、目の奥がじんと痛んだ。
頭上に添えられた手のひらが、今のそれよりもまだ一回りも二回りも小さかった頃。まだ丸みを帯びたあどけない顔で遠い日の従兄殿もそう云ったのだ。
どうせなら笑うだけにしろ、と。
「……ありがとうございます」
ぽたり。手の甲に冷たい何かが降ってきた。
途端、頭をかき回すようにぐしゃぐしゃと撫でられる。
「全く。本当に世話が焼ける。昔ッからちっとも変わらないな、伽夜は」
一筋、また一筋と熱いものが頬を伝って降りてくる。
ぐしゃぐしゃにされた髪を直そうと、彼の手を押しのける。手のひらに伝わってくる、いつもと変わらない温もり。
――――いつだって、文次郎ちゃんには敵わなくて。
子ども扱いされた恥ずかしさなどいつの間にかどこかに消え去っていく。それと同時に変わらぬ文次郎の言葉、その手のひらに何だか嬉しくなって、頬が緩んだ。
「……文次郎ちゃんには言われたくありません」
声が、震える。それは泣くのを我慢したからなのか、それとも声をあげて笑いだしたくなるのを堪えたからなのか、もうそんな事、どちらでもよかった。
春の到来を告げる空の色は、淡くやさしくまぶたに映った。